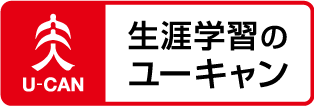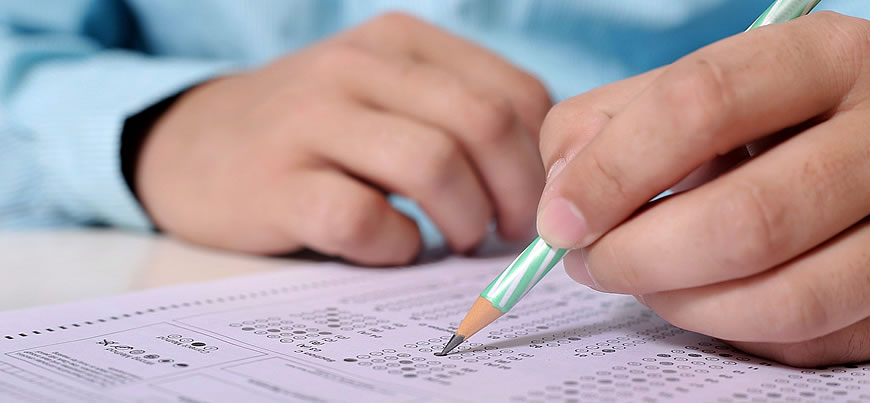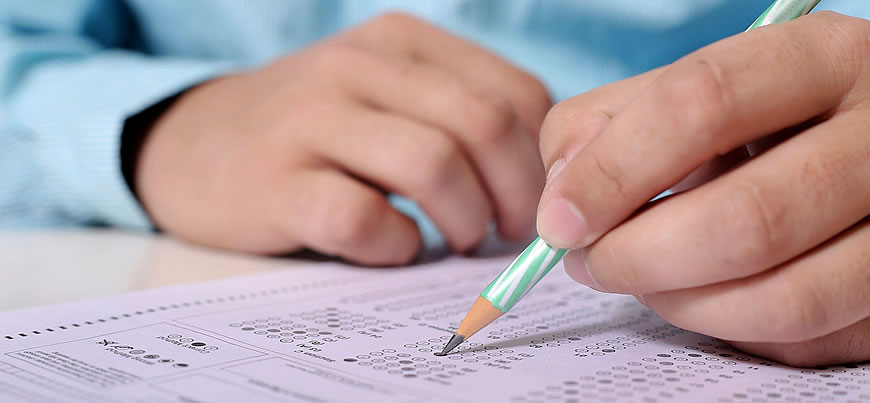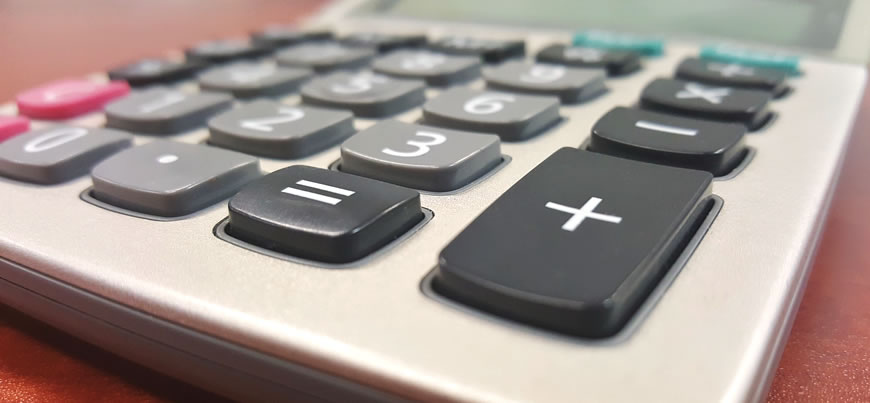- 簿記3級講座 もっと詳しく
【2025年度】簿記検定の試験日程と申込み期間

- 更新日:2025/10/03
簿記の知識は経理だけでなく、ビジネスで必要な数字の基礎知識であるため、資格取得を目指している人も多いのではないでしょうか。
この記事では簿記の資格を取りたい人のために、簿記検定の試験日程と申込み期間を紹介します。必要な勉強時間の目安なども解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
このページを簡潔にまとめると・・・
- 日商簿記検定の2級・3級の統一試験は年3回。ネット試験なら試験日を気にせず受験が可能。
- 年齢や学歴など受験資格に制限はなく誰でも受験できる。
- 日商簿記検定の合格率は、3級が30~40%、2級が20%前後、1級が10%前後で推移。
- 合格に必要な勉強時間の目安は、3級が50~100時間、2級が200~400時間、1級は1,000~2,000時間程度。試験日から起算した学習スケジュールの設定が重要。
- ユーキャンの簿記3級講座はこちら
2025年度「日商簿記検定」試験の概要
日商簿記検定の2級・3級試験は年に3回。受験制限は一切なく、どなたでも受験でき、合格のチャンスが多い試験です。
日商簿記検定の基本的な内容を確認しておきましょう。ここでは、2025年度の簿記試験の日程や科目、費用などの概要について紹介します。
日程
日商簿記検定の統一試験(ペーパー形式)は、各地の会場に受験者が集まって同時に受ける筆記形式の試験です。簿記2級・3級は、6月・11月・2月の年3回、1級は6月・11月の年2回実施されています。受験する際は事前に日程を確認しましょう。
2025年度の日商簿記の統一試験(ペーパー形式)の試験は、1級・2級・3級が、170回 2025年6月8日(日)、171回 2025年11月16日(日)に実施されます。1級の試験は172回 2026年2月22日(日)は実施されないため注意が必要です。2級・3級が年3回、1級は年2回のみとなっています。
| 申込開始 | 実施する級 | 合格発表日 | |
|---|---|---|---|
| 第170回(2025年6月8日) | 2025年4月下旬頃~ | 1級・2級・3級 | 7月上旬~7月下旬 |
| 第171回(2025年11月16日) | 2025年9月下旬頃~ | 1級・2級・3級 | 12月中旬~1月中旬 |
| 第172回(2026年2月22日) | 2026年1月初旬頃~ | 2級・3級 | 3月中旬~4月中旬 |
※各商工会議所によって申込開始日や合格発表日は異なるため、ご注意ください。詳しくは、試験実施団体の日本商工会議所でご確認ください。
商工会議所検索 | 商工会議所の検定試験
受験資格
日商簿記試験は、年齢・性別・学歴・国籍の制限なく、誰でも受験できます。また、1級・2級・3級と級がわかれていますが、3級から順番に受験する必要はなく、2級・1級からの受験もできます。さらに、1級と2級または2級と3級のように、連続する級の併願受験も認められています。
試験科目・時間・合格基準
簿記1級・2級・3級の試験科目・試験時間・合格基準は以下の通りです。
簿記1級
試験科目
商業簿記・会計学・工業簿記・原価計算の4科目です。
試験時間
1級の試験は前半と後半にわかれています。前半は商業簿記と会計学の2科目で、試験時間は90分です。後半は工業簿記と原価計算の2科目で、試験時間は同じく90分です。間に15分の休憩時間があります。
合格基準
全体の70%以上の得点で合格となります。ただし、1科目ごとの得点が40%以上である必要があります。
簿記2級
試験科目
商業簿記・工業簿記の2科目で、出題数は5問です。
試験時間
試験時間は90分です。途中休憩はありません。
合格基準
全体の70%以上の得点で合格です。
簿記3級
試験科目
商業簿記の1科目のみで、出題数は3問です。
試験時間
試験時間は60分です。途中休憩はありません。
合格基準
全体の70%以上の得点で合格です。
受験料・事務手数料
各級の受験料と事務手数料は以下の通りです。
- 1級受験料 8,800円(税込)
- 2級受験料 5,500円(税込)
- 3級受験料 3,300円(税込)
- 事務手数料 550円(税込)ただし、インターネットでの申込の場合は各商工会議所により異なります。
簿記ネット試験なら試験日を気にせず受験可能!
2020年12月よりネット試験が開始。2級と3級であれば指定日を除くほぼ毎日、受験が可能です。
日商簿記検定は従来は統一試験と呼ばれるペーパー形式のみでしたが、2020年12月よりネット試験が開始して、どちらも受けられるようになりました。ネット試験はパソコンを使う試験を指し、受けられるのは2級と3級のみです。
試験会場・試験日
統一試験(ペーパー形式)では、試験会場が決まっており、試験日も年に3回だったのに対して、ネットでの試験は随時受験が可能です。試験会場は日本全国のテストセンターで、指定日を除くほぼ毎日受験が可能です。合否判定も統一試験(ペーパー形式)では2~3週間かかるのに対し、ネット試験では即日分かります。
開始された背景
ネット試験が開始された背景には、新型コロナウイルスの感染拡大があります。2020年6月と11月に開催された簿記試験では、試験中止を余儀なくされた会場がありました。大人数を収容できる会場での試験を行えなくなったために、ネット試験が考案され実施されるようになったのです。少人数の会場で実施でき、試験日を分散できるネット試験では、以前よりも、安全に受験ができるメリットがあります。
簿記試験の最近の合格率はどれくらい?
日商簿記検定の最近の合格率は、1級が10%、2級は20%、3級は30~40%前後で推移しています。
簿記試験の合格率は回によって上下します。ここからは、最近の試験の合格率を紹介します。
簿記1級
第159~168回の簿記1級試験の受験者数・実受験者数・合格者数・合格率(合格者数÷実受験者数)は以下の通りです。ただし、第160回、第163回、第166回は1級の試験を行っていないため省略しています。1級の合格率はおおよそ10%前後で推移しています。
| 受験者数(実受験者数) | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|
| 第168回(2024年11月17日) | 12,939名(10,420名) | 1,572名 | 15.1% |
| 第167回(2024年6月9日) | 11,798名(9,457名) | 992名 | 10.5% |
| 第165回(2023年11月19日) | 12,886名(10,251名) | 1,722名 | 16.8% |
| 第164回(2023年6月11日) | 11,468名(9,295名) | 1,164名 | 12.5% |
| 第162回(2022年11月20日) | 12,286名(9,828名) | 1,027名 | 10.4% |
| 第161回(2022年6月12日) | 11,002名(8,918名) | 902名 | 10.1% |
| 第159回(2021年11月21日) | 11,389名(9,194名) | 935名 | 10.2% |
簿記2級
第162~169回の簿記2級試験の受験者数・実受験者数・合格者数・合格率は以下の通りです。2級の合格率は回によって幅がありますが、おおよそ20%前後となっています。
| 受験者数(実受験者数) | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|
| 第169回(2025年2月23日) | 8,606名(7,118名) | 1,486名 | 20.9% |
| 第168回(2024年11月17日) | 9,116名(7,589名) | 2,187名 | 28.8% |
| 第167回(2024年6月9日) | 7,786名(6,310名) | 1,442名 | 22.9% |
| 第166回(2024年2月25日) | 10,814名(8,728名) | 1,356名 | 15.5% |
| 第165回(2023年11月19日) | 11,572名(9,511名) | 1,133名 | 11.9% |
| 第164回(2023年6月11日) | 10,618名(8,454名) | 1,788名 | 21.1% |
| 第163回(2023年2月26日) | 15,103名(12,033名) | 2,983名 | 24.8% |
| 第162回(2022年11月20日) | 19,141名(15,570名) | 3,257名 | 20.9% |
簿記3級
第162~169回の簿記3級試験の受験者数・実受験者数・合格者数・合格率は以下の表の通りです。3級の合格率は1級・2級に比べて高く、30〜40%の人が合格しています。
| 受験者数(実受験者数) | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|
| 第169回(2025年2月23日) | 24,681名(21,026名) | 6,041名 | 28.7% |
| 第168回(2024年11月17日) | 22,922名(19,588名) | 5,785名 | 29.5% |
| 第167回(2024年6月9日) | 24,497名(20,927名) | 8,520名 | 40.7% |
| 第166回(2024年2月25日) | 28,565名(23,977名) | 8,706名 | 36.3% |
| 第165回(2023年11月19日) | 30,387名(25,727名) | 8,653名 | 33.6% |
| 第164回(2023年6月11日) | 31,818名(26,757名) | 9,107名 | 34.0% |
| 第163回(2023年2月26日) | 37,493名(31,556名) | 11,516名 | 36.5% |
| 第162回(2022年11月20日) | 39,055名(32,422名) | 9,786名 | 30.2% |
試験当日の持ちもの・注意事項は?
試験には持ち込み不可なものや注意点があります。予め確認しておくことで落ち着いて試験に臨み、しっかり実力を発揮しましょう。
ここからは、簿記試験当日に必要な持ちものや、受験における注意事項について説明します。
持ちもの・持ち込み不可のもの
簿記試験の際の持ちものと、持ち込みできないものは以下の通りです。
持ちもの
- 受験票
- 筆記用具(HBまたはBの黒鉛筆・シャープペンシル、消しゴムのみ)
- 電卓(特殊な機能のあるものなどは除く)、またはそろばん
- 顔写真つきの身分証明書(運転免許証、パスポート、顔写真つきの住民基本台帳カード、マイナンバーカード、学生証、社員証など)
- 腕時計(音が出ないもの)
- スリッパなどの上履き(会場による)
持ち込み不可のもの
- 印刷機能、メロディー(音の出る)機能、プログラム機能(関数電卓や売価計算・原価計算などの公式の記憶機能)、辞書機能がある電卓
- スマートフォン
- 携帯電話
- 情報通信機能やメロディー機能つきの時計
注意事項
受験の際の注意事項も確認しておきましょう。
受験料に関する注意
- 決められた期限までに受験料・事務手数料の払込みがなかった場合は受験できません
- 試験中止の場合を除き、一度支払った受験料・事務手数料は返金できません
試験中の禁止事項
- 試験官の指示に従わない行為
- 試験中に誰かに援助を与えたり、誰かから援助を受けたりする行為
- 試験問題等を複写する行為
- ほかの人の代わりに受験する行為
- 他の受験者に対する迷惑行為
- 暴力行為や器物破損など試験に対する妨害行為
- 携帯電話や情報通信機能のある機器の使用
- 録音機、カメラ、辞書などの使用
- その他の不正行為
その他の受験者への注意
- 答案用紙の持ち出しは禁止です
- 受験エリアや試験会場の変更はできません
- 集合時間に遅れたり、試験会場を間違えたりした場合は受験できません
- 試験中に退室した場合は再入場できません
- 説明開始後は飲食禁止です
- 自然災害などの影響により、試験時間を変更したり試験を中止したりする場合があります
簿記1級・2級・3級合格に必要な勉強時間の目安は?
ここでは、簿記の合格に必要な勉強時間や期間の目安を解説します。各級でどのくらい勉強が必要なのか把握しましょう。
3級の場合
簿記3級の合格には、100時間程度の勉強時間が必要です 。これはあくまで目安のため、仕事や授業で簿記について触れたことがあるという人は、もっと短い時間で合格を狙うこともできます。
3級の試験で問われる内容は、商業簿記の基本的なレベルです。経理業務に就いたことがある人は、業務の中で身に付けた知識が役に立ちます。経済学部や商学部出身の人も授業を通して簿記を学んでいることが多いでしょう。そのような場合は自分の知らない箇所にしぼって勉強すれば、時間を短縮できることもあります。
2級の場合
簿記2級の取得に必要な勉強時間は、その人の持つ簿記の知識量や勉強方法によって異なります。 簿記3級を保持している人なら、独学で250~350時間程度が必要 となり、1日2~3時間を学習時間に充てるとすると、期間の目安は4~6カ月程度です。通学や通信講座を利用するのであれば、150~250時間程度の学習時間が目安となります。通学や通信講座では、独学に比べて重要なポイントを効率よく勉強できるので、短い勉強時間で合格に近づけます。
3級を取得しておらず、業務や授業でも簿記の経験がない初心者が2級合格を目指す場合は、独学なら350~500時間、期間は6~8カ月程度が目安です。2級から受ける場合でも、3級の内容をしっかり身につけてから勉強を始めるようにしましょう。
1級の場合
簿記1級は、試験科目が多いうえにより深い理解を求められる、難易度の高い試験です。合格率も低く、2級や3級よりも多くの勉強時間が必要です。 簿記2級に合格している人や同等の知識がある人でも、独学の場合は1,000~2,000時間勉強しなければ合格は難しいでしょう 。
通学や通信講座を利用した場合でも、500~800時間は勉強する必要があります。
働きながら簿記試験合格を目指すコツは?
働きながら簿記試験に合格するには、試験日から起算した学習スケジュールの設定が不可欠!効率良く目指すなら、通信教育がおすすめです。
仕事をしながら勉強する際に重要なのがスケジュール管理です。1日のうち何時間勉強できるのか、必要な勉強時間を満たすために何カ月かかるのかを明確にし、確保できる時間数に応じて計画を作る必要があります。たとえば300時間の勉強が必要なら、1日2時間で5カ月以上が目安となります。
毎日決まった勉強時間を確保するのは大変ですが、通勤時間などの隙間時間を利用すれば、まとまった時間がとれなくても勉強できます。また、自分に合ったテキストを選ぶなど、効率的に勉強するための工夫も必要です。
通信講座で効率よく勉強するのがおすすめ
簿記は試験範囲が広く、初心者には難しい内容も含まれます。独学では疑問点を解決できないことも多いため、合格までの期間も長くなりがちです。特に、働きながら取得を目指す人には、効率的に勉強できるテキストやサポートがあるとよいでしょう。
通信講座なら重要なポイントを効率よく学習できます。スキマ時間を利用して着実に勉強を進められるため、モチベーションも維持できます。わからないところがあったら質問できるので、勉強に行き詰まることが少ない点もメリットです。
まとめ
忙しい社会人がスムーズに簿記検定に合格するためには、効率的に勉強することが大切です。必要な勉強時間を確保し、スケジュールを管理したうえで、合格に向けて着実に知識を積み重ねましょう。ユーキャンの簿記講座は、働きながら合格を目指す人にぴったりのテキストと充実したサポートを提供しています。
簿記2級講座では、出題傾向を徹底的に分析したテキストを使って効率的に学習できます。テキストにはマンガや図解が使用されており、工業簿記が苦手な人でもよりスムーズに理解できるよう工夫されています。
簿記3級講座なら、初心者でもたった3カ月で合格が目指せます。メールや郵送で気軽に質問もできるのも特長です。仕事をしながら簿記の取得を目指したい人は、ぜひ利用を検討してみてください。

- この記事の監修者は生涯学習のユーキャン
-
1954年設立。資格・実用・趣味という3つのカテゴリで多岐に渡る約150講座を展開する通信教育のパイオニア。気軽に始められる学びの手段として、多くの受講生から高い評価を受け、毎年多数の合格者を輩出しています。
近年はウェブ学習支援ツールを拡充し、紙の教材だけでは実現できない受講生サポートが可能に。通信教育の新しい未来を切り拓いていきます。
よくある質問
- 簿記は国家資格ですか?
-
簿記は国家資格ではないものの、資格としての活用度や企業からの評価が高い資格です。簿記の資格を持っていれば、就職や転職でも有利になります。
- 簿記検定はネット試験と統一試験どちらを受けるべき?
-
ネット試験でも統一試験でも合格すれば履歴書に記載でき、資格の価値に優劣はありません。
ネット試験は好きな時に試験が受けられるため、早く資格が欲しい場合はおすすめです。ただし、パソコンに慣れ親しんでいない人は、前もって操作の留意点を把握して試験に臨みましょう。
なお、日商簿記でネット試験に対応しているのは2級と3級のみで、1級は対応していません。 - 簿記検定は独学でも合格できる?
-
簿記資格は独学でも取得することができます。ただし、独学では、疑問点や学習の悩みにもすべて自力で解決しなくてはならず、間違った勉強方法で学習が非効率になったり、モチベーションが続かなくなるリスクも…。独学で乗り切る自信がない人は、スクールや通信講座など、自分にあった方法で学習することが大切です。
簿記3級講座

ユーキャンの簿記3級講座は、過去10年間で1万人以上の合格者を輩出。
添削・質問などのサポート体制も万全で、わずか3ヵ月でムリなく合格が目指せます。
当講座には、着実に合格力が身につくヒミツが満載!選ばれる5つの理由をぜひご覧ください。
簿記とは、帳簿をつけるために必要な技能のこと。実務で役立つ経理、会計の基礎知識が習得できるので、会計や財務の知識を得ようというときの、はじめの一歩にぴったりの資格。将来的に、簿記2級へとステップアップも見込めるため、経理・会計のスペシャリストへの第一歩になる資格です。
簿記の有資格者はニーズが安定しているので、職・転職が有利に!資格は生涯有効なので、出産・子育て後の再就職にも役立ちます。
ユーキャンの「簿記3級講座」では、簿記の基本となる仕訳を中心に学び、書き込み形式の演習でトレーニング。初学者にもやさしいテキストや嬉しいサポートで、ムリなく合格が目指せます。