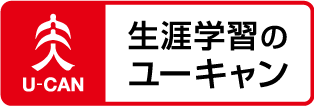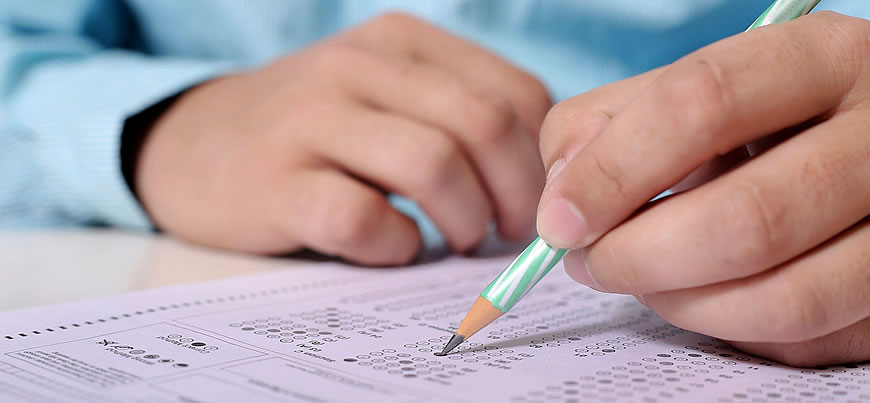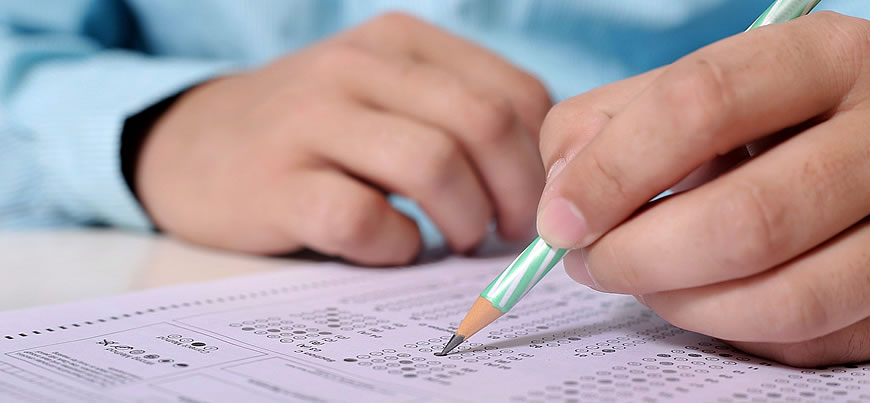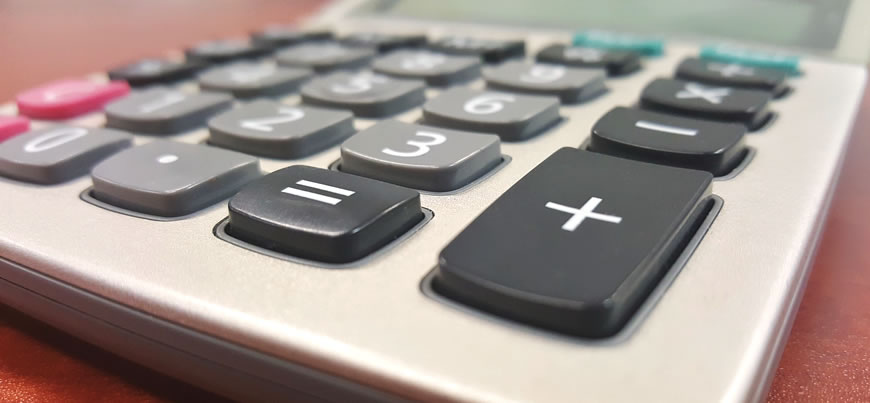- 簿記3級講座 もっと詳しく
簿記3級資格のメリット!取得することでどんな役に立つ?

- 更新日:2025/10/03
就職活動を有利に進めるため、何らかの資格を取得したいと思う人は多いです。簿記の資格はそんな人たちに人気があります。
この記事では、簿記3級を取得したいと考えている人に向けて、試験の内容・資格取得のメリット・勉強方法などを紹介します。受験する際の参考にして下さい。
このページを簡潔にまとめると・・・
- 簿記3級の取得は、経済に関する一般常識を得たり、仕事のスキルアップ、就職・転職が有利など、メリットが多い。
- 簿記3級は、履歴書の資格欄に記載が可能。
- 自営業や経理の実務にも役立ち、会計処理や確定申告などの際にも活躍する知識。
- 簿記3級は、2級や1級、税理士や公認会計士などの基礎知識でもあり、簿記3級の取得で上位資格が目指しやすくなる。
- ユーキャンの簿記3級講座はこちら
簿記3級の資格を取るメリット
簿記3級の取得は、社会人が経済に関する一般常識を得たり、仕事のスキルアップ、就職・転職が有利になるなど、メリットがたくさん!
簿記3級の資格を取ることで、どのようなメリットがあるのか解説します。
社会人としての一般常識が得られる
簿記3級の学習内容には、社会人として必要な経済に関する一般常識が多く含まれます。例えば、会社の経営状況をまとめた「財務諸表」の読み方が理解できるようになるので、取引先などの経営状況の把握に役立ちます。特に経理関係の部署で仕事をする場合には即戦力となれる可能性があります。
履歴書に記載できる
簿記3級は、履歴書の資格欄に記載できる資格です。経理の一般知識があることを履歴書で伝えられますので、就活の際により好印象を残せます。
自営業・経理の実務に役立つ
簿記3級は、自営業や経理の実務に役立ちます。簿記の知識があれば、財務諸表が読めますので、自社の経営分析ができます。会社経営に必要な知識も身に付くため、日々の会計処理や毎年の確定申告などをする際にも役立ちます。
上位の資格を目指せる
簿記3級を取得すれば、さらに上位の資格が目指しやすくなります。簿記3級は、2級や1級、税理士や公認会計士といった上位資格の基礎知識となるからです。簿記以外の資格を取得すれば、ダブルライセンスとしてキャリアアップもはかれます。
簿記3級合格の目安
簿記3級は比較的、簿記の中では難易度が低めです。計算が苦手でも、電卓が使えて、足し算・引き算など簡単な計算ができれば大丈夫!
簿記3級に合格するための目安について解説します。
独学でも合格できるのか?
簿記3級は、きちんとした学習計画を立てれば、独学でも合格を目指せる資格です。簿記の中では比較的難易度が低い資格ですが、独学では勉強をやり遂げる強い意志が求められます。また、勉強時間の確保と最適なテキスト選びも重要なポイントとなるでしょう。
しかし独学の場合、最新の情報を得るのが難しくなります。通信講座や専門学校の受講も検討してみましょう。直前模試を受けるなどの対策も必要となります。
計算が苦手だけれど合格できるのか?
計算が苦手でも、四則計算ができて、電卓が使えれば問題なく合格できます。難しい計算問題はなく、足し算や引き算などの簡単な計算で解けます。重要なのは、制限時間内に解くためのスピードです。
試験には計算問題が多く出題されますが、電卓の持ち込みは許可されていますので、速やかに解答できるように練習をしておけば問題ありません。普段から電卓を使いこなせるようにしておきましょう。
合格までの勉強時間はどれくらい?
簿記3級合格に必要な勉強時間は、約100時間といわれています。基礎知識の有無や個人のレベルにより異なりますが、効率よく勉強を進められれば、もっと少ない時間で合格することも可能です。
初心者のための簿記3級の勉強方法
簿記3級初心者の勉強方法には、参考書やアプリで独学、通信講座や専門学校などがあります。試験日から逆算し、学習スケジュールを設定しよう。
初心者のための簿記3級の勉強方法を解説します。試験日から逆算して、計画的なスケジュールを組みましょう。試験当日の雰囲気をつかんだり、情報収集をしたりするために、直前に行われる模試はぜひ受けておきたいものです。
参考書で勉強する
独学の場合は、参考書選びが非常に重要です。自分のレベルに合ったもので、見やすく、理解しやすい参考書を選びましょう。1冊の参考書を理解できるまで繰り返し読み、問題の傾向や全体の概要をつかんでから試験対策問題を解きます。
なお、参考書選び・過去問対策については、2019年6月に出題範囲が改定されたので注意が必要です。
簿記勉強方法について詳しくは
初心者が簿記3級の受験で気をつけるべきポイント
試験は70点以上の得点で合格!満点を目指す必要はありません。簿記3級初心者は問題演習を中心に勉強し、着実に実戦力を身につけることが重要!
ここでは、簿記3級を受験するにあたり、気をつけるべきポイントを解説します。
70点以上取れば合格できる
簿記3級は、100点満点中70点以上取れば合格できます。試験問題は全部で3問あり、60分以内で解答する必要があります。「仕訳問題(45点)」「精算表・貸借対照表・損益計算書のどれか1つを作成する問題(35点)」の2問は必ず出題されると考えてよい問題です。
2問の合計は80点と獲得点数も高いので、重点的に学習しましょう。
問題演習中心の勉強をする
テキストで理解を深めたら、問題演習を中心に勉強を進めます。間違えた問題はテキストの解答・解説をよく確認し、間違えた原因もしっかり把握しましょう。間違えた問題は、必ず解き直し、次は確実に解けるようにしておく必要があります。
2019年6月に出題範囲が改定されていますので、過去問を解く際は改定前の内容を避けるなどの注意が必要です。
問題を解く順序を決めておく
簿記3級を受験するにあたり、問題を解く順序をあらかじめ決めておきましょう。試験問題は全3問で、出題パターンはある程度予想が可能です。自分の得意分野が何かを把握し、解く順序を決めておくことをおすすめします。
例えば、まず第1問の「仕訳問題」を最初に解きます。続いて「精算表・貸借対照表・損益計算書(のどれか1つ)を作成する問題」に取組み、最後に、残りの問題を解くなどです。
この流れに限らず、自分流の解き方を見つけ、何度も実践しておきましょう。
使い慣れた電卓を使おう
本番の試験では、計算機(電卓)の持ち込みができます。普段から使い慣れた電卓を使いましょう。余計な機能は不要で、シンプルなものがおすすめです。メモリ機能(M+、M-、RM)や、グランドトータル機能(GT)、00キーがあれば充分です。
なお、機種によっては持ち込みが禁止されていることもあるので、事前にしっかり確認をしておきましょう。
簿記の資格取得に向いている人
簿記3級の資格取得は、就活に活かしたい主婦・学生、商店・中小企業などの自営業の方におすすめ!ダブルライセンスを目指す方にも。
どの級から受ければいいのか迷っている人に向けて、各級ごとに取得に向いている人を紹介します。
簿記3級に向いている人
簿記3級に向いている人は、就活に活用したい主婦・学生、商店・中小企業などの自営業の人などです。宅建士(宅地建物取引士)やFP(ファイナンシャル・プランナー)など他の資格も取得しようとしている人は、簿記3級の資格も取り、ダブルライセンスを目指すとよいでしょう。
簿記2級に向いている人
簿記3級より難易度が高めの簿記2級は、企業の経理や営業部門で活躍したい人、現職でのキャリアアップをはかりたい人などに向いています。試験には、商業簿記と工業簿記の両方の内容が含まれるので、製造業に携わる人にも役立ちます。
簿記1級に向いている人
簿記1級は、税理士・公認会計士を目指している人に向いています。簿記1級では、2級の試験内容に、会計学や原価計算が加わります。より専門性が高い分析や管理が行えるようになるため、就活ではかなり有利となります。
それぞれの試験範囲・難易度・想定勉強時間
簿記1級~3級それぞれの試験範囲・難易度・想定勉強時間は以下の通りです。
試験範囲
| 3級 | 「商業簿記」 |
|---|---|
| 2級 | 「商業簿記」「工業簿記(原価計算を含む)」 |
| 1級 | 「商業簿記」「会計学」「工業簿記」「原価計算」 |
難易度
| 3級 | 基本的に足し算・引き算の組み合わせなので、難易度はさほど高くなく、基本的な計算方法さえ身につければ問題ありません。初学者の方や、「数字が苦手…」という方でも十分に合格が狙えます。 |
|---|---|
| 2級 | 工業簿記は、ものづくりにおける原価計算などの知識が必要です。商業簿記も中小企業の経理業務が行えるレベルに。難易度は3級より格段に上がり、初心者にはハードルが高めの資格です。 |
| 1級 | 商業簿記・工業簿記に加えて会計学・原価計算の知識が求められます。難易度は高く、簿記1級に合格すると税理士試験の受験資格が得られることから、国家資格への登竜門とも呼ばれます。 |
想定勉強時間
| 3級 | 約100時間(3ヵ月程度) |
|---|---|
| 2級 | 簿記3級の知識がある場合:150~350時間(4~6ヵ月程度) 簿記初心者の場合:350~500時間(6~8ヵ月程度) |
| 1級 | 独学の場合:1,000~2,000時間 通学・通信講座を利用した場合:500~800時間 |
改定された日商簿記3級の対策
2019年6月の簿記3級出題範囲の改定。追加・削除された項目をしっかり押さえて万全な対策を。「株式会社」を意識した学習も必須!
簿記3級は、2019年6月に出題範囲の改定が行われました。使用する教材・学習内容・出題範囲の変更点についての対策を解説します。
独学する人は使用する教材に気をつけよう
独学で合格を目指す場合は、使用する教材選びに気をつけましょう。参考書は必ず、改定後の出題範囲に対応した最新版を選んでください。
また、過去問題集についても、改定前の出題範囲となっている場合があります。範囲外の過去問で時間を浪費しないよう、事前の確認が大切です。
「株式会社」を意識した学習をしよう
改定前の簿記3級では、「個人商店」を意識した問題が出題されていましたが、2019年6月から「小規模な株式会社」に改定されています。株式会社を意識した学習を行いましょう。
実務を重視して追加された内容
改定前の簿記3級試験では、実際の実務に即していない内容が数多くありましたが、改定後はより実務を重視した内容が追加されました。今回の改定で追加された内容は、以下の通りです。
- 株式会社の設立
- 剰余金の配当
- 増資
- 債権の譲渡
- 純損失の繰越利益剰余金勘定への振替
- 法人税・住民税及び事業税
簿記3級の試験から削除された内容
今回の改定により、簿記3級の試験から削除された内容を紹介します。
実務に即さない内容として削除されたもの
- 繰越試算表
- 6桁精算表
- 当座借越勘定を使った期中処理
- 資本の引き出しに関する処理
- 売上値引、仕入値引
- 消耗品購入時の資産処理
- 「見越し」「繰延べ」という表現など
個人商店特有の内容として削除されたもの
- 個人商店を前提とした資本金・引出金の処理
- 所得税
- 純損益の資本金勘定への振替
2級以上に繰り上げとなった内容
- 有価証券の購入・売却
- 減価償却の直接法
- 手形の裏書譲渡・割引など
重要度が高く2級から3級に移行された内容
今回の改定で、実務上の重要度が高いと判断された内容が2級から3級へと移行しています。3級に移行された主な内容は以下の通りです。
- 電子記録債権
- 電子記録債務
- クレジット売掛金
- 月次決算
- 貯蔵品処理
まとめ
簿記3級は、さまざまな資格への足がかりともなる資格です。比較的取得しやすい初心者向けの資格なので、しっかりと学習計画を立てて臨めば合格できるでしょう。ただし、独学の場合には、参考書の選び方が非常に重要なポイントとなります。参考書を選ぶ際は、2019年6月に出題範囲が改定されていることに留意して選ぶようにしましょう。
厳選されたテキストを使い、効率的な学習が行える通信講座もおすすめの勉強方法です。ユーキャンの簿記3級講座では、簿記初学者でも3カ月での合格を目指せます。出題傾向を徹底的に分析し作られたテキストを使用しているので効率的ですし、わからないところを講師に質問できるなど、合格のためのサポートも充実しています。スムーズに合格したい人は、ぜひ通信講座の受講も検討してみましょう。

- この記事の監修者は生涯学習のユーキャン
-
1954年設立。資格・実用・趣味という3つのカテゴリで多岐に渡る約150講座を展開する通信教育のパイオニア。気軽に始められる学びの手段として、多くの受講生から高い評価を受け、毎年多数の合格者を輩出しています。
近年はウェブ学習支援ツールを拡充し、紙の教材だけでは実現できない受講生サポートが可能に。通信教育の新しい未来を切り拓いていきます。
よくある質問
- 簿記3級を独学で取得するのは難しいですか?
-
簿記3級は、しっかり学習計画を立てれば、独学でも合格を目指せる資格です。簿記の中では比較的難易度が低い入門的な資格ですが、独学では勉強をやり遂げる強い意志が求められます。また、勉強時間の確保と最適なテキスト選びも重要なポイントです。
- 簿記3級の合格率は?
-
日商簿記3級の合格率は40~50%と高く、難易度は比較的低いといえます。 簿記3級の受験者は簿記検定を初めて受ける人が多く、その中で2人に1人は受かる傾向にあります。
- 簿記3級合格に必要な勉強時間は?
-
日商簿記3級の合格には、約100時間の勉強時間が必要といわれます。1日約3〜4時間勉強すれば1ヵ月程度で合格を目指せます。実際は、1日約2〜3時間で3ヵ月程度、または1日30~60分で4~5ヵ月程度の学習スケジュールで試験に臨む方が多いようです。
簿記3級講座

ユーキャンの簿記3級講座は、過去10年間で1万人以上の合格者を輩出。
添削・質問などのサポート体制も万全で、わずか3ヵ月でムリなく合格が目指せます。
当講座には、着実に合格力が身につくヒミツが満載!選ばれる5つの理由をぜひご覧ください。
簿記とは、帳簿をつけるために必要な技能のこと。実務で役立つ経理、会計の基礎知識が習得できるので、会計や財務の知識を得ようというときの、はじめの一歩にぴったりの資格。将来的に、簿記2級へとステップアップも見込めるため、経理・会計のスペシャリストへの第一歩になる資格です。
簿記の有資格者はニーズが安定しているので、職・転職が有利に!資格は生涯有効なので、出産・子育て後の再就職にも役立ちます。
ユーキャンの「簿記3級講座」では、簿記の基本となる仕訳を中心に学び、書き込み形式の演習でトレーニング。初学者にもやさしいテキストや嬉しいサポートで、ムリなく合格が目指せます。