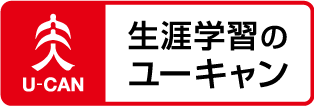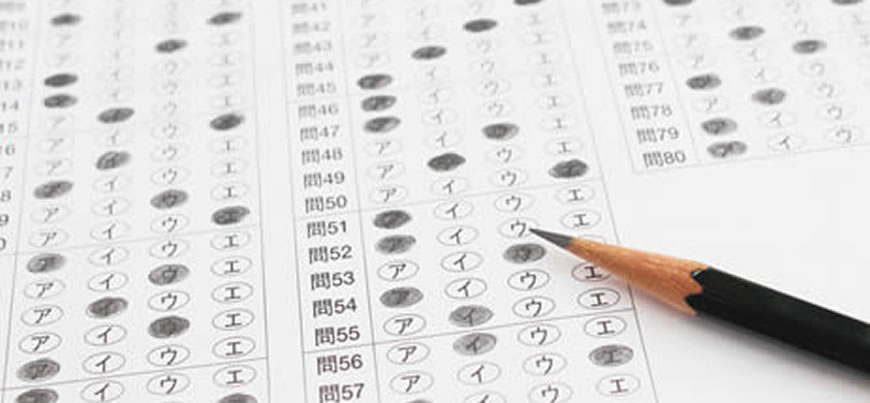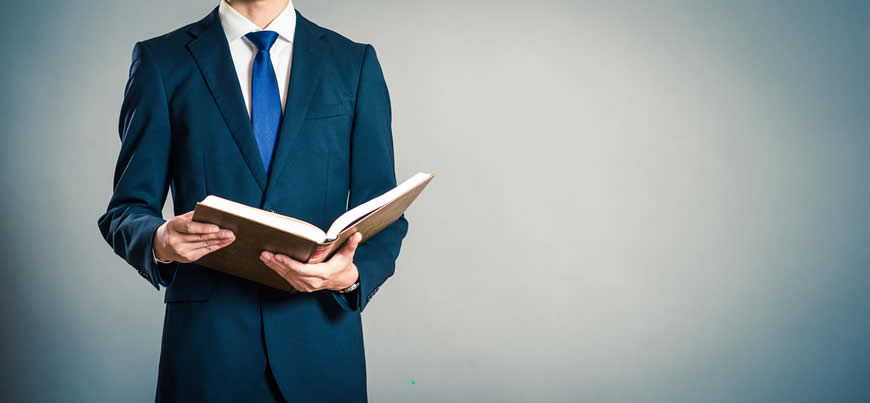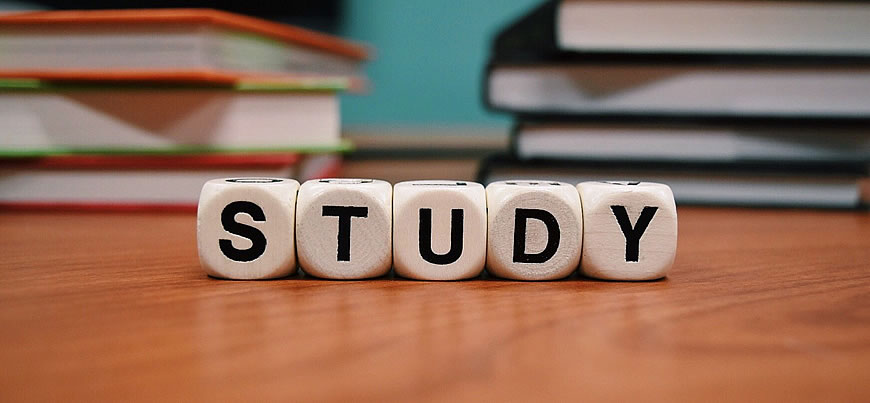社労士の合格率は6~7%?その理由と効率的な勉強のコツを解説!

社労士の試験は合格率が低いため、一般的に難しいイメージがあります。そのため、合格するには、コツを押さえてしっかり勉強に取り組まなければなりません。試験の難易度は、具体的にはどの程度なのでしょうか。
この記事では、社労士試験の概要から勉強方法までを網羅的に解説します。社労士を目指している人は、ぜひ参考にしてください。
このページを簡潔にまとめると・・・
- 社労士(社会保険労務士)は、社会保険労務士法に基づく国家資格。
- 社労士試験は科目数が多く出題される範囲が非常に広い。合格率は平均6~7%程度と難易度が高く、計画的な学習が必要。
- 社労士試験の合格に必要な勉強時間は、700~1000時間程度が目安。
- 社労士試験対策のコツは、「通信教育を上手に活用する」「参考書を理解し、問題集を繰り返す」「余裕ある学習スケジュールを立てる」など。
- ユーキャンの社会保険労務士講座はこちら
社労士試験の合格率
社労士試験の合格率は年度によってばらつきがあるものの、平均6~7%程度となっています。毎年の受験者数はおよそ4万人であり、そのうちの2000~3000人程度が合格しています。
特に最近は合格率が低めになっており、令和4年度が5.3%、令和5年度が6.4%、令和6年度が6.9%でした。平成27年度の合格率はわずか2.6%でした。ここまで合格率が低くなることは稀ですが、近年の合格率については6%程度と捉えておいたほうがよいでしょう。
社労士の試験の合格率は決して高いとはいえないため、受験するならしっかりとした対策が必要です。
社労士試験の受験者数・合格者数・合格率の推移
| 試験年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 43,421人 | 2,376人 | 5.47% |
| 2024年(令和6年) | 43,174人 | 2,974人 | 6.89% |
| 2023年(令和5年) | 42,741人 | 2,720人 | 6.36% |
| 2022年(令和4年) | 40,633人 | 2,134人 | 5.25% |
| 2021年(令和3年) | 37,306人 | 2,937人 | 7.87% |
| 2020年(令和2年) | 34,845人 | 2,237人 | 6.42% |
| 2019年(令和元年) | 38,428人 | 2,525人 | 6.57% |
| 2018年(平成30年) | 38,685人 | 2,613人 | 6.75% |
| 2017年(平成29年) | 38,685人 | 2,613人 | 6.75% |
| 2016年(平成28年) | 39,972人 | 1,770人 | 4.43% |
年齢別の社労士試験の合格率
令和7年度(2025年度)実施、第57回社労士試験の合格者の年齢別割合は、以下の通りです。
年齢別構成を見ると、30歳代が最も多く32.5%、次いで40歳代が27.5%、50歳代が18.9%となっています。20歳代以下は12.7%で、60歳代以上は8.4%と少数です。
また、合格者の最年少者は19歳、最年長者は78歳と幅広い年齢層からの受験がありました。
| 年代 | 合格率 |
|---|---|
| 20歳代以下 | 12.70% |
| 30歳代 | 32.50% |
| 40歳代 | 27.50% |
| 50歳代 | 18.90% |
| 60歳代以上 | 8.40% |
職業別の社労士試験の合格率
令和7年度(2025年度)実施、第57回社労士試験の合格者の職業別割合は、以下の通りです。
会社員が58.4%と最も高い割合を占めています。次いで無職が15.6%、公務員が6.9%、団体職員が4.6%、自営業が4.2%となっています。職業の多様性はあるものの、会社員が中心となっている傾向が見られます。
社労士は難関資格の一つですが、働きながらでも資格合格を目指すことができる資格であることがうかがえます。
| 職業 | 合格率 |
|---|---|
| 会社員 | 58.4% |
| 公務員 | 11.7% |
| 無職 | 11.0% |
| 団体職員 | 4.8% |
| 自営業 | 3.6% |
| 役員 | 2.8% |
| 学生 | 1.1% |
| その他 | 6.6% |
社労士と他資格の難しさの比較
社労士の試験は、ほかの士業と比べてどの程度の難易度なのでしょうか。ここでは、社労士とほかの資格の難易度について比較を交えて紹介します。
司法書士
司法書士は、主に登記や供託の手続きを扱うことのできる資格です。弁護士ならすべての法律に関する手続きに対応できますが、司法書士はその一部のみを扱うことができます。よって、司法書士の試験では、主に民法や商法などの知識が問われ、社労士の試験のように労働者に関する知識はあまり問われません。
司法書士の試験は司法試験にも匹敵するほど難しいといわれています。合格までにかかる期間も、5年以上が平均で、社労士よりも司法書士のほうが難易度は高いといえます。ちなみに司法書士の試験の合格率は約3%です。
税理士
税理士は、税に関する手続きをおこなうための資格です。税理士の資格があれば、税務や確定申告を代理することもできます。
税理士の試験では、会計や税法に関する科目が出題されます。全11科目のうち5科目に合格すれば、税理士の資格を得ることが可能です。実践的な計算問題が出題されることや論理的な思考を必要とすることから、税理士の試験は難易度が高いといわれています。
税理士は税務に特化した資格であるのに対し、社労士は労働者の手続きに特化した資格です。社労士の試験においても、労働者に関する税の知識が問われる可能性はありますが、それはごく一部です。社労士は暗記や法令の解釈を理解することで試験合格を目指せるため、税理士に比べると難易度は低いでしょう。
行政書士
行政書士は、公的な書類を作成するための資格です。官公庁に提出するための書類を作成したり、契約書の作成を代理でおこなったりできます。行政書士が作成できる書類は1万種類以上あるので、さまざまな場面で活躍できる可能性があるでしょう。
また資格試験では、労働者に関する手続きを試験範囲とする社労士とは異なり、行政書士の試験では、憲法や行政法などの法令とともに政治や経済に関する一般常識が問われます。
行政書士の試験の難易度は、社労士の試験と比べるとやや低いです。ただし、試験内容はまったく異なるため、人によって感じ方は違うかもしれません。また、それぞれ別の試験対策が必要となります。
社労士試験が難しい理由
社労士試験は、なぜ難しいといわれているのでしょうか。ここでは、社労士試験の難易度が高いといわれる理由についてみてみましょう。
試験範囲がとても広い
社労士試験の特徴として、試験範囲が広いことがあげられます。ひと口に「労働法」といっても、たとえば労働基準法と労働者災害補償保険法などさまざまな法律があり、当然ながら法律によって内容や手続きは異なります。社労士試験に合格するためには、それらすべてについてしっかりと対策しなければなりません。
労働法以外にも、社会保険に関する健康保険法や国民年金法など複数の法律に関する問題が出題されます。加えて、労働者に関わる一般常識的な知識も問われるため、社労士試験のために覚えなければならないことは膨大です。
勉強時間の確保が難しい
社労士試験は、社会人が受験することが多く、実際に合格者の内訳をみると半分以上が会社員となっています。会社に勤めながら勉強するのは、想像以上に大変なことです。これから社労士試験の受験を考えている人の中には、すでに会社と家の往復だけでヘトヘトになっている人もいるのではないでしょうか。
社労士試験に合格するためには、700~1000時間程度の勉強が必要だといわれています。社会人の場合、これほどの勉強時間を働きながら確保するのは大変です。休日だけでなく平日も勉強時間を確保しなければ、合格ラインに到達するのは厳しいでしょう。
社労士試験の勉強のコツ
社労士試験に合格するためには、どのような勉強をしたらいいのでしょうか。社労士試験の勉強のコツを紹介します。
通信教育を上手に活用する
社労士試験に合格するためには、通信教育を上手に活用するのがおすすめです。独学でも社労士試験の合格は目指せますが、通信教育を活用した場合に比べると時間がかかるケースが多いです。通信教育ではプロの指導により重要なポイントをスムーズに理解できるため、時間のない社会人でも効率的に勉強できます。
社労士試験の合格者の約9.8人に1人はユーキャンの社会保険労務士講座を利用しています。すでに30年以上の開講実績があるため、信頼度も高いです。また、ユーキャンの通信教育を活用すれば法改正に関する最新の情報も入手できるので、確実な試験対策が可能です。
参考書を理解し、問題集を繰り返す
社労士試験の対策では、最初にしっかりと参考書の内容を理解することが大切です。初めて社労士の勉強を始める場合、法律の独特の言い回しが難しく感じられることもあります。そのため、参考書を一度読むだけでは理解できない部分もあるでしょう。そういった部分は何度も参考書を読み返したり、言葉を噛み砕いて把握したりして、確実に理解する必要があります。
参考書の内容をしっかり理解できた後は、問題集を繰り返し解いていきます。演習問題に慣れたら、過去問を解いて実際の出題形式にも慣れておきましょう。解けなかった問題は自力で解けるようになるまで繰り返し、確実に解答できるようにしてください。
勉強計画を立てる
社労士試験に合格するためには、試験に向けて計画的に勉強する必要があります。社労士試験は毎年8月の第4週におこなわれるので、そのあたりを目指して勉強計画を立てましょう。本格的な勉強を開始する時期としては、前年の11月頃が無理のない期間でおすすめです。そこから約9ヶ月をかけてしっかりと準備をし、試験合格を目指しましょう。
都合により11月頃から勉強を開始できない場合でも、なるべく早い段階から勉強できるような計画を立てる必要があります。最低でも700時間は勉強できるようにし、できるだけ余裕のあるスケジュールを立てましょう。早い段階である程度の知識を身につけられていれば、試験直前になって慌てる必要もなくなります。
まとめ
社労士の試験は難易度が高いため、計画的な学習が必要です。例えば通信講座を上手く活用し、着実に理解を深めていけば、社労士の試験に合格できるレベルに到達できるでしょう。
ユーキャンの社会保険労務士講座では、過去10年間で1,801名の合格者を輩出した高い実績と、30年以上の開講実績があり、効率的に社労士の勉強を進めることができます。また、ユーキャンは初心者にとっても分かりやすい解説をしているので、これから社労士の勉強をスタートさせたい人にぴったりです。
また、頻繁におこなわれる法改正の情報もしっかりフォローしてくれるので、受験対策も万全です。資料請求は無料なので、ぜひお試しください。早めの準備をして、社労士試験の合格を目指しましょう。
- 合格者数は、当講座受講生へのアンケートに回答された方で、実際に合格された方、および合格のお知らせを下さった方の数値です。(2024年8月現在、当社調べ)

- この記事の監修者は生涯学習のユーキャン
-
1954年設立。資格・実用・趣味という3つのカテゴリで多岐に渡る約150講座を展開する通信教育のパイオニア。気軽に始められる学びの手段として、多くの受講生から高い評価を受け、毎年多数の合格者を輩出しています。
近年はウェブ学習支援ツールを拡充し、紙の教材だけでは実現できない受講生サポートが可能に。通信教育の新しい未来を切り拓いていきます。
よくある質問
- 社労士が独立開業するには?
-
通常、社労士として独立開業するには2年以上の実務経験が必要です。
2年未満で開業する場合は、事務指定講習の受講により可能となります。講習後、「社労士名簿に登録」と「税務署に開業届を提出」の手続きを行います。
社労士として独立開業するメリットは、自分の裁量で働けたり、働き方や頑張り次第で高収入が目指せること。仕事を確保できないと収入が不安定な点はデメリットといえます。このため、仕事を得る営業力が不可欠で、集客にはネットの活用やセミナー開催も有効です。 - 社労士と相性が良く、メリットが大きいダブルライセンスとは?
-
社労士とのダブルライセンスに相性のよい資格には、「ファイナンシャルプランナー(FP)」「行政書士」「中小企業診断士」「司法書士」「個人情報保護士」「メンタルヘルス・マネジメント(R)検定」「税理士」「キャリアコンサルタント」「司法試験」「人事総務検定」などが挙げられます。
社労士はさまざまな資格と組み合わせることでキャリアアップできます。 - 社会保険労務士(社労士)の仕事とは?
-
社労士は社会保険や年金、労務管理をあつかう専門家。複雑化する年金などの社会保障制度を、円滑に活用できるよう手助けします。
また、経営者と労働者がよい関係を結ぶために雇用問題にも対応します。
社労士の仕事は具体的には、大きく次の3つに分けられます。
・手続き代行(1号業務)
・労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成(2号業務)
・人事労務管理のコンサルティング(3号業務)
このうち、1号業務、2号業務は社労士しか行うことができない「独占業務」です。
社会保険労務士講座

過去10年間でなんと1,801名もの合格者を輩出してきたユーキャンの社労士講座!
動画とテキストを活用し、徹底的に絞り込んだカリキュラムで最短距離での合格を目指していただけます。
質問サービス、添削、法改正情報のお知らせなど……、サポート体制も充実!
社会保険労務士(社労士)は、労働問題や年金問題、社会保険のエキスパート。社労士試験には、受験資格があります。次の代表的な受験資格(学歴・実務経験・試験合格・過去受験)のいずれかを満たす必要があります。まずは「学歴」です。1)大学、短大、高専(高等専門学校)等を卒業した方、2)4年制大学で、62単位以上を修得した方又は一般教養科目36単位以上かつ専門教育科目等の単位を加えて合計48単位以上を修得した方、3)修業年限が2年以上、かつ、課程修了に必要とされる総授業時間数が1,700時間(62単位)以上の専修学校の専門課程を修了した方などと定められています。次に「実務経験」における主な要件は、「法人の役員または従業員(いずれも常勤)として、通算3年以上事務に従事した方」などです。また、「試験合格」「過去受験」における主な要件として、行政書士試験や厚生労働大臣が認める国家試験の合格者及び直近の過去3回のいずれかの社労士試験の受験票又は成績(結果)通知書を所持している方などにも受験資格が与えられます。