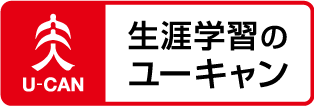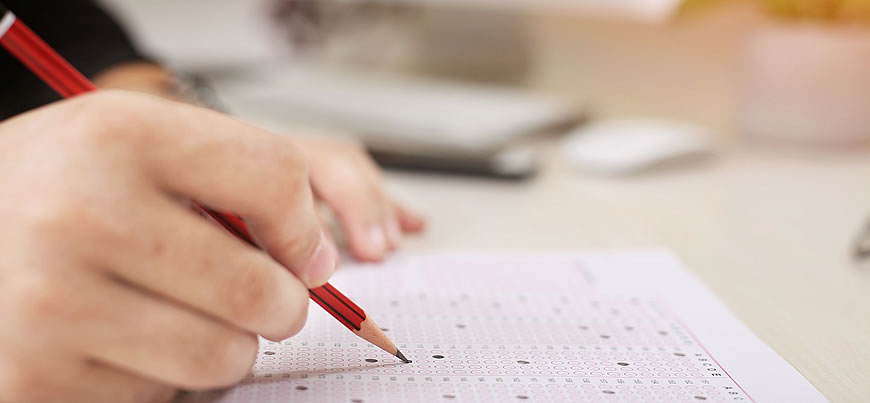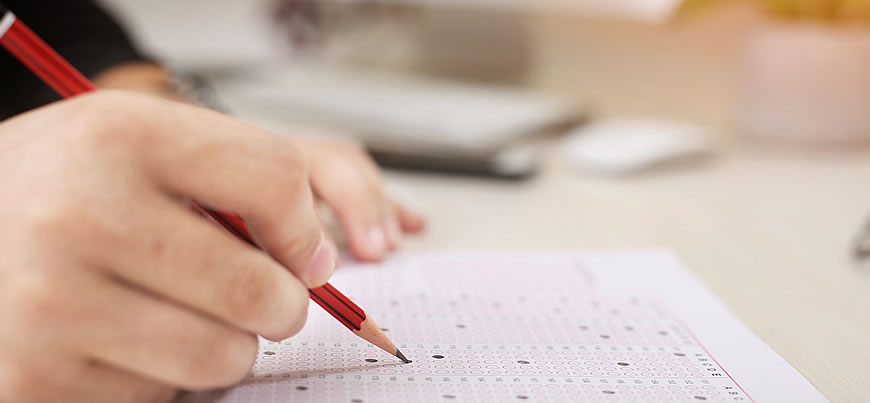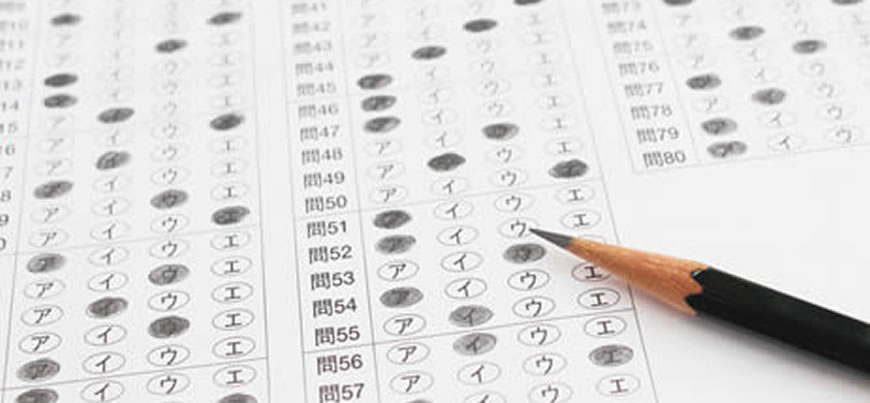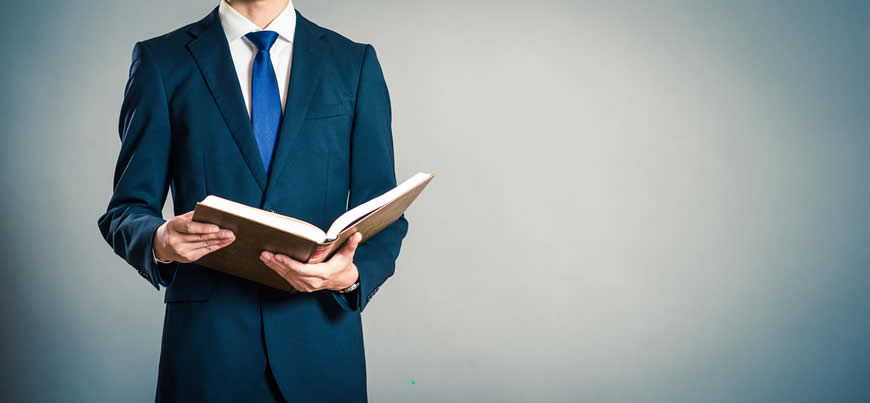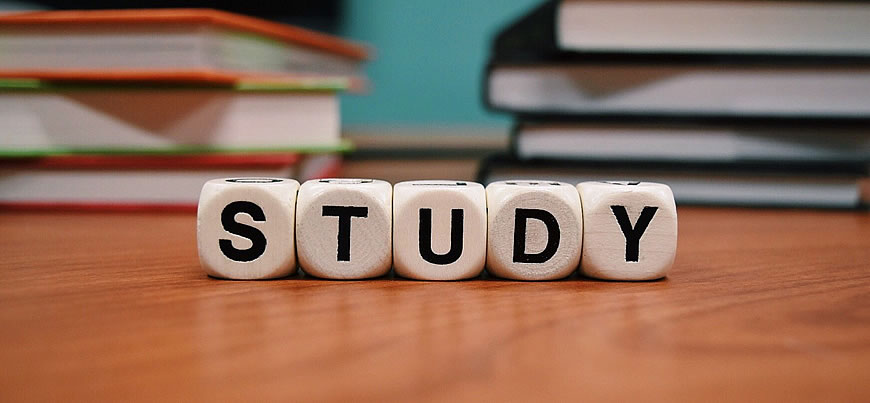- 社会保険労務士講座 もっと詳しく
社労士試験の合格基準は?試験科目まで解説!

- 更新日:2026/01/27
近年、注目度が高まってきている「社会保険労務士(社労士)」は就職や転職が有利になるだけでなく、学ぶことで得られる「年金」や「健康保険」の知識を自身のライフプランに活かせると勉強する人が増えています。さらには、合格者の3割は女性で、法律系の国家資格としてはかなり高い数値となっています。
この記事では、気になる社会保険労務士の合格基準、試験内容、合格率について解説します。資格取得を検討する際の参考として、ぜひ役立てて下さい。
このページを簡潔にまとめると・・・
- 社労士の試験問題のうち約90%が法令に関する出題。
- 社労士に関わる法律は「労働基準法」「雇用保険法」「健康保険法」など20種類以上。
- 法改正の頻度が高く、出題される可能性も高いため、最新の参考書で学習することが重要。
- 合格基準点は、採点結果が出てから決まる。合格ラインは各科目が最低40%、全体で60~70%以上の正解率が目安。
- 難易度が高いため、通信講座などを活用し、効率的な学習が望ましい。
- ユーキャンの社会保険労務士講座はこちら
社労士試験の内容
社労士は、年金や健康保険などの社会保険、労務管理を扱うための知識を学べる資格です。資格試験の出題のうち約90%が法令に関する出題となっています。
社労士資格にかかわる法律は、「労働基準法」「雇用保険法」「健康保険法」など、20種類以上です。なおかつ、改正が頻繁に行われるため、参考書などは最新のものを使用しなければなりません。特に、改定されたポイントは出題される可能性が高いため、要点を押さえておく必要があります。
社労士試験の合格基準点の決め方
社労士資格の合格基準点は、毎年の採点結果が出てから決まります。総得点は平均点に連動し、科目別の基準点は得点の分布に連動しています。
一応、社労士の合格基準点は平成12年度以降、厚生労働省によって次のように定められています。
- 選択式試験総得点40点中28点以上、かつ各科目5点中3点以上
- 択一式試験総得点70点中49点以上、かつ各科目10点中4点以上
しかし、年度ごとの出題難易度は変わるため上記基準をもとに補正が行われます。ちなみに、第43回以降の「択一式」の総合得点合格基準点は、45点もしくは46点です(平成28年を除く)。そのため、「択一式」の総合得点「合格基準点」は、45~46点前後になる確率が高いと考えてよいでしょう。
社労士試験の合格ラインの目安
社労士試験の合格ラインは、全体の7割の点数を獲得する必要があると考えられます。なおかつ、「択一式」は科目ごとに満点の40%以上、「選択式」では60%以上の点数を獲得しなければなりません。
1科目でも合格基準点に満たない場合は、総合点数が合格ラインにあっても不合格となりますので注意しましょう。
社労士試験の過去の合格基準点
過去5年分の社労士試験の合格基準点を見てみます。
| 年度(回数) | 択一式 | 選択式 |
|---|---|---|
| 令和5年度(第55回) | 45点以上、かつ各科目4点以上 | 総得点26点以上、かつ各科目3点以上 |
| 令和4年度(第54回) | 45点以上、かつ各科目4点以上 | 総得点27点以上、かつ各科目3点以上 |
| 令和3年度(第53回) | 45点以上、かつ各科目4点以上 | 総得点24点以上、かつ労働に関する一般常識1点以上、国民年金法2点以上、その他各科目3点以上 |
| 令和2年度(第52回) | 44点以上、かつ各科目4点以上 | 総得点25点以上、かつ労働に関する一般常識、社会保険に関する一般常識、健康保険法2点以上、その他科目3点以上 |
| 令和元年度(第51回) | 44点以上、かつ各科目4点以上 | 総得点26点以上、かつ社会保険に関する一般常識2点以上、その他科目3点以上 |
- ※出典:厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roumushi/shiken.html)
社労士試験の合格率
社労士試験は毎年4万人前後(過去10年)が受験しており、合格率は平均6~7%となっています。年度によっては5%を下回ることもあります。平成27年に至っては合格率2.6%と厳しい結果になりました。
合格率が低い理由として「試験範囲がとても広いこと」「科目合格制度がないこと」「法改正に都度対応が必要なこと」などがあげられます。
いずれにせよしっかり対策をして試験に臨む必要があります。
まとめ
社労士資格の合格基準や試験内容、合格率について解説しました。出題範囲が広く法改正も頻繁な社労士資格は、通信講座などを活用して効率的に勉強するのが望ましいといえます。
通信講座を選ぶなら、過去10年間で1,944名の合格者を輩出しているユーキャンがおすすめです。ユーキャンでは多くの受講生が学習経験ゼロからスタートしています。30年以上の開講実績を誇り、法改正のたびに知らせてくれるので学ぶポイントが押さえやすいのもユーキャンならではです。ユーキャンを活用して社労士合格を目指しましょう。

- この記事の監修者は生涯学習のユーキャン
-
1954年設立。資格・実用・趣味という3つのカテゴリで多岐に渡る約150講座を展開する通信教育のパイオニア。気軽に始められる学びの手段として、多くの受講生から高い評価を受け、毎年多数の合格者を輩出しています。
近年はウェブ学習支援ツールを拡充し、紙の教材だけでは実現できない受講生サポートが可能に。通信教育の新しい未来を切り拓いていきます。
よくある質問
- 社労士に関する仕事が未経験でも就職できますか?
-
社労士に関する仕事の求人は、資格より実務経験を重視する傾向にありますが、求人によってはまったくの未経験でも応募できるものがあります。また、社労士資格はあくまで歓迎条件であり、他の実務における経験者を求めているケースも少なくありません。
- 社労士と司法書士では、どちらが難しい?
-
合格率は社労士が5~7%程度、司法書士は3%前後。合格に必要な勉強時間は、社労士が1,000時間程度、司法書士は3,000時間超といわれています。
司法書士試験と比較すると、社労士は合格率が高く目指しやすい試験といえますが、それでも難しい試験です。
なお、法律系の試験の中で、司法試験についで難しいのが司法書士試験といわれています。試験科目が多い社労士試験よりさらに科目が多く、択一試験の問題の難易度は司法試験と同レベルといわれています。 - 社労士の受験資格は?
-
社労士試験には、次のいずれかの受験資格の条件を満たす必要があります。
・短大卒と同等以上の学歴がある方
・学歴による受験資格がなくても、一定の実務経験がある方
・行政書士資格を有している方
大学、短大、高専(高等専門学校)を卒業した方であれば「学歴」の条件をクリアできます。
中卒や高卒の方は、「実務経験」「国家試験の合格者」のいずれかを満たすことで受験資格が得られます。
社会保険労務士講座

過去10年間でなんと1,483名もの合格者を輩出してきたユーキャンの社労士講座!
動画とテキストを活用し、徹底的に絞り込んだカリキュラムで最短距離での合格を目指していただけます。
質問サービス、添削、法改正情報のお知らせなど……、サポート体制も充実!
社会保険労務士(社労士)は、労働問題や年金問題、社会保険のエキスパート。社労士試験には、受験資格があります。次の代表的な受験資格(学歴・実務経験・試験合格・過去受験)のいずれかを満たす必要があります。まずは「学歴」です。1)大学、短大、高専(高等専門学校)等を卒業した方、2)4年制大学で、62単位以上を修得した方又は一般教養科目36単位以上かつ専門教育科目等の単位を加えて合計48単位以上を修得した方、3)修業年限が2年以上、かつ、課程修了に必要とされる総授業時間数が1,700時間(62単位)以上の専修学校の専門課程を修了した方などと定められています。次に「実務経験」における主な要件は、「法人の役員または従業員(いずれも常勤)として、通算3年以上事務に従事した方」などです。また、「試験合格」「過去受験」における主な要件として、行政書士試験や厚生労働大臣が認める国家試験の合格者及び直近の過去3回のいずれかの社労士試験の受験票又は成績(結果)通知書を所持している方などにも受験資格が与えられます。