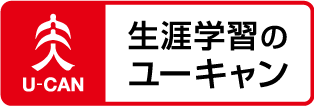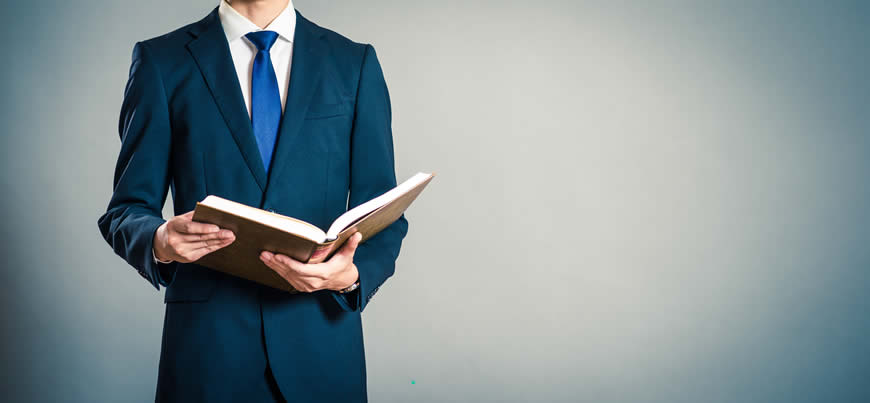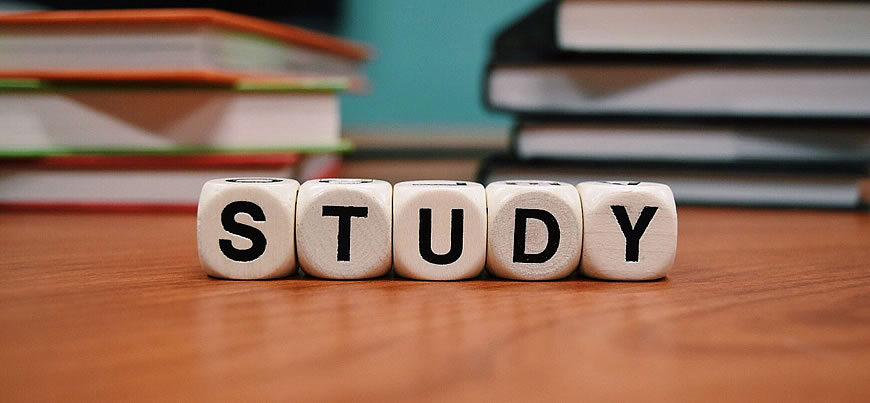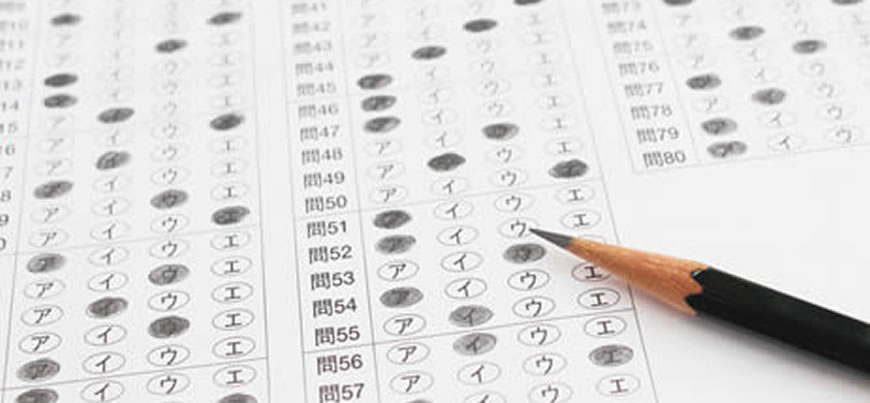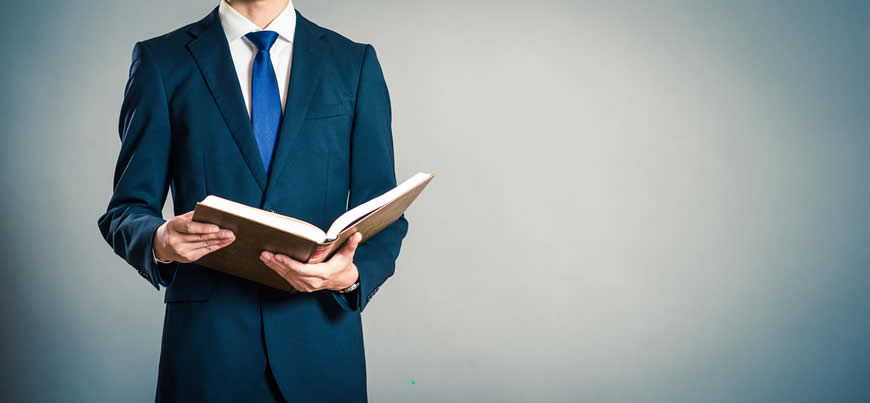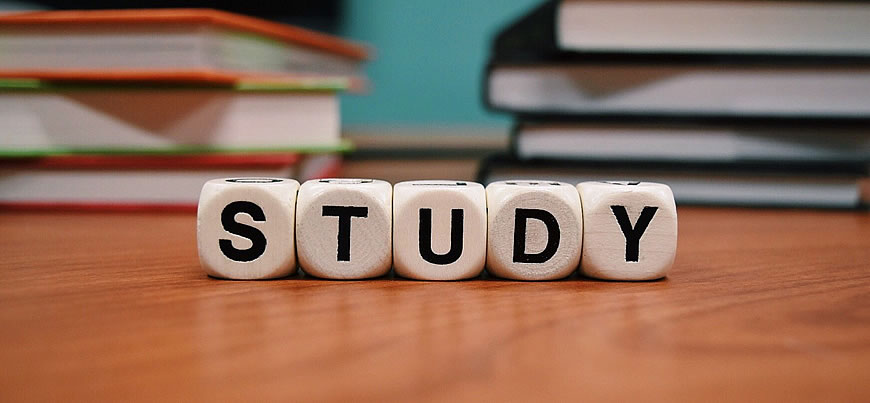- 社会保険労務士講座 もっと詳しく
社労士・社会保険労務士とは?仕事内容・試験概要などを網羅的に紹介

- 更新日:2025/08/20
資格にはさまざまなものがありますが、中でも社労士は人気の資格です。しかし、その仕事内容についてはあまり広く知られていません。
この記事では、社労士の仕事内容や就職先、資格の難易度などについて詳しく解説します。社労士事情を知って、資格取得を目指すための参考にしてみてください。
このページを簡潔にまとめると・・・
- 社労士は、雇用や社会保険、労働問題、公的年金の分野で唯一の国家資格であり、企業からの需要も高い。
- 社労士の仕事は、大きく1号業務、2号業務、3号業務の3つに分けられ、1号業務、2号業務は社労士の独占業務。
- 社労士として働くには、試験に合格し、国家資格を取得する必要がある。
- 社労士試験の合格率は平均6~7%程度の難関資格。試験範囲も広く、計画的なスケジュールで着実な対策が必要。
- ユーキャンの社会保険労務士講座はこちら
社会保険労務士(社労士)とは
社労士とは社会保険労務士の略称で、社会保険や労働関連の法律の専門家として人事や労務管理を行う人のことを指します。
社労士は誰でも就ける職業ではなく、国家資格である社労士資格を取得している人のみが就ける仕事です。雇用や社会保険、労働問題、公的年金の分野では唯一の国家資格となっているため、需要の高い仕事です。
企業の成長には「お金・モノ・人材」が必要です。社労士はその中で人材に関する専門家であり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として、業務を行います。
社労士は、企業において、採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」に応じる人事のスペシャリスト、業務の内容は広範囲にわたります。
社会保険労務士(社労士)の仕事とは
社労士の仕事内容を分かりやすく説明すると、社労士は社会保険や年金、労務管理をあつかう専門家で、複雑化してゆく年金などの社会保障制度を、円滑に活用できるよう手助けをします。また、経営者と労働者がよい関係を結ぶための相談にも応じます。
社会保険労務士(社労士)の仕事は具体的には、1号業務、2号業務、3号業務というおおきく3つの業務に分けられます。
そのうち、1号業務、2号業務は社労士の「独占業務」となっており、社労士にしか業務を行うことができません。
一つ一つについて詳しく解説します。
手続き代行(1号業務)
社労士しか行うことができない独占業務に、1号業務に分類される手続き代行があります。健康保険や雇用保険、厚生年金などに関連する書類を作成し、労働基準監督署などの行政官庁へと提出する代行をする業務です。
これらの仕事を社労士が行うことで、手続きのミスや法律違反を防ぐことができます。企業が従業員との信頼関係を維持するためには大変有効といえるでしょう。
労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成(2号業務)
労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成も、社労士の独占業務となっています。企業においては、就業規則や労働者名簿、賃金台帳などが「労働社会保険諸法令に基づいて作成すべき帳簿書類」にあたり、社労士はこれらを法律にのっとって作成するのです。
法律の知識なしに帳簿書類を作ると、場合によっては法律の範囲を超えてしまう危険性もあるかもしれません。帳簿書類は企業の基本ともいうべき書類のため、法律の専門家である社労士がその作成を請け負うことが多いのです。
人事労務管理のコンサルティング(3号業務)
近年では働き方が多様化し、正社員以外にも契約社員やアルバイトといった形で働く人が多くいます。それに伴い、人事労務の問題も複雑化し、会社内では解決が難しい場面もあります。その際に活躍するのが社労士で、専門家の立場からコンサルティングを行います。
3号業務である人事労務管理のコンサルティングは、社労士の独占業務ではないものの、難しい判断が必要となるケースも多くあり、プロである社労士の出番となるのです。
社労士の仕事のやりがいは?
社労士は、労働者の正当な権利を守る助けをすることで多くの人の役に立つ仕事です。法律などの専門的な知識を駆使することで、知識を持たない労働者のサポートをする、社会的責任の大きな仕事です。
また、さまざまな立場の人や職業の人とコミュニケーションを取ることができる点もやりがいの1つといえます。この経験を通して培ったコミュニケーション力は、プライベートでも仕事でも、自分にとって大きなプラスとなることでしょう。
社労士の仕事に必要なことは?
社労士の仕事は、勉強をし続けなければならないという特徴があります。法律に関わるという仕事柄、頻繁に行われる法改正についてはしっかり対応していかなければなりません。仕事をする限り常に勉強がセットとなることについては、社労士ならではの大変さがあるかもしれません。
社会保険労務士(社労士)の将来性とは
深刻化する人材不足や働き方改革などの影響により、就業規則や賃金体系を見直そうと考える企業が増えています。また、雇用問題も複雑化しており、高度な人事労務問題に対応するために、専門知識を有する社労士の需要は高まるといえるでしょう。
ただし、社労士資格を取得する人は年々増えているため、資格を取得するのみならず、スキルなどを磨くことで顧客からの信頼を得る必要も出て来る可能性があります。
社会保険労務士(社労士)の就職先とは
社労士の就職先としては「社労士事務所」が浮かぶかもしれませんが、それ以外にも「企業の人事総務部門」や「他の士業の法律事務所」も挙げられます。
しかし、いずれも求人数はあまり多くはありなく、社労士として独立して、事務所を開業することも選択肢の1つです。資格を取得し全国社会保険労務士会連合会に登録することで、独立開業への道を進むことができるようになります。
社会保険労務士(社労士)の給与とは
社労士の平均年収は、500万円程度とされています。しかし、勤めている企業の規模や個々の経験などによって金額は異なります。そのため、平均はあくまでも平均値であり、一概に給与額を提示できるものではありません。
中には、開業することで年収1000万円超えという社労士も存在します。また、男女における賃金格差は少なく、女性でも年収500万円やそれ以上をめざすことも十分に可能となっています。
社会保険労務士(社労士)に必要な適性は
社労士は、多くの事務作業を処理しなければなりません。複雑な作業を正確に進めるために、1つ1つの仕事を丁寧に仕上げていく能力が求められます。また、月々の健康保険料の計算なども業務となるため、計算能力も不可欠です。
さらに、経営や労働問題のコンサルティングを行う際には、事業主と対等にはなし説得をする、コミュニケーションスキルも求められます。
社会保険労務士(社労士)になるには
社労士として働くには、社会保険労務士試験に合格して国家資格を取得する必要があります。例年8月に行われる社会保険労務士試験は、完全マークシート方式ですが、科目ごとに一定の点数に満たない場合はその場で不合格となる合格基準点が設定されているため、平均的に幅広く学習しなければなりません。
合格率は、令和6年度が6.9%ですが、低い年度には2%台となることもありました。合格率は高くないものの、満点を狙う必要はなく、全体の6~7割の点数を獲得すれば合格できるといわれています。これをクリアできるように学習計画を立てましょう。試験に合格したら全国社会保険労務士会連合会への登録をすることで、社労士になることができます。
社会保険労務士(社労士)試験の試験概要
| 受験時期 | 毎年1回・例年8月の第4日曜日 |
|---|---|
| 受験資格 | 次のいずれかに該当している方 ・短大卒と同等以上の学歴がある方 ・学歴による受験資格がなくても、一定の実務経験がある方 ・行政書士資格を有している方 |
| 試験内容 | ・労働基準法及び労働安全衛生法 ・労働者災害補償保険法 ・雇用保険法 ・労務管理その他の労働に関する一般常識 ・社会保険に関する一般常識 ・健康保険法 ・厚生年金保険法 ・国民年金法 |
| 受験手続 | 例年4月中旬以降に、関係機関より受験案内が配布されますので、各自ご請求のうえ、所定の期間内(例年5月末頃まで)に受験手続をとることが必要です。 |
| 試験形式 | 選択式:40問、択一式:70問 |
| 受験料 | 15,000円 |
| 試験実施団体 | 全国社会保険労務士会連合会試験センター |
令和7年度 受験のスケジュール
-
試験詳細の公表
4月 -
受験申込の受付
4月14日(月)~5月31日(土) -
試験日
8月24日(日) -
合格発表
10月1日(水)
合格発表は、例年は11月の上旬に行われます。前年度と同様、令和7年度は10月1日と例年よりおよそ1か月弱早い発表となります。
社会保険労務士(社労士)試験の難易度
社労士試験の合格率は年度によってばらつきがあるものの、平均6~7%程度です。決して高い合格率とはいえず、難関資格として知られており、合格に向けてしっかりとした対策が必要です。
試験範囲も広く合格するためには700~1000時間程度の勉強が必要だと言われています。
社会保険労務士(社労士)に必要な勉強時間
前述の通り、社労士試験の合格までに必要な勉強時間は700~1000時間程度です。
しかし、1,000時間勉強すれば必ず合格できるとは限りませんので、目安として考えるとよいでしょう。
社労士試験の勉強はいつから始めるの?
社労士の試験は年に1回、8月の第4日曜日に実施されます。
1日の勉強時間により、始める時期が変わるので、前述の1000時間を基に試験日から逆算した計画を立てましょう。
たとえば、1日2時間の勉強であれば、1,000時間÷2時間=500日≒約1年4ヶ月半必要となり、受験する前年の4月中旬が開始時期となります。
ご自身のライフスタイルに合わせて長期的な計画を立てることが大切です。
社会保険労務士(社労士)になるための勉強方法
社労士試験の合格に向けて大切なことは、根気よく何度も繰り返すことです。
参考書や問題集の分からないところをしっかりと理解するまで、何度も繰り返して勉強することが合格への第一歩です。
おすすめの参考書って?
問題集と参考書は、それぞれが連動していることがほとんどです。
そのため別々に購入するのではなく、同じ予備校・塾のものを選ぶことで、より学習の効率が良くなります。
また、予備校や塾によって参考書の特長は様々です。
例えば、ユーキャンなら、六法全書や参考書を必要としない「1冊徹底主義」で作られています。たくさんの本を行き来しなくても、テキストだけでわかりやすくまとめられているのが特長です。
まとめ
社労士の仕事は、さまざまな企業から必要とされる重要なものです。社労士しか行うことができない独占業務もあるため、多くの企業からの需要が見込まれる資格といえるでしょう。
社労士になるためには、国家試験に合格する必要があります。ユーキャンの「社会保険労務士講座」は、開講から30年以上の実績のある講座です。法改正の際も都度お知らせが来るので、最新の情報で効率的な勉強ができます。社労士試験対策をするのならば、ユーキャンの社会保険労務士講座を検討してみてはいかがでしょうか?

- この記事の監修者は生涯学習のユーキャン
-
1954年設立。資格・実用・趣味という3つのカテゴリで多岐に渡る約150講座を展開する通信教育のパイオニア。気軽に始められる学びの手段として、多くの受講生から高い評価を受け、毎年多数の合格者を輩出しています。
近年はウェブ学習支援ツールを拡充し、紙の教材だけでは実現できない受講生サポートが可能に。通信教育の新しい未来を切り拓いていきます。
よくある質問
- 社労士試験の難易度は?
-
社労士試験は、合格率は約5~7%と低く、試験内容を見ても難易度が高いことでも有名です。 具体的には社労士の難易度はFP1級、宅建士、行政書士よりは高く、税理士や司法書士よりは比較的易しいと言われています。
- 社労士試験は記述式ですか?
-
試験は記述式ではなく、全てマークシート形式で行われます。
「労働関係」と「社会保険」のジャンルから全8科目が出題され、選択式の問題と択一式の問題で構成されます。各科目で合格基準点が設定されているため、全科目で合格点を取るための勉強が必要です。 - 社労士試験は独学でも目指せますか?
-
独学でも社労士試験の合格は目指せますが、試験範囲が広く、合格率が一桁など難易度が高いため、独学では合格が難しい資格試験のひとつです。
通信教育やスクールを活用した場合に比べると時間がかかるケースが多いです。
社会保険労務士講座

過去10年間でなんと1,483名もの合格者を輩出してきたユーキャンの社労士講座!
動画とテキストを活用し、徹底的に絞り込んだカリキュラムで最短距離での合格を目指していただけます。
質問サービス、添削、法改正情報のお知らせなど……、サポート体制も充実!
社会保険労務士(社労士)は、労働問題や年金問題、社会保険のエキスパート。社労士試験には、受験資格があります。次の代表的な受験資格(学歴・実務経験・試験合格・過去受験)のいずれかを満たす必要があります。まずは「学歴」です。1)大学、短大、高専(高等専門学校)等を卒業した方、2)4年制大学で、62単位以上を修得した方又は一般教養科目36単位以上かつ専門教育科目等の単位を加えて合計48単位以上を修得した方、3)修業年限が2年以上、かつ、課程修了に必要とされる総授業時間数が1,700時間(62単位)以上の専修学校の専門課程を修了した方などと定められています。次に「実務経験」における主な要件は、「法人の役員または従業員(いずれも常勤)として、通算3年以上事務に従事した方」などです。また、「試験合格」「過去受験」における主な要件として、行政書士試験や厚生労働大臣が認める国家試験の合格者及び直近の過去3回のいずれかの社労士試験の受験票又は成績(結果)通知書を所持している方などにも受験資格が与えられます。