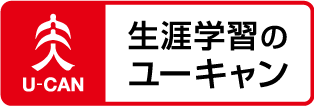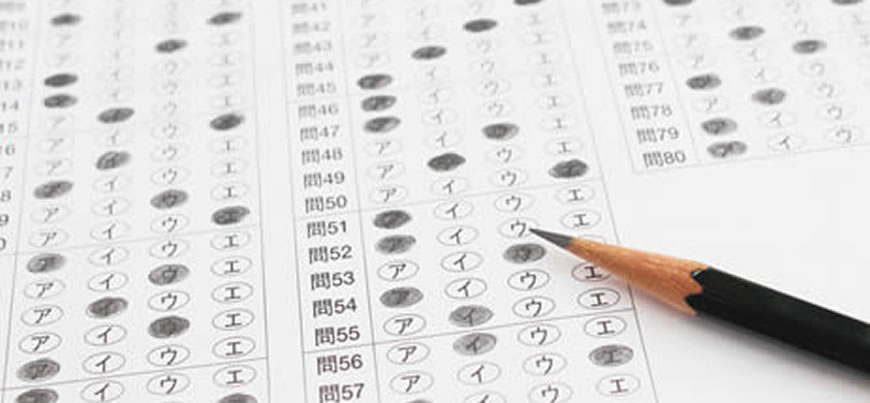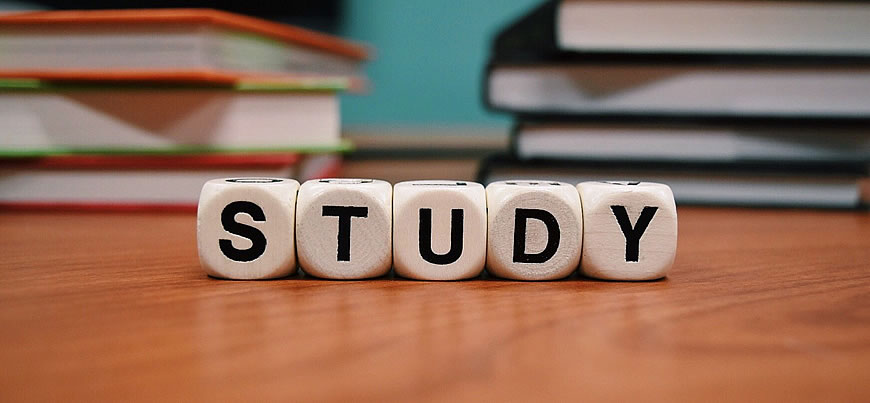- 社会保険労務士講座 もっと詳しく
社労士の勉強時間は?いつから開始すべきかや合格を早めるポイントも解説
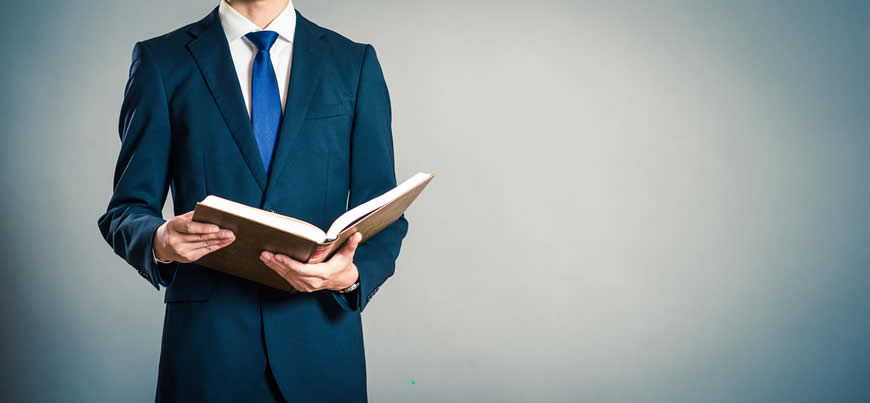
- 更新日:2025/08/21
社会保険労務士(社労士)試験における令和6年の合格率はわずか6.9%です。受験した人の平均受験回数が4〜5回ということからも、難易度が高いことがうかがえます。
しかし、合格後のキャリアを考えると、できるだけ短い期間で合格したいと考える方も多いでしょう。この記事では、社労士試験に合格するために必要な勉強時間や、勉強の開始時期について解説します。受験資格や合格するためのポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
このページを簡潔にまとめると・・・
- 社労士試験の合格に必要な勉強時間の目安は1,000時間以上といわれている。
- 仮に試験の10ヵ月前から勉強を始める場合、毎日の学習時間は3時間20分が目安。
- 各科目に合格基準点が設定され、各科目7割の正解を目指すのがポイント。
- 受験科目は7~8科目。それぞれ内容が膨大で細かい暗記が必要なため、出題確率が高い箇所を絞り込み、効率良く勉強することが重要。
- ユーキャンの社会保険労務士講座はこちら
社会保険労務士(社労士)合格に必要な勉強時間
社労士試験に合格するために必要な勉強時間は、目安として1,000時間以上といわれています。1日4時間勉強すると8ヵ月間ほどです。しかし難関資格のため、1回目で合格する割合は少なく、何度も受験している人も大勢います。
つまり、1,000時間勉強すれば必ず合格できるとは限りませんので、目安として考えるとよいでしょう。
社会保険労務士(社労士)試験はいつから勉強を始める?
効率のいい勉強をするなら、いつから勉強を始めるのがベストでしょうか。
試験は年に1回、8月の第4日曜日に実施されます。
予備校では、前年の10月頃に講座が開講されるのが一般的です。
そのため、次の設定で計算するとよいです。
- 合格に必要な勉強時間:1,000時間
- 勉強期間:10ヵ月間
- 1日に必要な勉強時間:1,000時間÷300日=約3時間20分
仕事をしていると、毎日これだけの勉強時間を確保するのは難しいケースが多いでしょう。
その場合、たとえば1日2時間に減らして計算すると、1,000時間÷2時間=500日≒約1年4ヵ月半必要となり、受験する前年の4月中旬が開始時期となります。
逆に、現在は仕事についておらず、1日に10時間勉強できるなら、1,000時間÷10時間=100日で約3ヵ月半必要です。受験する年の5月中旬に開始しても間に合う計算になります。
1日の勉強時間から逆算すると?
社労士試験の合格に必要な学習期間を1,000時間として、1日の勉強時間が2時間と3時間とで換算すると、必要な学習期間は以下のようになります。
- 1日2時間勉強した場合:1,000時間÷2時間=約500日 必要な学習期間は約1年4〜5ヵ月
- 1日3時間勉強した場合:1,000時間÷3時間=約344日 必要な学習期間は約11ヵ月
1日の学習時間を長く確保するのが難しい方、 働きながら合格を目指す方は、余裕を持ったスケジュールを立てることも少なくありません。
社会保険労務士(社労士)に合格するためのポイント
では、社労士試験に合格するためのポイントは、どのようなものがあるのでしょうか。
各科目7割正解を目指す
社労士試験は、選択式試験と択一式試験の2つの形式で出題されます。
選択式試験は、文章の空欄にあてはまる選択肢を選びます。
択一式試験は、問題の回答にあてはまるものを、複数の選択肢から選びます。
令和6年(第56回)試験における、配点と合格基準点は次のようになっています。
試験の難易度に差が生じたため、令和5年(第54回)試験を補正した合格基準となっています。
| 配点 | 合格基準点 | |
|---|---|---|
| 選択式試験 | 40点満点 (1科目:5点満点) |
・総得点:25点以上 ・各科目:3点以上 |
| 択一式試験 | 70点満点 (1科目:10点満点) |
・総得点:44点以上 ・各科目:4点以上 |
合格基準点は、選択式試験が25点/40点、択一式試験が44点/70点で、約6割程度がボーダーラインとなっています。
つまり、7割正解を目指せば合格が十分可能ということになります。
試験は、選択式では8科目、択一式では7科目が出題されます。
各科目ごとにも合格基準点が設定されており、特定の科目で高得点を取っても、別の科目で合格基準点を超えられなければ不合格となるため、まんべんなく得点を取れるように勉強する必要があります。
勉強する箇所を絞り込む
受験科目は7〜8科目もあり、それぞれ内容が膨大で細かい暗記も必要となります。
そのため、出題確率が高い箇所を絞り込んで、効率よく勉強することが大切です。
受験科目は大別すると労働保険・社会保険の2つのジャンルに分けられます。各科目は関連性が強いため、効率よく勉強するには適切な学習の順番を考える必要もあります。
科目ごとに重点の置き方を考えたり、学習の順番について工夫するなど、事前に戦略を立てるのが合格のためのポイントです。
まとめ
社会保険労務士(社労士)試験合格に必要な勉強時間の目安は1,000時間です。そのため、試験の10ヵ月前から勉強を始めるなら、毎日3時間20分の勉強が必要となります。さらには合格のためには、「各科目7割正解を目指す」「勉強する箇所を絞り込む」のがポイントですので、できるだけ少ない時間で合格を目指すなら、通信講座がおすすめです。
信頼の開講実績は30年以上、過去10年間で1,801名の合格者を輩出しているユーキャンなら、初めて学ぶ方でも安心です。さらに、法改正についても常に最新の情報を提供しています。
独学では難しいと感じはじめたら、ぜひ受講を検討してみてください。

- この記事の監修者は生涯学習のユーキャン
-
1954年設立。資格・実用・趣味という3つのカテゴリで多岐に渡る約150講座を展開する通信教育のパイオニア。気軽に始められる学びの手段として、多くの受講生から高い評価を受け、毎年多数の合格者を輩出しています。
近年はウェブ学習支援ツールを拡充し、紙の教材だけでは実現できない受講生サポートが可能に。通信教育の新しい未来を切り拓いていきます。
よくある質問
- 社労士の平均年収は?
-
社労士の平均年収は500万円程度といわれています。社労士の年収は、働き方などによって大きく変動し、勤務型社労士の場合、平均的な年収は400万円~500万円であるのに対し、独立開業型は年収1,000万円以上を目指すこともできます。
- 社労士と相性が良く、メリットが大きいダブルライセンスとは?
-
社労士とのダブルライセンスに相性のよい資格には、「ファイナンシャルプランナー(FP)」「行政書士」「中小企業診断士」「司法書士」「個人情報保護士」「メンタルヘルス・マネジメント(R)検定」「税理士」「キャリアコンサルタント」「司法試験」「人事総務検定」などが挙げられます。
社労士はさまざまな資格と組み合わせることでキャリアアップできます。 - 社労士が独立開業するには?
-
通常、社労士として独立開業するには2年以上の実務経験が必要です。
2年未満で開業する場合は、事務指定講習の受講により可能となります。講習後、「社労士名簿に登録」と「税務署に開業届を提出」の手続きを行います。
社労士として独立開業するメリットは、自分の裁量で働けたり、働き方や頑張り次第で高収入が目指せること。仕事を確保できないと収入が不安定な点はデメリットといえます。このため、仕事を得る営業力が不可欠で、集客にはネットの活用やセミナー開催も有効です。
社会保険労務士講座

過去10年間でなんと1,483名もの合格者を輩出してきたユーキャンの社労士講座!
動画とテキストを活用し、徹底的に絞り込んだカリキュラムで最短距離での合格を目指していただけます。
質問サービス、添削、法改正情報のお知らせなど……、サポート体制も充実!
社会保険労務士(社労士)は、労働問題や年金問題、社会保険のエキスパート。社労士試験には、受験資格があります。次の代表的な受験資格(学歴・実務経験・試験合格・過去受験)のいずれかを満たす必要があります。まずは「学歴」です。1)大学、短大、高専(高等専門学校)等を卒業した方、2)4年制大学で、62単位以上を修得した方又は一般教養科目36単位以上かつ専門教育科目等の単位を加えて合計48単位以上を修得した方、3)修業年限が2年以上、かつ、課程修了に必要とされる総授業時間数が1,700時間(62単位)以上の専修学校の専門課程を修了した方などと定められています。次に「実務経験」における主な要件は、「法人の役員または従業員(いずれも常勤)として、通算3年以上事務に従事した方」などです。また、「試験合格」「過去受験」における主な要件として、行政書士試験や厚生労働大臣が認める国家試験の合格者及び直近の過去3回のいずれかの社労士試験の受験票又は成績(結果)通知書を所持している方などにも受験資格が与えられます。