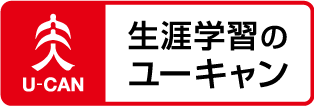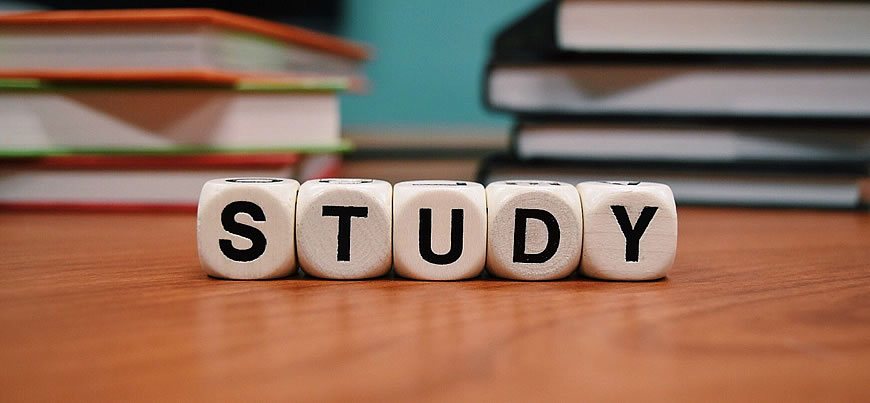宅建の合格率・難易度は?合格ラインを見極めて万全の準備を!

- 更新日:2026/01/28
独占業務があることから不動産業界で非常に重宝される宅建士。宅建試験の合格率は約15~17%と高くなく、試験の難易度も簡単でないことで知られています。実際、宅建試験の合格率や難易度、合格ラインはどの程度なのでしょうか?この記事で詳しくご紹介します。
このページを簡潔にまとめると・・・
- 宅建試験の合格率は約15~17%で、毎年3万~4万人程度が合格しています。
- 合格ラインは50点満点中35点前後、約70%以上の正答率が目安です。
- 司法書士など他資格と比較すると難易度は低めで、国家資格の中では比較的合格の可能性が高い。
- ユーキャンの宅地建物取引士講座はこちら
宅建の合格率は約15~17%。
過去10年間の宅建試験合格率は約15〜17%です(最新の令和7年度は18.7%)。合格点は50点満点で35点前後、約70%以上の正答率が目安です(令和7年度試験の合格点は33点)。
宅建士試験の合格率は安定しており、数字だけ見ると合格率が低いと感じる方も多いかと思いますが、国家資格の中では、比較的合格できる可能性が高い資格です。
過去10年間の宅建試験の合格率、合格点(合格ライン)の推移とは?
下の表は宅建試験の結果について、受験者数、合格者数、合格率、合格点(合格ライン)を過去10年分まとめたデータです。例年、20万人程度の人が資格試験に挑戦していますが、合格できるのは3~4万人ほどであることがわかります。
最新の令和7年度の宅建試験の合格率は18.7%、合格点(合格ライン)は33点となりました。合格点(合格ライン)は毎年変わりますが、近年では合格点35点、つまり70%程度の正答率が求められています。本番の試験で70%以上の問題に正解するためには、演習の段階でそれ以上の点数が出せるよう実力をつけておくようにしましょう。
| 年度 | 合格率 | 合格者数 | 受験者数 | 合格点 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 18.7% | 45,821人 | 245,462人 | 33点 |
| 令和6年度 | 18.6% | 44,992人 | 241,436人 | 37点 |
| 令和5年度 | 17.2% | 40,025人 | 233,276人 | 36点 |
| 令和4年度 | 17.0% | 38,525人 | 226,048人 | 36点 |
| 令和3年度(12月) | 15.6% | 3,892人 | 24,965人 | 34点 |
| 令和3年度(10月) | 17.9% | 37,579人 | 209,749人 | 34点 |
| 令和2年度(12月) | 13.1% | 4,610人 | 35,261人 | 36点 |
| 令和2年度(10月) | 17.6% | 29,728人 | 168,989人 | 38点 |
| 令和元年度 | 17.0% | 37,481人 | 220,797人 | 35点 |
| 平成30年度 | 15.6% | 33,360人 | 213,993人 | 37点 |
| 平成29年度 | 15.6% | 32,644人 | 209,354人 | 35点 |
| 平成28年度 | 15.4% | 30,589人 | 198,463人 | 35点 |
最新の宅建合格率は?
令和7年度(2025年度)の試験結果詳細
『令和7年度宅地建物取引士資格試験結果の概要』によると、令和7年度の宅建試験の合格率は18.7%(受験者数245,462人 、合格者数は45,821人)、合格点は33点という結果となりました。
合格率は平均的な数値となりました。
| 試験日 | 10月19日(日) |
|---|---|
| 申込者数 | 306,099人 |
| 受験者数 | 245,462人 |
| 受験率 | 80.2% |
| 合格点(合格ライン) | 50問中33点以上 (登録講習修了者は45問中28点以上) |
| 合格者数 | 45,821人 |
| 合格率 | 18.7% |
| 合格者の平均年齢 | 36.2 歳 (男 36.4 歳 女 35.9 歳) |
| 合格者の職業構成 | 不動産業 33.2% 金融業 8.1% 建設業 8.7% 他業種 27.9% 学生 10.9% その他 11.3%
|
宅建試験の合格率が低い理由
宅建の合格率が低い理由の一つに、受験資格に制限がないことが挙げられます。ほかの国家試験では、それなりの受験資格が必要です。たとえば、司法試験の場合は、法科大学院課程の修了、または司法試験予備試験への合格、いずれかが必須となっています。したがって、ある程度知識が蓄積されないと、受験できません。
一方、受験資格に制限がない宅建では、誰でも受けられるので、「とりあえず受けてみようか」という軽い気持ちで受験される方も相当数いるため、合格率の低さに繋がっているといえます。
また、不動産業界・もしくは不動産を取り扱う業種であれば、入社早々に宅建の受験勉強をさせるケースが多いことも理由として挙げられます。新入社員や、転職してきた方は、半ば強制的に受験をさせられ、十分な勉強時間をとらないまま試験に臨む方も多いと推測されます。宅建の試験範囲は広いので、学習が間に合わない場合も大いにあるでしょう。独学で勉強する場合は特に、モチベーションの維持と、計画的な学習が重要といえます。
宅建難易度を関連資格と比較
宅建試験の難易度は国家資格の中では比較的合格しやすい部類に入りますが、合格率だけで見ると決して簡単ではありません。
宅建試験の難易度を他の関連資格と比較するとFP2級よりは難易度が高く、マンション管理士と比較すると易しいと位置付けられます。
FP
3級合格率:60~70%、受験者数:約15,000~25,000人
2級合格率:30~40%、受験者数:約15,000~20,000人
不動産について、お金の観点から学ぶのがFPです。宅地建物取引士(宅建)とファイナンシャルプランナー(FP)では、宅地建物取引士の方が難易度が高いといわれています。
FPの試験科目は「リスク管理」、「金融資産運用」、「タックスプランニング」など全6科目です。6科目と聞くと試験範囲が非常に広く感じられますが、学習内容としては保険や税金など日常生活の中で親しんでいるテーマも多く、勉強に取り組み易い点が特徴です。
マンション管理士
合格率:約10%、受験者数:約12,000人
民法や借地借家法など、宅建でもおなじみの単元が問われますが、区分所有法・標準管理規約など、暗記色の強い単元から細かい知識を問われます。合格率は10%に届かず、マンション管理士の方がかなり難しいです。宅地建物取引士(宅建)とマンション管理士では、マンション管理士の方が難易度が高いといわれています。
試験では「民法」「区分所有法」「宅建業法」のほか、多くの分野が宅建と共通して出題されます。ただし、問題の難易度には大きな差があり、マンション管理士は合格率が10%に届かない難関資格です。勉強時間も600~700時間と、宅建の250~350時間と比べて長期戦です。
もし、ダブルライセンスを考えているのであれば、まずは宅建から取得していきましょう。宅建の試験勉強で学んだ知識は、マンション管理士の試験対策に十分活かすことができます。
宅建試験の出題科目・試験内容
宅建試験は、4肢択一式のマークシート式です。出題科目は大きく4科目に分かれ、「宅建業法」「権利関係(民法など)」「法令上の制限」「税・その他」となっています。権利関係などは過去の判例などからも出題されるため、しっかりとした対策が必要です。
詳細は以下の記事で解説します。
宅建の試験勉強はいつから始める?
個人差はありますが、勉強を開始した時期が早ければ早いほど合格する確率も高くなる傾向があります。ここでは、学習開始の時期を説明します。
試験前年からスタートの場合
時間に余裕がありますので、適度な休みと十分な復習時間をとりつつ勉強することができます。特に、得手不得手が分かれやすく合否に直結する科目である「民法等」にじっくり向き合うことができるのは大きなメリット。確実に合格したい方におススメです。
4月スタートの場合
受験生が勉強を始める時期として最も多いのが、この4月です。あせらず、急がず勉強できる最後の時期といって良いでしょう。試験の論点を、基本から応用へと効率よく勉強していくことで、無理なく合格圏に達することができます。
夏からスタートの場合
いわゆる「短期集中型」の方におススメです。もちろん時間的には厳しいですが、内容を重要論点に絞り込み、問題演習を中心に取り組んでいけば、十分合格は狙えるでしょう。
宅建を通信教育で学習するメリット・デメリット
宅建士を通信教育を受講して目指すにはメリットとデメリットがあります。
【メリット】
- 分からないところは講師に質問できる
- 自分で教材選びをする必要がない
- 法改正にも適切に対応してもらえる
【デメリット】
- 独学と比較して費用が掛かる
通信教育の大きなメリットは、不明点を講師に質問できること、教材選びの手間が掛からないこと、法改正の情報をまとめて教えてもらえることです。通信教育の場合はカリキュラムが決まっており、さらに添削をしてくれるシステムもあります。独学よりも学習を続けやすい体制が整っていると言えるでしょう。 独学よりも費用は多少掛かるものの、その分学習に役立つメリットは大きく、効率良く試験合格を目指せるのではないでしょうか。
宅建合格者の声
宅建試験に合格後、宅建士資格を取得し活躍中の方の声をご紹介いたします。
- 仕事の範囲も広がっています!
(30代・女性) -
資格取得前までは契約書の作成までが仕事でしたが、説明や交付もできるようになりました。今までは重要事項の説明も他の宅建士資格取得者がやっているのを聞いているだけでしたが、自分が関わるとなると重みが全然違うというか、お客様にとっては大きな買い物なのですごく責任があるなぁというのはますます感じるようになりましたね。
- 家を買う時にも役立ちました!
(30代・男性) -
マイホームを買う時、土地選びの際に宅建士の知識が活かせました。実際に私、角地を選んだんですけど、角地は建ぺい率が10%プラスになるので、そういう話を業者にしたりとか、第一種低層地域だと小さいお店は建つけども、大きいビルは建たないから静かな景観だなとか、そういうところの環境を想像する上でも役立ちましたね。
- スムーズに転職が決まった!
(40代・女性) -
宅建士を受ける時は全然転職を考えていなかったんですけれども、もっと大きな不動産会社で働きたいという気持ちもあったんです。探し始めたら地元では有数の不動産会社の募集を見つけ、ダメ元で履歴書を送ってみたら、40人応募があった中で採用され、やはり資格の効果は大きいな、と実感しました
もっと見たい方はこちら
まとめ
宅建は人気のある資格ですが、合格率などを考慮すると、他の国家試験よりも易しいと言えます。しかしながら合格率は20%未満のため、努力なしで簡単に受かるものではありません。宅建試験に合格するためには、しっかりと対策を立てて効率良く勉強する必要があります。
教材などをうまく活用して効果的な勉強を行えば、独学でも十分合格は可能ですが、独学だけでは不安な方や1人で努力し続ける自信のない方は、通信教育の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
独学、通信教育、どちらもそれぞれメリット・デメリットがあるため、自分のライフスタイルに合わせた勉強方法を選び、宅建試験合格を目指しましょう。

- この記事の監修者は生涯学習のユーキャン
-
1954年設立。資格・実用・趣味という3つのカテゴリで多岐に渡る約150講座を展開する通信教育のパイオニア。気軽に始められる学びの手段として、多くの受講生から高い評価を受け、毎年多数の合格者を輩出しています。
近年はウェブ学習支援ツールを拡充し、紙の教材だけでは実現できない受講生サポートが可能に。通信教育の新しい未来を切り拓いていきます。
よくある質問
- 宅建士の平均年収は?
-
宅建士の年収は、年齢・地域・企業規模・独立など、働く条件によって大きく異なります。企業勤務の場合、平均年収は約470万円~626万円程度です。
宅建士の年収は物価や不動産価格に依存するため、都市圏は年収が高い傾向にあります。 - 宅建試験に独学で合格するための勉強法は?
-
宅建試験は出題範囲が広いため、独学で合格を目指すには、学習方法に工夫が必要です。
効率的な対策には、優先順位をつけ、配点・出題数が多い科目を優先的に学習します。特に出題範囲も広く配点も多い「宅建業法」を優先して取り組み、十分に対策することがポイントです。
勉強の進め方は、参考書を読み全体を把握し、試験に出題される4科目の特徴を理解します。過去問対策や模試の活用も不可欠です。 - 宅建試験に合格したら宅建士を名乗れるのでしょうか?
-
宅建士として仕事をするには登録が必要です。宅建試験の合格後に登録・宅建士証の交付を受けることで、正式に宅建士としての資格を取得したことになります。
登録には2年以上の実務経験が必要です。実務経験がない場合は宅建士の登録実務講習受講で登録が可能です。
宅建士の登録により、「重要事項説明(35条書面)」「重要事項説明書(35条書面)への記名」「契約書(37条書面)への記名」など、宅建士の独占業務ができるようになります。 - 宅建士(宅地建物取引士)の仕事内容は?
-
不動産取引の際にお客様が知っておくべき事項(重要事項)を説明するのが宅建士の仕事です。不動産取引は非常に高額であり、お客様の多くは不動産に関する専門知識や売買経験がほとんどないため、不当な契約で損害を被ることがないよう、重要事項をお客様に説明します。いわば宅建士は、不動産取引の専門家を示す資格といえます。
宅地建物取引士講座

ユーキャンの宅地建物取引士講座の人気の理由は教材の分かりやすさ!教材は学習内容を絞り、テキストと動画講義の組み合わせで効率的に学習が進みます。スマホでも学べるので、忙しい方もムリなく続けられるのが嬉しいポイント。さらに、独学では手に入りにくい法改正などの情報を、適宜お知らせ!情報収集に時間を費やすことなく、学習に集中できます。
不動産関連の仕事に直結するエキスパート資格である宅建。不動産売買や賃貸の仲介に不可欠な国家資格です。宅建資格取得によって、物件の取引条件や手付け金、登記、不動産に関する条件など重要事項の説明や、重要事項説明書への記名、契約後のトラブル防止となる37条書面の記入など、不動産関連の職種での重要な手続きに携わることができます。
ユーキャンの「宅地建物取引士(宅建士)」講座なら、不動産業界で働く方はもちろん、転職や独立を考える方にぴったり! 基礎テキストは驚くほどスリムな3冊のみで、専門的な法律用語をわかりやすく解説し、忙しい方でも短期間で効率的に合格力が身につきます。