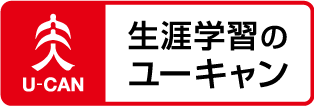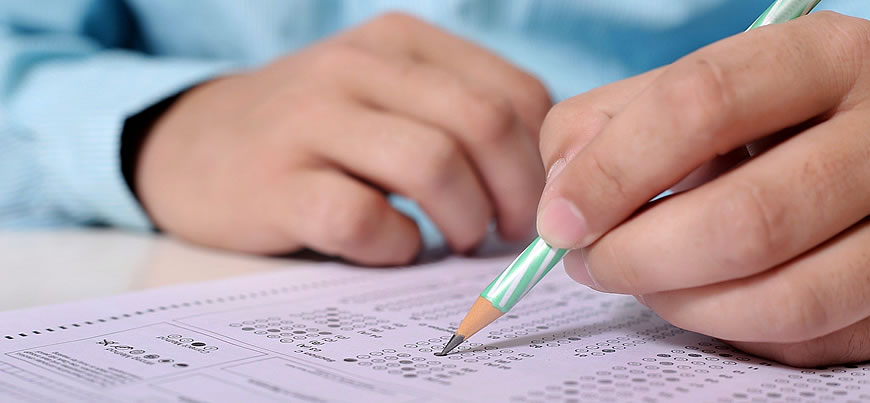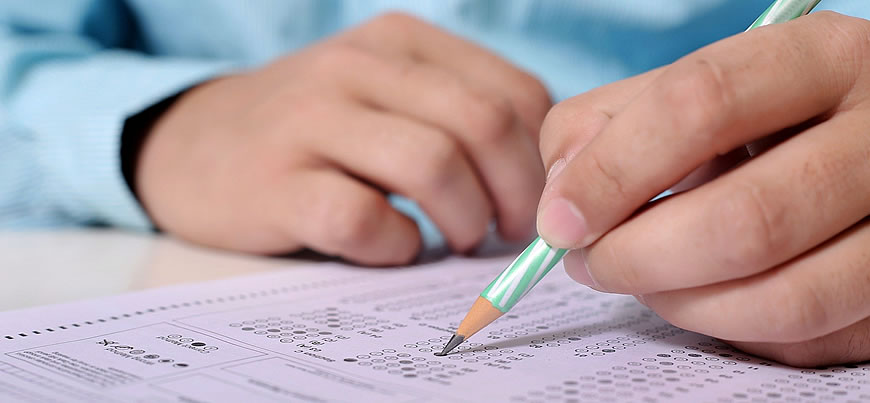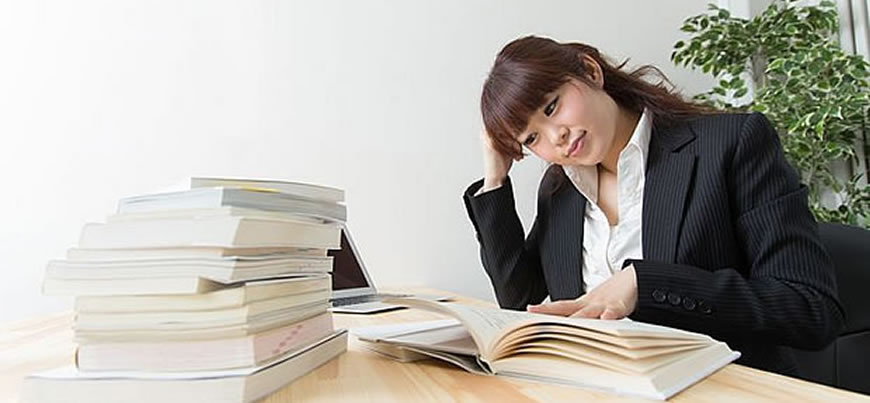行政書士試験の内容は?試験対策のポイントを徹底解説!
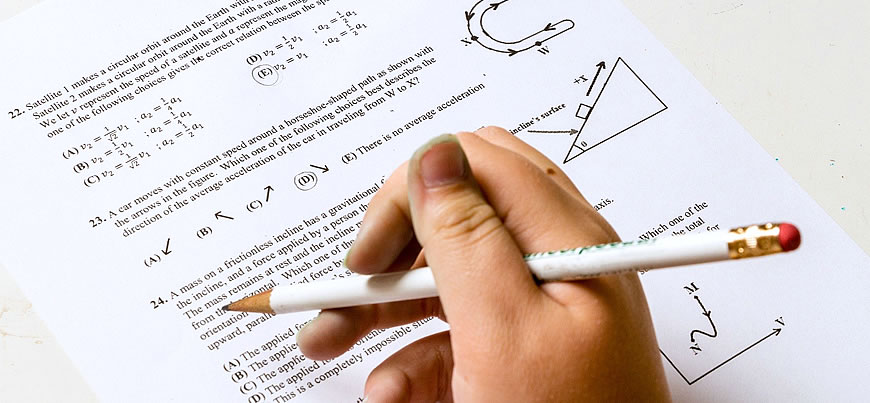
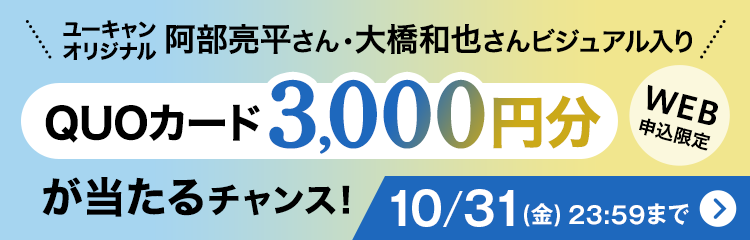
キャリアアップを実現するための方法のひとつとして、資格を取得することがあげられます。行政書士は数ある資格の中でも人気がある資格です。この記事では、行政書士試験の概要、試験対策のポイントなどを解説します。行政書士試験を受験する際の参考にしてください。
このページを簡潔にまとめると・・・
- 行政書士試験の内容は、大きく分けて法令等科目と基礎知識科目の2つ。
- 法令等科目は、民法・行政法・憲法など、基礎知識科目は、一般知識・文章理解などが出題される。
- 試験対策のポイントは、過去問演習、直前模試の活用、本番で使える実践力の養成など。
- 効率的な学習のコツは「基礎知識科目の問題は基準点以上の獲得を目指す」「行政法と民法に力を入れる」など。
- ユーキャンの行政書士講座はこちら
行政書士試験の概要
行政書士試験の対策は事前に試験内容や合格基準を把握しておくことが大切です。ここでは、試験の概要を説明します。
行政書士試験のスケジュール
-
7月初旬
試験要項の発表 -
7月下旬~8月下旬
受験申込み -
11月の第2日曜日
試験本番 -
翌1月下旬
合格発表
例年、試験日の4ヵ月位前に試験要項が発表され、行政書士試験の申し込みは7月下旬~8月下旬に行われます。
試験は各都道府県で実施され、現住所や住民票の住所に関係なく、どの試験会場でも受験可能です。 試験場は毎年7月の第2週に公示されるので、ご自身の都合に合った会場で出願をしましょう。 試験は毎年1回、11月に実施され、合格発表は翌年1月です。
行政書士試験の試験概要
| 受験資格 | 受験資格の制限なし。どなたでも受験できます。 |
|---|---|
| 試験時期 | 年1回、11月の第2日曜日 試験時間は午後1時~4時 |
| 試験場所 | 全国47都道府県。 現住所や住民票の住所に関係なく、どの試験場でも受験可能。 |
| 試験科目 | 「行政書士の業務に関し必要な法令等」と「行政書士の業務に関し必要な基礎知識」にわけられ、問題数は全部で60問 法令等:憲法、行政法、民法、商法、基礎法学の中から46問出題 基礎知識:一般知識(政治・経済・社会)、諸法令(戸籍法・住民基本台帳法・行政書士法)、情報通信・個人情報保護、文章理解から14問出題 |
| 試験方式 | 筆記試験 法令等:択一式および記述式 基礎知識:択一式 |
| 受験料 | 10,400円 |
| 資格の有効期限 | 一生有効(行政書士登録申請に、期限はありません) |
受験資格
行政書士の受験資格には制限がなく、学歴、性別、国籍を問わず誰でも受験できます。ただし、資格を取得しても、未成年者は行政書士として登録することができません。
法律関係の資格には多くの場合、受験資格に条件があります。たとえば、司法試験であればロースクール卒業修了、税理士であれば簿記1級、社労士(社会保険労務士)であれば短大卒以上などです。行政書士は受験資格に制限がないことから、法律関係のなかでも目指しやすい資格といえます。
行政書士試験の難易度
2023年度に実施された行政書士試験では、合格率が13.98%となっています。過去10年間で見ると、合格率は若干上昇傾向にあります。しかしながら、合格する人は約10人に1人なので、難易度自体は高い試験といえるでしょう。ただし、ほかの法律系の資格として弁護士や弁理士、司法書士などがありますが、その中では難易度は低めとなっています。
試験内容は、民法や行政法などの法律関連の問題が多く、法律の予備知識がない場合は途中で挫折してしまうことも少なくありません。合格するためには試験対策をしっかりと行い、効率的に学習を進めていくことが重要です。
行政書士試験の合格点
行政書士試験に合格するためには、以下3つの条件すべてを満たす必要があります。
- 「行政書士の業務に関し必要な法令等科目」において得点が122点以上(満点の50%以上)
- 「行政書士の業務に関し必要な基礎知識科目」において得点が24点以上(満点の40%以上)
- 試験全体の得点が180点以上(満点の60%以上)
また、行政書士試験には、「補正措置」という特別な制度があります。 これは平均点が高すぎたり低すぎたりしたときに、合格基準を変更する制度です。
補正措置が実施されるかどうかは、試験の実施後にしかわかりません。 2014年度以外に実施事例はなく、今後実施される可能性は低いと考えましょう。
行政書士試験の内容
試験内容
行政書士試験は内容が多岐に渡り出題範囲が広いため、「試験でよく出る分野」に絞って勉強することが、合格への近道です。試験内容は、大きく分けて2つあります。「行政書士の業務に関し必要な法令等科目」では46問が出題され、計244点です。「行政書士の業務に関し必要な基礎知識科目」では14問が出題され、計56点が配分されています。2つの分野を合計した300点満点で、行政書士試験は構成されています。
法令等(行政書士の業務に関し必要な法令等科目)
「行政書士の業務に関し必要な法令等科目」の科目・出題形式・出題数・配点は、以下のとおりです。
| 科目 | 出題形式 | 出題数 | 配点(1問) | 配点合計(出題形式別) | 配点合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎法学 | 五肢択一式 | 2問 | 4点 | 8点 | 8点 |
| 憲法 | 五肢択一式 | 5問 | 4点 | 20点 | 28点 |
| 多肢択一式 | 1問 | 8点 ※空欄(ア~エ)1つにつき2点 |
8点 | ||
| 行政法 | 五肢択一式 | 19問 | 4点 | 76点 | 112点 |
| 多肢択一式 | 2問 | 8点 ※空欄(ア~エ)1つにつき2点 |
16点 | ||
| 記述式 | 1問 | 20点 | 20点 | ||
| 民法 | 五肢択一式 | 9問 | 4点 | 36点 | 76点 |
| 記述式 | 2問 | 20点 | 40点 | ||
| 商法 | 五肢択一式 | 5問 | 4点 | 20点 | 20点 |
| 合計 | - | - | - | - | 244点 |
基礎法学
基礎法学の分野では、法学全般の知識が問われます。範囲が広いにもかかわらず、2問しか出題されないため対策が取りにくいです。テキストや過去問題集など基本的な知識を確認しておく程度でいいでしょう。ただし、法令用語や法律についての諸原則などはしっかり確認しておくことが大切です。
憲法
憲法の分野からは、5肢択一式の問題形式が5問、多肢選択式の問題が1問出題されます。難易度の低い問題が出題されることも少なくありませんので、しっかり点数を取りたい科目といえます。年によって問題の難易度や出題テーマにバラツキがありますので、過去問題集を参考にし、出題率の高いテーマを中心とした学習を行いましょう。人権分野の問題は判例から出題されることが多いのでよく理解しておきましょう。
民法
民法の分野からは、5肢択一式が9問、記述式が2問出題されます。配点が76点と高い科目であるため、合格基準に達するための十分な対策が必要となります。民法は問題文が長めなものが出題されがちですので、文章の読解力も磨く必要があります。
特に、記述式問題の配点は2問で40点となるため、制限文字数内で要点を絞った文章が書けるように練習しておきましょう。民法は直近に改正されたテーマから出題されることも少なくないので、改正内容に応じた試験対策が必要となります。
行政法(地方自治法含む)
行政法の分野からは、5肢択一式の問題が19問、多肢選択式が2問、記述式が1問出題されます。配点が112点と、300点満点のほぼ3分の1を占める重要な科目です。行政法の問題では、条文について幅広い知識が問われるため、学習時間を十分に確保し、条文をしっかりと学習しておくことが大切です。単に暗記するのではなく、過去問題集などを解きながら理解を深めていく方がいいでしょう。
商法
商法の分野からは、5肢択一式の問題が5問出題され、そのうち商法が1問、会社法が4問になります。これらの学習は基本的にテキストや過去問題集を中心に行うとよいでしょう。ただ、得点を稼ぎにくい科目ですので、出題の多いテーマに絞って、効率よく学習することをおすすめします。
基礎知識(行政書士の業務に関し必要な基礎知識科目)
令和6年度試験より、諸法令(戸籍法・住民基本台帳法・行政書士法)の追加が発表されました。一般知識(政治・経済・社会)、諸法令(戸籍法・住民基本台帳法・行政書士法)、情報通信・個人情報保護、文章理解から14問出題されます。
| 科目 | 出題形式 | 出題数 | 配点合計 |
|---|---|---|---|
| 一般知識(政治・経済・社会) | 五肢択一式 | 14問 | 56点 |
| 諸法令(戸籍法・住民基本台帳法・行政書士法) | |||
| 情報通信・個人情報保護 | |||
| 文章理解 |
一般知識
一般知識は、政治・経済・社会の分野から、5問程度が出題されます。出題範囲がとても広く、たとえば、政治では国内外の政治制度や日本の選挙制度、経済では財政問題や金融政策、社会では社会保障などが出題されます。一般知識の対策としては、日頃からニュースや新聞などを活用して時事問題も意識しておきましょう。高校などの授業で習う政治経済などの基本的な知識も復習しておくといいでしょう。
情報通信・個人情報保護
情報通信・個人情報保護の分野からは、毎回4問程度出題されます。情報通信は、通信技術に関する知識や法律について問われます。個人情報保護では、個人情報保護法などが出題範囲となります。
情報通信分野の対策としては、インターネットに関する用語を理解しておくことが大切です。個人情報保護分野では、個人情報保護法の仕組みを押さえるとともに、過去問題集を活用して理解を深めておくといいでしょう。
諸法令
諸法令の分野は、令和6年度試験では2問出題されましたが、今後も2問程度出題されることが予想されます。令和6年度試験では、行政書士法と住民基本台帳法から基本的な条文知識が出題されましたので、今後の試験対策として、戸籍法・住民基本台帳法・行政書士法の条文知識を押さえていくことになります。
文章理解
文章理解の分野からは3問出題されます。国語の問題で、出題形式は並べ替えや空欄補充、文章要旨把握となります。毎年出題形式が決まっているため、対策が立てやすく、確実に点数を取りたい科目です。
基礎知識は56点満点で、24点以上という合格基準点があります。文章理解は12点満点なので、ここで点数を取ることには大きな意義があります。学習のポイントとしては、過去問題集を活用するのがおすすめです。
行政書士試験対策のポイント5選
行政書士試験対策にはいくつかポイントが!問題演習や直前模試も不可欠です。ここでは、試験に合格するための具体的な対策のポイントについて5つ解説します。2006年度に行政書士試験制度が大きく変化し、難易度が高くなっています。
多肢選択式問題を解答するコツ
多肢選択式問題を解答するコツ 多肢選択式問題は、20個の選択肢の中から、正解を4つ選ぶ形式の問題です。多肢選択式問題は、3問出され合計24点の配点で、1問につき4つの穴埋めをします。1つの穴埋めに正解すると2点もらえるので、確実に点を取れるようにしましょう。
解き方のポイントとしては、①何について書かれている文章であるのかを読み取る、②文章の中から空欄に入る言葉のヒントを探す、という2点があります。過去問題を解いて、この解き方に慣れておきましょう。
記述式問題を解答するコツ
行政書士試験の記述式問題は、3問出され1問20点の配点です。45マスの解答枠があり、40文字程度での記述が求められます。問題文をしっかり読み取り、何が求められているのかを把握し、余計なことを記載せず、45マスで納まるように記述することが重要です。
記述式問題では部分点がつくので、必要なキーワードを意識的に使うようにするのがポイントです。実際に問題文を読み、解答となる文章をまとめる練習が必要となります。漢字の誤記入などは減点対象になる可能性もあるので、記述式問題に慣れておくことをおすすめします。
行政法と民法を徹底的に学習する
行政法の配点が112点、民法の配点が76点と全体の約60%を占めることになるので、しっかり学習しておく必要があります。民法・行政法共に、具体的な事例に関連した問題が出題されるため、条文・判例を理解し、重要な用語は正確に暗記しておきましょう。
全体像をなんとなく理解しただけでは解答することが難しいため、細かく丁寧に知識を身につけることをおすすめします。全体像や出題形式に慣れることから始めるといいでしょう。
過去問題を繰り返し解いてみよう
行政書士試験対策として、過去問題を繰り返し解きましょう。過去問題で解答できなかった部分については、「なぜ解けなかったのか?」をしっかり理解しておくことが大切です。出題傾向を把握することで、効率のいい学習が進められます。
直前模試は必ず受けよう
本番の予行演習をすることは非常に重要なので、直前の模擬試験は必ず受けましょう。模擬試験を受けることで、自分の実力や足りない知識を正確に把握でき、試験本番までに復習すべきポイントがわかります。また、本番と同じ問題量を制限時間内に解くことで、問題を解くペースが身につきます。本番に備えて自分なりの戦略を立てられます。
行政書士試験の学習のポイント
行政書士試験の学習を効率的に進めていく学習方法のポイントには「わからない問題はあと回しにする」「基礎知識科目の問題は基準点以上の獲得を目指す」 「行政法と民法に力を入れる」などがあります。
「繰り返し学習」で法律の理解を深める
行政書士試験の問題に出てくるような法律や判例は、一度読んだだけで内容を理解したり、覚えたりすることは難しいです。過去問やテキストで繰り返し学習することで、法律の理解を深めていくことができます。確実に実力をつけていくためにも、最低でも3回以上繰り返し学習するようにしましょう。
また、覚えたことを忘れないためにも、間を空けて繰り返し学習を行うこともポイントです。
行政書士試験用の教材を使って学習する
試験対策として、いきなり最初から六法全書を理解しようとしたり、暗記したりすることは難易度が高いです。まずは、読みやすく書かれたテキストを読んで理解することがポイントです。
ある程度学習が進んできたときに一番おすすめの教材は過去問題集です。過去問を何度も解いていくことで、試験問題に対応できる知識をつけることができ、出題傾向も把握できます。また、解説が充実した過去問題集を選ぶことで、どこをどう間違ったのかについて理解を深められます。
わからない問題はあと回しにする
行政書士試験は出題範囲が広く、わからない問題が出題されることも想定されます。そのため、わからない問題に焦ってしまうと、実力が十分に発揮できないということも考えられます。
試験でわからない問題が出たら、まずは落ち着いて考えてみることが大切です。ただし、考えてもわからない場合は、わかる問題から解くようにしましょう。時間配分のミスを防ぐためにも最後にわからない問題に取り組むのがおすすめです。
行政法と民法に力を入れる
行政書士試験では、法令等科目で5割、基礎知識科目で4割クリアすることを前提として、総合点で6割の得点を取ることができれば合格できます。法令等科目では、244点中188点(77%)、総合点では、300点中188点(63%)を行政法と民法が占めています。したがって、行政法と民法だけで合格点をクリアできるほど、この2つの科目は重要です。
行政書士試験の学習では、ただやみくもに試験範囲を網羅的に学習するのは効率的ではありません。 行政法と民法に力をいれて効率的に学習を進めていきましょう。
基礎知識科目の問題は基準点以上の獲得を目指す
試験の総合点や法令等科目で合格ラインを突破しても、全体の合格基準に達しない可能性もあります。基礎知識科目で40%の基準点をクリアすることができずに、不合格になることもあります。
出題数が多い法令等科目に重点的に力を入れることはいいのですが、基礎知識科目の学習もおろそかにはできません。過去の出題傾向を研究し、普段からニュースなどをチェックすることも大切です。基礎知識科目の問題は、基準点以上の獲得を目指すことを目標に学習を進めましょう。
記述式問題への対策
行政書士試験は、選択式のマークシート問題と記述式問題で構成されています。記述式問題を得点に結びつけるためには、正確な知識が必要です。記述式問題では、論文のような長い文章を書く必要はなく、問題文に対して40字程度で解答を作成する形式です。正確な知識を引き出すことができれば解答欄を埋めることができるでしょう。
対策として、学習した知識から解答に必要なキーワードを導き、組み合わせて解答を作るなど知識の使い方のトレーニングを行うことが大切です。
行政書士試験の合格率とは?
行政書士試験の合格率は、直近5年間では10~15%と高くはありませんが、しっかり対策すれば、初心者でも合格が可能です。
過去に行われた行政書士試験の合格率を紹介します。
直近5年間の合格率
以下の表は、行政書士試験の直近5年間の合格率をまとめたものです。
| 回(実施年月日) | 受験者数(人) | 実受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020年(令和2年)度 | 54,847人 | 41,681人 | 4,470人 | 10.7% |
| 2021年(令和3年)度 | 61,869人 | 47,870人 | 5,353人 | 11.2% |
| 2022年(令和4年)度 | 60,479人 | 47,850人 | 5,802人 | 12.1% |
| 2023年(令和5年)度 | 59,460人 | 46,991人 | 6,571人 | 14.0% |
| 2024年(令和6年)度 | 59,832人 | 47,785人 | 6,165人 | 12.9% |
直近5年間の合格率を見ると、ほぼ10~15%の間で推移しています。行政書士試験の合格基準は、各試験科目で一定の得点を取ったうえで、300満点中180点以上の得点を取得することとなっており、幅広い法律の分野をいかに効率的に学習するかが重要になります。合格率はあまり高くはありませんが、しっかり対策をすれば、初心者でも合格が可能となります。
まとめ
行政書士試験の試験内容としては、大きく分けて法令等科目と基礎知識科目の2つがあります。法令等科目は、民法・行政法・憲法などがあり、行政書士として知っておくべき法律知識についての問題が出題されます。基礎知識科目には、文章理解などがあり、基準点に達しない場合は不合格となるためこちらも十分な学習が必要となります。
学習の対策を立てるためには、試験で出題される問題の形式と解答方法を事前に把握しておきましょう。過去問題集や直前模試を活用して、本番で使える実践力を身につけることがポイントです。
行政書士試験の対策としては、効率的に学習できる通信講座の受講もおすすめです。ユーキャンの行政書士講座では、優先順位の高い民法と行政法から効率的に学習していきます。行政書士試験対策として重要な過去問題について非常に丁寧な解説を行っています。これから行政書士を目指す人は、ぜひ検討してください。

- この記事の監修者は海野 高弘(うみの たかひろ)
-
東京都出身
東京都行政書士会文京支部理事
趣味は、資格試験短期合格法の研究、野球、釣り、旅(判例現場巡り&寅さんロケ地巡り)
2000年 行政書士試験受験、翌年合格
2004年 ユーキャン行政書士講座 講師
2012年 ユーキャン行政書士講座 主任講師
モットーは、「夢なき者に成功なし」「短期合格は第一歩がすべて」「法律は暗記ではなく思考力」
★ユーキャン行政書士講座 公式YouTubeチャンネル
よくある質問
- 行政書士には、どんな人が向いている?
-
行政書士の適性は、責任感があり、正確でスピーディーな事務処理能力や営業力、コミュニケーション能力の高い人が向いているといわれています。
- 行政書士の資格はどんなところで活かせますか?
-
行政書士の資格が活かせる場は、士業事務所、建設業や不動産業、一般企業の法務部や総務部など、多岐に渡ります。行政書士の求人は「未経験の有資格者でも可」「独立前提」など雇用形態の幅が広く、将来性のある仕事といえます。
就職活動では、動機と就職希望先のマッチングの他、キャリア形成や将来性、代表との相性なども重要です。 - 行政書士は何ヵ月で取れる?
-
行政書士試験対策に必要な学習期間は、1日の勉強時間を平均でどれほど確保できるかによって変わります。行政書士試験の合格に必要な学習時間は800時間ほどが目安といわれますが、その場合、1日当たり平均で2.5時間とすると約10ヵ月となります。1日当たり平均が4時間なら約7ヵ月、5時間なら約5ヵ月の学習期間となります。
行政書士講座

ユーキャンの行政書士講座の人気の理由は教材の分かりやすさと手厚いサポート体制!
要点を絞り込んだテキストと人気の動画講義の組合せで理解が進みます。
スマホでも学べるので、忙しい方もムリなく続けられるのが嬉しいポイント。サポートも万全で、6ヵ月でムリなく合格が目指せます!
合格者は過去10年間でなんと2,581名を輩出!
ユーキャンで目指せる国家資格の中で人気の「行政書士」。市民と官公署とをつなぐ法務と実務のスペシャリストです。
資格取得後は、法律関連の業務全般について、書類作成業務や官公署への書類提出手続き代理業務、契約書等代理作成業務など、気軽に市民の目線で相談できる「頼れる法律家」に。扱える書類は数千種類もあり、業務範囲の広い国家資格です。独立・開業して社会に役立つことはもちろん、企業への就職・転職にも有利になります! 国家資格の中では難関試験として知られている行政書士ですが、ユーキャンでは試験突破に向けて、仕事と両立しながら続けられるようにカリキュラムを工夫。まったく知識が無い方でも着実に資格取得までのプロセスを身につけることが可能な通信講座です!