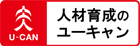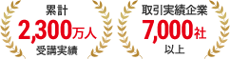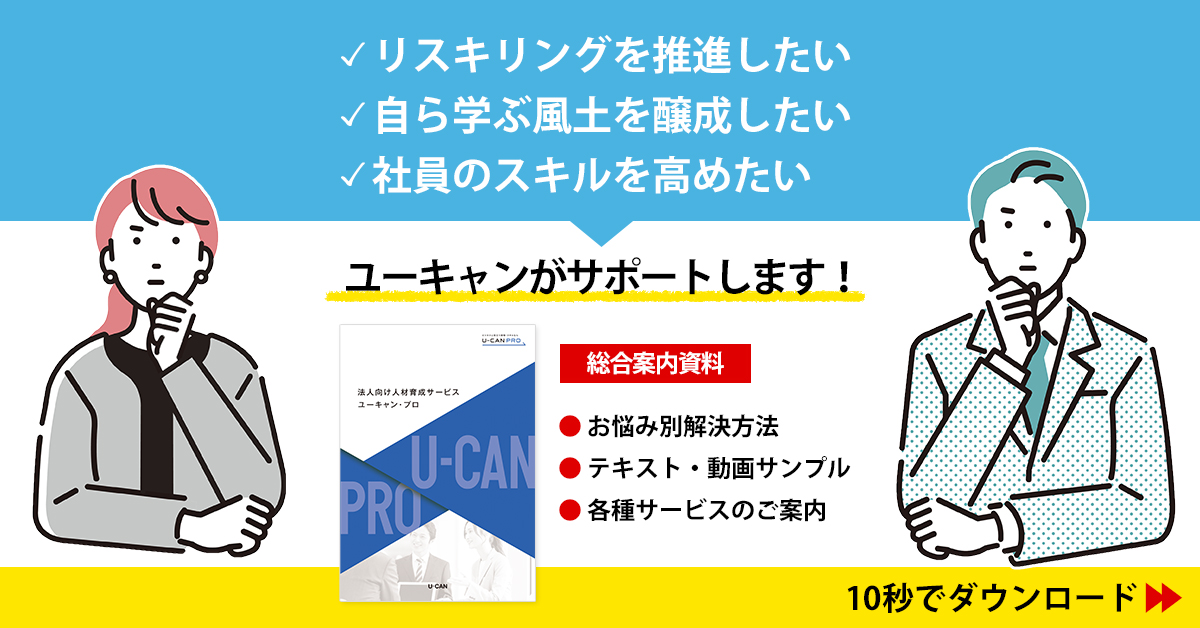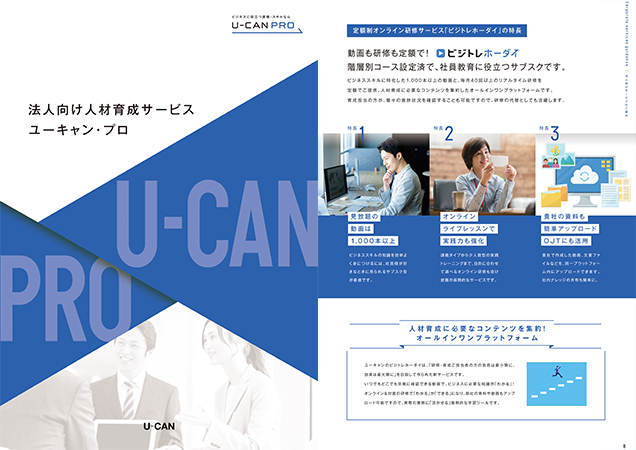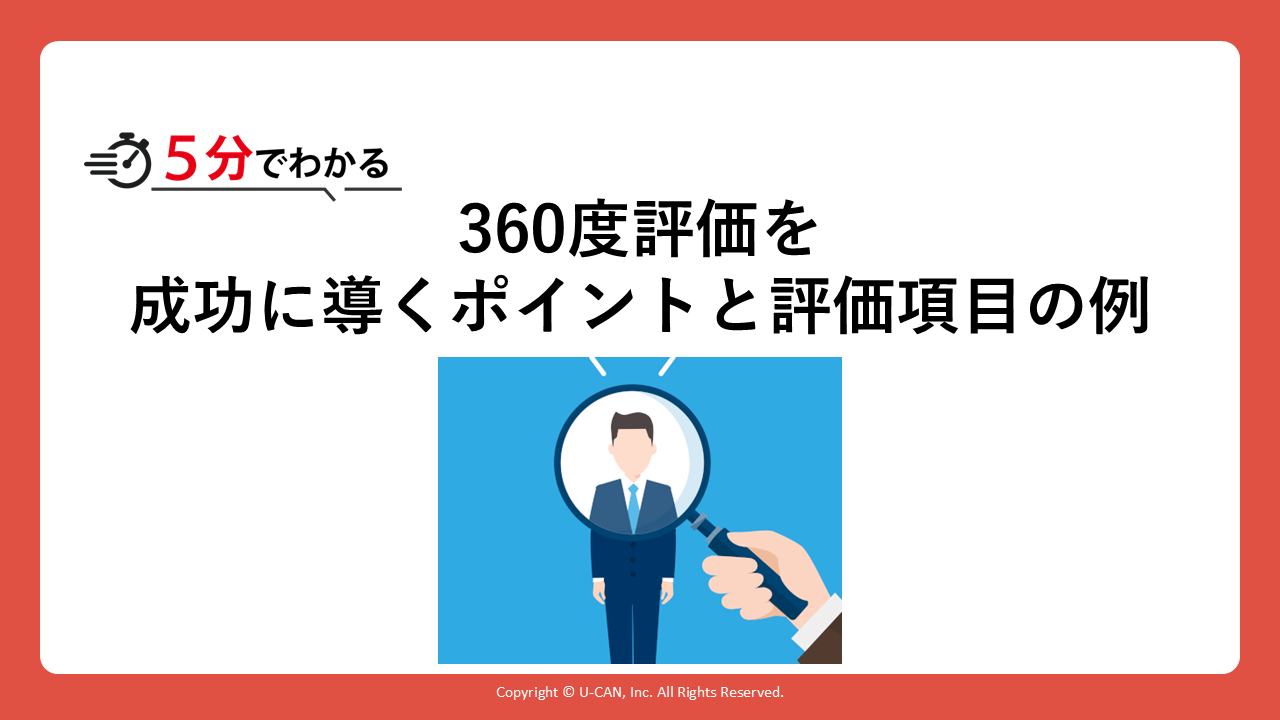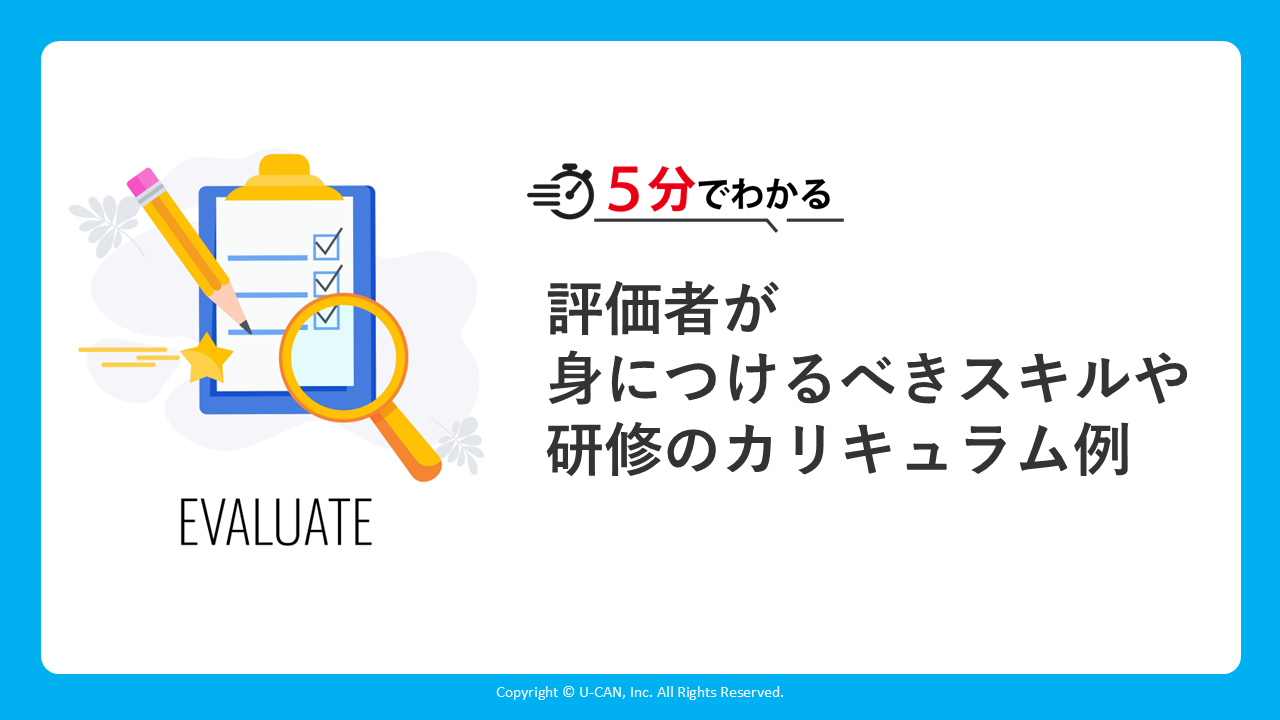フィードバックとは?
ビジネスの領域におけるフィードバックとは、「従業員の行動に対して評価や指摘を伝えること」です。 もともとは、ITや工学分野で使われていた用語ですが、様々な場面で使われるようになり浸透しました。フィードバックは、従業員に自身の課題を理解させ問題解決に導いたり、成長を促進したりする目的で行われています。
フィードバックの適切なタイミング
フィードバックの適切なタイミングは、主に以下のとおりです。
・対象者の結果が現れ始めたとき
・対象者に余裕があるとき
・フィードバックをする時間が確保できるとき
フィードバックは、時間の経過とともに効果が薄れます。あまりにも遅いフィードバックはいまさら感が高まり、対象者から不信感や反感を抱かれる可能性があります。そのため 対象者の結果が現れ始めた比較的早い段階で、フィードバックを実施しましょう。また対象者が精神的に追い詰められている状態でフィードバックを実施しても、効果が期待できません。対象者の受け入れ態勢が整ってから、実施するのが望ましいでしょう。ていねいな評価をするために、十分な時間が確保できるときを狙ってフィードバックを実施するのがおすすめです。
フィードバックのビジネスでの意味
ビジネスにおけるフィードバックとは、相手の仕事の進め方や成果に対して、気づきや改善点を伝えることです。上司が部下に行うだけでなく、同僚同士でも活用され、相手の成長を促したり、仕事の質を高めたりするのに役立ちます。適切なフィードバックは信頼関係を築き、組織全体のパフォーマンス向上にもつながります。
フィードバックの目的
フィードバックには、主に以下の目的があります。
・人材育成を図るため
・対象者のモチベーションを向上させるため
・個人やチームの目標を達成するため
それぞれの目的について、詳しく解説します。
人材育成を図るため
フィードバックは、対象者の成長のために欠かせない取り組みです。フィードバックの実施は、部下が対象者について知ることができます。業務における対象者の課題を把握することで今後の業務に反映させられるでしょう。また対象者が仕事における自身の問題点や改善点に気がつければ、より効率のよい成長が期待できます。企業によっては数値的な成果よりも対象者の成長を重視するところもあるほどで、これは人材育成で得られるものが大きいことを示しています。
対象者のモチベーションを向上させるため
対象者のモチベーションを上げるのも、フィードバックの目的の1つです。フィードバックでは、問題点を見直して解決策を見出します。対象者だけでは難しいと感じる問題は、評価者が一緒に対策方法を練ることで思考を転換するきっかけとなるでしょう。「できるかもしれない」というポジティブな思考は業務への前向きな姿勢につながるだけでなく、対象者の自己効力感を高めるでしょう。定期的なフィードバックにより対象者の自己効力感が高まれば、業務へのモチベーションの向上が期待できます。
個人やチームの目標を達成するため
こまめなフィードバックは、結果的に対象者の目標達成につながります。方向性を見失った場合はその都度軌道修正を図ることで、遠回りせずに目標に近づくことができるでしょう。最適な取り組み方法が分かれば、効率的な目標の達成が期待できます。またフィードバックは、個人のみならずチームの目標達成にも効果的です。 定期的なフィードバックの実施は、チーム全体の業務の見直しや方向性の改善などができます。 1人で達成するのは難しい目標も、チームが一丸となることで効率的な達成につながるでしょう。対象者やチームの目標達成には、定期的なフィードバックが欠かせません。
フィードバックがもたらす効果・メリット
フィードバックを行うことでどのようなメリットが得られるのでしょうか。ここでは、4つのメリットを解説します。
対応力とスキルが高まり、仕事の質が向上する
フィードバックは、対象者の強みや課題を明確にし、スキルアップに直結します。課題点だけでなく、具体的な改善方法やノウハウを伝えることで、仕事への対応力が高まり、成果物の質も向上します。結果として、より良いパフォーマンスが実現できます。
モチベーションが向上する
納得感のあるフィードバックは、自己肯定感ややる気を引き出す効果があります。「自分のことをしっかり見てもらえている」という安心感や成長実感は、モチベーションを高め、前向きに仕事へ取り組む原動力となります。
目標達成に近づける
定期的なフィードバックにより、業務目標に対する取り組みのズレに気づきやすくなります。その都度軌道修正を行うことで、目標に向けた正しい方向性を持って進むことができ、成果につながりやすくなります。
信頼関係を築き、コミュニケーションを促進する
1on1や面談などでのフィードバックは、上司と部下の対話の機会となり、相互理解を深めます。定期的なやり取りを通じて意識のズレを防ぎ、信頼関係の構築や組織全体のエンゲージメント向上にもつながります。
フィードバックの基本となる2つの種類
ビジネスにおけるフィードバックの傾向は、主に以下の2つに分かれます。
・ポジティブフィードバック
・ネガティブフィードバック
ポジティブフィードバック
ポジティブフィードバックとは、相手の良い行動や成果に対して前向きな評価や感謝を伝えることです。例えば、目標を達成した、工夫した提案を出した、周囲を助けたなどの場面で使われます。相手のモチベーションや自信を高め、行動の定着を促します。伝える際は「すごいね」だけで終わらせず、「どこがどう良かったか」を具体的に伝えることが大切です。過剰なお世辞は避け、事実に基づいたタイミングのよい声かけが効果的です。
ネガティブフィードバック
ネガティブフィードバックとは、相手の改善すべき行動や結果に対して建設的な指摘を行うことです。ミスや遅延、ルール違反など、業務上の問題があったときに必要となります。目的は相手を責めることではなく、改善を促し成長を支援することです。伝えるときは感情的にならず、具体的な行動に焦点を当て、事実に基づいて冷静に伝えることが大切です。人格否定にならないよう配慮し、相手の意見も聞く姿勢を持つことが信頼関係を築く鍵です。
フィードバックの手法3選
ビジネスシーンにおける「フィードバック」とは、相手の行動や成果に対して評価や改善点を伝えるコミュニケーション手法です。適切なフィードバックは、従業員のスキル向上やモチベーション維持、信頼関係の構築、さらには組織全体の生産性向上にも寄与します。ここでは、実務で活用される代表的な3つのフィードバック手法(SBI型・サンドイッチ型・ペンドルトン型)を詳しく解説します。
① SBI型フィードバック(Situation・Behavior・Impact)
SBI型フィードバックとは、「状況(Situation)」「行動(Behavior)」「影響(Impact)」の3つの要素に分けて相手に伝えるフィードバック手法です。
具体的には、「どんな状況で」「どのような行動があり」「その結果どんな影響を与えたか」を順序立てて伝えることで、相手にとって理解しやすく、納得感を得やすいのが特徴です。
たとえば以下のように伝えます。
S(状況):「今日のプレゼンテーションのことだけど」
B(行動):「プレゼン資料がわかりやすく丁寧に作成されていた」
I(影響):「そのおかげで参加者にとても好評だった。次回もぜひ意識してプレゼンしてほしい」
SBI型は、ポジティブなフィードバックにもネガティブなフィードバックにも使える汎用性の高い方法です。順序だてて具体的に伝えることで、相手が自分の行動を客観視しやすくなり、自ら次の行動につなげる意識が芽生えます。また、相手との信頼関係を築きやすいのも大きなメリットです。
② サンドイッチ型フィードバック
サンドイッチ型フィードバックは、「ポジティブ → ネガティブ → ポジティブ」という順に伝える手法で、評価の中に改善点を挟み込むことで、相手の受け入れやすさや心理的安全性を高める方法です。
最初と最後に前向きなフィードバックを行うことで、ネガティブな内容がストレートに伝わりすぎず、相手のモチベーション低下を防ぐ効果があります。
たとえば以下のように構成します。
ポジティブ:「今日のプレゼンの内容はとても分かりやすく良かった」
ネガティブ:「ただ、早口になってしまった部分があったので、次はもう少し落ち着いて話すともっと伝わりやすくなるよ」
ポジティブ:「全体としてはとても魅力的なプレゼンだったと思う」
この手法は特に、初めてフィードバックを行う上司や、相手との信頼関係が浅い場合にも有効です。言いにくい指摘も受け入れてもらいやすく、フィードバック後の関係悪化を防ぐ点でも広く使われています。
③ ペンドルトン型フィードバック
ペンドルトン型は、心理学者のペンドルトンによって開発された手法で、相手の自己評価や反省を起点に対話を進める特徴があります。評価者が一方的に指摘するのではなく、まず対象者自身に「うまくいった点」「改善したい点」などを話してもらい、そのうえで上司がフィードバックを加えていきます。
たとえば以下のように進めます。
部下の反省:「昨日のプレゼンでは質問にうまく答えられなかった」
上司のコメント:「そうだね。事前に想定質問を準備しておくと安心できるし、必要な情報を整理しておくことも大切だよ」
この手法の最大の利点は、相手の主体性を引き出せる点にあります。フィードバックが対話形式になることで、相手も自らの課題を整理しやすく、納得して次の行動につなげやすくなります。丁寧なコミュニケーションが求められる分、信頼関係の強化にもつながります。
|
|
SBI型 |
サンドイッチ型 | ペンドルトン型 |
| 特徴 |
現状説明に加えて実際の行動がどんな結果につながったかを伝える手法 |
負の評価を前向きな評価で挟む手法 | 評価者からの報告だけでなく対象者自身に改善点を考えさせる手法 |
| 期待できる効果 |
対象者の理解を得やすい |
対象者のモチベーションの低下を軽減する | 対象者の主体性がはぐくまれる |
| 主な手順 |
➀Situation(状況) |
➀褒める ➁指摘する ➂褒める |
➀評価者による説明の目的や内容の確認 ➁良かった点の報告 ➂対象者による改善点の考案 ➃両者による今後の計画 |
フィードバックの具体例
ここではサンドイッチ型・SBI型・ペンドルトン型それぞれの実用的なフィードバックの具体例を紹介します。
サンドイッチ型の手順や具体例
サンドイッチ型は、指摘事項や改善点などのネガティブなフィードバックがある場合におすすめの手法です。サンドイッチ型を取り入れる際は、以下の手順で進めましょう。
➀ポジティブなフィードバック=褒める
➁ネガティブなフィードバック=指摘や改善策の提案
➂ポジティブなフィードバック=褒める
上記の手順をビジネスで活用する際の例文は、以下の表のとおりです。
| 手順 | 例文 |
| ➀ポジティブなフィードバック(=褒める) | プレゼンの資料内容が充実しており、会場にいた方からとても好評でした。 |
| ➁ネガティブなフィードバック(=指摘や改善策の提案) | しかし、質疑応答の対応に時間がかかり、全員が納得する回答ができていなかった点も見られました。あらかじめ指摘されやすい箇所を把握し、回答を準備しておくとよいかもしれません。 |
| ➂ポジティブなフィードバック(=褒める) | プレゼンの説明や資料は問題なくたいへん素晴らしい出来でしたので、今度社内で共有させていただきます。 |
ネガティブなフィードバックでは、どうすればよいか具体的なアドバイスを取り入れることで、対象者のモチベーション低下を防げるでしょう。
SBI型の手順や具体例
SBI型は、ポジティブとネガティブどちらのフィードバックにも効果的です。フィードバックで具体的な行動を振り返る際に役立つ方法でもあります。SBI型を活用する際は、以下の手順で説明を進めます。
➀Situation(状況)=いつ、どこで起きたことか
➁Behavior(行動)=実際にとった行動
➂Impact(結果)=行動の結果感じたこと
上記の手順をポジティブなフィードバックとしてビジネスで活用する際は、以下の表のように説明しましょう。
| 手順 | 例文 |
| ①Situation(状況) =いつ、どこで起きたことか |
先週の会議での出来事です。 |
| ➁Behavior(行動) =実際にとった行動 |
あなたは疑問が生じた際、発言者に積極的に質問をしていました。会議にいるメンバーはあなたの積極的な態度に感化され、次第に全体の発言が増えて意見が飛び交う素敵な議論ができました。 |
|
➂Impact(結果) |
スタート直後はなかなか発言が見られなかったため、会議の雰囲気が良くなりたいへん助かりました。 |
また、ネガティブなフィードバックでは、以下の表のように説明します。
| 手順 | 例文 |
| Situation(状況) =いつ、どこで起きたことか |
先日の会議の準備を進めている際の出来事です。 |
| ➁Behavior(行動) =実際にとった行動 |
あなたに、会議で使用する資料を会議の1週間前までに提出するようお願いしました。しかし、あなたは会議前日に提出をしてきました。 |
| ➂Impact(結果) =行動の結果感じたこと |
確認漏れが起こるリスクを招くだけでなく、印刷などの準備が大幅に遅れました。大切な資料の準備をあなたに任せない方がよいのではと、部署全体にあなたに対してマイナスのイメージが広がりました。 |
順序立てて伝えることで、対象者がいつどんな状況での出来事だったかを振り返りやすくなります。また分かりやすい説明は、対象者の理解を得られるでしょう。
ペンドルトン型の手順や具体例
ペンドルトン型は、SBI型と同じくポジティブとネガティブどちらにも効果的なフィードバック方法です。施策やプロジェクトに対して、より具体的に振り返りたいときにおすすめの方法です。ペンドルトン型を活用する際は、以下の手順でフィードバックを実施します。
➀内容の確認
➁よい点の振り返り
➂改善点の抽出
➃具体的な行動計画
⑤まとめ
上記の手順をビジネスで活用する際は、以下の表のように説明しましょう。
| 手順 | 例文(対象者) | 例文(評価者) |
| ➀内容の確認 | 先日の会議についてです。わたしは、資料作成を担当しました。 |
まずは、会議での資料作成について振り返ってみましょう。どのような点を意識して取り組まれましたか? |
| ➁よい点の振り返り | 例年の資料を参考にしつつ最新の情報を盛り込み、資料のアップデートを試みました。いままでにないクオリティで作成できたのではないかと思っています。 | 会議資料、素晴らしい出来でした。図や表を用いた説明は視覚的にも分かりやすく、参加者は有意義な会議の時間を過ごせたのではないかと思います。 |
| ➂改善点の抽出 | しかし、資料を整理するのに多くの時間がかかりました。また、資料の確認を願い出たのが会議の前日となり、多くの方にご迷惑をおかけしてしまいました。 | そうですね。情報量の多い資料の作成にはたくさんの時間がかかります。今回の反省は今後にどう活かそうと考えていますか? |
| ➃具体的な行動計画 | 資料作成の進捗状況をこまめに確認し、上司に報告するよう心がけます。どうしても間に合いそうにない場合はアドバイスをいただき、必要な情報と不要な情報の整理をし、効率よく準備が進められるようにします。 | 素晴らしい改善策です。ぜひ、今後に活かしていただきたいです。 |
| ⑤まとめ | 1ヶ月後に会議があり、資料制作を任されているため、スケジュールをしっかりと管理して準備を進めたいと思います。 |
今回の振り返りを通して、学びが次の行動に結びついていることがよく分かりました。次の会議も期待していますので、引き続き頑張ってください。 |
評価者は必要に応じて補足を加え、対象者が前向きに考えられるようアドバイスをしましょう。
効果的なフィードバックを行うためのポイント
効果的なフィードバックを行うためには、意識したいポイントが7つあります。ここでは、各ポイントについて解説します。
具体的な内容を伝える
フィードバックを行う際には、具体的に伝えることを意識しましょう。たとえば、「プレゼンが良くなかった」だけでは、どこに問題があるのか理解できません。そのため、「プレゼン内容はよかった。しかし、早口で聞き取りにくい」というように、具体的な内容や良い点・悪い点などを伝えるようにします。
指摘に対する理由を明確化して伝える
指摘するだけでなく、その理由を明確に伝えることも大切です。具体的な部下の行動や状況を指摘するだけでは、部下が納得できないケースもあります。そのため、なぜその行動や良いのか、悪いのか、明確な理由を含めて伝えることが重要です。論理的であればあるほど相手は納得しやすくなり、フィードバックへの信頼感が高まります。
今後どうすべきかまでアドバイスする
フィードバックでは、問題点を指摘するだけではなく、今後改善するためにはどうすればいいのか具体的なアドバイスをすることが大切です。ただし、単に答えを教えたのでは意味がありません。アドバイスによって部下が自ら考えるきっかけを作ることや、自発的に解決方法を見つけられるように手助けをすることも意識しましょう。
フィードバックはすぐに行う
フィードバックはできるだけすぐに行うことが重要です。行動から時間が経過してしまうと記憶が曖昧になり、フィードバックをしても理解できないケースもあるためすぐに実施するといいでしょう。できるだけ早くフィードバックをすることで、改善のスピードも早くなり部下の成長にもつながります。
信頼関係を築いておく
普段から部下とコミュニケーションを取って、信頼関係を築いておくことも大切です。信頼関係が構築されていれば、アドバイスや指摘などを部下が受け入れやすくなるため、フィードバックが行いやすくなります。信頼関係が築けていないと、部下は身構えてしまい上手く指摘が伝わらないケースもあるため注意しましょう。
部下に気付きを与える質問をする
フィードバックは上司の考えを押し付けるのでは上手くいきません。部下に答えや自分の考えを押し付けるのではなく、気付きを与えるような質問をしましょう。 たとえば、「次はこうするといいのでは?」「理解できたかな?」など、提案をしたり確認を入れたりするのがポイントです。確認することで、部下も質問しやすくなります。
ポジティブな視点も積極的に取り入れる
問題点を指摘する際には、ポジティブな内容も取り入れるようにしましょう。ネガティブな内容に偏りすぎてしまうと、部下のモチベーション低下につながります。そのため、問題点を指摘する際にはポジティブとネガティブを組み合わせたサンドイッチ型を積極的に活用するなど、ポジティブな内容も含めると効果的です。
フィードバックで効果が出ない時の対処法
フィードバックは、相手の成長や行動改善を促す重要なコミュニケーション手段ですが、うまく伝わらなければ逆効果になることもあります。ここでは、フィードバックをしても効果が見られない場合に見直すべきポイントや、改善のための対処法をご紹介します。
1. 目的を明確にする
フィードバックの目的が曖昧なままだと、受け手に響きません。「成長を促す」「行動を改善する」など、何のためにフィードバックをしているのかを最初に共有しましょう。
2. タイミングを見直す
フィードバックは早すぎても遅すぎても効果が半減します。できるだけ行動直後など、記憶が新しいうちに伝えることで、相手も状況を思い出しやすくなり、納得感が高まります。
3. 伝え方を変える
ネガティブな指摘ばかりだと、相手の防御反応を招き逆効果になることもあります。ペンドルトン型やSBI型など、ポジティブ要素も含めたフィードバック手法を使って、受け入れやすい形にしましょう。
4. 相手の理解度を確認する
フィードバックが一方通行になっていませんか?相手が本当に理解しているか、質問をしたり言葉で言い換えてもらったりして、理解度を確認することが大切です。
5. 信頼関係を築く
日頃のコミュニケーションが希薄だと、どれだけ正しいフィードバックでも届きません。普段から雑談やねぎらいの言葉を交え、信頼を土台にすることが、効果的なフィードバックには不可欠です。
まとめ
フィードバックとは、過去の行動を振り返り、未来の成長へと繋げる大切な対話です。重要なことは、相手の成長と目標達成を真剣に願い、具体的かつ建設的に伝えることです。そうすれば、相手は自身の強みや課題を理解し、前向きに改善へ取り組むことで、やる気を高め、結果として個人やチームの目標達成へと繋がります。この対話を通じて信頼関係も深まり、組織全体の力も高まります。ぜひ、フィードバックの効果を最大限に高めていきましょう。