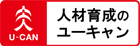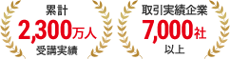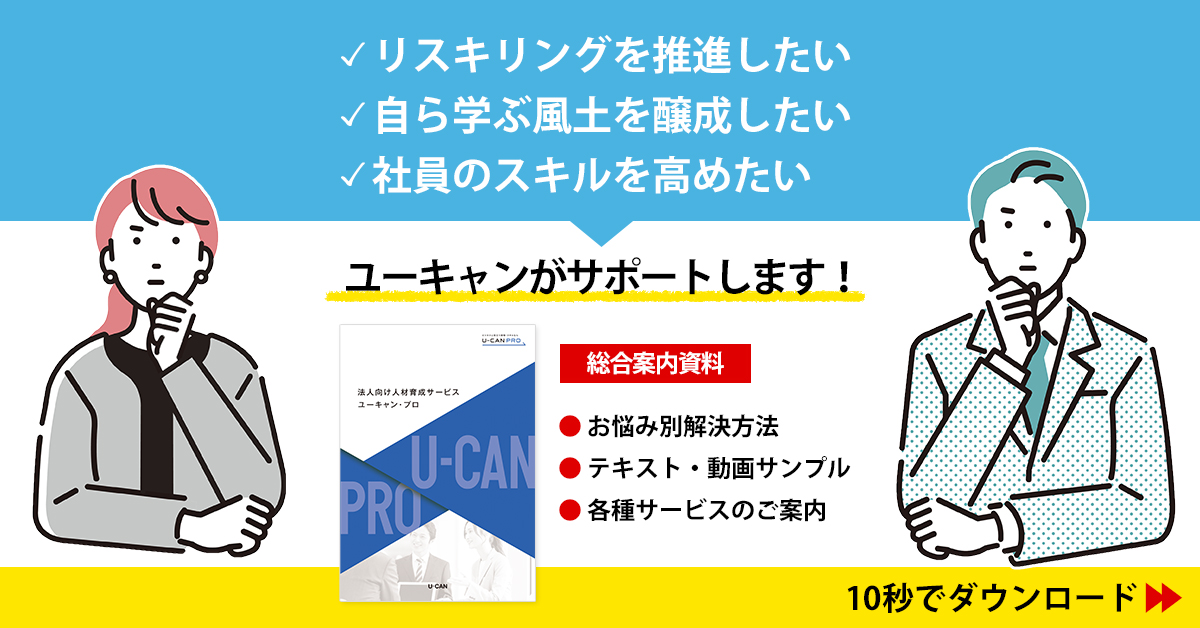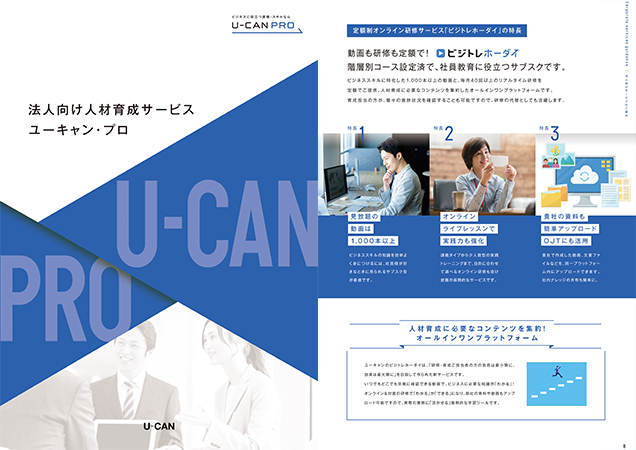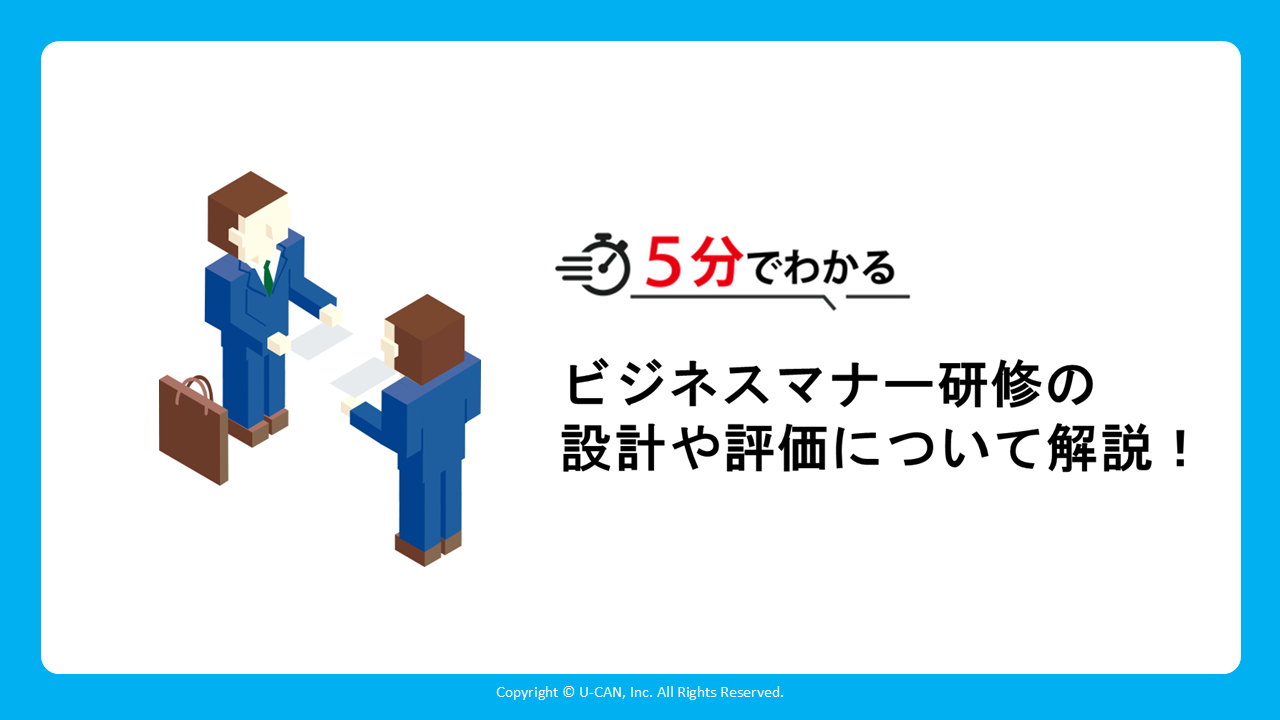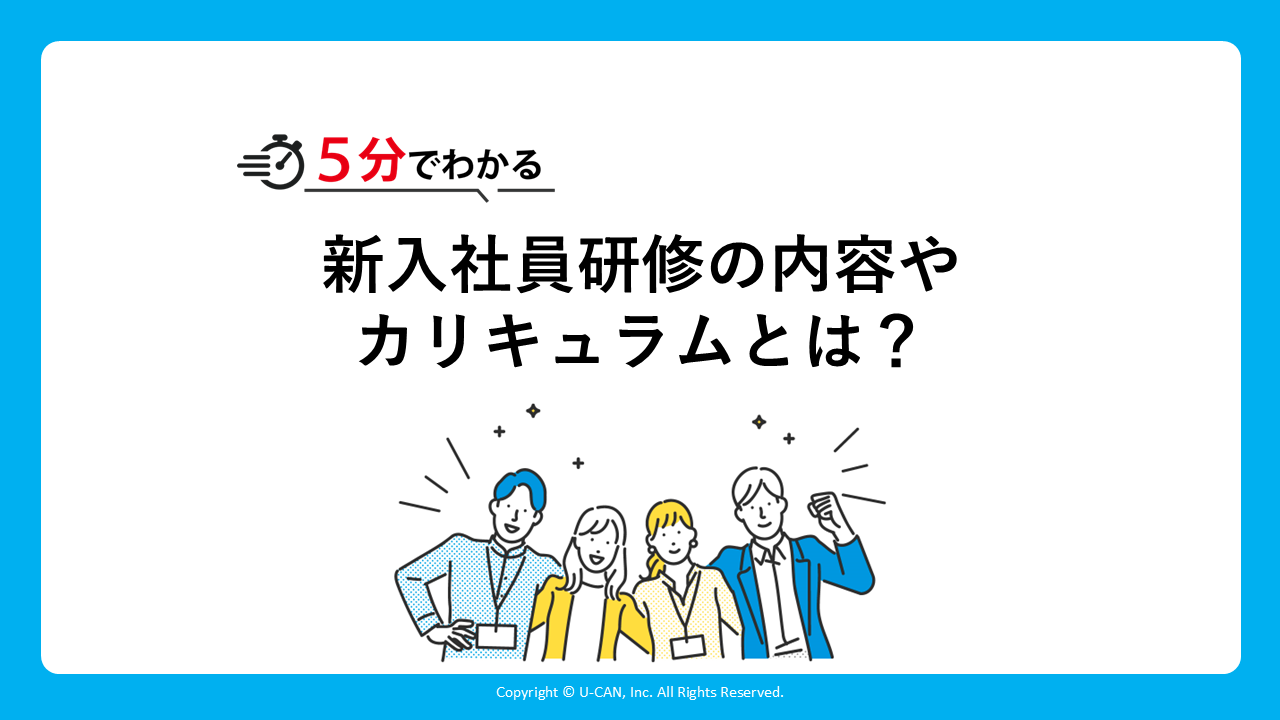オンボーディングとは何か
オンボーディングとは、新入社員が早期に組織に適応し、活躍できるよう支援する仕組みです。語源は「船に乗る」を意味する“on board”で、1970年代に米国企業で広まった人材定着施策に由来します。
人材育成とカスタマーサクセスにおけるオンボーディング
オンボーディングとは、新たな関係者がスムーズに組織やサービスに適応し、早期に成果を上げられるよう支援するプロセスです。社内では新入社員や異動者に対し、企業文化、業務知識、ツールの使い方などを体系的に伝えることで、早期戦力化と定着を促進します。たとえばIT業界では入社後すぐにプロジェクトへ参画できるよう、eラーニングやメンター制度を取り入れたオンボーディングが一般的です。社外では、顧客が導入した商品やサービスを正しく理解・活用できるよう支援するカスタマーサクセスの一環としても活用されます。SaaS業界では、導入時の操作説明や活用事例紹介を通じて顧客の定着と満足度向上を図ることも多いです。このようにオンボーディングは、企業の内外における関係構築と成果創出を加速する重要な仕組みであり、業界や目的に応じて手法や内容が工夫されています。
オンボーディングの目的
職場への順応を円滑にする
オンボーディングの目的のひとつは、入社した従業員が職場へスムーズに適応するための支援です。オンボーディングにより、職場のルールや組織体制などを教育して、企業の戦力になるように支援します。入社直後で知るべきことが多い新しい従業員の教育に効果的です。
教育格差をゼロにする
オンボーディングは、企業内の教育レベルの差を減らす目的で導入される場合があります。部署や教育担当者によって生じやすい教育方法の違いや質の差を埋め、すべての従業員が平等かつ公平に教育を受けるために有効な手段です。
早期退職を防ぐ
入社間もない従業員の早期退職の防止にも、オンボーディングは有効です。ミーティングや面談を実施して、従業員が相談しやすい環境づくりに取り組みます。早期退職の原因にもなりえるコミュニケーションや業務への理解不足を改善するために効果的です。
オンボーディングが注目を集める背景とは
働き方、ワークスタイルの変化
オンボーディングが注目される背景には、コロナ禍以降のリモートワーク普及による働き方の変化があります。対面での指導や社内交流が難しくなり、新入社員や異動者が孤立しやすくなるという課題が顕在化しました。そこでZoomやSlack、LMS(学習管理システム)などのオンライン研修ツールを活用し、業務知識の共有やコミュニケーション支援を行うオンボーディング施策が急速に導入されています。企業はこうした仕組みで早期定着と戦力化を目指しており、注目を集めています。
関連リンク:オンライン研修のメリット・デメリットとは? 実施のポイントや注意点も解説
人材不足
人材不足が深刻化する中、企業は早期に新入社員の戦力化が求められています。そのため、オンボーディングを通じて組織文化や業務理解を効率的に促進し、離職防止と即戦力化を両立させる取り組みが注目されています。
入社間もない従業員の早期退職
入社間もない従業員の早期退職が増える中、組織への定着や業務理解を支援するオンボーディングの重要性が高まっています。適切な導入教育やフォローを行うことで、離職防止と早期戦力化を両立させ、企業の人材不足対策にもつながります。
オンボーディングとOJT・Off-JTの違い
オンボーディングは職場や組織の環境・風土に馴染んでもらうことが目的であり、スキルアップを目的とするOJTやOff-JTとは違いがあります。どのような違いがあるのか紹介します。
OJTとの違い
OJTは、現場の業務に取り組みながら、実践的に知識や技術を教育する方法です。OJTとは、On The Job Trainingの頭文字を取っています。オンボーディングは、OJTよりも支援する内容や範囲が広く、社内の人間関係や企業風土に馴染むための支援も含まれます。
OJTについて詳しく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。
OJTとは? |ユーキャンの法人向け人材教育サービス
Off-JTの違い
Off-JTは職場や業務中といった仕事環境から離れ、別の場所と時間を確保したうえで行う研修や教育です。目的は従業員の知識やスキルの習得であり、職場環境への適応を目的とするオンボーディングとは根本的に違います。
オンボーディングのメリット
企業がオンボーディングを導入するメリットは、以下の4つです。
- ・生産性の向上
- ・従業員の満足度の向上
- ・人材育成の体制整備
- ・採用コストの削減
以下で詳しく解説します。導入を検討する際の参考にしてください。
生産性の向上
オンボーディングを導入することで、生産性の向上につながります。オンボーディングの実施には、全社的な社員教育に対応できる仕組みや体制の構築が必要になります。教育体制の構築により、業務の効率化や生産性の向上が期待できます。
社内の生産性にお困りの場合は、以下の講座をご覧ください。
業務改善・効率化講座(eラーニング)|ユーキャンの法人向け人材教育サービス
従業員の満足度の向上
オンボーディングは、従業員の満足度を高める効果があります。オンボーディングの実施に伴い、既存の従業員と入社間もない従業員との間にコミュニケーションが生まれ、組織の活性化につながります。
既存の従業員と入社したての従業員両方にメリットがあり、組織に対する従業員の満足度が高まるため、退職を防ぎ、人材の定着につながります。企業の業績を上げる重要なポイントです。
人材育成の体制整備
オンボーディングの導入を通じて、社内における人材育成の体制の確立・強化が実現できます。従業員の定着率を改善しながら、入社したての従業員を即戦力として育成することが可能になります。即戦力として育成するためには、教育方法の統一やマニュアル作成が大切です。
人材育成について詳しく知りたい人は、以下のページをご覧ください。
人材育成とは?|ユーキャンの法人向け人材教育サービス
採用コストの削減
オンボーディングにより、早期退職者を減らすことができれば、採用コストの削減にもつながります。新たに入社した従業員が早期退職すれば、採用や教育などのさまざまなコストが増え、人材採用による効果も十分に発揮できません。
就労人口が不足している現代では、従業員1人あたりの採用・教育にかかるコストは増加傾向です。採用・教育コスト削減は大きなメリットとなります。
組織文化の浸透と帰属意識の強化
オンボーディングは、単なる業務習得支援にとどまらず、組織文化の浸透にも大きな役割を果たします。初期段階から企業の理念や行動指針、価値観を一貫して伝えることで、新入社員や異動者が自社の方向性を理解しやすくなり、行動の基準が明確になります。特にメンター制度や座談会などを通じた対話の機会は、形式的な研修では伝わりにくい組織の雰囲気や文化の共有に効果的です。こうしたプロセスを経ることで、参加者は自らを組織の一員と感じやすくなり、帰属意識やエンゲージメントが高まります。その結果、離職防止や自発的な行動の促進にもつながります。
オンボーディングの導入プロセス
オンボーディングは、以下の導入プロセスに沿って実施します。
1.目標を設定する
2.プランを立案・作成
3.実行と振り返りをする
それぞれについて、以下で詳しく解説します。
1.目標を設定する
導入にあたって、最初にすべきことはどのような成長を遂げてほしいのか、目指してもらいたい姿を目標設定することです。例えば営業職なら自力で新規契約を獲得する、事務職なら会議のファシリテーターを担うなど、具体的なイメージを目標にしましょう。また各目標には一定の期限を設けておくことで、社員の成長や目標の進捗状況が把握しやすくなります。重要なことは具体的な目標を設定することと、期間内に達成可能な目標であることです。この2点を重視することで、支援を受ける従業員もモチベーションアップにつながり、成長の方向性をつかみやすくなります。
短期目標と長期目標の設定方法
オンボーディング導入時は、期間ごとに短期・長期の目標を段階的に設定することが重要です。たとえば、次のような期間別での目標設定例があります。
・1週間:社内システムの基本操作習得
・1ヶ月:業務フローの理解と簡単なタスク完了
・3ヶ月:独立した業務遂行
・6か月:部門目標への貢献
これらの目標はさらにSMART原則(具体的・測定可能・達成可能・関連性・期限)に基づき、「1ヶ月以内に3件の顧客対応を上司の確認なしで完了する」といった形で具体化することが成功の鍵です。
KPIの決め方
オンボーディングの効果を測定するには、明確なKPI設定が不可欠です。たとえば「業務習得期間」「初期離職率」「OJT進捗率」「入社後3ヶ月の自己評価・上司評価」などが代表例です。業種によって重視すべき指標は異なり、次のようなKPI設定例もあります。
・営業職:初契約までの日数
・IT業界:担当案件数やバグ対応数
・接客業:顧客対応満足度
役割や業種に応じて成果と成長を数値で可視化することが、適切な運用の鍵です。
2.プランを立案・作成
オンボーディングの目標を設定したら、次は具体的なプランの立案と詳しいカリキュラムの作成に入ります。プランを立案・作成する際は、従業員の職場の上司や同僚、関連部署の意見も取り入れながら、必要な支援内容を決定していきます。例えば事務職であれば資料作成スキルとPC操作スキル、エンジニアなら必要なプログラミング言語の習得などです。実際に実務で必要なスキルや求められる姿に沿ってプランを作ることで、支援を受ける従業員側も成長を実感しやすくなります。
対象者別プランニングのポイント
対象者別オンボーディングプランのポイントは次の通りです。
| 対象者 | プラン作成のポイント | アプローチ方法 |
| 新卒 | 基礎構築の研修と職場適応を支援する内容 | マナー、制度理解、OJTを段階的に実施する |
| 中途採用 | 即戦力化につながる内容 | 組織文化の理解と業務フローを早期共有する |
| 管理職 | 企業戦略の浸透と人間関係構築スキル向上につながる内容 | 経営方針の理解、関係部署との連携を強化する |
必要なリソースと準備物
オンボーディングを導入する際は、以下のリソースが必要になります。
| 人的リソース | 物的リソース |
| ・教育担当者(OJTトレーナー) ・人事・総務担当者 ・メンター・上司 | ・業務マニュアル ・社内システム(LMS、チャットツール等) ・PC、IDアカウント、デスク・備品 |
3.実行と振り返りをする
最後に作成したプランに基づいて実行し、その後の振り返りを行います。実行の段階では、プランに沿って実施しつつ、計画を進めながら内容の調整も行います。計画通りに進むケースもあれば、思うように進まないケースもあるでしょう。まずは従業員が環境へ適応できるように、負担を感じない範囲で進めることが重要です。そして実施後は次回のオンボーディングに生かすための振り返りと評価を行い、改善点を検討します。振り返りでは実際にオンボーディングを受けた従業員も参加し、支援を受けた側からの意見も交えることで、より効果的な施策へと発展していきます。
効果測定の方法
オンボーディングの効果測定には、定量的手法と定性的手法の併用が有効です。定量的には、業務習得スピード、初期離職率、成果指標(営業成績や対応件数)などをKPIとして評価します。定性的には、定期的なアンケートや1on1面談を通じて、理解度や不安の有無、職場適応状況などを確認しましょう。これらの情報を基に、プランの改善や支援の再設計を行うことで、オンボーディングの質を継続的に高めることができます。
PDCAサイクルの回し方
オンボーディングにおけるPDCAは、Planで対象者別プランを策定し、Doで実施(研修・OJT・面談)します。Checkではアンケートや業務成果を通じて効果を測定し、Actで内容や進行方法を改善し、再びPlanへと戻ります。このPDCAサイクルを繰り返すことが、オンボーディングの質向上において重要です。たとえば「業務理解が遅い」という課題に対し、Checkで面談結果を分析し、Actでマニュアルを動画形式に変更した結果、理解度が向上したケースもあります。
オンボーディングを導入する際のポイント
オンボーディングは、以下のポイントを意識して導入します。
- ・教育体制を整備する
- ・企業と従業員間の期待値を確認する
- ・良好な人間関係づくりをサポートする
- ・指導者を育てる
- ・全社的にオンボーディングへの意識づけをする
教育体制を整備する
オンボーディングを導入する際には、入社直後の従業員が学びやすい仕組みを整えましょう。入社してすぐは、企業文化や職場のルールなど学ぶ内容が多岐に渡ります。教育体制を事前に整備しておけば、効率よく育成することが可能です。 いつでも確認できるマニュアルの作成や、社内の教育方法のすり合わせなど、教育体制の構築を進めましょう。
企業と従業員間の期待値を確認する
オンボーディングを導入する前に、企業と従業員の期待値を調整します。入社前からお互いの期待値に差があると、入社後に後悔や落胆となるため、事前に確認し、すり合わせることが大切です。インターンを活用して、互いが希望する条件や成果を共有できれば、入社後のミスマッチを未然に防止できます。
良好な人間関係づくりをサポートする
社内の人間関係づくりの支援は、オンボーディングにおいて重要なポイントです。入社したばかりでは、人間関係の相関や相談先はわかりません。周囲の支援があれば、従業員の負担が軽減されて、オンボーディングの成功率が高まります。入社したての従業員が相談できる窓口の設置や、チームもしくは部署メンバーが交流できるランチ会などを企画して、従業員を支援しましょう。
指導者を育てる
スモールステップ法は、設定した目標の実現を着実に可能にする手法です。スモールステップ法を活用して、入社間もない従業員の育成を実施をすれば、成功を実感しながら着実にスキルアップできます。教育担当者やチームで継続的に支援して、従業員の成長を促しましょう。スモールステップ法は、従業員の即戦力化を効率よく実現できる手法です。
関連リンク:https://www.u-can.co.jp/houjin/column/cl017.html
全社的にオンボーディングへの意識づけをする
オンボーディングは、社内全体で入社したての従業員を育成する動きが大切です。人事部や配属部署をはじめ、すべての従業員が入社を歓迎し、支援する体制が求められます。社内全体にオンボーディングへの理解を促す過程で、支援についても意識づけをしましょう。 例えば、従業員同士の自然な交流を生み出す取り組みを実施すれば、従業員が職場に馴染みやすくなります。
デジタルツールを効果的に活用する
オンボーディングでは、LMS(学習管理システム)やチャットツール、動画研修などのデジタルツールの活用が効果的です。LMSはeラーニングの進捗管理やテスト機能に優れ、体系的な学習の支援に向いています。チャットツール(例:Slack、Teams)は、気軽な質問や情報共有を促進し、孤立感の軽減にも有効です。動画研修は繰り返し視聴できるため、自分のペースで学習が可能です。それぞれの優れた点を組み合わせることで、効率的で柔軟なオンボーディングが実現できます。
オンボーディングの導入事例から学べることとは
近年、多くの企業がオンボーディングを導入し、課題解決に成功しています。以下で紹介する2社は、オンボーディングを導入した代表的な例です。オンボーディングの導入を検討する際の参考にしてください。
A社(インターネット関連会社)
A社は、従業員の帰属意識の希薄さに課題を抱えており、オンボーディングを活用した課題解決に取り組みました。社内全体で取り組む方法に切り替えたため、入社直後の従業員をすべての従業員で育成する風土が生まれ、課題解決につながった事例です。
B社(ソフトウェア開発会社)
B社は、企業規模が大きくなり、急激に従業員数が増加したことで、入社間もない従業員の経験値やスキルの差に課題がありました。入社後の3か月間限定で受講できる企業や自社製品について学べる研修の場を設けた結果、従業員のスキルが一定のレベルまで向上し、課題解決に成功しました。
まとめ
オンボーディングは、入社した従業員の職場への順応、早期退職の防止、教育格差をなくすなどの目的で実施する教育方法です。企業がそれぞれ抱える課題解決の方法として、多くの企業でオンボーディングが導入されています。導入する際は、社内全体で入社直後の従業員を支援する体制・仕組みを構築することが大切です。
ユーキャンの法人向け人材育成サービスは丁寧なヒアリングで課題を抽出し、それぞれの法人様にフィットする提案をしています。60年以上の歴史のなかで得たノウハウをもとに、人材育成を支援します。
オンボーディングを取り入れて人材育成に力を入れたいと考えている方は、以下のページをご覧ください。