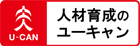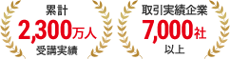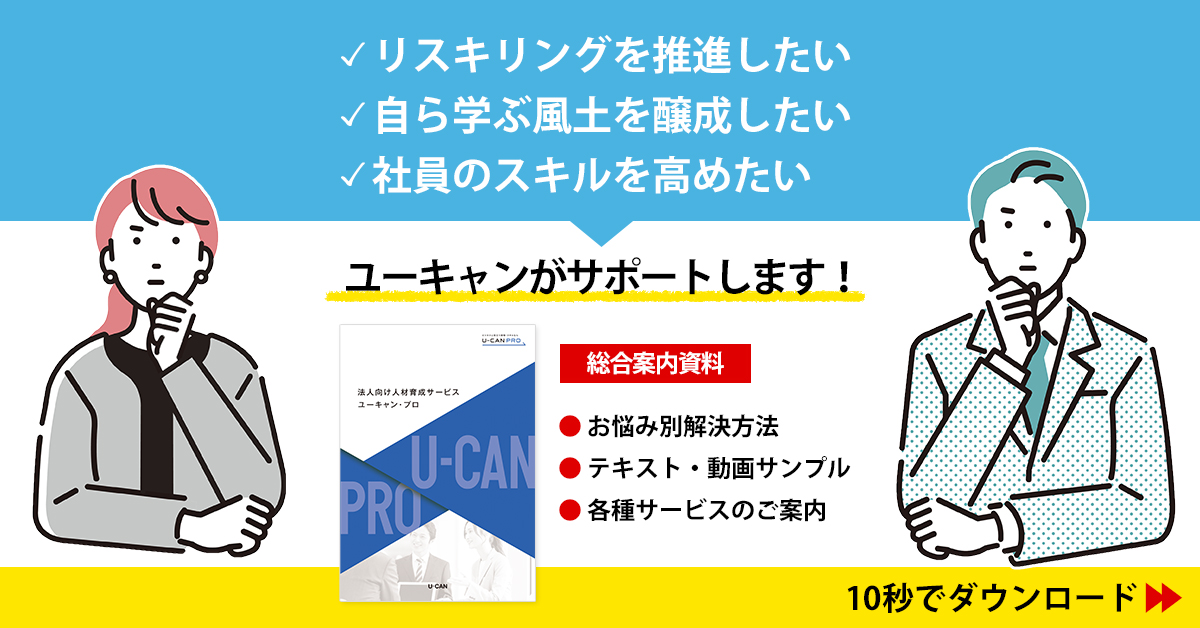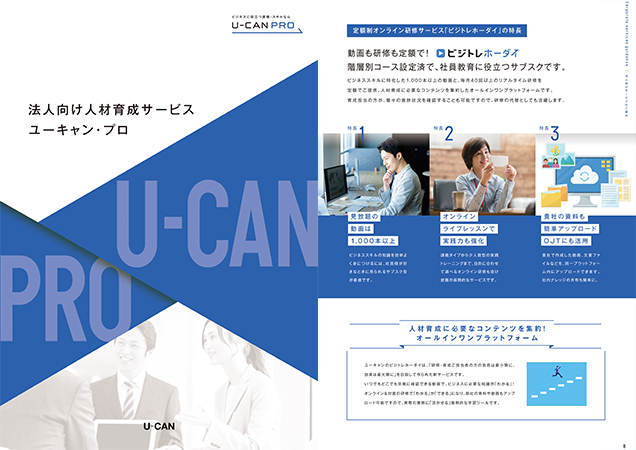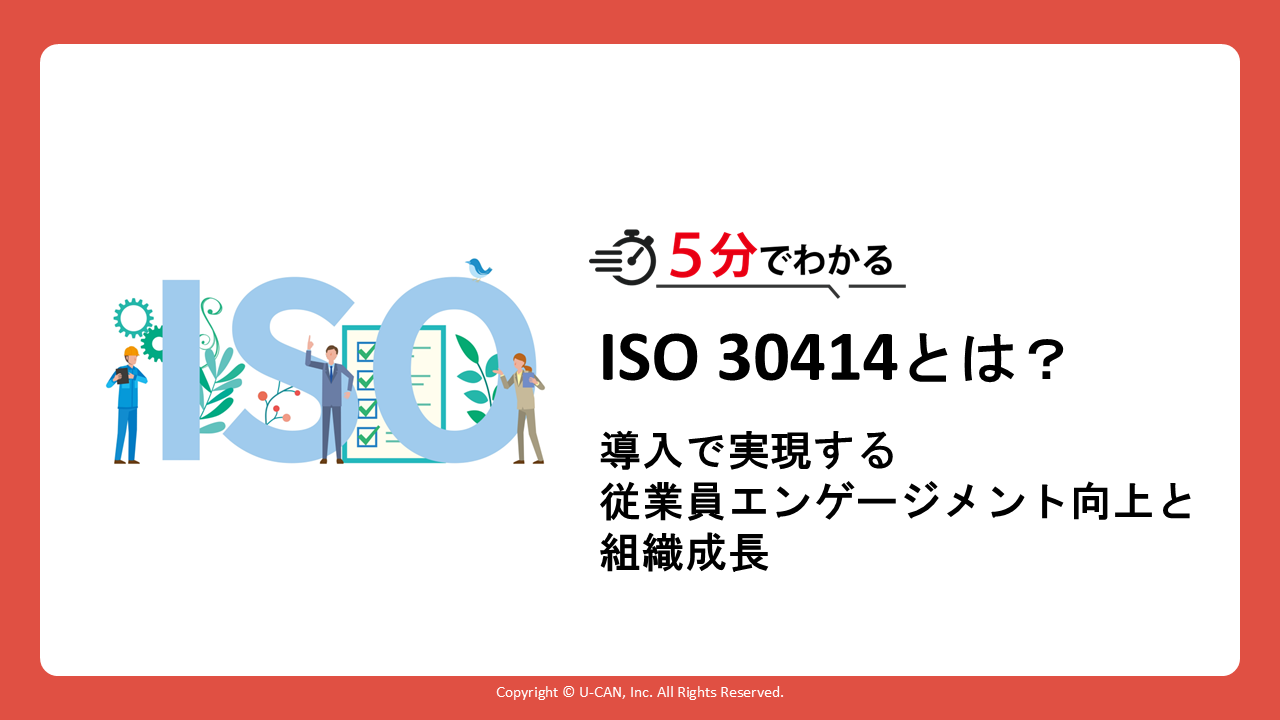人的資本経営とは?
人的資本経営とは、経済産業省によると「人材を資本としてみなし、人材の価値を最大限に引き出すことにより、中長期的な企業の価値向上につなげる経営のあり方」と定義されています。企業が投資する資本は「有形資本」と「無形資本」の2つに分類され、人的資本は無形資本にカテゴライズされます。
※参考:人的資本経営 ~人材の価値を最大限に引き出す~ (METI/経済産業省)
人的資本経営と従来の経営の違い
従来の経営では、人材は「資源」の1つと捉えられており、年功序列や終身雇用などで人材の囲い込みが行われてきました。一方で、人的資本経営では人材を「資本」として捉え、企業と人材が選び合う関係へと変革しています。
人的資本経営が注目されている背景・理由
人的資本経営が注目されるようになった2つの背景について解説します。
ESG投資への関心
ESG投資への関心の高まりは、人的資本経営が注目された背景として挙げられます。ESGとは、環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)のそれぞれの頭文字をとったワードです。人的資本経営は、社会(Social)、企業統治(Governance)の2つに深く関連があることから推し進める企業が増えています。
人材と働き方の多様化
人材と働き方の多様化は、人的資本経営が注目された背景の1つです。現在では、外国人従業員やシニア世代などが増加しているため、従来の人材管理では限界に達しています。そのため、それぞれの人材に適した働き方で価値を引き出す、人的資本経営が必要とされています。
イノベーション創出の重要性
人的資本経営が注目される背景のひとつに、イノベーション創出の重要性があります。変化の激しい現代において、企業は従来の延長線上ではなく、新たな価値やビジネスモデルを生み出す力が求められています。その原動力となるのが、多様なスキルや視点を持つ「人材」です。人的資本経営は従業員の能力を把握・可視化し、育成・活用することで組織内に創造性や挑戦意欲を育て、イノベーションの土壌を整えるアプローチです。また異なる価値観を尊重する文化や失敗を許容する風土の醸成も、人材活用と一体で進めることが求められます。こうした視点から人的資本は企業の成長戦略の中核と位置づけられており、注目が高まっています。
労働人口の減少
人的資本経営が注目される背景には、労働人口の減少という深刻な社会課題があります。日本では少子高齢化の進行により生産年齢人口が年々減少し、多くの企業が人手不足に直面しています。このような状況下では新たな人材の確保だけでなく、既存の人材一人ひとりの能力を最大限に活かすことが不可欠です。その点で人的資本経営は、従業員のスキルや経験を可視化し、適切に配置・育成・活用することで、組織全体の生産性向上と持続的な競争力確保を目指す考え方です。また多様な人材の活躍推進やリスキリングの支援を通じて、限られた人材資源を有効活用できる点も評価されており、企業にとって重要な経営戦略の一環となっています。
人的資本情報の開示要請
人的資本経営が注目される背景のひとつに、人的資本情報の開示要請の高まりがあります。近年ISO30414などの国際基準や金融庁・東京証券取引所によるガイドライン整備により、企業は人的資本に関する情報を有価証券報告書などで開示することが求められるようになりました。これにより投資家や社会は企業の人材戦略や育成方針、多様性の取り組みを評価する視点を持ち始めています。単なるコストとしての人件費ではなく、将来の価値創出に資する「資本」としての人材への投資のあり方が問われており、企業は人的資本経営を戦略的に推進する必要に迫られています。
企業競争力の源泉が人材へと移行
人的資本経営が注目される背景には、企業競争力の源泉が「人材」へと移行しているという大きな変化があります。これまでの競争力は、資金力や設備、技術などの有形資産に依存していました。しかしデジタル化や市場の変化が激化する中で、変化にも柔軟に対応し、新たな価値を創出できる人材の存在が、持続的な成長の鍵となっています。特に知識集約型産業やイノベーション創出が求められる現代では、従業員のスキルや創造性、多様な視点が企業価値に直結します。そのため人材を単なる労働力ではなく「資本」として戦略的に育成・活用する人的資本経営が、企業の競争優位を築く中核的な経営手法として注目されるようになりました。
リスキリング・再配置の必要性
人的資本経営が注目される理由のひとつに、リスキリングと人材の再配置の必要性があります。デジタル技術の進展や業界構造の変化により、従来のスキルや職能だけでは対応できない場面が増えています。こうした環境下で企業が競争力を維持するためには、従業員に新たなスキルを習得させ、適材適所での再配置を行うことが不可欠です。人的資本経営は、従業員のスキルやキャリア志向を可視化し、継続的な学びの支援と戦略的な人材活用を推進する仕組みです。この取り組みにより、個人の成長と組織の持続的な進化を両立させることができ、企業の柔軟な経営対応力を高めることにつながります。
従業員エンゲージメントと企業成果の関係性
人的資本経営が注目される背景として、従業員エンゲージメントと企業成果の強い相関関係が明らかになってきたことがあります。エンゲージメントの高い従業員は、仕事への主体性や責任感が強く、生産性の向上や顧客満足度の改善、離職率の低下にもつながります。こうした個々のパフォーマンス向上は、結果として企業の競争力や収益性の強化に直結する要素です。人的資本経営では従業員の満足度や働きがいに目を向け、継続的な育成やキャリア支援、働きやすい環境整備を通じてエンゲージメントを高めることを重視しています。そのため人的資本への投資はコストではなく、中長期的な企業価値向上の源泉と捉えられ、注目されています。
人材資本経営で企業に求められる開示情報について
人的資本経営の注目が高まる中で、日本では情報開示に関する制度的な整備が進んでいます。2022年に内閣官房が公表した「人的資本可視化指針」や、2023年3月期以降の有価証券報告書における開示義務化により、上場企業は人的資本に関する戦略的な方針と具体的な指標・目標の開示が求められています。企業に求められる開示情報は大きく分けて、コンプライアンス色の強い項目(例:研修時間、離職率、男女間賃金格差などの比較可能なデータ)と、戦略的意図を持った独自性の高い取組みの2種類です。特に後者では、経営戦略と連動した人材戦略を提示し、その取り組みがどのように企業価値の創出や財務パフォーマンスと結びつくかを、KPIを用いて定量的に開示することが重要です。また現在の人材に関する「As is(現状)」と、目指す「To be(理想像)」のギャップを明確にし、その解消に向けた施策と投資内容を具体的に説明することも求められます。さらに従業員のキャリア形成支援や人材ポートフォリオに関する方針など、人材活用の質を高める視点の開示も今後の課題とされます。加えて単なる実績値の羅列ではなく、自社のビジネスモデルと関連づけたストーリー性のある開示が期待されており、時系列データの提示や、進捗モニタリングに用いる社内指標の一部開示も有用です。人的資本がどのように価値創造とつながるかを明示することで、投資家や社会との信頼関係の構築につながります。
・サステナビリティに関する考え方および取組
人的資本経営における「サステナビリティに関する考え方および取組」の開示では、企業の戦略や経営課題と関連づけた重要性(マテリアリティ)の明確化が求められます。「戦略」や「指標・目標」を記載しない場合でも、その判断と根拠を説明することが望まれます。また女性管理職比率など多様性に関する指標は、連結ベースでの開示に努めるべきとされ、企業全体としての姿勢が問われる課題です。さらに気候変動などサステナビリティ上の重要課題については「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標・目標」の各枠組みに沿って開示することが期待され、人的資本とサステナビリティの統合的な情報開示が求められています。
・人的資本、多様性に関する情報
人的資本経営における「人的資本、多様性に関する情報」の開示では、人材育成や社内環境整備の方針、およびそれに基づく指標や目標の記載が必須とされています。特に「女性管理職比率」「男性の育児休業取得率」「男女間賃金格差」といった多様性に関する指標は、有価証券報告書等においても記載が求められ、提出企業および連結子会社を含む範囲での開示が推奨されています。また任意で補足情報を追加することも可能であり、実績値の記載にあたっては注記内容の明確化も企業の信頼性向上において重要です。これにより、企業のダイバーシティ推進に関する姿勢と実績が、より透明に評価されるようになります。
・コーポレートガバナンスに関する情報
人的資本経営において求められる「コーポレートガバナンスに関する情報」の開示では、取締役会や委員会の運営状況や監査体制の実効性に関する情報の透明性が重視されます。具体的には取締役会・指名委員会・報酬委員会の開催頻度や検討内容、出席状況の開示が求められ、意思決定プロセスの健全性を示すことが重要です。また内部監査の実効性については、デュアルレポーティング体制の有無などを含めて説明することが期待されます。さらに、政策保有株式と発行会社との関係についても業務提携などの概要を記載する必要があります。
参考:https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230131/20230131.html
人的資本経営における「3つの視点」「5つの共通要素」
人材版伊藤レポートとは、経済産業省が開催した、人的資本に関する研究会の成果をまとめたレポートです。ここでは、人材版伊藤レポートをもとに、人的資本経営における3つの視点、5つの共通要素について解説します。
人的資本経営における「3つの視点(3P)」
人材版伊藤レポートでは、人的資本経営において人材戦略に必要な3つの視点(Perspectives)を定めています。
1.経営戦略と人材戦略の連動
2.As is-To beギャップの定量把握
3.企業文化への定着
人的資本経営を進める際には、経営戦略と連動させた人材戦略を策定し、実行する必要があります。目標(To be)が決まったら、目標とのギャップ(As is-)を定量的に把握し、定期的に見直すことが大切です。企業文化として定着させるためには、経営陣が人材戦略に関して積極的に発信し、従業員と直接対話するのが有効です。
人的資本経営における「5つの共通要素(5F)」
人材版伊藤レポートでは、人的資本経営において人材戦略に必要な5つの共通要素(Factors)を定めています。
1.動的な人材ポートフォリオ
2.知・経験のダイバーシティ&インクルージョン
3.リスキル・学び直し
4.従業員エンゲージメント
5.時間や場所にとらわれない働き方
経営戦略を実現する際には、必要な人材を定義し、採用・育成計画を立てる必要があります。中長期的に企業価値を高めるためには、多様な人材を取り込むことも大切です。個人のリスキル・学び直しは、従業員の価値観の多様化に対応するために必要です。
人的資本経営のメリット
人的資本経営は、従来の経営にはないメリットが得られる経営スタイルです。ここでは、人的資本経営のメリットについて解説します。
投資家が投資してくれる可能性がある
投資家が投資してくれる可能性がある点は、人的資本経営のメリットとして挙げられます。現在では、人的資本に投資する企業に関心をもつ投資家が増えています。そのため、多くの投資家に人的資本経営を推進している企業だと知らせることで、積極的な投資を促せるでしょう。
企業ブランドの向上につながる
企業ブランドの向上につながるという点も、人的資本経営のメリットです。人的資本経営を行っていると、従業員のことを考えている企業であると想定されるためです。投資家からだけではなく、世間からの企業イメージも向上することが期待できます。
生産性や従業員のエンゲージメントが向上する
生産性やエンゲージメントが向上するという点も、人的資本経営のメリットの1つです。人的資本に投資することで、従業員の質が上がり、生産性も向上するためです。また、働きやすい環境の整備により、エンゲージメントの向上にもつながるでしょう。
従業員の能力最大化が図れる
人的資本経営の大きなメリットのひとつが、従業員の能力を最大限に引き出せることです。従業員一人ひとりのスキルや経験、価値観、キャリア志向などを可視化・把握することで、適材適所の人材配置が可能となり、個々が最も力を発揮できる環境を整えることができます。またリスキリングや研修といった成長機会を提供することで、継続的なスキル向上や新たなチャレンジの後押しも可能です。結果として従業員のモチベーションやエンゲージメントが高まり、組織全体の生産性や創造性の向上につながります。人的資本経営は、企業の持続的成長を支える基盤として、能力の最大化を実現する有効なアプローチです。
イノベーションが促進できる
人的資本経営を推進することで、イノベーションの促進が期待できます。多様なバックグラウンドや価値観を持つ人材を積極的に登用し、それぞれの強みや視点を活かすことで、従来にない発想やアイデアが生まれやすくなります。また学び直し(リスキリング)や成長機会の提供により、従業員の知識やスキルが常に更新され、新しい技術や市場への適応力が高まる点もメリットです。さらに心理的安全性の高い職場を整えることで、挑戦や提案がしやすくなり、組織内に創造的な風土が醸成されます。このように人的資本経営は人材の力を起点とした継続的な価値創出を可能にし、企業の競争力強化につながります。
人的資本経営を実践する際の手順
人的資本経営を行う際の手順について、4つのステップに分けて解説します。
1.経営戦略と人材戦略を連動させる
人的資本経営を実践する際は、まずは経営戦略に沿った人材戦略を策定しましょう。経営戦略を実現するためには、人材戦略と連動させることが重要です。経営に関する課題を整理したうえで、人材戦略に反映させるのがポイントです。
2.目指す姿と現在の姿のギャップを明確にする
自社が目指す姿(To be)を設定し、現在の姿(As is)とのズレや違いなどのギャップを明確にしましょう。ギャップを把握する際には、基本的には人事がイニシアチブをとって、従業員の経験やスキルを収集し、分析します。
3.ギャップを埋めるための施策を考える
自社が目指す姿と現在の姿のギャップを埋めるための施策を考えましょう。施策を考案する際には、施策を投資として捉え、自社が目指すべき姿から逆算して考えるのがポイントです。
4.施策を実行して効果検証する
施策を実行して、効果検証をしましょう。施策の精度を高めるポイントは、PDCAを回すことです。定期的にモニタリングして、施策による変化や目標達成度を把握するようにしましょう。
人的資本経営を実践する際のポイント
人的資本経営を実践する際には、自社の内情や目標などを踏まえた設計にすることが重要です。どのようなポイントが重要になるのか、3点を紹介します。
経営戦略と人材戦略の連動
人的資本経営を実践するうえで重要なのが、経営戦略と人材戦略を連動させることです。企業が中長期的に持続的成長を実現するためには、事業目標の達成に向けて、どのような人材が必要で、どのように育成・配置・活用すべきかを明確にする必要があります。たとえばDX推進を経営課題とする企業であれば、ITスキルを持つ人材の採用やリスキリングが不可欠です。経営戦略と整合性のある人材戦略を策定し、組織の方向性と従業員の成長が一体となることで、人的資本の最大活用と企業価値の向上が可能となります。
人材の見える化とデータ活用
人的資本経営を実践するうえで欠かせないのが、人材の見える化とデータ活用です。従業員一人ひとりのスキル、経験、価値観、キャリア志向といった情報を把握・可視化することで、適切な配置や育成、キャリア支援が可能になります。また人事データを活用して離職傾向や人材の強み・課題を分析することで、より戦略的な人材マネジメントが実現できます。人的資本を単なる「コスト」ではなく「投資対象」と捉えることができ、企業全体の生産性や組織力の向上にも効果的です。さらにデータに基づいた判断は、社内外への説明責任や信頼性の確保にもつながります。
KPIに基づく成果の定量評価と開示
人的資本経営を実践するには、KPI(重要業績評価指標)に基づく成果の定量評価と開示が重要です。人的資本に対する取り組みが企業価値や成果にどう結びついているかを明確にするためには、研修時間、離職率、エンゲージメントスコア、多様性指標などのKPIを設定し、数値として管理・評価することが求められます。これにより経営戦略との連動性や課題が可視化され、改善につながります。またこれらの指標を社内外に開示することで、企業の透明性や信頼性が高まり、ステークホルダーからの評価や投資判断にも良い影響を与えられるでしょう。
人的資本経営を実践する企業事例
人的資本経営は労働者人口の減少が続く日本企業にとって、人手不足解消につながる重要施策です。実際に人的資本経営を実践している企業の事例について、3社紹介します。
花王
花王株式会社は、人的資本経営を積極的に推進している代表的な企業のひとつです。同社は「Kirei Lifestyle Plan」というESG戦略の一環として、2030年までのコミットメントを示した人的資本を中核に据えた取り組みを行っています。特に力を入れているのが、人材育成、ダイバーシティ推進、働きがいのある職場づくりです。たとえば全従業員を対象としたキャリア開発支援制度、女性管理職比率向上のためのリーダーシップ研修、柔軟な働き方を実現する在宅勤務制度など、多角的な施策を展開しています。また有価証券報告書では、研修時間や多様性関連KPIなどを開示し、人的資本の可視化と透明性の確保にも注力している点も特徴です。これにより従業員のエンゲージメントや能力の最大化を図り、企業の持続的成長と社会的価値の両立を目指しています。
トヨタ自動車
トヨタ自動車は人的資本を企業競争力の源泉と位置づけ、戦略的な人材育成・活用を行っている代表的企業です。特に注力しているのが、従業員の自律的なキャリア形成支援とリスキリングです。トヨタは「モノづくりは人づくり」として、技術力だけでなく、現場での課題解決力やグローバルな視点を持つ人材育成に取り組んでいます。たとえば次世代リーダー育成のための社内大学制度(トヨタインスティチュート)や、デジタルスキル強化のためのオンライン研修プログラムの導入が代表的です。また有価証券報告書では、人材戦略や育成方針、主要KPI(教育時間、離職率など)を開示し、人的資本の可視化と説明責任を果たしています。こうした取り組みにより、変化に強い組織づくりと長期的な企業価値向上を実現しています。
リクルート
リクルートホールディングスは、人的資本経営を経営の中核に据え、従業員の成長と企業価値の向上を両立させる取り組みを積極的に行っています。同社は「個の尊重」を企業文化の根幹とし、多様な人材が自律的に働ける環境の整備に力を入れている点が特徴です。具体的には全社員に対してパフォーマンスと成長を可視化する評価制度を導入し、キャリア支援と人材配置にデータを活用しています。またエンゲージメントサーベイを定期的に実施し、社員の声を反映した組織運営を積極的に進めている点も強みです。さらに人的資本に関するKPI(多様性指標、教育投資額、エンゲージメントスコアなど)を開示し、社内外への透明性も確保し、社員とステークホルダーへの信頼性も高めています。このようにリクルートは、従業員の能力を最大限に引き出すことでイノベーションの創出と持続的な成長を実現しています。
まとめ
生産年齢人口が減少局面にある日本社会において、積極的な人的資本経営の導入はあらゆる企業にとっての課題といえます。従業員が個々の能力を発揮しやすい環境を作り出すためにも、企業側が制度設計や企業文化を時代に合わせていくことが重要です。