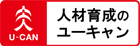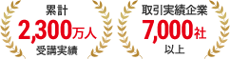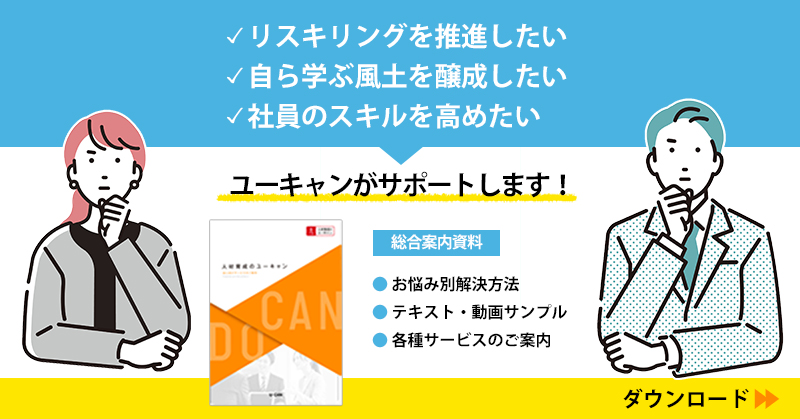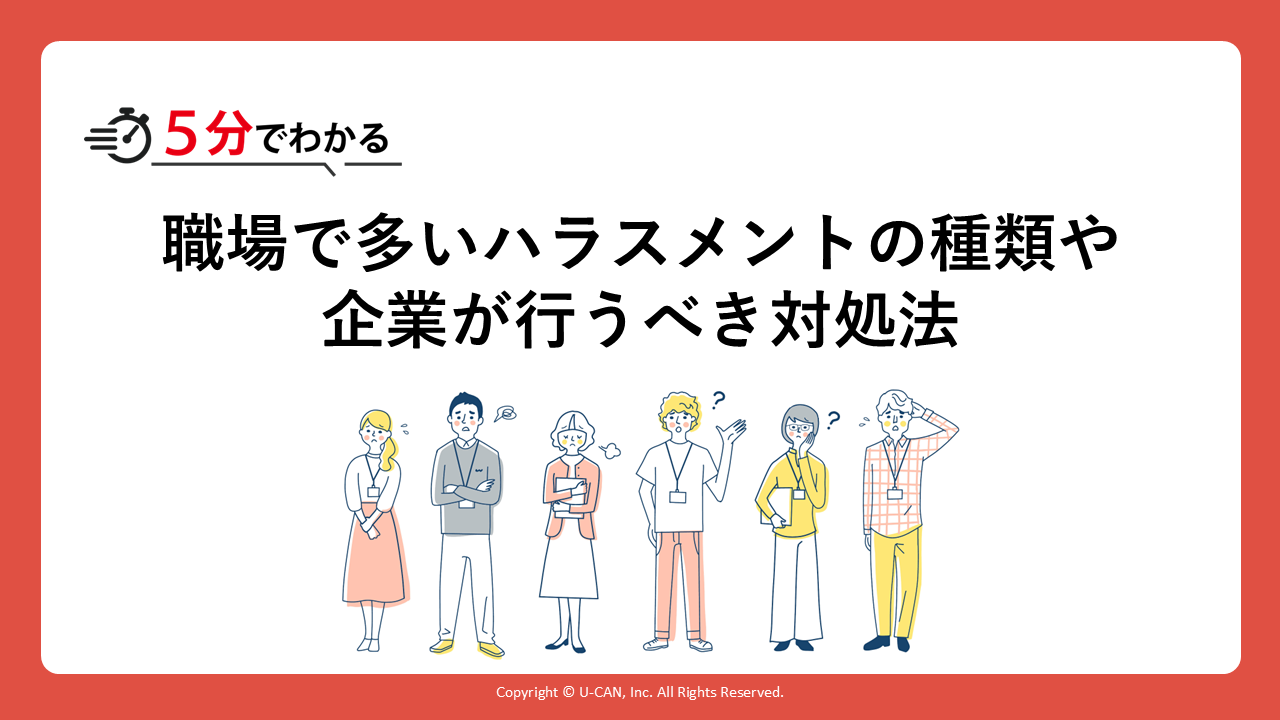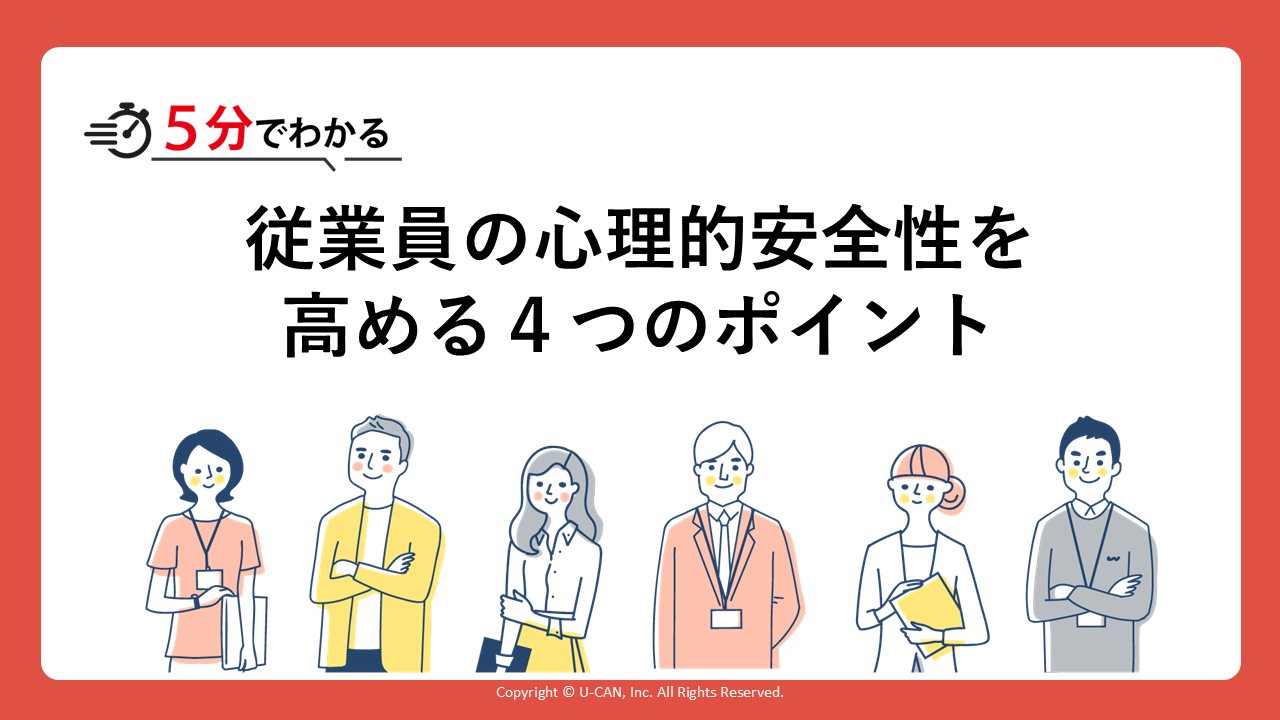ハラスメント研修とは
ハラスメント研修は、職場におけるハラスメントについて学ぶ研修です。ハラスメントとは、不快にさせたり、苦痛を与えたりする言動や行動などを指します。ハラスメントに対する従業員の理解を促し、予防や対策などを実施します。職場でいじめや嫌がらせがあると人権侵害に発展する可能性があるため、社員1人ひとりに対する学習機会の提供が必要です。
ハラスメントの種類
ハラスメントには数多くの種類があります。以下で、代表的なハラスメントについて解説します。
パワーハラスメント
パワーハラスメント(パワハラ)は、職場や学校での上下関係、権力を利用した嫌がらせ行為や強要行為を指します。職場の場合は上司から部下、または先輩から後輩に対して、優位な立場から不必要な指導を行ったり、精神的な苦痛を与えたりする行為はパワハラに該当します。一方で、指導と嫌がらせを判別するには、個別の状況と双方の意見を聞いたうえで対応をしなければ、パワーハラスメントの客観的な判断は難しいでしょう。暴言や脅迫、人間関係の切り離し、過大または過小な仕事を要求するなどの行為があればパワーハラスメントと認定される可能性が高いです。
セクシャルハラスメント
セクシャルハラスメント(セクハラ)は、性的な言動または行動によって、心身に苦痛を生じさせたり、就業環境を害したりするハラスメントです。例えば上司から女性社員に対して、権力を利用して性的な言動を行ったり、身体に触れたりするのが典型的なセクシャルハラスメントです。また性別や年齢、容姿、プライベートな生活などについて、個人の価値観や尊厳を傷つける発言をするケースも、セクシャルハラスメントとして認定されます。セクシャルハラスメントは日本で認知されるのが1980年代と非常に早く、当時は男性から女性への嫌がらせが一般的でしたが、現在は性別関係なくセクシャルハラスメントと定義されています。
マタニティハラスメント
マタニティハラスメント(マタハラ)は、妊娠・出産・子育てに関連した嫌がらせ、職務上不利益な取り扱いを行うハラスメントです。女性の場合はマタニティハラスメント、男性の場合はパタニティハラスメントといわれます。マタニティハラスメントの具体的な例としては、妊娠を理由に過小な業務を命じたり、配置転換をさせたり、自主退職を迫ったりするケースがあります。妊娠・出産・子育てに関連した嫌がらせ行為は、育児介護休業法で違法とされているため、必要に応じて労働基準監督署に報告すべきです。
ハラスメント研修の対象者
ハラスメント研修は、すべての従業員を対象に実施することが望ましいですが、特に重要なのは管理職やリーダー層です。管理職は部下と関わる機会が多く、無意識の言動がハラスメントと受け取られるリスクがあるほか、職場でのハラスメントを未然に防ぎ、発生時には適切に対応する責任がある立場だからです。また一般社員にも研修を行うことで、加害者・被害者の両面でのリスクを低減し、職場全体での意識向上につながります。従業員全員の理解と協力が、ハラスメントのない健全な職場環境をつくる第一歩です。
ハラスメント研修の目的
ハラスメント研修は管理職を含め、幅広い従業員がハラスメントへの理解を深め、被害者・加害者にならないために重要な施策です。ハラスメント研修にはその他にもさまざまな目的があることから、どのような目的・意図を持って実施すべきなのかを解説します。
ハラスメントに関する正しい知識の共有
ハラスメント研修の目的のひとつは、ハラスメントの定義や具体的なケース、法的リスクを従業員に正しく理解させることです。無自覚な言動がハラスメントに該当することもあるため、「知らなかった」では済まされないという認識を持たせることが重要です。全社員がハラスメントに対する共通認識を持つことで、不要なトラブルの予防や誤解による人間関係の悪化を防ぐ効果が期待できます。
職場環境の改善と心理的安全性の向上
ハラスメント研修は、全従業員が安心して働ける職場づくりに寄与する重要な施策です。誰もが尊重される環境をつくることで、一人ひとりの心理的安全性が高まり、コミュニケーションが活性化しやすくなります。その結果、チームワークや生産性の向上が期待できます。ハラスメントのない職場は、従業員の定着率や満足度向上にもつながり、優秀な人材を確保しやすくなるでしょう。
管理職の対応能力向上と組織的リスク管理
管理職にはハラスメントを未然に防ぎ、発生時に適切に対処する責任があります。研修を通じて対応スキルを身につけることで、問題を見逃さず、迅速かつ公正な判断ができるようになります。また組織として研修を行うことは、ハラスメント対策に取り組む姿勢を社内外に示す機会ともなり、法的リスクや レピュテーションリスクの回避にも効果的です。研修を一過性のもので終わらせず、社会から信頼される企業であり続けることが大切です。
ハラスメント研修の内容
ハラスメント研修で学習した後は、職場環境の見直しが必要です。職場におけるハラスメントを予防し、従業員それぞれが対処法を身につけましょう。以下で解説します。
ハラスメントについて学習する
・ハラスメントの定義を学ぶ
ハラスメントには明確な定義というものはなく「受けた人の感じ方」によってはハラスメントになります。主観的には「労働者が何らかの不快感を覚えること」となっており、かつ不快であることと中止を求めているにもかかわらず、繰り返し同様の行為が繰り返されればハラスメントです。ただし、ハラスメントと認定されるには一定の客観性が必要であり、認定には証拠も必要です。
・ハラスメントの現状について学ぶ
厚生労働省が2021年4月に発表した「職場のハラスメントに関する実態調査」では、7割以上の企業でパワハラやセクハラ、約半数の企業でマタハラ・パタハラがあったという結果が出ています。ハラスメントの件数は、セクハラこそ減少してるものの、パワハラはほとんど変化がなく、ハラスメント問題は根強く残っていることがわかります。
・ハラスメントの影響について学ぶ
ハラスメントは放置すると、被害者からの告発や訴訟問題となり、多額の賠償金を支払うことになります。また賠償金以上に大きな問題が、企業の信用失墜、株価の大幅な下落、生産性の低下、退職者の増加などの悪影響です。個々の問題を解決しても、企業としての環境や体質を改善しなければ繰り返される問題であり、根本的な解決には組織を挙げて取り組む必要があります。
職場環境の見直し
職場環境を見直すことで、ハラスメントの実態の調査ができます。ハラスメントのチェックリストを作成し、業務における問題点を洗い出しましょう。指導とハラスメントの明確な違いを把握し、普段の行動や言動を見直す必要があります。職場におけるコミュニケーションを見直し、ハラスメントにならない伝え方のスキルを高めることが重要です。
ハラスメントの予防や対処法を学ぶ
従業員がハラスメントの予防や対処法を学ぶと、職場の安全性を確保できます。同僚に対する心遣いやマナーを身につけて、ハラスメントの発生をなくしましょう。万が一、ハラスメントが起きたら、職場全体で再発防止の仕組みを構築します。研修を行い、職場のハラスメントにおける共通認識を作り、良好な関係性を築ける工夫をしてください。
※ページ内で紹介していないハラスメントの種類に関してはこちらの記事へ
ハラスメントの種類は? 職場で起こる原因と発生した場合のリスク、対処法を解説
ハラスメント研修の実施手順
ハラスメント研修を実施する際は、きちんと段階を踏んで実施することが重要です。どのような手順で進めるべきか、4つのステップに分けて解説します。
目的と対象者を明確にする
研修を始める前にまず行うべきは、研修の目的と対象者を明確にすることです。たとえば「ハラスメントの基本知識を習得する」「管理職としての対応力を身につける」など、誰に何を学ばせたいかを明確にすることで、研修内容の焦点が定まり、効果的な研修設計が可能になります。そして対象者は全社員としつつも、管理職向けに別途応用的な内容を用意するなど、役職や立場に応じたカリキュラム構成も検討すると効果的です。明確な目的設定は、受講者の意識や学習効果にも大きく寄与します。
研修内容と実施方法を設計する
次に、目的に合った研修内容と実施方法を設計します。基本的なハラスメントの種類(パワハラ・セクハラ・モラハラなど)や法令、実際の事例、対応方法などを盛り込み、具体的な状況を想定したケーススタディやロールプレイを交えることで、理解が深まります。また座学だけでなく、グループワークや意見交換を取り入れることで、自分の価値観を見直すきっかけとすることも重要です。さらに対面形式・オンライン・eラーニングなど、受講者のスケジュールや職場環境に応じた実施形式を検討することも重要です。内容と手法のバランスを取ることで、効果的な学びにつながります。
研修を実施し、理解促進を図る
研修実施の際は、単なる知識の伝達に終わらず、受講者の理解を促す工夫を取り入れることが大切です。たとえば実例や統計データを活用して説得力を高め、受講者が自分事として捉えられるような問いかけや対話形式を取り入れると効果的です。また質疑応答やグループディスカッションの時間を確保し、参加型の研修方式にすることで、より深い気づきを得られます。さらに資料の配布や振り返りシートの活用によって、研修後の見直しや行動変容の促進につなげることができます。一方通行の講義で終わらせず、対話と考察の場にすることが成功の鍵です。
研修後のフォローアップと効果測定を行う
研修を実施した後は、その効果を定着させるためのフォローアップが欠かせません。たとえば研修内容に関する小テストやアンケート、理解度チェックなどを実施し、受講者の学習状況を確認すると同時に、研修の改善点を把握する手がかりとなります。また社内報や掲示板で内容を再度周知したり、定期的な面談や1on1の中で研修内容の実践状況を確認したりすることも有効です。さらに相談窓口の整備やルールの明文化など、制度面でのサポートを併せて行うことで、ハラスメント防止の意識が組織に浸透しやすくなります。ハラスメント研修は単発で終わらせず、継続的な取り組みとして位置づけることが重要です。
ハラスメント研修を成功させるポイント
ハラスメント研修を成功させるには、従業員の目的意識や当事者意識が求められます。カリキュラムの改善も必要となります。
1、目的を明確にする
ハラスメント研修は、目的を決めて従業員の意識や行動を変化させることが重要です。すべての従業員がハラスメントについて理解し、自主的に予防や職場環境の改善に取り組まなければなりません。従業員がハラスメントに関する知識やノウハウを身につけられるように目的を設定し、働きやすい環境を構築するための研修を実施しましょう。
2、当事者意識をもたせる
ハラスメント研修は従業員ごとにプログラムを設定し、役職に合わせて当事者意識を持たせることが重要です。研修内容に対して他人事に感じてしまうと、従業員の参加意欲が低下する可能性があります。研修は座学だけではなく、グループワークや講師への質問の機会を設けるなど、従業員を積極的に参加させる体制を構築しましょう。
3、アンケートを実施する
研修においては、実施後の改善が必要となるため、研修の参加前と参加後にアンケートを取りましょう。参加前のアンケートの結果をもとに研修のカリキュラムを調整し、参加後のフィードバックを参考に改善を繰り返します。研修の内容は1度の受講だけでは理解が難しいため、定期的に研修を開催して従業員の理解を促しましょう。
4、ハラスメントを許さない組織風土を醸成する
受講者にハラスメント研修を当事者意識を持って臨んでもらうためには「ハラスメントを許さない」風土を組織内で醸成する事が重要です。そのため、経営者から全従業員へ向けて以下のような発信や行動をするべきです。
・明確な意思表示をする
・ハラスメント防止に向けた行動を率先して行う
たとえば、経営者が従業員とともにハラスメント防止研修を受けることは、従業員への強力なメッセージとなります。
5、繰り返し行う
ハラスメント防止研修は1度限りの実施では、行動や意識を定着させることが出来ません。繰り返し行うことで風土を育て、行動の定着化を推進できます。ハラスメントが起きてしまうことでの従業員へのリスクや、企業へのリスクを予測し、定期的に繰り返し実施するべきです。
研修以外のハラスメント防止に向けた取り組み
ハラスメント研修以外にも、企業がハラスメントを防止するためにできることはあります。どのような取り組みが考えられるのか、具体的な内容を紹介します。
相談窓口の設置や通報制度の導入
ハラスメントの早期発見と対応のためには、社内外に相談窓口や通報制度を設けることが重要です。被害者や第三者が安心して相談できるよう、相談内容の秘密性保持や不利益な取り扱いをしない旨を明確にし、信頼できる体制を整えることが求められます。可能であれば社外の第三者機関と連携した外部相談窓口も設けることで、社内の利害関係を避けた中立的な対応が可能になります。また制度を設けるだけでなく、定期的に存在を周知し、相談しやすい雰囲気づくりを意識することが大切です。適切な対応体制が整っていれば、社員が不安を抱え込むことなく、問題が深刻化する前に対処できる環境を構築できます。
社内ルールの整備や就業規則での明文化
ハラスメント防止の具体的な取組として、企業としての姿勢や対応方針を社内規程や就業規則に明文化し、全社員に周知することが重要です。パワハラ・セクハラ・マタハラなどの定義や禁止事項、違反時の懲戒処分、相談時の対応フローなどを明確に示すことで、社員一人ひとりの行動基準が明らかになり予防効果が高まります。またルール整備によって、発生時の対応が曖昧にならず、組織として一貫性のある判断・処分が可能となります。さらに、これらのルールを社内のネットワークや就業規則の改訂通知などを通じて定期的に再確認する仕組みを持つことで、対策の形骸化を防ぎ社員の意識に定着させることが可能です。ルールづくりは、組織文化の土台を築く第一歩です。
組織風土の見直しとコミュニケーションの活性化
ハラスメントの温床となるのは、風通しが悪く、上司や同僚に気軽に意見を言えない閉鎖的な職場環境です。そのため、企業は日頃から自由に意見交換ができる組織風土の形成に努める必要があります。たとえば1on1ミーティングの実施やチームでの定例ミーティング、意見箱の設置など、社員の声を拾い上げる仕組みを構築することが効果的です。また管理職に対しては「聴く力」を重視したコミュニケーションの指導を行うことで、部下が安心して相談できる関係性を築くことができます。日常的なコミュニケーションが活性化することで、小さな違和感や不満にも早期に気づくことができ、ハラスメントの予防につながります。組織風土の見直しは、時間はかかりますが最も本質的で重要な対策です。
まとめ
ハラスメント研修は、ハラスメント対策としてすべての企業において必要な取り組みです。職場の環境を改善するために、従業員のハラスメントに対する理解を促し、働きやすい職場を目指して繰り返しの学習を行います。従業員が自主的にハラスメント対策に取り組めるように、専門の講師を呼んで、質の高い研修を実施しましょう。
ユーキャンの法人向け人材育成サービスは丁寧なヒアリングで課題を抽出し、最適な提案を行います。ハラスメント研修を実施する際は、ぜひ利用をご検討ください。