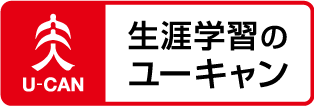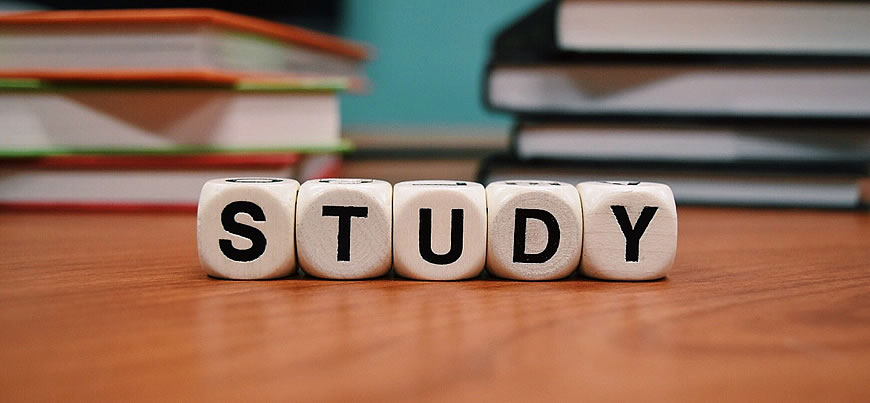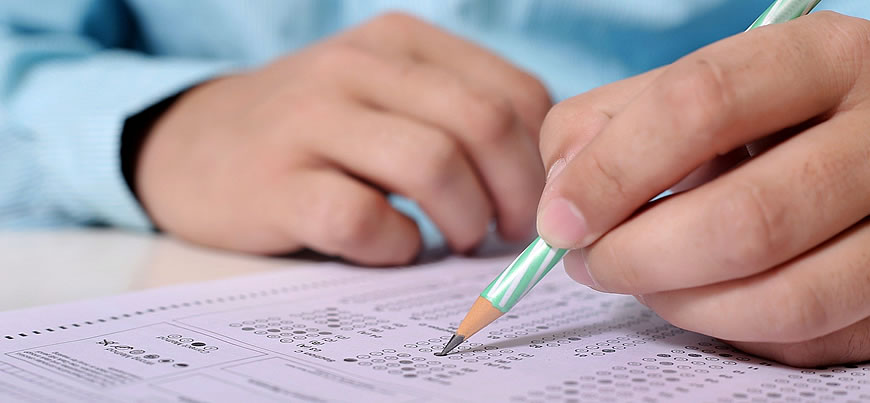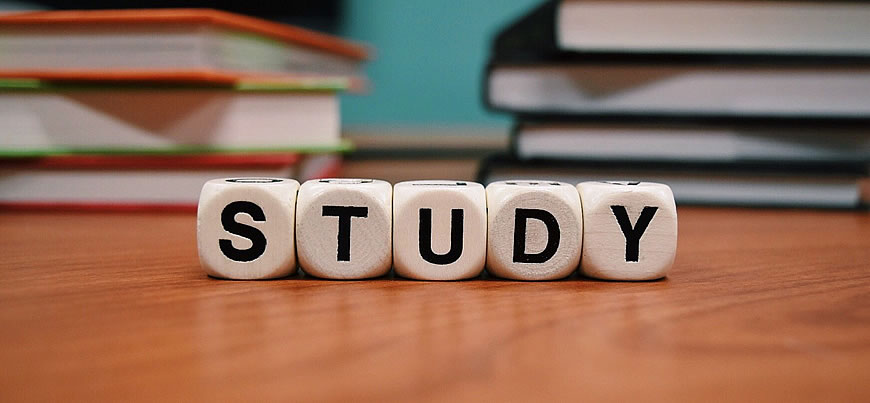- 登録販売者講座 もっと詳しく
登録販売者の給料はどれくらい?年収目安や合格難易度を紹介

- 更新日:2026/01/28
登録販売者は年々受験者数が増えている人気資格の1つです。資格受験を検討するにあたり、登録販売者の年収や今後の将来性が気になっている人も多いのではないでしょうか。この記事では、登録販売者の平均年収や求人状況などを詳細に紹介します。ぜひ参考にしてください。
このページを簡潔にまとめると・・・
- 登録販売者の平均年収は正社員で働く場合、300万円~400万円が目安。賞与や資格手当などが付く場合も。
- 薬剤師と比較すると給料は低いが、試験難易度が違うため。薬剤師になるには薬学部で6年間勉強することが条件。
- 給料以外の面で、ニーズが高く在宅医療や介護の場でも活躍が期待されることや、働き方が柔軟などメリットが多い。
- ユーキャンの登録販売者講座はこちら
登録販売者の給料は?
登録販売者の平均年収は300万円前後。正社員で働く場合、300万円~400万円が平均年収の目安です。パートで働く場合、資格手当を含めて平均時給1,000〜1,300円ほどです。
正社員とパートにわけて詳しくご紹介します。一つの目安として参考にしてください。
正社員として働く場合
正社員として働く場合の平均月収は約20万円、平均年収300万円~400万円が目安です。加えて、資格手当が支給されることもあります。 ドラッグストアの求人を例としてあげると、平均月収20万円〜27万円。資格手当に加えて夜勤手当も支給される場合があります。また、店長として働く場合は、平均月収35万円程度が目安です。 登録販売者資格を歓迎する営業の求人のなかには、平均月収18万円〜22万円で営業実績手当も支給されるところもあります。
パートとして働く場合
パートとして働く場合の時給は、資格手当を含めて平均1,000〜1,300円です。地域によっても差があり、こちらは求人サイトの関東のデータを元にした数値です。 ドラッグストアでは、時給約1,000円、深夜帯の時給は約1,300円で求人を募集しています。また、ホームセンターやスーパーにおいても、ドラッグストアと同じく、時給約1,000〜1,300円で募集している求人が多いようです。資格手当は会社によって異なりますが、数百円時給に加算される場合が多いです。 給与アップを目指して、パート勤務中に登録販売者資格を取得する方も多いようです。
- 参考:ユーキャン仕事オンライン 資格や経験を活かせる求人情報満載!(https://shigoto.u-can.co.jp/)
働く場所によって給料は変わる!
登録販売者の給料は働く場所によって異なります。たとえば、コンビニエンスストアとドラッグストアや調剤薬局とを比較すると、コンビニエンスストアの給料が高い傾向にあります。これは、コンビニエンスストアは、登録販売者の雇用に苦戦しており、人材が不足しているためです。
他にも、登録販売者を募集している職場は、医薬品通信販売のテレフォンオペレーターや介護サービスなど多岐にわたります。資格手当は会社によって金額が異なります。そのため、求人に応募する前にしっかりと確認することが大切です。広い目で登録販売者の求人を探すと、給料アップが叶うかもしれません。
登録販売者の給料は低い? 薬剤師との比較
薬剤師と登録販売者では、給料の面で差があります。薬剤師の平均年収は約599万円であり、登録販売者の年収を大きく上回ります。また、資格手当の金額も異なります。
- 参考:https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/158
薬剤師と給料の差が生まれてしまう原因
薬剤師と給料の差が生まれてしまう原因は、資格試験の難易度の違いにあります。薬剤師の試験には受験資格があり、薬学部で6年間勉強することが条件です。限られた人しか受験ができない、難易度が高い資格と言えます。一方、登録販売者の試験は受験資格がなく誰でも受験することができます。試験の難易度も登録販売者のほうが低く、取得しやすい資格と言えるでしょう。難易度の差が、給料の差につながっています。
登録販売者の将来性は?
一般用医薬品を取り扱う場所がドラッグストアだけでなく、コンビニエンスストアや家電量販店、インターネットなど増えてきています。それに伴い、登録販売者の活躍の場も広がるため、さまざまな職場で働くことができます。
在宅医療や介護の場でも活躍が期待
また、日本の高齢化が進むにあたって、在宅医療や介護の場でも活躍が期待されています。要介護者は、医薬品を常用的に服用していたり、医薬品とサプリメントを併用したりする場合があります。そこで、一般用医薬品に対する専門知識を持っている登録販売者が、飲み合わせの確認をしたり、アドバイスをしたりすることが求められています。
このように登録販売者の需要は高まっており、将来性のある仕事だといえます。
登録販売者のメリット
登録販売者の資格を持っていると、毎月5千~1万円程度の資格手当が支給されるケースが多かったり、時給も高くなる場合があります。収入アップを目指したい場合におすすめの資格といえます。
また、就職や転職にも有利だったり、幅広い場所で活躍できるというメリットもあります。取得した資格はその後永続的に有効となるため、いつでも働きたいときに活かすことができるので、自分のライフスタイルに合わせた働き方が可能となります。
登録販売者になるには
登録販売者になるには、まず試験に合格する必要があります。
登録販売者の試験内容は、5つの項目で構成されています。全体のうち7割以上の得点、かつ各試験項目の出題数に対して3.5割以上の正答率を達成する必要があります。
また、登録販売者試験の合格率は40%〜50%となっており、難易度はそれほど高くないといえます。受験資格もないので、医薬品の知識がない未経験者でも、挑戦することができます。
登録販売者試験に合格したあとは、販売従事登録することで登録販売者になることができます。
まとめ
登録販売者には資格手当があり、給与面で優遇されます。また、活躍の場が多くあり、今後はさらにニーズが高まる見込みです。試験の難易度は比較的優しく、受験資格の制限もないため、未経験であってもチャレンジがしやすいでしょう。
登録販売者の試験対策には、ユーキャンの「登録販売者合格指導講座」の活用がおすすめです。登録販売者合格指導講座は、自分のペースで取り組むことができ、不明点があれば気軽に講師陣に質問することが可能です。試験本番前には、総合模試があり十分なシミュレーションを行えます。登録販売者の資格取得を検討している人は、ぜひご活用ください。

- この記事の監修者は生涯学習のユーキャン
-
1954年設立。資格・実用・趣味という3つのカテゴリで多岐に渡る約150講座を展開する通信教育のパイオニア。気軽に始められる学びの手段として、多くの受講生から高い評価を受け、毎年多数の合格者を輩出しています。
近年はウェブ学習支援ツールを拡充し、紙の教材だけでは実現できない受講生サポートが可能に。通信教育の新しい未来を切り拓いていきます。
よくある質問
- 登録販売者試験の合格率や難易度は?
-
登録販売者の合格率は、全国平均で約40~50%。合格基準点は、全体で総得点の70%以上、かつ各試験項目の正答率が35~40%以上の正解が目安です。しっかり対策すれば、登録販売者試験の難易度はそれほど高くないといえます。
- 登録販売者は独学でも合格できる?
-
登録販売者試験を受験するためには実務経験も必要なく、文系でも学習さえすれば合格できるため、やり方次第では独学で合格することも不可能ではありません。登録販売者試験の合格に必要な勉強時間は約400時間と言われているため、ポイントを押さえた学習が大切です。
登録販売者講座

当講座では過去10年間でなんと13,137名もの合格者を輩出しています!
学習効率を高める工夫を凝らしたテキストや、いつでもどこでも学べるスマホ学習、問題集や模試などの副教材も充実!
添削指導や質問回答サービスなどの安心のサポート体制も多くの方に支持される人気の理由です。
登録販売者とは、ドラッグストアや薬局などで一般用医薬品の販売ができる医薬品販売の専門資格です。資格保有者がいれば、一般用医薬品の多数を占める第二類・第三類医薬品の販売が可能になるため、企業にとって大きな戦力に。国による医療費抑制の施策によりセルフメディケーションが推進されるなか、地域医療のサポート役として、ニーズも高く、医療関係の事務職のほか、小売業やドラッグストア、薬局などへの就職・転職を考えている方に人気の資格です。
登録販売者の仕事内容は医薬品の販売のほかにも、お客様への情報提供やご相談に対する対応・アドバイスも重要な仕事の1つ。購入者の視点に立って、医薬品の適切な選択を行えるように手助けすることも求められます。
登録販売者になるには、例年8~12月頃に行われる各都道府県で実施される登録販売者試験に合格する必要があります。全国どこで受験してもOK、受験資格もありませんので、どなたでもチャレンジできます。