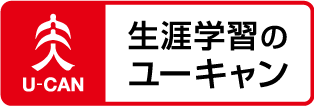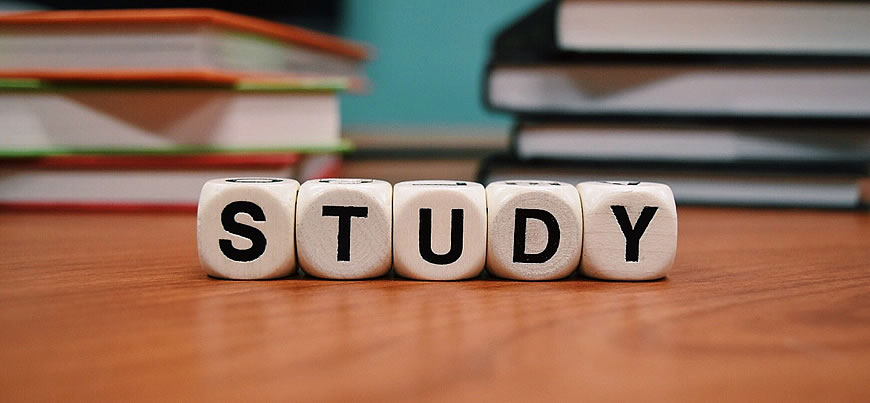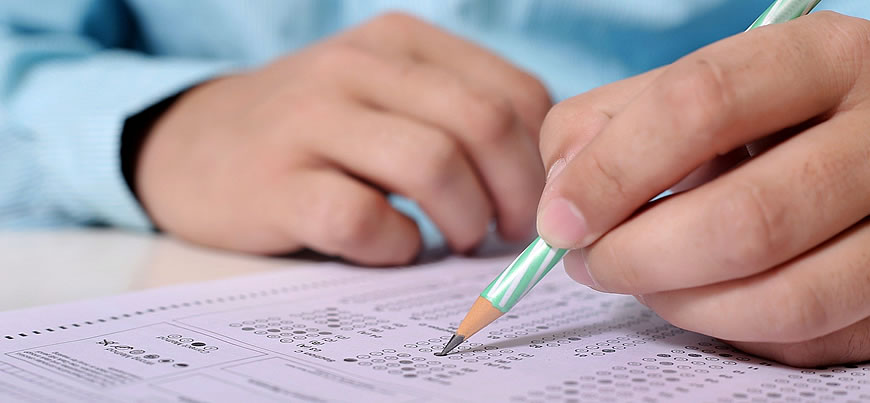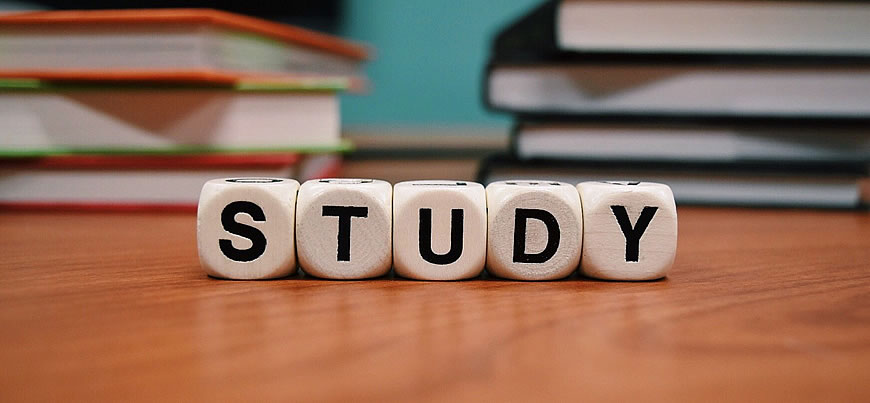- 登録販売者講座 もっと詳しく
登録販売者の試験の日程は?申込方法や過去の合格率も解説

- 更新日:2025/03/04
医薬品に関わる資格にはさまざまな資格がありますが、そのなかでも取得しやすい資格が登録販売者です。この記事では、登録販売者試験の試験日や申込み方法について詳しく解説します。試験範囲や合格ライン、勉強方法まで詳しく解説するため、受験を検討している人はぜひ参考にしてください。
このページを簡潔にまとめると・・・
- 登録販売者試験は年1回、例年8月下旬~12月中旬に行われ、都道府県により実施日が違う。約2か月前が申込み期限。
- 登録販売者試験の申込み手順は「願書の入手」「願書を提出期限までに提出する」「受験票を受け取る」の流れ。
- 各都道府県によって試験日や申込み期限が異なるため、住んでいる都道府県の日程をしっかりと確認しましょう。
- ユーキャンの登録販売者講座はこちら
登録販売者の試験日と申込み期限
登録販売者試験は、都道府県ごとに試験日と申込み期限が定められています。自分が受験する地域の試験日や申込み期限をしっかり把握しておきましょう。
試験日
試験日は、例年8月下旬~12月中旬となっており、年に1回試験が行われます。都道府県によって試験日は異なるため、住んでいる都道府県の試験日を確認しておきましょう。令和4年度の試験日は以下の表のとおりです。
| 試験日 | 都道府県 |
|---|---|
| 8月28日(日) | 福井県・滋賀県・和歌山県・京都府・大阪府・兵庫県・徳島県 |
| 8月31日(水) | 北海道・青森県・秋田県・山形県・福島県 |
| 9月6日(火) | 茨城県・栃木県・群馬県・新潟県・山梨県・長野県 |
| 9月7日(水) | 富山県・石川県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 |
| 9月11日(日) | 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県 |
| 9月25日(日) | 奈良県 |
| 11月8日(火) | 岡山県・広島県・鳥取県・島根県・山口県・香川県・愛媛県・高知県 |
| 12月11日(日) | 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 |
申込み期限
申込み期限も都道府県によって異なるため、住んでいる都道府県の申込み期限を確認しておきましょう。基本的には、試験日の約3か月前から申込みが開始され、約2か月前が申込み期限となるケースが多いようです。令和4年度の申込み期限は以下の表のとおりです。
| 申込み期限 | 都道府県 |
|---|---|
| 5月23日(月)~6月3日(金) | 東京都・神奈川県・埼玉県 |
| 5月30日(月)~6月10日(金) | 長野県 |
| 5月30日(月)~6月17日(金) | 新潟県・福井県 |
| 5月31日(月)~6月28日(火) | 福島県 |
| 6月3日(金)~6月13日(月) | 滋賀県・和歌山県・京都府・大阪府・兵庫県・徳島県 |
| 6月6日(月)~6月10日(金) | 静岡県 |
| 6月6日(月)~6月17日(金) | 富山県・石川県・岐阜県 |
| 6月7日(火)~6月28日(火) | 北海道・青森県・秋田県・山形県 |
| 6月9日(木)~6月15日(水) | 奈良県 |
| 6月13日(月)~6月17日(金) | 愛知県 |
| 6月13日(月)~6月24日(金) | 山梨県・三重県 |
| 6月20日(月)~6月24日(金) | 栃木県 |
| 6月20日(月)~7月1日(金) | 茨城県・群馬県 |
| 6月20日(月)~7月8日(金) | 千葉県 |
| 8月9日(火)~8月23日(火) | 岡山県・広島県・鳥取県・島根県・山口県・香川県・愛媛県・高知県 |
| 8月22日(月)~9月2日(金) | 福岡県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 |
| 8月22日(月)~9月16日(金) | 佐賀県 |
登録販売者試験の申込み方法
登録販売者試験に申込む際には、3つの手順を行う必要があります。「願書の入手」「願書を提出期限までに提出する」「受験票を受け取る」の流れです。ここでは、それぞれの手順について解説します。
願書(受験申請書類)の入手
まずは、願書(受験申請書類)を入手しましょう。願書の入手方法は以下の3つです。
1.直接受け取る
2.郵送で受け取る
3.インターネットからダウンロードする
以下では、それぞれの詳しい手順を解説するので、参考にしてください。
直接受け取る方法
願書を直接受け取る際には、各都道府県の試験管轄や保健所、健康福祉センターなどに行って受け取る必要があります。場所と時間帯については各都道府県によって異なるため、事前にしっかり確認しておくことが重要です。
郵送で受け取る方法
保健所などに直接受け取りに行く時間がない場合は、郵送で取り寄せることも可能です。ただし、取り寄せるタイミングが遅いと、願書提出日までに願書が届かない場合もあるため注意しましょう。郵送の場合は、できるだけ早めに取り寄せることがポイントです。
インターネットからダウンロードする方法
各都道府県のホームページから、願書をダウンロードすることも可能です。受験案内や手引きなどを確認して、間違えずに印刷しましょう。都道府県によっては、インターネットからのダウンロードに対応していないケースもあるため、確認してください。
願書(申請書)を提出期日までに提出
願書を入手したら必要事項を記入し、提出期限までに提出します。願書の提出は郵送、提出先は各都道府県の試験管轄です。願書提出期限は各都道府県によって異なるため、必ず確認し期限に間に合うように郵送してください。提出書類は、願書、写真、受験手数料(各都道府県指定の収入印紙)、返信用封筒切手代などが一般的です。受験料は都道府県により異なります。
受験票を受け取る
受験票は申込み後、受験者本人に郵送されます。試験実施日の二週間前になっても届かない場合には、各都道府県の管轄先に問い合わせてください。試験当日に持参する必要があるため、なくさないようにしっかりと保管しましょう。
登録販売者試験の概要
登録販売者試験はマークシート方式で出題され、合格発表は試験の約1か月後、各都道府県のホームページもしくは都道府県庁で確認できます。
登録販売者試験の当日は、受験票・鉛筆・消しゴム・腕時計・昼食を持参します。試験は午前と午後に分かれているため、昼食を用意しておきましょう。鉛筆削りも持参しておくと安心です。
登録販売者試験の出題範囲
登録販売者試験は、厚生労働省が作成する「試験問題の作成に関する手引き」に沿った内容が出題されます。全部で5つの分野から合計120題出題されます。以下では、各分野について解説するため、参考にしてください。
医薬品に共通する特性と基本的な知識(20問)
医薬品販売を適切に行うための基本的な知識が出題されます。
- 医薬品概論
- 医薬品の効き目や安全性に影響を与える要因
- 適切な医薬品選択と受診勧奨
- 薬害の歴史
人体の働きと医薬品(20問)
人間の体について出題される分野です。
- 精神神経に作用する薬
- 呼吸器官に作用する薬
- 胃腸に作用する薬
- 心臓などの器官や血液に作用する薬
- 排泄に関わる部位に作用する薬
- 婦人薬
- 内服アレルギー用薬(鼻炎用内服薬を含)
- 鼻に用いる薬
- 眼科用薬
- 皮膚に用いる薬
- 歯や口中に用いる薬
- 禁煙補助剤
- 滋養強壮保健薬
- 漢方処方製剤、生薬製剤
- 公衆衛生用薬
- 一般用検査薬
主な医薬品とその作用(40問)
医薬品の有効成分や作用、副作用について出題されます。
- 精神神経に作用する薬
- 呼吸器官に作用する薬
- 胃腸に作用する薬
- 心臓などの器官や血液に作用する薬
- 排泄に関わる部位に作用する薬
- 婦人薬
- 内服アレルギー用薬(鼻炎用内服薬を含)
- 鼻に用いる薬
- 眼科用薬
- 皮膚に用いる薬
- 歯や口中に用いる薬
- 禁煙補助剤
- 滋養強壮保健薬
- 漢方処方製剤、生薬製剤
- 公衆衛生用薬
- 一般用検査薬
薬事に関する法規と制度(20問)
薬に関する法律について問われる分野です。
- 医薬品、医療機器などの品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の目的など
- 医薬品の分類、取り扱いなど
- 医薬品の販売業の許可
- 医薬品販売に関する法令遵守
医薬品の適正使用と安全対策(20問)
医薬品の添付文書や副作用報告制度、知識の応用力が問われる分野です。
- 医薬品の適正使用情報
- 医薬品の安全対策
- 医薬品の副作用などによる健康被害の救済
- 一般用医薬品に関する主な安全対策
- 医薬品の適正使用のための啓発活動
登録販売者試験の合格ライン
登録販売者試験に合格するには、以下の2つをどちらも満たさなければいけません。
- 全体の正答率が70%以上(84問以上正解する)
- 各分野の正答率が35%以上、もしくは40%以上(都道府県によって条件が異なる)
登録販売者試験の難易度
国家試験のなかには合格率が1桁台の試験もあり、比較すると登録販売者試験の難易度は低めです。また、2014年度までは受験資格として学歴や実務経験が求められていましたが、現在では、誰でも受験可能です。地域によって試験内容は異なりますが、手引きに沿った内容となっているため勉強すれば決して難しくはありません。独学での合格も可能です。
登録販売者試験の合格率
登録販売者試験の合格率はどの程度なのでしょうか。ここでは、全国平均と都道府県による違いを解説します。
全国平均
登録販売者試験の合格率は全国平均で約30~50%となっており、比較的高めです。直近三年の合格率は、2022年度が44.6%、2023年度が43.7%、2024年度が46.7%で、平均内を推移していることが分かります。
都道府県ごとの違い
登録販売者試験は、都道府県によって合格率が大きく異なります。2024年度は都道府県によって3倍近い差があり、合格率がもっとも高かった地域は北海道で62.3%、もっとも低かった県は沖縄県で24.5%です。試験難易度に大きな差はありませんが、問題の内容は都道府県ごとに異なるため合格率に差が出ると考えられています。
登録販売者試験の過去問
以下の表は2024年度版の過去問です。登録販売者試験の前に目を通しておきましょう。
| 都道府県 | 試験問題 | 解答 | 過去問題 |
|---|---|---|---|
| 北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県 | 前半試験問題 後半試験問題 |
解答 | 一覧 |
| 茨城県・栃木県・群馬県・新潟県・山梨県・長野県 | 前半試験問題 後半試験問題 |
解答 | 一覧 |
| 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県 | 前半試験問題 後半試験問題 |
解答 | 一覧 |
| 富山県・石川県・愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 | 前半試験問題 後半試験問題 |
解答 | 一覧 |
| 大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・和歌山県・徳島県 | 前半試験問題 後半試験問題 |
解答 | 一覧 |
| 福井県 | 前半試験問題 後半試験問題 |
解答 | 一覧 |
| 奈良県 | 試験問題解答 | 一覧 | |
| 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 | 前半試験問題 後半試験問題 |
解答 | 一覧 |
| 香川県・愛媛県・高知県 | 前半試験問題 後半試験問題 |
解答 | 一覧 |
| 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 | 前半試験問題 後半試験問題 |
解答 | 一覧 |
登録販売者試験の勉強方法
登録販売者試験にチャレンジする際には、どのような勉強をすればいいのでしょうか。ここでは、勉強方法を紹介します。
独学
独学でも合格は可能で、400時間程度の勉強時間を確保すれば合格できるといわれています。独学の場合、最新のテキストで知識を学び、過去問題集を繰り返し解いて知識を定着させましょう。費用が安く済み、自分のペースで勉強できるというメリットがあります。
通信講座
通信講座は、スマートフォンやタブレットなどを用いて、どこでも勉強できます。分からないことがあれば質問できるため、スムーズに解決できる点がメリットです。いくつかの通信講座があるため、自分に合ったものを選びましょう。
そもそも登録販売者とは
登録販売者とは、医薬品の販売に関する専門資格で、一般用医薬品のうち第2類医薬品と第3類医薬品の販売が可能となります。登録販売者の仕事内容は、市販薬の販売、顧客に対して有効成分や効能・効果、服用方法や副作用、使用上の注意などを説明することです。また、生活習慣や養生方法についてのアドバイスなども行います。
まとめ
登録販売者試験は、各都道府県によって試験日や申込み期限が異なるため、住んでいる都道府県の日程をしっかりと確認しましょう。登録販売者試験に合格するためには、独学で勉強する方法もありますが、より効率的に合格を目指したいのなら通信講座を利用する方法もあります。
ユーキャンでは、登録販売者講座を提供しています。7回の添削指導が受けられ、受講から12ヵ月までサポートと充実のサポート体制が魅力です。就職活動のサポートも受けられるため、医薬品に関わる仕事をしたい人にもいいでしょう。登録販売者の取得をお考えなら、ぜひお申込みください。

- この記事の監修者は生涯学習のユーキャン
-
1954年設立。資格・実用・趣味という3つのカテゴリで多岐に渡る約150講座を展開する通信教育のパイオニア。気軽に始められる学びの手段として、多くの受講生から高い評価を受け、毎年多数の合格者を輩出しています。
近年はウェブ学習支援ツールを拡充し、紙の教材だけでは実現できない受講生サポートが可能に。通信教育の新しい未来を切り拓いていきます。
よくある質問
- 登録販売者になるのに実務経験は必要?
-
登録販売者になるためには、試験に合格するだけでなく、一般用医薬品を取り扱っている店舗での実務経験が必要です。資格は取ったものの実務経験がない、という場合は研修中の扱いになり、正式な登録販売者として独り立ちすることができません。
登録販売者講座

当講座では過去10年間でなんと13,137名もの合格者を輩出しています!
学習効率を高める工夫を凝らしたテキストや、いつでもどこでも学べるスマホ学習、問題集や模試などの副教材も充実!
添削指導や質問回答サービスなどの安心のサポート体制も多くの方に支持される人気の理由です。
登録販売者とは、ドラッグストアや薬局などで一般用医薬品の販売ができる医薬品販売の専門資格です。資格保有者がいれば、一般用医薬品の多数を占める第二類・第三類医薬品の販売が可能になるため、企業にとって大きな戦力に。国による医療費抑制の施策によりセルフメディケーションが推進されるなか、地域医療のサポート役として、ニーズも高く、医療関係の事務職のほか、小売業やドラッグストア、薬局などへの就職・転職を考えている方に人気の資格です。
登録販売者の仕事内容は医薬品の販売のほかにも、お客様への情報提供やご相談に対する対応・アドバイスも重要な仕事の1つ。購入者の視点に立って、医薬品の適切な選択を行えるように手助けすることも求められます。
登録販売者になるには、例年8~12月頃に行われる各都道府県で実施される登録販売者試験に合格する必要があります。全国どこで受験してもOK、受験資格もありませんので、どなたでもチャレンジできます。