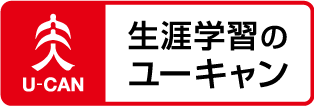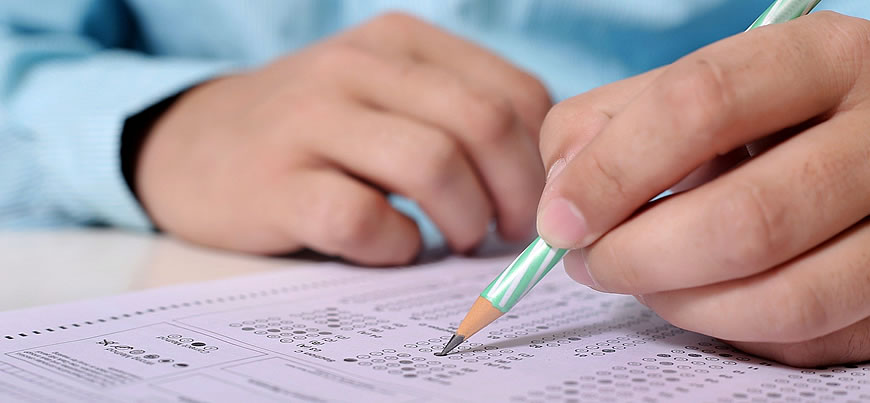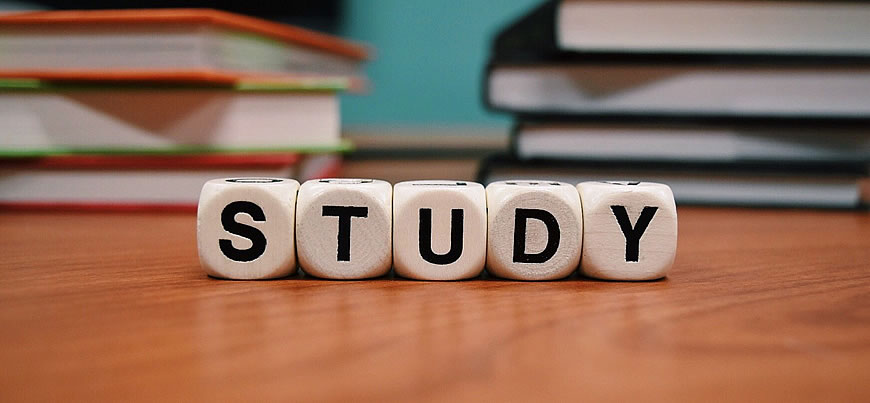- 登録販売者講座 もっと詳しく
登録販売者試験の合格率や難易度は?試験のコツを伝授!
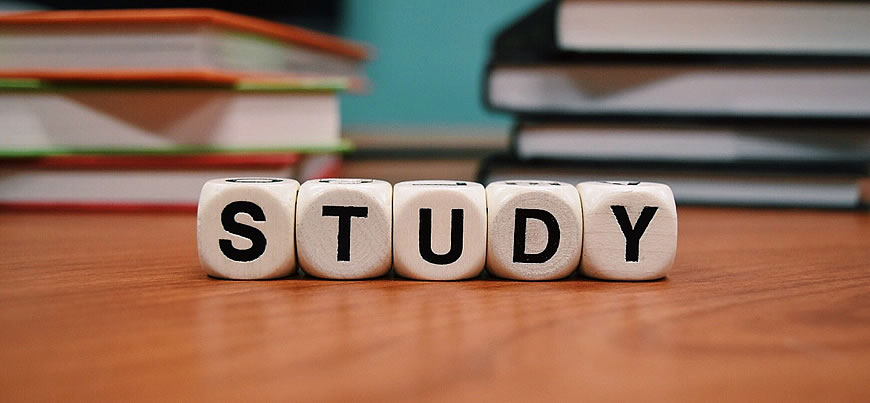
- 更新日:2025/10/10
ドラッグストアで「登録販売者」の名札を付けたスタッフを見たことはありませんか?
薬剤師不足を補うために生まれた登録販売者資格は、2015年に受験資格が撤廃され、誰でも受験できるようになりました。活躍の場も広がっているため、取得して損はない資格です。
ここでは、登録販売者試験の合格率や難易度、試験内容や対策法についてご紹介します。
このページを簡潔にまとめると・・・
- 登録販売者試験の合格率は、約40~50%。ただし、年度によっては都道府県によって合格率に2~3倍の差が生じる。
- 二人に一人は合格できるため、しっかり対策すれば、登録販売者試験の難易度はそれほど高くない。
- 登録販売者試験の合格点・合格ラインは正答率が70%以上、かる各試験項目の正答率が35~40%以上。
- 地域ごとに試験内容が違うが、基本的に「試験問題の作成に関する手引き」の中から出題される。基本を理解し、問題を何度も解くことが重要。
- ユーキャンの登録販売者講座はこちら
登録販売者資格試験の合格率と難易度は?
登録販売者試験の合格率は、約40~50%(全国平均)です。
登録販売者の合格率は、全国平均で約40~50%となっています。合格基準点は、全体で総得点の70%以上、かつ各試験項目の正答率が35~40%以上の正解が目安です。しっかり対策すれば、登録販売者試験の難易度はそれほど高くないといえます。出題範囲をまんべんなく勉強し、苦手項目を作らないことがポイントです。
なお、試験は都道府県ごとに実施されるため、地域や年度によって合格率が異なります。全体的な点数は7割を超えていても、5項目のうち1項目でも都道府県が決める基準点を下回る場合は不合格となります。
受験資格を得るために6年間大学に通い、さらに試験に備えて難しい勉強をしなければならない薬剤師国家試験とは異なり、登録販売者試験は誰でも受験でき、通信教育やスクールなどを活用した受験勉強で十分合格を目指せる試験です。
| 試験実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2024年度(令和6年度) | 54,516人 | 25,459人 | 46.7% |
| 2023年度(令和5年度) | 52,214人 | 22,814人 | 43.7% |
| 2022年度(令和4年度) | 55,606人 | 24,707人 | 44.4% |
| 2021年度(令和3年度) | 61,070人 | 30,082人 | 49.3% |
| 2020年度(令和2年度) | 52,959人 | 21,953人 | 41.5% |
| 2019年度(令和元年度) | 65,288人 | 28,328人 | 43.4% |
| 2018年度(平成30年度) | 65,500人 | 27,022人 | 41.3% |
| 2017年度(平成29年度) | 61,126人 | 26,606人 | 43.5% |
| 2016年度(平成28年度) | 53,369人 | 23,330人 | 43.7% |
| 2015年度(平成27年度) | 49,864人 | 22,901人 | 45.9% |
| 2014年度(平成26年度) | 31,362人 | 13,627人 | 43.5% |
登録販売者資格試験の合格率と難易度は都道府県別に異なる?
合格率には2~3倍の差が生まれることも。
都道府県ごとに実施される登録販売者試験。日程が異なるので、試験問題も異なりますが、都道府県によって難易度に差があるのでしょうか。
基本的にどの都道府県でも厚生労働省発表の「試験問題の作成に関する手引き」から出題され、なるべく難易度の差が生まれないようにされていますが、年度によっては都道府県によって合格率に2~3倍の差が生まれています。
以下は都道府県別の2024年度、2023年度試験の合格率一覧です。
※ 2024年度のデータは、厚生労働省の公表している情報に基づきますが、合格取消などで数値が変動する可能性があります。
| 都道府県 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|
| 北海道 | 62.3% | 51.2% |
| 青森県 | 54.9% | 43.3% |
| 岩手県 | 51.5% | 44.3% |
| 宮城県 | 55.0% | 44.7% |
| 秋田県 | 50.0% | 39.7% |
| 山形県 | 52.5% | 41.9% |
| 福島県 | 47.5% | 40.1% |
| 茨城県 | 46.5% | 53.7% |
| 栃木県 | 42.8% | 48.0% |
| 群馬県 | 51.2% | 55.2% |
| 埼玉県 | 46.7% | 45.3% |
| 千葉県 | 45.9% | 43.2% |
| 東京都 | 45.8% | 44.0% |
| 神奈川県 | 47.8% | 47.5% |
| 新潟県 | 43.5% | 50.8% |
| 山梨県 | 40.1% | 45.0% |
| 長野県 | 42.0% | 50.7% |
| 富山県 | 52.2% | 41.6% |
| 石川県 | 52.2% | 43.5% |
| 岐阜県 | 55.1% | 45.1% |
| 静岡県 | 56.6% | 52.7% |
| 愛知県 | 56.7% | 47.5% |
| 三重県 | 57.2% | 43.2% |
| 福井県 | 40.1% | 33.8% |
| 奈良県 | 41.8% | 54.2% |
| 関西広域連合(滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山、徳島) | 46.7% | 34.4% |
| 鳥取県 | 53.1% | 26.3% |
| 島根県 | 50.2% | 28.2% |
| 岡山県 | 51.8% | 28.1% |
| 広島県 | 55.9% | 30.7% |
| 山口県 | 54.3% | 29.7% |
| 香川県 | 52.8% | 24.9% |
| 愛媛県 | 51.8% | 25.3% |
| 高知県 | 46.6% | 21.4% |
| 福岡県 | 30.9% | 53.4% |
| 佐賀県 | 28.7% | 45.9% |
| 長崎県 | 30.3% | 47.0% |
| 熊本県 | 31.3% | 48.8% |
| 大分県 | 35.7% | 54.9% |
| 宮崎県 | 29.4% | 46.0% |
| 鹿児島県 | 28.8% | 45.1% |
| 沖縄県 | 24.5% | 39.5% |
登録販売者の難易度は他の資格と比べて高い?
調剤薬局事務より難易度は高い
薬を扱う資格には登録販売者のほか、薬剤師や調剤薬局事務といったものがあります。登録販売者の難易度は他の2つの資格と比べてどれくらいなのでしょうか。
まず、調剤薬局事務として働くための一般的な資格「調剤事務管理士」の合格率は50%ほどです。合格率は登録販売者と大きく変わりませんが、難易度は低く、勉強時間も3ヵ月ほどと短めです。登録販売者の方が難易度は高いといえます。
薬剤師より取得しやすい
一方、薬剤師ですが合格率は平均して60%~80%と高めではありますが、そもそもの受験資格である「6年制薬学部の卒業」が難しい条件です。薬学部の卒業には6年必要です。社会人から資格を目指すことも可能ですが、一度仕事を辞めて大学へ入る必要があるため、時間や費用を要します。登録販売者の方が取得しやすいと言えるでしょう。
女性に人気の資格には、ケアマネジャー(合格率10~20%)、社会福祉士(合格率約30%)、介護福祉士(合格率約70%)などもありますが、受験資格なども考慮すると、登録販売者は比較的取得しやすい資格といえます。
登録販売者ができることは?
登録販売者は、一般用医薬品の約9割を占める第二類医薬品・第三類医薬品を販売できます。
登録販売者も薬剤師も医薬品の販売に従事する専門家ですが、業務面ではどのような違いがあるのでしょうか?
薬剤師と比較しながら、登録販売者ができることを確認してみましょう。
まず、登録販売者と薬剤師は販売できる医薬品の種類が異なります。
登録販売者は、一般用医薬品の約9割を占める第二類医薬品・第三類医薬品を販売できます。ただし、第一類医薬品と要指導医薬品は販売することができません。それに対して、薬剤師は要指導医薬品・第一類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品の全てを販売できます。
また、登録販売者は処方箋にもとづく調剤が行えませんが、薬剤師は調剤も可能です。
このように、受験資格のない登録販売者は、薬剤師に比べてできることが限られます。
しかし薬剤師不足の昨今、ほとんどの一般用医薬品を扱える登録販売者の需要は高まっています。
登録販売者資格試験の出題範囲と対策は?
登録販売者試験の合格点・合格ラインは都道府県で差異はなく、全体120問(試験時間4時間)に対する正答率が70%以上つまり84点以上です。また、各試験項目の出題数に対する正答率が35~40%以上が必要です。
ただし、各試験項目の出題数に対する正答率(足切り)は都道府県によって異なります(東京都の場合は35%)。
登録販売者試験の出題範囲
出題範囲は下記5項目で、厚生労働省が公開している「試験問題の作成に関する手引き」の中から出題されます。登録販売者が扱える医薬品は第二類医薬品と第三類医薬品のみですが、お客様の相談を受けることも多いため、医薬品に対する全般的な知識の習得が求められます。
- 【1】医薬品に共通する特性と基本的な知識(医薬品の基本的な知識や薬害の歴史など)
- 【2】人体の働きと医薬品(人体の構造や薬が効く仕組み、副作用など)
- 【3】主な医薬品とその作用(各部位に作用する薬の種類など)
- 【4】薬事関連法規・制度(医薬品の取り扱いや販売業の許可など)
- 【5】医薬品の適正使用・安全対策(医薬品の安全対策や健康被害の対応・安全対策など)
●登録販売者試験の対策
薬学について初めて学ぶ方が、自分ひとりで勉強して試験に臨むことは難しいかもしれません。その場合は、通信教育やスクールなどを利用して受験勉強することをおすすめします。
試験は地域ごとに出題内容が違いますが、基本的に「試験問題の作成に関する手引き」の中から出題されるため、基本を理解し、問題を何度も解くことが大変重要です。登録販売者試験には足切りがあるため、一点集中型の勉強法は向いていません。出題範囲をまんべんなく勉強し、苦手項目を作らないことが合格の秘訣です。
まとめ
今回は、登録販売者試験の合格率や難易度、試験対策についてご紹介しました。
登録販売者は全国で求められており、合格した都道府県に限らず、どの地域でも活躍することができる有用な資格です。医薬品を扱う仕事に興味がある方は、ぜひ登録販売者の資格取得を目指してみてください。
ユーキャンの登録販売者講座は、ポイントをやさしくつかめるカリキュラムだから、初めて挑戦する方も安心。専門的な薬の知識をわかりやすく解説したテキストや、試験を徹底分析した問題集、充実の副教材で無理なく試験合格ラインの「7割クリア」を目指せます。

- この記事の監修者は生涯学習のユーキャン
-
1954年設立。資格・実用・趣味という3つのカテゴリで多岐に渡る約150講座を展開する通信教育のパイオニア。気軽に始められる学びの手段として、多くの受講生から高い評価を受け、毎年多数の合格者を輩出しています。
近年はウェブ学習支援ツールを拡充し、紙の教材だけでは実現できない受講生サポートが可能に。通信教育の新しい未来を切り拓いていきます。
よくある質問
- 登録販売者の試験日は?
-
登録販売者の試験日は、例年8月下旬~12月中旬となっており、年に1回試験が行われます。都道府県によって試験日は異なるため、住んでいる都道府県の試験日を確認しておきましょう。
- 登録販売者は独学でも合格できる?
-
登録販売者試験を受験するためには実務経験も必要なく、文系でも学習さえすれば合格できるため、やり方次第では独学で合格することも不可能ではありません。登録販売者試験の合格に必要な勉強時間は約400時間と言われているため、ポイントを押さえた学習が大切です。
登録販売者講座

当講座では過去10年間でなんと13,137名もの合格者を輩出しています!
学習効率を高める工夫を凝らしたテキストや、いつでもどこでも学べるスマホ学習、問題集や模試などの副教材も充実!
添削指導や質問回答サービスなどの安心のサポート体制も多くの方に支持される人気の理由です。
登録販売者とは、ドラッグストアや薬局などで一般用医薬品の販売ができる医薬品販売の専門資格です。資格保有者がいれば、一般用医薬品の多数を占める第二類・第三類医薬品の販売が可能になるため、企業にとって大きな戦力に。国による医療費抑制の施策によりセルフメディケーションが推進されるなか、地域医療のサポート役として、ニーズも高く、医療関係の事務職のほか、小売業やドラッグストア、薬局などへの就職・転職を考えている方に人気の資格です。
登録販売者の仕事内容は医薬品の販売のほかにも、お客様への情報提供やご相談に対する対応・アドバイスも重要な仕事の1つ。購入者の視点に立って、医薬品の適切な選択を行えるように手助けすることも求められます。
登録販売者になるには、例年8~12月頃に行われる各都道府県で実施される登録販売者試験に合格する必要があります。全国どこで受験してもOK、受験資格もありませんので、どなたでもチャレンジできます。