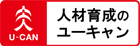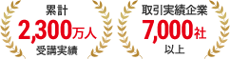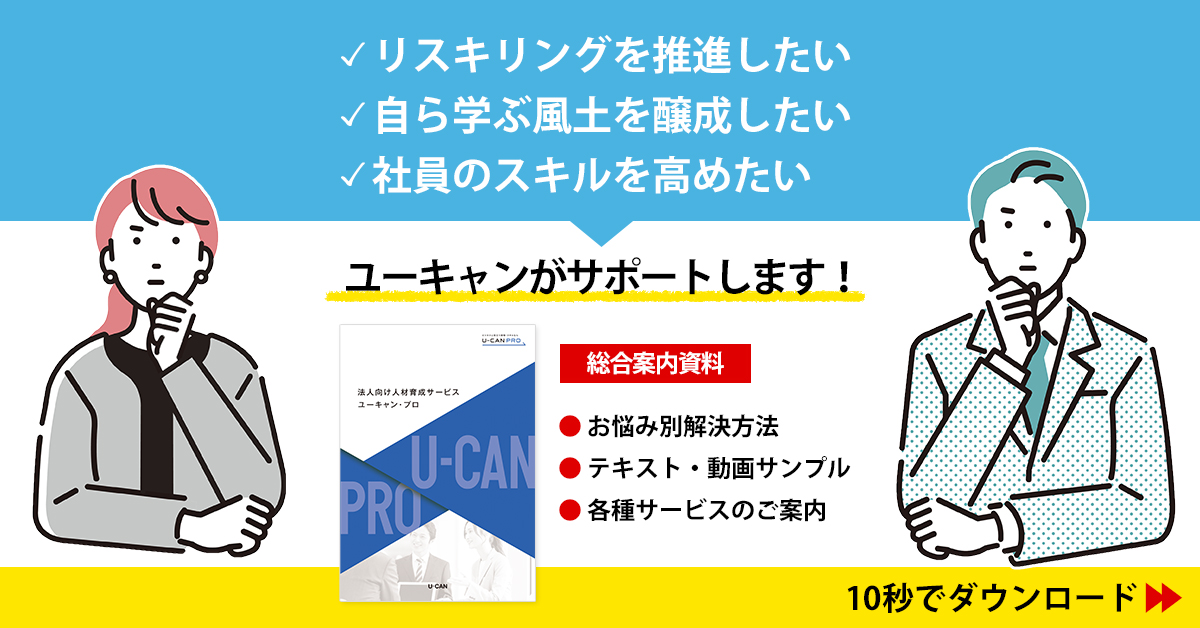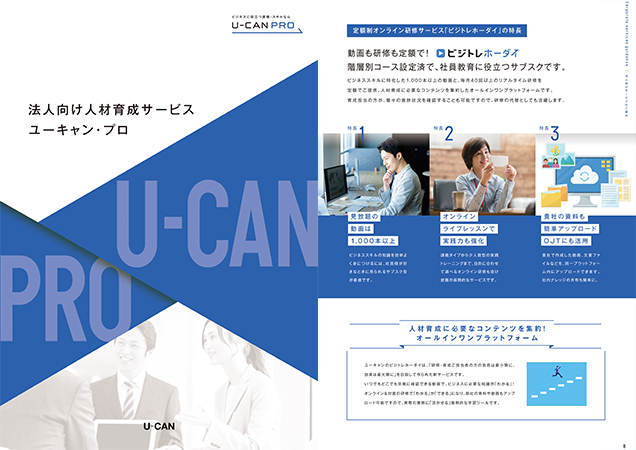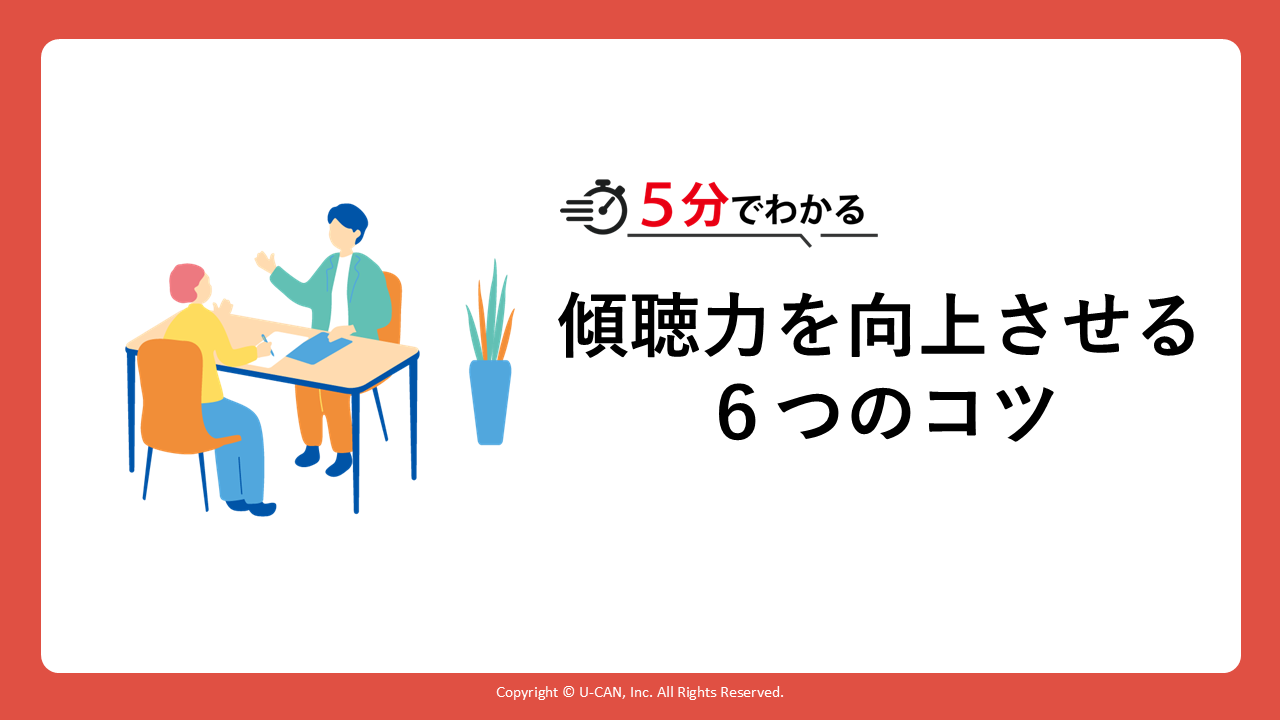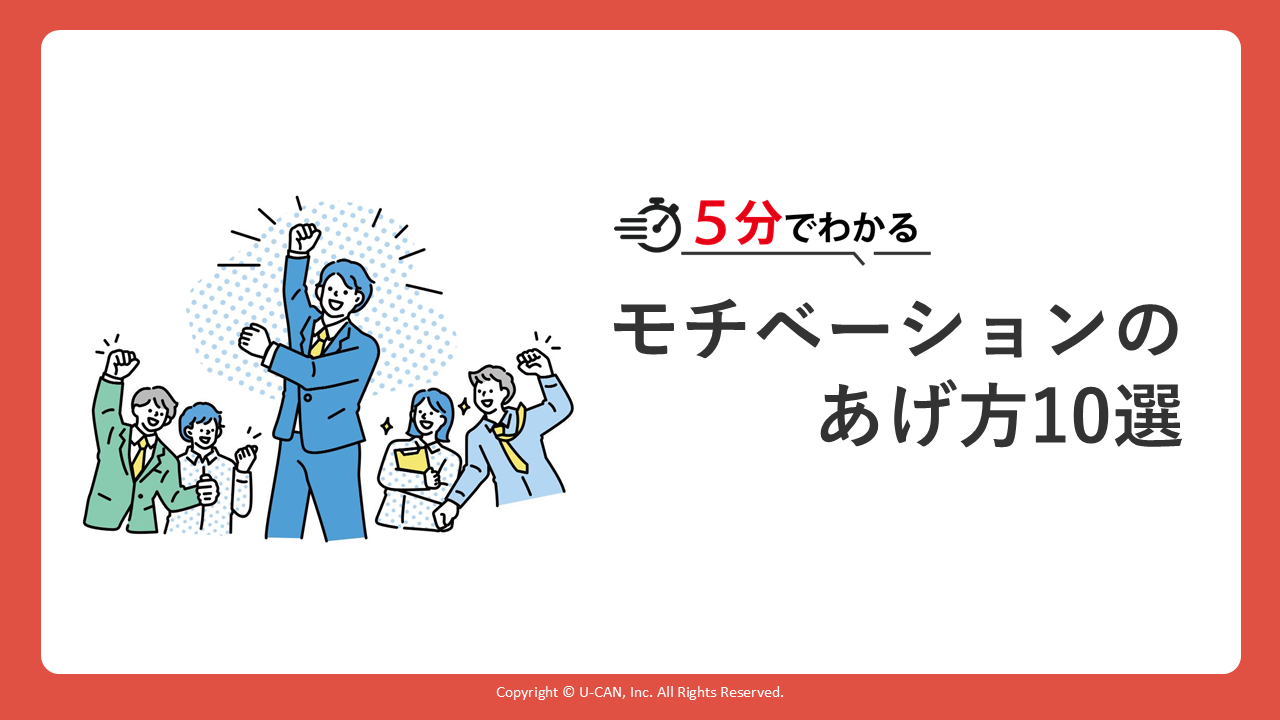Z世代とは
Z世代とは1990年代後半から2010年頃までに生まれた世代のことを指します。
Z世代の語源や年齢について詳しくご紹介します。
Z世代の語源
Z世代の語源は1960~1970年代のアメリカで生まれた人を指す「ジェネレーションX」です。X世代から世代が変わるごとにX、Y、Zと表現も変わってきました。Z世代はX世代の孫世代にあたり、デジタルネイティブ世代とも呼ばれています。生まれた時からインターネットや携帯電話などの先端技術に触れており、テクノロジーとの親和性が高いためです。また別の呼び方として、Z世代の前の世代はミレニアル世代とも呼ばれていたため、Z世代をポストミレニアル世代と呼ぶこともあります。2023年現在ではZ世代が生産年齢人口となり、これからの社会の変化、消費の中心になっていくことが予想されています。
Z世代の年齢は?
Z世代の年齢は明確に定義されているわけではありませんが、一般的には1990年代後半から2010年頃までに生まれた人とされています。2023年時点では10代前半~20代前半までの方がZ世代といえるでしょう。ただし明確な定義があるわけではないため、2023年時点でおおよそ15~25歳になっている人と考えるとわかりやすいです。日本は人口減少局面に入っていますが、世界的にはZ世代に当てはまる人が多く、世界人口の25%を占めるとされています。
Z世代の特徴
Z世代は生まれた時からインターネットやパソコン、スマートフォンなどのデジタルと触れてきた世代です。他の世代とは違った特徴があるため、ライフスタイル、消費傾向、価値観をご紹介します。
価値観の特徴
近年の若手世代は、これまでの常識とは異なる価値観を持ち、多様な物事に関心を寄せています。ここでは、特にZ世代などに見られる代表的な価値観の特徴を3つ紹介し、職場での理解や対応のヒントにしていただけます。
① 多様性を尊重している
現代の若手世代は、人種・性別・宗教・性的指向・働き方など、多様な価値観を自然に受け入れる傾向があります。自分自身が個性を大切にされたいと願う一方で、他者の違いも尊重する意識が高く、企業や組織にもその姿勢を求めがちです。管理職や育成担当者にとっては、画一的な指導や押し付けは逆効果になりやすく、個々の価値観や背景に寄り添った柔軟な対応が求められます。
② 環境・社会問題への関心が強い
若手世代の多くは、SDGsや気候変動、ジェンダー平等といった社会課題に強い関心を持っています。「自分の仕事や会社が、社会にどのように貢献しているか」を重視し、企業の理念やCSR活動に共感を持って入社を決めるケースも少なくありません。そのため、企業側も採用や育成において、「社会とのつながり」や「意義」を明示することが、モチベーション維持やエンゲージメント向上につながります。
③ 着実志向を持つ
SNSや不安定な社会情勢の影響もあり、若手の多くは「地に足のついた生き方」を好む傾向にあります。短期間での急成長や過度な成果主義には懐疑的で、自分のペースでコツコツとスキルを積み上げたいと考える人が増えています。また、キャリアにおいても長期的な見通しや安定性を重視し、明確な成長ルートやサポート体制があるかどうかが、企業選びや定着に影響を与えます。
消費行動の特徴
Z世代は、これまでの世代とは異なる視点で商品やサービスを選びます。価格やブランド名よりも、自分の価値観やライフスタイルに合っているかを重視する傾向があり、消費行動にもその特徴が色濃く表れています。
①ブランドより価値観の合う商品を購入する
Z世代は、「有名だから」「流行っているから」ではなく、自分の考えや信念に合っているかを基準に商品を選ぶ傾向があります。たとえば、サステナブルな製品、ジェンダーフリーのファッション、動物実験を行っていない化粧品など、社会的な価値やストーリーを重視。ブランドよりも“共感”を重視するため、企業や商品に対しても透明性や姿勢が問われるようになっています。共感できる価値観が購買の決め手になる時代です。
②ECサイトの利用が多い
Z世代はスマホネイティブ世代として、オンラインでの買い物が日常的です。店舗に足を運ばず、SNSや口コミ、動画レビューなどを通じて情報を得て、ECサイトで購入する流れが一般的。商品の比較や検討もスマホ1台で完結できるため、スピーディで効率的な購買行動が特徴です。加えて、欲しいものを“今すぐ”手に入れたいという即時性も重視される傾向があり、ECにおける利便性やUI/UXの良さが購入率に大きく影響します。
情報収集の特徴
Z世代は、情報収集の手段としてSNSや動画プラットフォームを日常的に活用しています。Google検索よりもInstagramやTikTokで調べるケースも多く、短時間で視覚的に理解できる情報を好む傾向があります。また、企業や公式サイトの情報だけでなく、リアルな体験談やレビューを重視するため、信頼できる「第三者の声」が判断基準となることも。多様な情報源を横断的に活用し、自分に合った情報を取捨選択する力に長けています。
働き方の特徴
Z世代の働き方に対する価値観は、柔軟性と安定性をバランスよく求めるのが特徴です。従来とは異なる働き方の理想像や、プライベートとの調和を重視する傾向が見られます。
①働き方はオフィス出社が理想リモートワークが広がる一方で、Z世代の中には「オフィス出社」を好む声も多くあります。特に入社間もない若手社員にとっては、リアルなコミュニケーションの方が安心感があり、上司や先輩の働きぶりを直接見ることで学びやすいという利点があります。出社によってオン・オフの切り替えがしやすく、孤独感の軽減にもつながるため、必ずしも「在宅=理想」ではないというのがZ世代のリアルな本音と言えるでしょう。
②ワークライフバランスを重視している
Z世代は、「仕事のために生きる」のではなく、「仕事もプライベートも大切にしたい」という考えが強い傾向にあります。休日や残業時間の管理、メンタルヘルスの配慮など、働きやすさへの意識が高く、企業の制度や職場の風土も重視されます。また、将来への不安が強い世代だからこそ、無理をしてでも成果を出すより、持続可能な働き方を重視。長く健やかに働き続けるための環境を求める声が増えています。
Z世代とミレニアル世代・他の世代との違い
Z世代の他にもミレニアル世代・Y世代・α世代など、様々な呼び方をされる世代もあります。Z世代と各世代の違いについてご紹介します。
ミレニアル世代との違い
ミレニアル世代とは1980~1995年頃に生まれた世代で、Y世代とも重なります。ミレニアル世代は若い年代でインターネットや携帯電話、スマホが普及し始めたため、インターネットやコンピュータの取り扱いへの理解があります。現代の情報社会の過渡期を知っていることから、変化への適応力が高く、仕事と生活のワークライフバランスを重視する人が多いという特徴もあります。そのためX世代よりも多様な価値観への理解があり、他者と自分の価値観の両面を大切にする人が多いです。一方で上下関係の強い縦社会を嫌う傾向があり、横とのつながりを重視する点がZ世代とも近いといえます。
Y世代との違い
Y世代はミレニアル世代と重なっているため、共通する価値観を持っています。
Z世代との違いとしては、夢や理想を追い求め、目標に向かうことを重視する特徴がある点です。Z世代は現実主義の価値観を持っているため、タイムパフォーマンスを重視し、社会問題や環境問題に強い関心がある点で違いがあります。またY世代はメールでのコミュニケーションが強いことから、文章を用いたコミュニケーションに強い点も違いといえるでしょう。
α(アルファ)世代との違い
α(アルファ)世代とは、Z世代の次に生まれた世代を指します。具体的には2013年以降に生まれた人をα世代と呼んでいます。2023年時点では年長者でも10~11才で、消費の中心にはなっていません。
しかしα世代は学校教育にデジタルが取り入れられ、プログラミングも教育課程に入っています。そのためZ世代以上にデジタルネイティブとしての色合いが強く、オンラインやリモート環境が当たり前になっている世代です。インターネットを通じて世界中の情報や知識を得られることから、Z世代以上に多様な価値観を持つ人が多くなると予測できます。
Z世代の育成方法
価値観や働き方が多様化するZ世代を育てるには、従来のやり方だけでは通用しません。信頼関係を築きながら、自立を促すアプローチが求められています。ここでは、効果的な育成方法を3つご紹介します。
日本においてもデジタル技術の進歩を含め、以下の点にZ世代が注目される理由があります。
・DX・IoT・オンラインでのコミュニケーションの普及
・少子化による生産年齢人口の変化
・終身雇用制の崩壊とキャリアビジョンの多様化
・情報化社会により価値観が多様化
従来の社会では、コミュニケーションツールは対面、電話、手紙、1990年代後半からはメール、2000年代以降はチャットも一般化しました。デジタルに高い理解のあるZ世代は、社会において新しい価値観をもたらし、時代の変化を象徴する年代といえます。Z世代という言葉は、ゆとり世代と同様にネガティブな意味合いで使われることも多いです。しかしZ世代はこれからの時代を支えていく存在であり、社会を維持していくためには必要な存在です。
Z世代の価値観を理解したうえで関係性を構築しなければ、企業が存続し、成長を続けていくのは困難でしょう。世代間の価値観の違いを埋めつつ、すべての世代が働きやすい組織の基盤を作るために、Z世代への注目が高まっています。
フィードバックは「肯定」と「提案」のセットで
Z世代は自己肯定感が不安定な一方で、承認欲求が強く、評価に敏感な傾向があります。育成の場では「ダメ出し」ではなく、できている点をまず肯定したうえで、次のアクションにつながる前向きな提案をセットで伝えることが効果的です。また、定期的な1on1での対話を通じて、安心感や信頼を築くことも重要。結果だけでなくプロセスにも目を向けた、丁寧なフィードバックが成長意欲を高めます。
自ら考える機会を意図的に設ける
指示待ちではなく、自分で考えて動けるZ世代を育てるには、「答えを教える」よりも「考えるきっかけを与える」関わり方が効果的です。問いかけを通じて思考を促したり、複数の選択肢から自分で判断させる機会をつくったりすることで、主体性や問題解決力が育ちます。また、試行錯誤のプロセスを見守りながら適度にサポートすることで、自信を持って行動できる人材へと成長していきます。
意義や背景をセットで伝える
Z世代は「なぜそれをやるのか」に納得できないと、モチベーションが上がりにくい世代です。業務の指示を出す際には、単なる「やり方」や「目的」だけでなく、その背景や意味づけまで丁寧に説明することが重要です。社会とのつながりや、チームへの貢献、自身の成長といった文脈が伝わることで、業務への理解が深まり、前向きに取り組めるようになります。納得感は、意欲と継続の原動力となります。
まとめ
本記事ではZ世代の特徴や他の世代との違い、関わり方のポイントなどを解説しました。
X・Y・Z世代と時代によって価値観は変わり、世代間でものの見方や人生観は大きく変わります。今回はZ世代について詳しく紹介しましたが、わかりやすい傾向を解説したにすぎません。Z世代というカテゴライズで人を見るのではなく、個人の持つ特性や価値観は何か、背景について理解することが相互理解の鍵になります。