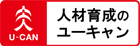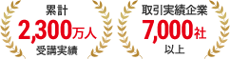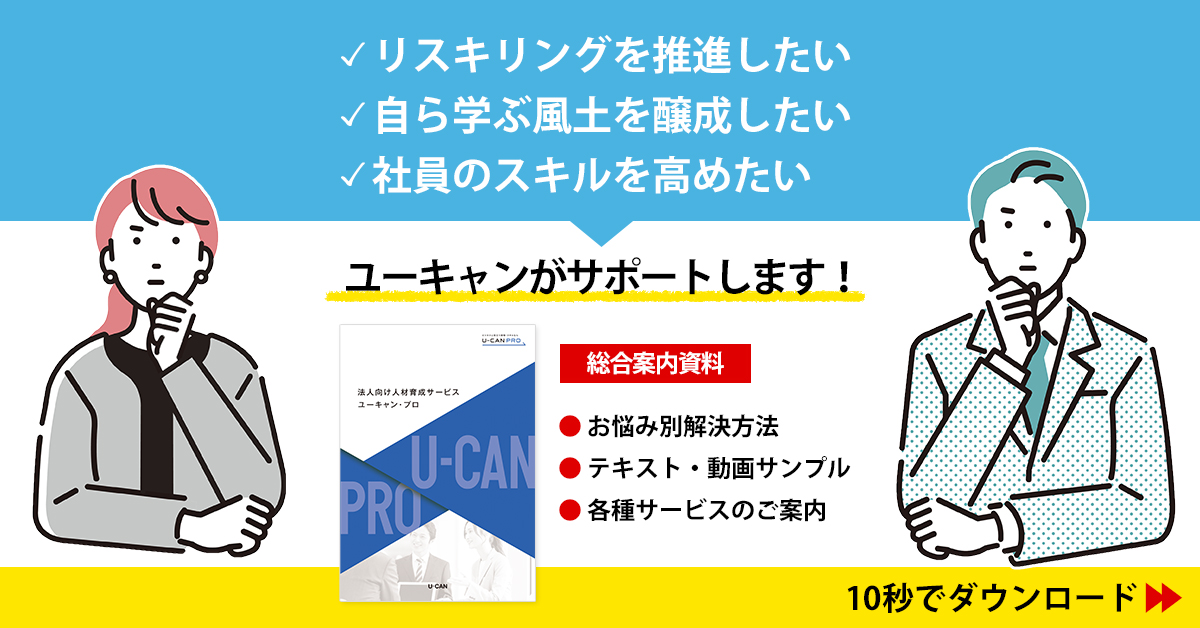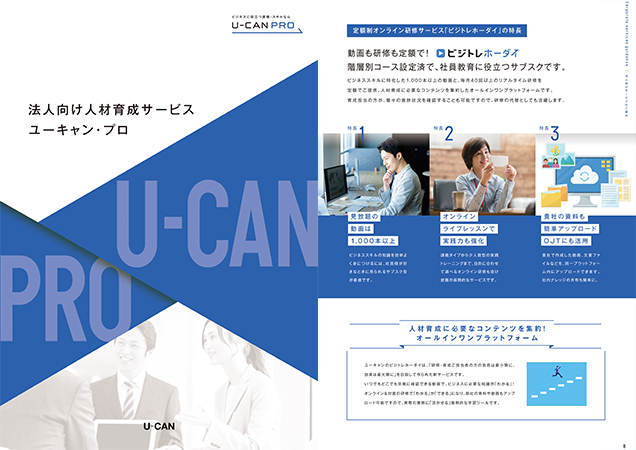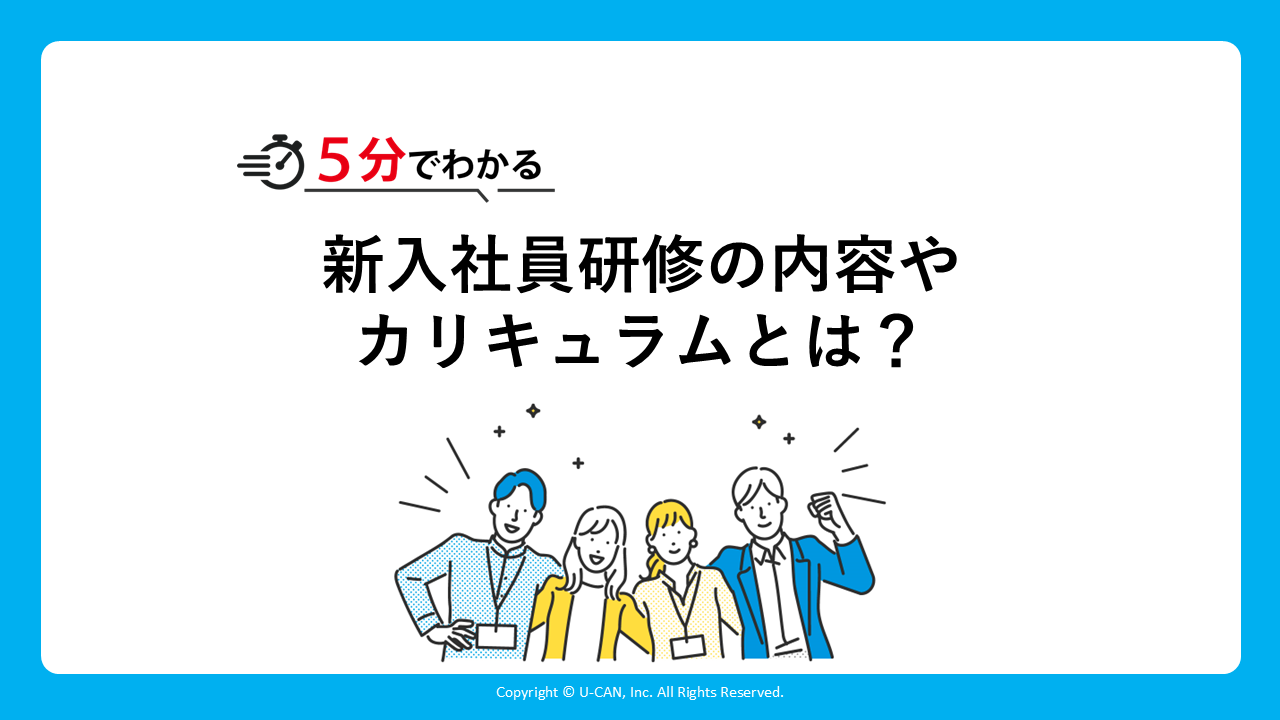企業研修とは何か?
企業研修は業績や生産性を向上し、企業としての社会的信頼や価値を高めるために、社員を対象に行う教育です。企業研修を通して社員の業務遂行能力を高め、業務で求められる知識や技術を習得させることが一番の目的です。そして企業研修には集合研修、オンライン研修、e-ラーニングなどの代表的な形式に加え、OJTのような実務型の研修があります。いずれの研修も最大の目的は社員の能力向上、ひいては企業の業績と生産性向上、組織開発などが含まれます。ただし企業研修は対象とする社員の階層、年齢層、業務内容によって実施形式や内容が全く違う点には注意しなければなりません。社員の成長を促し、自社の業績向上を狙ううえで、何が有効な企業研修となるかをしっかりと検討する必要があります。
関連リンク :研修とは? 意味・目的や種類、実施する手順や成功のポイントまで解説
企業研修の目的とは
①人材開発
企業研修の目的の1つは、既存の人材を教育し、スキルアップを支援することです。企業で働いていくには一定のスキルが求められ、社員の階層によって求められる知識、スキルのレベルも変わります。
例えば、新入社員を早期に戦力として活躍できるように教育し、実務能力を高める研修・講座などが代表的です。また、新人だけでなく中堅やベテランにもレベルに応じた研修を行い、専門性を深めたり、リスキリングを促したりすることもあります。優秀な能力を持つ人材には管理職や経営者向けのマネジメント研修も行い、スキル向上につなげることもできます。
②組織開発
企業研修のもう1つの目的は、研修を通して企業の経営や社員の成長に必要な学習を行い、組織全体の生産性・経営効率を高めることです。 新入社員や若手、中堅、管理職などキャリアプランに合わせた研修を用意し、社員がキャリアビジョンを明確にする必要があります。
個人の目標や将来就きたい役職に合わせてスキル研修を実施することで、組織内での競争やスキルの底上げを促せます。また研修を通して社員の得意・不得意が明確化しやすく、人員配置を決定する際の参考にもなるでしょう。
企業研修における概念の変化
社会の変化が起こることで、企業研修の概念も徐々に変化しています。2000年以前はインターネットを活用した企業研修は稀でしたが、現代ではオンライン研修やe-ラーニングなどが一般化しているのが良い例でしょう。企業研修の概念がどう変化してきたのか、現代のトレンドはどうなっているかなどを紹介します。
人材育成の歴史と概念の変化
日本において人材育成という考えの基礎が築かれたのは、高度経済成長期前の1960年代とされています。この時代は戦後復興が進み、各地の工場で大量生産の時代が到来したことで、製造業や重工業を中心に若い労働力が必要とされました。その結果、基本的な知識とスキルを身につけてもらうために、現代でいうOJTを中心とした教育が進められました。そこから時代が進み、バブル経済崩壊を迎える1990年代初頭には、年功序列制から成果主義への意識の変化が始まり、キャリア開発を重視した企業研修が広まります。さらに2000年代以降は通信技術の発達でグローバル化、ダイバーシティも広がり、近年では個々の人材が持つ能力を経営資源と捉え、最大限活用するタレントマネジメントがトレンドになりつつあります。
企業研修の現在のトレンド
企業研修の現在のトレンドはいくつかあり、その中でも代表的なものは次のものです。
・ウェルビーイング
・ダイバーシティ
・リベラルアーツ
・タレントマネジメント
エンプロイーエクスペリエンスの登場
エンプロイーエクスペリエンスとは「従業員が企業や組織の中で得る経験価値」のことで、社員のエンゲージメントやスキルアップなどに関わるとされる経験のことです。元々は、カスタマーエクスペリエンスやユーザーエクスペリエンスが元になった概念です。従来の人材育成は企業を中心に考えられてきたものが、社員中心へと移行してきた結果生まれた考え方でもあります。社員が仕事に対して熱意や向上心を持つには、社員の能力とやる気を引き出すことが重要です。先述のウェルビーイングやダイバーシティなどとも通じる考え方といえるでしょう。
人材育成での個別最適化
近年の企業研修では、全体への教育はもちろんですが、個別最適化も重要とされています。例えばパーソナライズドラーニングやアダプティブラーニング、体験型研修などがあります。いずれも個人の能力や関心、学習意欲、習熟度などを把握・分析し、一人ひとりに合わせた研修を行うことで効果を高める学習方法です。個別最適化されたカリキュラムやプログラムを学ぶことで、社員は個性を最大限伸ばし、新たなキャリア開発へとつなげられます。人材育成では画一的な学びの機会を提供するだけでなく、社員の個別性を考慮した内容がトレンドとなっています。
上記のトレンドは受講者一人ひとりの全人的な幸福、多様性への理解、専門職としての教養や技能など、社員個人に焦点を当てている点が特徴です。日本では少子高齢化により若手人材が不足していることに加え、若手社員は転職によるキャリア開発にも積極的です。優秀な人材を企業が確保するには、社員の幸福や多様性への理解、特化した技能などを活かせる教育と学びを生かせる場の提供が必須となっています。
企業研修における手法の変化
企業研修における運営方法や、近年のトレンドの変化について紹介します。
一般的な運営方法
企業研修で一般的な方法としては、実務を通して学ぶOJTと従来型の研修方法であるOff-JTがあります。2つの研修方法は今も多くの企業で実施されており、知識のインプットとアウトプットの両方ができる研修方法です。それぞれの特徴とメリット・デメリットについても紹介します。
①OJT
OJTは「On the Job Training」の略称で、実務での経験やワンシーンを上司または先輩社員とともに振り返ることで、正しい対応や技術を学ぶ研修手法です。実務で実際に経験する内容に基づいて学べることから、業務遂行に必要な知識と経験が身につけられます。OJTを行うメリットとしては、実践的な内容を学べることと、指導者から正しい技術や対応について直接学べる点です。各部署で必要な知識とスキルを学べるため、即戦力として成長しやすい研修方法とされています。一方のデメリットは1on1での指導となるため、人的資源が必要になることと、社員の成長が指導者のスキルに依存してしまうことです。人材不足の企業ではOJTに十分な時間をかけられないうえ、指導者のスキル以上の内容は教育できません。
②Off-JT
Off-JTはOJTとは違い、職場外で行う研修のことを指します。実務的な内容を学ぶことよりも、研修を通して業務に必要な知識やスキルのインプットのほか、業務から離れて学ぶ機会を提供することが主な目的です。Off-JTのメリットは、専門的な知識を学びやすいほか、社員同士の交流が生まれやすい点です。OJTは限られた部署内でのつながりになりますが、Off-JTは研修対象者を1箇所に集める特性上、さまざまな部署の人と関わりを持てます。一方のデメリットは、必ずしも業務に必要な知識・技術を学べるとは限らず、実務で活かせるかどうかは人による点です。長期的に見れば必要な知識でも、すぐに活用できる場面がなければ、社員のモチベーション低下につながる可能性があります。
最近のトレンドの方法
近年の企業研修では、従来のOJTやOff-JTのようなインプット型の学習方法だけでなく、体験型の研修も取り入れられています。人気の高い研修方法であるワークショップ型やe-ラーニングについて、それぞれの特徴とメリット・デメリットについても紹介します。
①ワークショップ型研修
ワークショップ型研修は、一か所に受講者が集合し、グループを作ってゲームや討論を行う体験型の研修方法です。インプット学習で学んだ知識をその場で活用できるため、アウトプットも兼ねた効率的な学習スタイルです。メリットとしては、ゲーム要素を通じて楽しみながら知識を定着でき、チームビルディングの基本も学べることでしょう。受講者が興味を持って研修に臨めるため、高い学習効果が期待できます。一方のデメリットは研修に時間がかかることと、一定のコストがかかる点です。ワークショップ型研修はさまざまなゲームを体験して学ぶため、最低でも2時間以上行うことになり、休憩を挟まなければ集中力を維持するのは難しいでしょう。
②e-ラーニング
e-ラーニングはインターネットを通じて教育・研修を行う方法です。パソコン・スマートフォン・タブレットを利用し、インターネット環境さえあればいつでもどこでも研修を受講できます。近年はe-ラーニングと集合研修・対面学習を併用する「ブレンディッドラーニング」、受講者の理解度や進捗・必要なスキルなどに合わせて学習内容を変更する「パーソナライズトラーニング」、数分で学べる「マイクロラーニング」などが人気です。いずれも受講者の業務内容やライフスタイルに合わせて、選びやすい点が魅力となります。
企業研修を実施する際の注意点
企業研修を成功させるには、実施するための注意点を意識する必要があります。どのような点に注意すべきか、3つのポイントを紹介します。
研修目的・目標の明確化
企業研修を実施するには、まず研修でどのような知識・スキルを身につけてほしいのか、どのような人材を育てたいかといった目的や目標を明確に設定することが大切です。単に知識とスキルを高めるだけであっても、成長の方向性を示さなければ、社員のキャリア開発や一人ひとりの生産性向上にはつながりにくいからです。また目的や目標を明確化することで、研修を受ける社員のモチベーションにもつながり、エンゲージメントも向上します。
研修後の振り返り・フィードバックの実施
研修は実施した後、どのくらい学びが身についているか振り返り、指導者からのフィードバックも行うことで確かな実力へと昇華されます。例えば研修で学んだ知識があっても、実践の場で瞬時に力を発揮できなければ学びが定着したとはいえません。そのため研修後は研修担当者や上司も交えて、研修を通しての学びや課題、改善方法などを振り返るのがよいでしょう。受講した社員にとっても、「自分を見てくれている」という安心感とモチベーションアップになり、研修効果を高める効果が期待できます。
研修コストの計算
研修を実施する際は、常にコストを意識しながら計画を立てる必要があります。社内で行う場合には、準備する資料や人件費、通信費、その他雑費まで多くの費用が発生します。また社外に依頼する場合にも、講師に支払う謝礼、会場の利用料、交通費などさまざまな費用がかかります。企業研修にかけられるコストを計算したうえで、適切なカリキュラムを設計することが重要です。
企業研修の事例
企業研修を導入して成功した企業の例について2社紹介します。
株式会社ツクイ
介護事業で全国展開する株式会社ツクイでは、社員から学び支援の希望が強かったことから多様な通信講座を導入する決定を行いました。通信講座の内容は仕事に関することだけでなく、趣味や教養など多岐にわたり、企業研修の導入によって社員の学びに対する意識の変化が起こりました。学びに対する支援も行ったことで、社員は通信講座でも大きな不安を抱くことなく学びに集中できたようです。また副次的効果として社員同士で共通の話題ができ、社員間のコミュニケーションも活性化されました。企業研修を通して、社員のモチベーションとエンゲージメントを高めることに成功した事例といえます。
株式会社TSIホールディングス
株式会社TSIホールディングスでは、2016年からグループを横断する形で教育制度の構築を進めてきました。その一環として、社員階層別の必須知識やスキルの習得、社員間のコミュニケーション活性化を目的に、集合研修やグループワーク形式での研修を取り入れました。企業研修の実施にあたり重視したポイントが「カスタマイズ性」と「コストパフォーマンス」です。講師の経験も研修内容に盛り込んだ柔軟性の高い研修内容と、費用対効果の高さを意識した研修により、階層別での知識・スキル習熟度の向上とコミュニケーションの活性化につながりました。また研修後はフォローシートで効果を確認することで、実際の業務で社員が学びを行動化できているか確認したことで、社員の意識も変化しました。
まとめ
今回紹介した研修のようなトレンドに合わせたカリキュラムを用意することで、社員に必要な知識・スキルを効果的に学習してもらうことが可能です。企業研修に頭を悩ませている担当者の方のために、課題解決のための最適な研修プログラムをご提案いたします。ぜひ貴社の課題をお聞かせください。