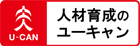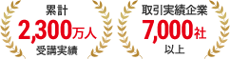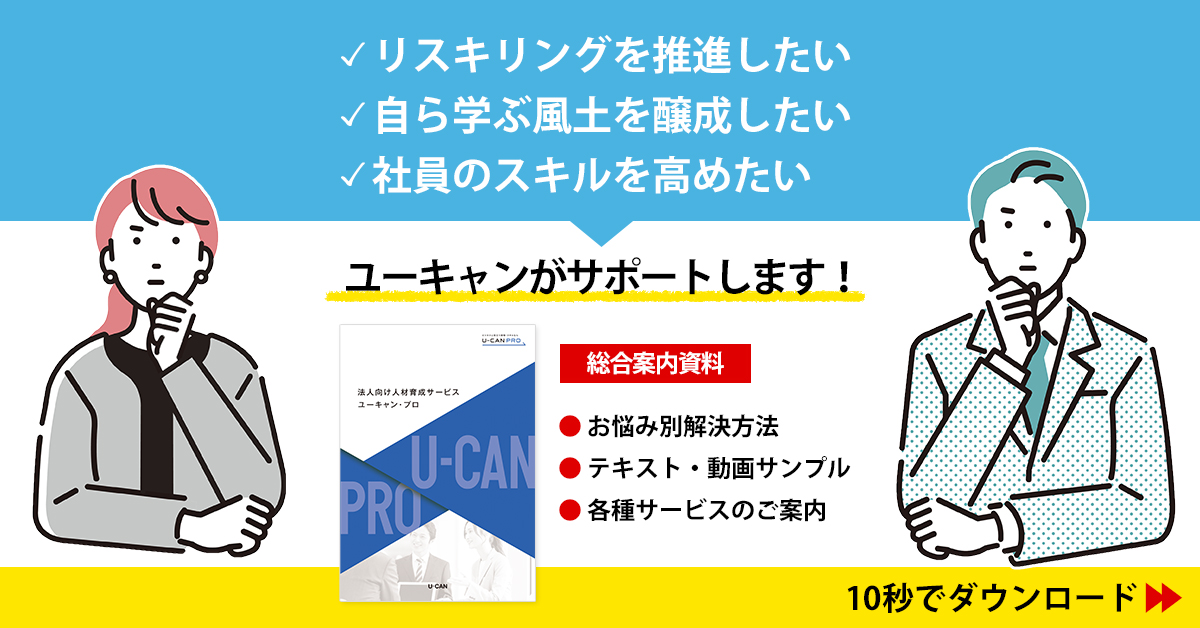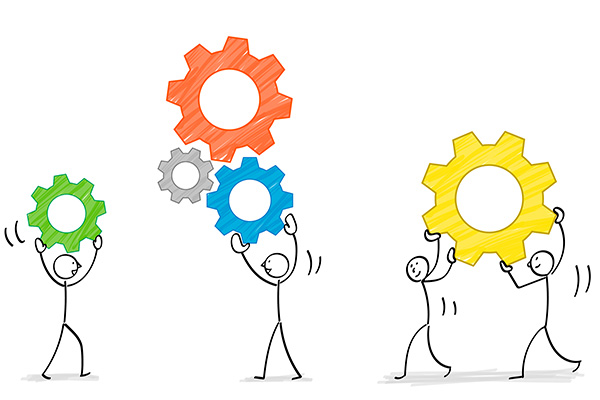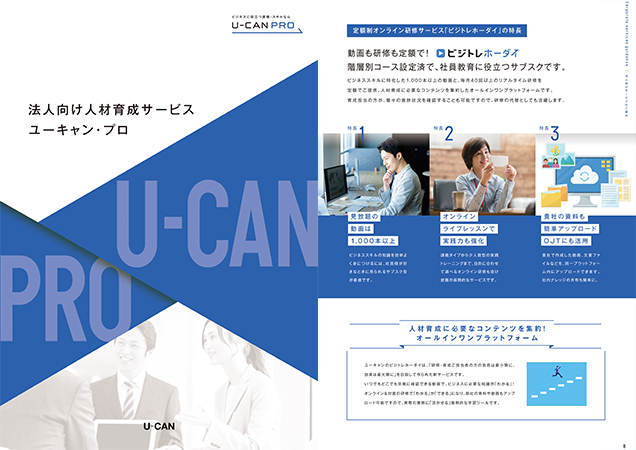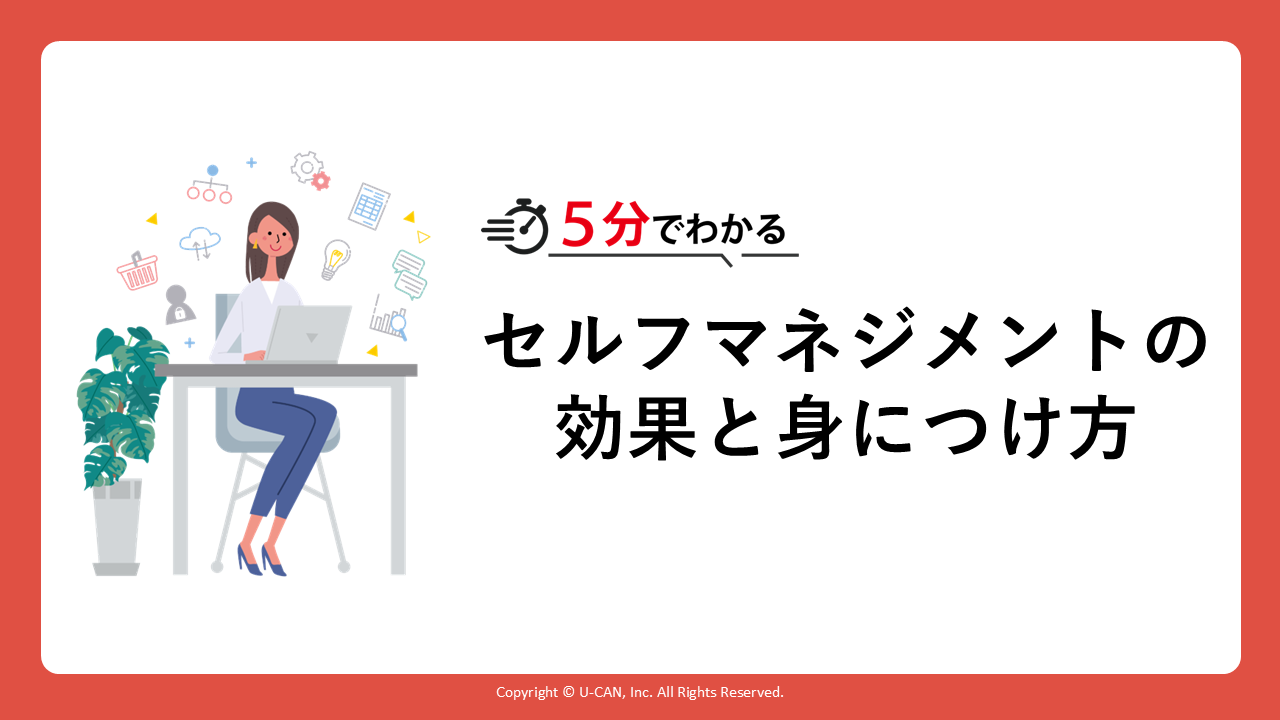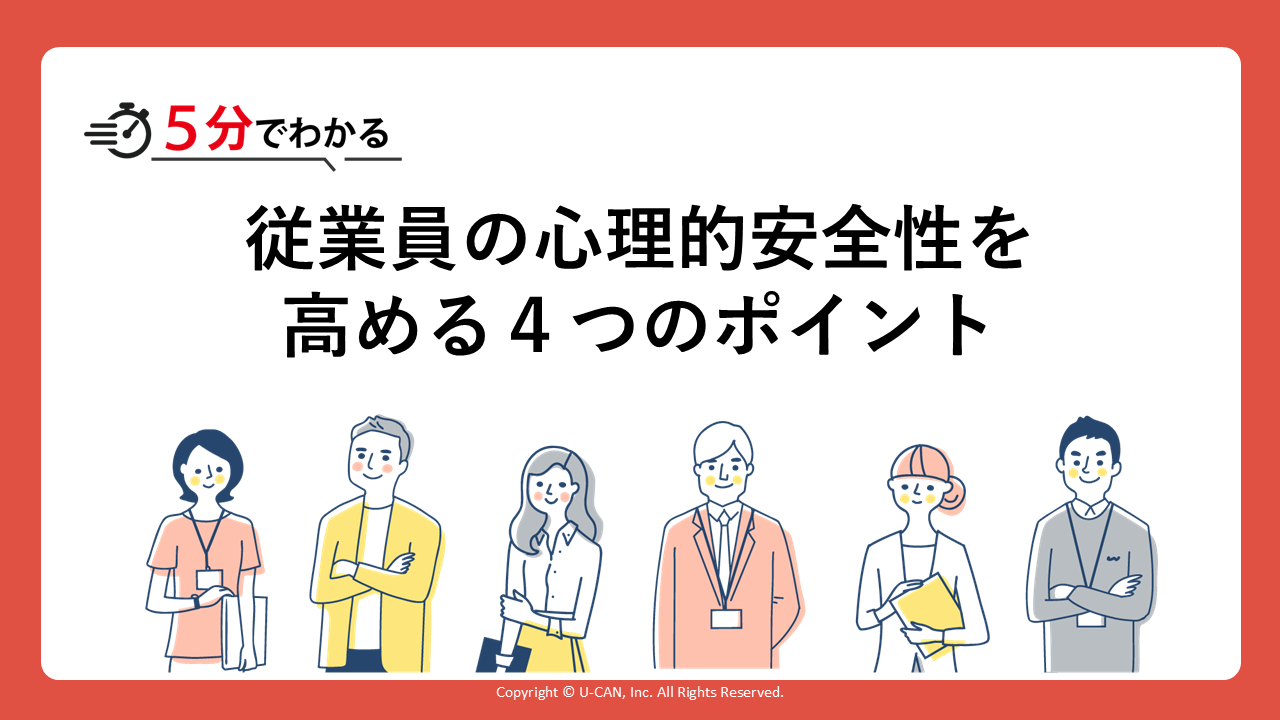レジリエンスとは何か?
レジリエンスについて、以下の2点を解説します。
- ・レジリエンスは「困難を乗り越え回復する力」
- ・ビジネスにおけるレジリエンス
レジリエンスは「困難を乗り越え回復する力」
レジリエンスとは、物理学の分野で用いられてきた用語です。「外からの力によって変形した物体が、元に戻ろうとする力」を表す言葉で、現在は心理学の分野で使われることが増えています。
心理学におけるレジリエンスとは、逆境やストレスに直面したときに適応する「精神的な回復力」を表す言葉として用いられています。 対義語は「脆弱性」と呼ばれ、情報セキュリティにおける脆弱性と区別するために、「ストレス脆弱性」と呼ぶこともあります。
ビジネスにおけるレジリエンス
ビジネスにおいても、レジリエンスの視点は欠かせません。定期的な健康診断で従業員の身体の不調を把握するように、精神的な不調をフォローする体制が必要視されているためです。
レジリエンスを強化することは、従業員の心身の健康を維持し、生産性の向上や作業効率改善を目指す「健康経営」の戦略的な実践に直結します。企業と従業員双方にメリットのある健康経営を実現する意味でも、レジリエンスは重要です。
心理学から見たレジリエンスの定義
心理学におけるレジリエンスとは、困難やストレスに直面した際に柔軟に対応し、回復・適応する力を指します。アメリカの心理学者エミー・ワーナーは、逆境を乗り越えて健全に成長する子どもの研究を通じて、レジリエンスは先天的資質だけでなく環境要因にも影響されると指摘しました。またマーティン・セリグマンは、ポジティブ心理学の観点から、レジリエンスは「習得可能なスキル」であり、楽観性や自己効力感の強化によって高められると述べました。さらに心理学者アン・マステンは、レジリエンスを「日常的な適応力の驚異(ordinary magic)」とし、多くの人が本来備えている力と捉えています。これらの見解は、レジリエンスが固定的な性質ではなく、育成や環境によって高めることができる力であることを示しています。
レジリエンスの歴史的背景
レジリエンスの概念は、もともと物理学において「外部からの衝撃に対して元の形に戻る力」として用いられていました。これが心理学に応用されたのは1970年代であり、エミー・ワーナーらが逆境下でも健全に成長する子どもの研究を通じて、心理的レジリエンスの重要性を提唱しました。1980~90年代にはストレス理論や発達心理学の研究と結びつき、個人の回復力や適応力として注目されるようになります。2000年代以降、マーティン・セリグマンのポジティブ心理学の影響を受け「レジリエンスは育成可能なスキル」との認識が広まりました。さらに近年ではレジリエンスはビジネス領域でも注目され、変化や逆境に強い組織づくりや人材育成のキーワードとして活用されています。
ビジネスでレジリエンスが注目される理由
昨今のビジネスシーンで、特にレジリエンスが注目され始めている理由は3つあります。
- ・メンタルヘルスの社会問題化
- ・新型コロナウイルスの流行
- ・VUCA時代への対処
以下で詳しく解説します。
メンタルヘルスの社会問題化
日本では、職場におけるメンタルヘルスの問題が顕在化し、社会問題の1つとして認知が急速に広がっています。2015年にはストレスチェックが義務化されるなど、国も問題解決に力を入れており、企業に何らかの対策を講じることが求められています。
メンタルヘルスの改善につながると期待されているのが、精神的回復力を意味する「レジリエンス」の強化です。メンタルヘルス対策として重要な、ストレス耐性や思考の柔軟性は、レジリエンスとも深い関係があります。
新型コロナウイルスの流行
新型コロナウイルスの流行によって、日々の暮らしや働き方にも大きな変化が生じました。外出の自粛やリモートワークの普及などで、人々の消費活動が変容したことで、これまでになかったストレスに悩まされる人も増えています。
企業は時代に適したビジネス形態を模索することに加えて、従業員の心身的なサポート体制を構築していかなければなりません。 レジリエンスを高めることで、これまでにない困難や逆境を乗り越える力を養うことができます。
VUCA時代への対処
VUCA(ブーカ)とはVolatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字で構成した造語です。社会情勢や環境の変化が目まぐるしく、未来の予測が難しい状況のことを表します。
VUCA時代に対応しながらビジネスを進めていくには、レジリエンスが重要です。レジリエンスは、ストレス要因をなくすのではなく、ストレスに適応することを目指します。精神的回復力が高まることで、不確実で煩雑な問題にも柔軟に対応しやすくなります。
急速な技術革新への適応
DX(デジタルトランスフォーメーション)が進む現代では、AI、IoT、自動化といった技術革新が急速に進行し、業務や働き方の変化に柔軟に対応する力が求められています。このような環境下でレジリエンスは変化に適応し、ストレスを乗り越えながら前向きに行動する力として非常に重要です。特にビジネス現場では、技術に対する不安や業務変化に対処するために個人・組織のレジリエンス向上が不可欠となっています。
働き方改革の導入
働き方改革により、テレワークやフレックスタイム、副業など多様な働き方が広がる中、従業員には環境や役割の変化にも柔軟に対応する力が求められています。レジリエンスは孤立感や自己管理の難しさといった新しい働き方に伴う課題に対処し、自律的かつ前向きに働くための重要な力です。こうした背景から、変化に強く自己を適切にコントロールできる人材として、レジリエンスの高い人がビジネス現場で注目されています。
レジリエンスにおける因子と尺度
レジリエンスを測定するおもな尺度として、下記のものが挙げられます。
危険因子と保護因子
レジリエンスへの理解を深めるためには、危険因子と保護因子について知っておく必要があります。元々は医療現場で使われていた用語ですが、ビジネスの場における意味について、以下で詳しく解説します。
・危険因子
危険因子とは、困難な状況をもたらす原因を指します。例えば、虐待や離婚、貧困、災害、戦争などが危険因子に該当します。ビジネスシーンでは、病気や人間関係の悪化、希望していない部門への配属などが危険因子として挙げられます。
・保護因子
保護因子とは、困難な状況を乗り越える力を指します。性格といった先天的かつ個人的な因子や、問題解決能力といった、後天的な因子などが保護因子に該当します。 保護因子には家族や友人によるサポートなどの環境要因も含まれており、ビジネスシーンでは企業が従業員をフォローする体制を整えることも保護因子に相当します。
精神的回復力
精神的回復力とは、レジリエンスをもたらす個人内因子です。レジリエンスを、測定の1つである精神的回復力尺度で取り上げており、次の3因子で構成されています。
- ●新奇性追求
- ●感情調整
- ●肯定的な未来志向
精神的回復力尺度は、パーソナリティ心理学や発達心理学を専門とする、小塩真司氏の研究グループによって考案され、精神的回復力を21項目から測定していきます。21項目の内訳は、新奇性追求が7項目、感情調整が9項目、肯定的な未来志向が5項目です。
※参考:「ネガティブな出来事からの立ち直りを導く心理的特性 ― 精神的回復力尺度の作成」(カウンセリング研究, 35(1), 57-65)
新奇性追求
新奇性追求とは、習慣や常識にとらわれずチャレンジする姿勢や、新しいことへの興味を指します。下記は、精神的回復力尺度における新奇性追求を測定する質問文の一例です。- ・色々なことにチャレンジするのが好きだ
- ・困難があっても、それは人生にとって価値のあるものだと思う
感情調整
感情調整とは、気持ちのコントロールを表しており、怒りや悲しみといったマイナスの感情を調整することを指します。下記は、精神的回復力尺度における感情調整を測定する質問文の一例です。- ・自分の感情をコントロールできる方だ
- ・ねばり強い人間だと思う
肯定的な未来志向
肯定的な未来志向とは、未来に対してポジティブに向き合い、目標に向かって計画を立て実践することを指します。下記は、精神的回復力尺度における肯定的な未来志向を測定する質問文の一例です。- ・自分の未来にはきっといいことがあると思う
- ・自分の目標のために努力している
資質的要因と獲得的要因
資質的要因と獲得的要因は、臨床心理学やパーソナリティ心理学を専門とする平野真理氏の研究グループが考案した尺度です。二次元レジリエンス要因尺度では、資質的要因は後天的に身につきやすく、獲得的要因は先天的な要素が大きいとされています。
※参考:Study | hiranolab
資質的レジリエンス要因(資質的要因)
資質的レジリエンス要因(資質的要因)は、次の4項目で構成されています。- ・楽観性
- ・統御性
- ・社交性
- ・行動力
獲得的レジリエンス要因(獲得的要因)
獲得的レジリエンス要因(獲得的要因)は、次の3項目で構成されています。- ・問題解決志向
- ・自己理解
- ・他者心理の理解
レジリエンスを測定する主な尺度
レジリエンスを測定する4つの尺度には、それぞれ下記の特徴があります。
| 尺度の名称 | 因子・尺度 | 項目数 |
| レジリエンススケール (RS、Resilience Scale) | 個人的コンピテンス (Personal Competence) 自己と人生の受容 (Acceptance of Self and Life) | 25項目 |
| 森敏昭氏らのレジリエンス尺度 | I am 因子 I can 因子 I have 因 I will/do 因子 | 29項目 |
| 精神的回復力尺度 (ARS、Adolescent Resilience Scale) | 新奇性追求 感情調整 肯定的な未来志向 | 21項目 |
| 二次元レジリエンス要因尺度 (BRS、Bidimensional Resilience Scale) | 資質的要因 獲得的要因 | 21項目 |
どの尺度においても、簡単な質問文に回答するだけで、レジリエンスの高さが測定できます。
自己診断でわかるレジリエンスチェック方法
レジリエンスには「自己効力感」「感情調整力」「対人関係力」などの因子があり、自己診断を通じて自分の強みや課題を把握できます。以下は簡易的なセルフチェックリストです。
・困難に直面しても前向きに乗り越えようとする気持ちを持てる
・失敗しても自分には改善できる力があると信じている
・感情が乱れたときに自分なりの方法で落ち着きを取り戻せる
・周囲に相談できる人や信頼できる人がいる
・変化の多い状況や環境でも柔軟に対応できる
各項目に対して「はい/どちらともいえない/いいえ」のいずれかで答え、「はい」が多いほどレジリエンスが高い傾向にあります。このような簡易的なチェックでも自分の傾向を知る第一歩となりますから、必要に応じて専門的な尺度(CD-RISCなど)を用いることも有効です。
レジリエンスと似ている用語との違い
レジリエンスと似ている用語には、以下のようなものがあります。
- ・メンタルヘルス
- ・ハーディネス
- ・ストレス耐性・ストレスコーピング
それぞれの用語の意味と、レジリエンスとの相違点を解説します。
「メンタルヘルス」との違い
メンタルヘルスは精神的な健康を意味しており、不調の軽減や精神的なサポートが必要な場面で使われる用語です。近年、職場におけるメンタルヘルスケアの重要性が高まっており、多くの企業が積極的な施策を展開しています。レジリエンスは、ストレスに直面した際の回復力を示す用語で、困難にどう適応するか、上手く回復できるかを意味します。
「ハーディネス」との違い
ハーディネスとは、ストレスを受けている状況下でも、メンタルの健康を維持しようとする特性を表す用語です。 例えば、困難な状況に陥ったとき、「何とかなるだろう」と前向きな気持ちになれる人はハーディネスの傾向が強いといえます。ハーディネスがストレスを防御する精神的な強さと捉えられるのに対して、レジリエンスはストレスへの適応力を意味します。
「ストレス耐性・ストレスコーピング」との違い
ストレス耐性はストレスに耐える力の程度を指し、レジリエンスを構成する要素の1つとして位置付けられています。一方、ストレスコーピングは、ストレスに対処する方法を意味します。「愚痴を聞いてもらうことでストレスが緩和される」といった状態は、ストレスコーピングの代表例です。レジリエンスがストレスに対する耐久力や回復力を示しているのに対して、ストレスコーピングはストレスを切り抜けるものといえます。
「マインドフルネス」との違い
マインドフルネスとレジリエンスは共に心理的健康を高める概念ですが、その定義・目的・実践方法に違いがあります。マインドフルネスは「今この瞬間の体験に注意を向け、評価せずに受け入れる心の在り方」を指し、目的はストレス軽減や自己認識の向上です。実践方法としては、呼吸瞑想やボディスキャンなどがあります。一方のレジリエンスは「困難や逆境から回復・適応する力」を意味し、目的は逆境を乗り越え、持続的に前進する能力の強化です。実践方法にはポジティブな思考習慣の構築、自己効力感の育成、ソーシャルサポートの活用などがあります。つまりマインドフルネスは“気づき”に重点を置く内省的な技法であり、レジリエンスは“回復・適応”に向けた行動力の側面が強いという違いがあります。
関連記事:https://www.u-can.co.jp/houjin/column/cl095.html?srsltid=AfmBOoq3HzbxeCGQWLBm07zKWNxX3ipbHoHGCiXhwv6am1OF3tn8Xl5s
「アンチフラジャイル」との違い
レジリエンスは「困難や変化に対して元の状態に回復する力」のことです。一方、ナシム・ニコラス・タレブが提唱した「アンチフラジャイル(Antifragile)」は、それを超えて「変化やストレスを受けることで、むしろ成長・強化される性質」を意味します。つまりレジリエンスは現状維持・回復に重点があるのに対し、アンチフラジャイルは進化・適応による改善という点が大きな違いです。ビジネスの例としては、複数の収益源を持ち、市場変化に応じて柔軟に戦略を変える企業がアンチフラジャイル型といえます。たとえばAmazonはパンデミックなどの外的ショックを通じてECやクラウド事業を急成長させており、逆境を好機に変える代表例とされています。
企業にとってのレジリエンスの重要性
レジリエンスを高めることで、企業が得られるメリットは4つあります。
- ・情勢の変化に対応できる
- ・従業員の健康維持・促進
- ・組織の業績向上
- ・社会的な評価が上がる
以下で詳しく解説します。
情勢の変化に対応できる
社会情勢の変化が激しい現代社会において、組織のレジリエンスが高ければ、臨機応変な対応をとりやすくなります。企業があらゆる困難、課題を乗り越え、成長を持続させるには、従業員一人一人のレジリエンスを強化することが重要です。
従業員の健康維持・促進
従業員のレジリエンスが高ければ、ストレスへの対応力、回復力が向上するため、健康の維持促進につながります。従業員のレジリエンスを重視することで、離職率の低下や、仕事に対する意欲向上などが期待できます。
組織の業績向上
レジリエンスが高い組織は、目標を達成する力が強く、変化に適応して成長し続けることが可能です。 失敗を恐れず新しいことに挑戦する従業員が増えれば、組織としての業績向上にもつながります。
社会的な評価が上がる
レジリエンスへの取り組みが、企業を評価する指標の1つとなるケースが増えています。柔軟な発想で新しい価値を創造するためにも、レジリエンスは欠かせません。投資家の判断要素としても重視されていることからも、企業として積極的に取り組む姿勢が求められます。
イノベーション創出の土台になる
レジリエンスが高い組織は変化や失敗を恐れず挑戦する風土を持つため、イノベーションを生み出しやすい特性があります。まず困難な状況でも柔軟に対応し前向きに学ぶ姿勢が根付いているため、新たなアイデアを試す余地が生まれます。次に失敗を成長の機会と捉える文化があることで、社員はリスクを取ることにも前向きになり、結果として創造性が高まるという好循環に入るためです。たとえばトヨタ自動車は「失敗から学ぶ文化」と現場主義を重視し、ハイブリッド車や自動運転技術といった革新を次々と実現してきました。このように、レジリエンスは変化に耐えるだけでなく、未来を切り開く土台となります。
危機管理能力の向上
企業にとってレジリエンスは、危機管理能力を高める重要な基盤です。危機対応には「予防・準備・対応・回復」の4段階があります。まずレジリエンスが高い組織は日常的にリスクを予測・察知する力があり、問題の予防が可能です。次に、危機が発生することを前提とした訓練やマニュアル整備といった準備を怠りません。実際に危機が起きた際には、迅速かつ柔軟な対応ができる体制が整っており、混乱を最小限に抑えます。そして最後の回復段階では、被害からの立て直しだけでなく、経験から学び組織の強化へとつなげるという一連の対応力を支えるのが組織のレジリエンスです。
レジリエンスにおける6つのコンピテンシー(要素)
コンピテンシー(要素)とは、高い成果につながる行動特性のことを指します。レジリエンス研究の第一人者であるカレン・ライビッチ博士は、6つの要素を提唱しています。
- ・自己認識
- ・自制心(セルフコントロール)
- ・現実的楽観性
- ・精神的柔軟性
- ・自己効力感
- ・人とのつながり
以下で詳しく解説します。
自己認識
自己認識とは、自分の思考や感情、行動を認識する能力です。困難に直面した場合も感情に流されず、客観的に状況を認識することが問題解決の第一歩となります。動揺しても自分を落ち着かせる方法が分かっている人は、自己認識力が高いといえます。
自制心(セルフコントロール)
自制心(セルフコントロール)は、自分の思考や行動を、目的に向かわせる能力です。 自律心や自己調整、自己鍛錬などと似ていて、訓練することでコントロールしやすい特性があります。感情に流されず、自らの感情を制御することができれば、どんな状況においても冷静に対処しやすくなります。
現実的楽観性
現実的楽観性は、困難に対して楽観的かつ前向きに考える能力です。ただし、根拠のない楽観的な思考で物事を捉えてしまうと、最善の対処はできません。楽観性を持って現実的な行動を起こす能力があってこそ、レジリエンスにおける重要な要素となります。現実的楽観性を高めることで、「困難な状況を乗り越えることで人生の糧となる」と考えることができ、課題に対してポジティブに取り組めます。
精神的柔軟性
精神的柔軟性は、物事の本質を捉える能力です。難しい課題に対して前向きな気持ちで取り組むことは大切ですが、感情が高ぶりすぎると視野が狭くなるリスクがあります。レジリエンスでは、多角的な視点で冷静に判断することが重視されます。精神的柔軟性があることで、物事を広い視野で把握しやすくなり、課題に対して柔軟に対処できます。
自己効力感
自己効力感は、状況のコントロールや、問題の解決が可能だと信じる能力です。自己効力感は「セルフ・エフィカシー」と呼ばれることもあり、自分への自信を表します。自己効力感が高い人は「自分ならできる」と信じて、困難に立ち向かう行動力があります。
人とのつながり
人とのつながりは、チームワークによって課題解決につなげる能力です。レジリエンスは、個人の内面的な要素だけでなく、外部の対人関係によっても強化できます。良好な人間関係があれば、困難が生じた際にサポートを受けやすく、チームとしての解決が目指せます。
企業のレジリエンスを高める方法
レジリエンスの強化は従業員個人の問題ではありません。企業がレジリエンスを効果的に高めるためには、4つの方法があります。
- ・従業員のレジリエンスを高める
- ・働きやすい環境を整備する
- ・BCPに取り組む
- ・ビジョンを浸透させる
以下で詳しく解説します。
従業員のレジリエンスを高める
企業のレジリエンスを高めるためには、従業員のレジリエンスが育つ環境を整える必要があります。従業員1人ひとりのレジリエンスが強化されると、結果として組織全体のレジリエンスが底上げされます。
ただし、レジリエンスを高めるには時間を要するため、トレーニングや研修を行いながら、少しずつ浸透させていくことが重要です。また、レジリエンスを従来の根性や気合いといった、精神論と同等のものと捉えてしまうと、悪影響を及ぼしかねません。企業がレジリエンスを正しく理解して、従業員の教育に反映させることを意識しましょう。
働きやすい環境を整備する
柔軟性のある組織風土を醸成していくことで、企業のレジリエンスは高まります。例えば、組織全体で、チャレンジを評価するシステムを取り入れるのも、1つの方法です。従業員が新しいことに挑戦しやすい環境を整備することで、レジリエンスが高まるだけではなく、エンゲージメントの向上といった、さまざまな効果が期待できます。
また、従業員の評価において、減点方式をやめれば、失敗を恐れず挑戦しやすくなります。レジリエンスが高い人でも、ミスをするたびにネガティブな評価をされると、モチベーションは低下します。ミスした従業員に責任を負わせるのではなく、組織の課題として対処することで、再発防止策を講じることが可能です。問題が生じた原因を分析し、組織全体で共有すれば成功につながるナレッジにもなるでしょう。
BCPに取り組む
BCPは「Business Continuity Planning」の略称で、事業継続計画を指します。災害などのトラブルに備えて、企業があらかじめ決めておく対処策のことで、「社内データのバックアップ体制を構築する」「電力を確保するための設備を用意する」といった例が代表的です。
BCPに取り組んでいれば、有事の際も被害を最小限に抑えて、事業を継続させられます。また、BCPは企業のレジリエンスを高める観点からも重要です。災害は困難な状況をもたらす「危険因子」となるため、従業員のストレスを緩和させる体制を整えなければなりません。例えば、事故や災害が発生しても、対応方法のガイドラインが用意されていれば、スムーズな復旧が見込めます。
また、テレワークを推進している企業は、サイバー攻撃や情報漏洩といったトラブルが起こるリスクを抱えているため、事前にBCPを整えておきましょう。
ビジョンを浸透させる
企業としてレジリエンスを高めるには、従業員へのビジョンやミッションの浸透が不可欠です。組織の隅々まで正しい理解を浸透させるためには、一度ではなく繰り返しビジョンを伝えていく必要があります。ビジョンが行き渡っていれば、従業員1人ひとりが適切な判断をしやすくなり、組織内での認識のズレを減らせます。
また、ビジョンの浸透では、企業と従業員で目指す方向性をマッチさせることも重要です。社会情勢の変化が激しい現代社会では、市場の移り変わりも早いため、柔軟な対応が求められます。従業員全員に経営方針、事業展望が伝わっていれば、企業として統一感のある施策が講じられます。
個人のレジリエンスを高める実践的な方法
個人のレジリエンスを高めるためには、日常生活での継続的な習慣が効果的です。具体的には次のような方法があります。
・ポジティブな思考習慣:困難の中にも学びや意味を見出す練習をし、前向きな解釈力を養います。
・感情のセルフモニタリング:日記やアプリで感情を記録し、自分の反応パターンを把握します。
・適度な運動:ウォーキングやストレッチは心身のストレスを緩和し、気分を安定させます。
・十分な睡眠と規則正しい生活:心身の回復力を高め、判断力や集中力の維持に役立ちま
す。
・信頼できる人とのつながり:相談や共感の機会を通じて、孤立感を防ぎ心理的支えを得られます。
・マインドフルネスの実践:瞑想などにより心の安定を保ち、感情のコントロール力を強化します。
これらを日常的に意識して取り入れることで、困難にしなやかに対応できる力が養われるでしょう。列挙した方法以外にもさまざまな実践方法がありますから、ライフスタイルも踏まえて最適な方法を発見することが大切です。
ポジティブ思考の習慣化
ポジティブ思考を習慣化することは、レジリエンスを高める有効な方法です。まず効果的なのが「感謝日記」です。毎日感謝できる出来事を3つ書き出すことで、日常のポジティブな側面に目を向ける習慣が身につきます。次に「リフレーミング」は、否定的な出来事を別の視点から捉え直す技法で、「失敗した」ではなく「学びの機会だった」といった肯定的な解釈を促すものです。また「肯定的自己対話」は、自分自身に対して前向きな言葉をかけることで、不安や自己否定の感情を和らげ、自己効力感を高めます。これらの方法を継続することで、困難に対しても柔軟かつ前向きに向き合える心の土台が築けます。
ソーシャルサポートネットワークの構築
ソーシャルサポートネットワークの構築は、個人のレジリエンスを高めるうえで重要な要素です。人とのつながりは、精神的な安心感や孤立の防止に大きく貢献し、困難な状況でも前向きに対応する力を支えてくれます。信頼できる友人や家族、同僚との関係を築くことで、共感や助言を得やすくなり、ストレスの緩和や視野の広がりにつながるでしょう。このような効果的なネットワークをつくるには、日頃から感謝や気配りを忘れず、相手との信頼関係を育むことが大切です。また自分から積極的に声をかけ、困ったときに助けを求める姿勢も重要です。
ストレス対処法の習得
ストレス対処法を習得することは、レジリエンスを高めるために不可欠です。効果的な技術のひとつが「深呼吸法」で、鼻からゆっくり4秒吸い、口から6秒かけて吐くことを数回繰り返すと副交感神経が優位になり心が落ち着きます。また「マインドフルネス瞑想」は、静かな場所で姿勢を整え、呼吸に意識を向けながら5~10分間思考を流すように観察することで、思考の整理と感情の安定に効果的です。さらにウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動は、ストレスホルモンを減少させ気分の改善に役立ちます。これらの習慣を日常に取り入れることでストレスに対する耐性が高まり、困難な状況にも落ち着いて対応できる力が育まれます。
まとめ
健康経営や従業員のメンタルヘルスケアを重視する企業が増加しているなかで、レジリエンスへの注目度が高まっています。 レジリエンスとは、困難を乗り越え回復する力を意味する言葉で、強化することで、企業と従業員双方にメリットがあります。 一方で、正しい理解のないままレジリエンス対策を進めてしまうと、根性や気合いといった精神論に陥ってしまうリスクも懸念されます。
「レジリエンスを高めたいけれど、何から始めればいいのか分からない」といった場合は、スマホでも受講ができる、「レジリエンス講座」がおすすめです。基礎学習から、実践的なスキルが身につくワークも多数ご用意していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。