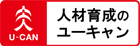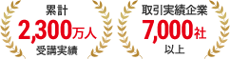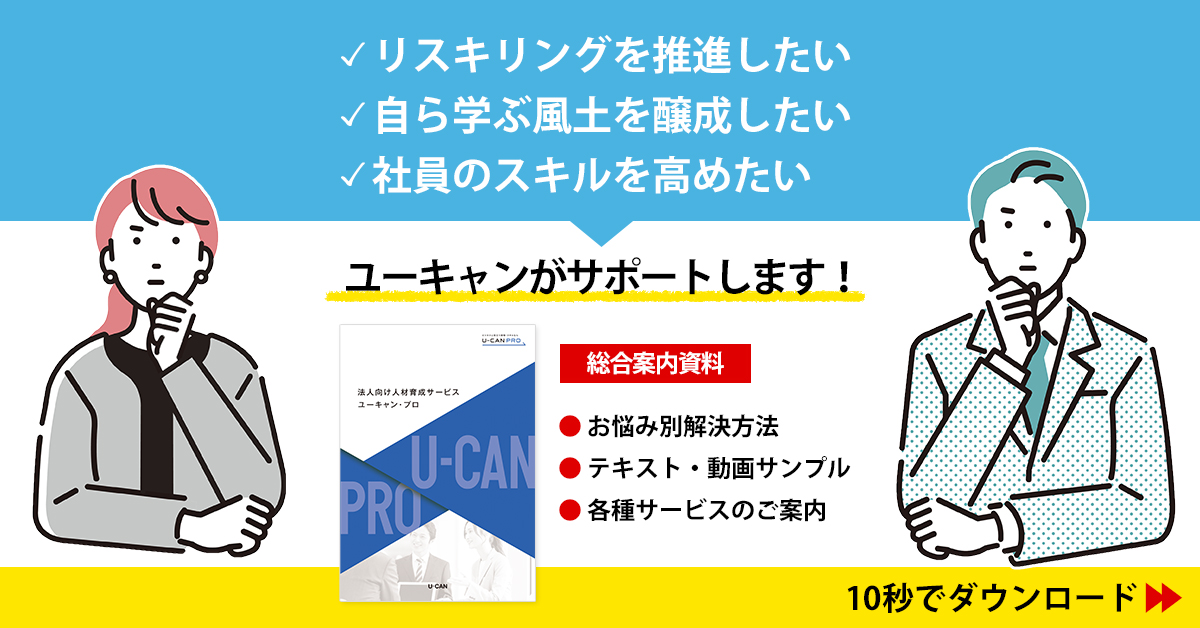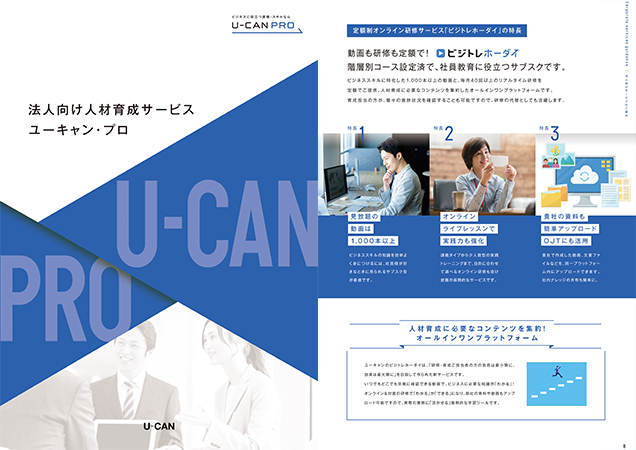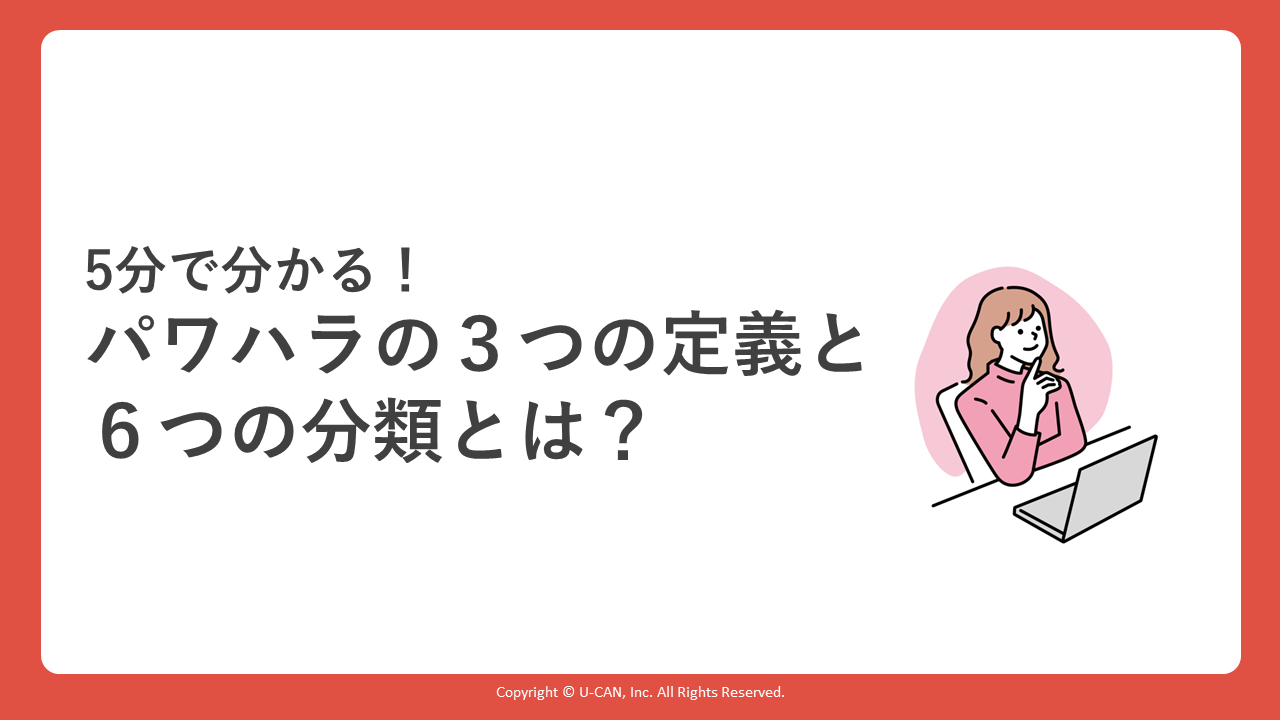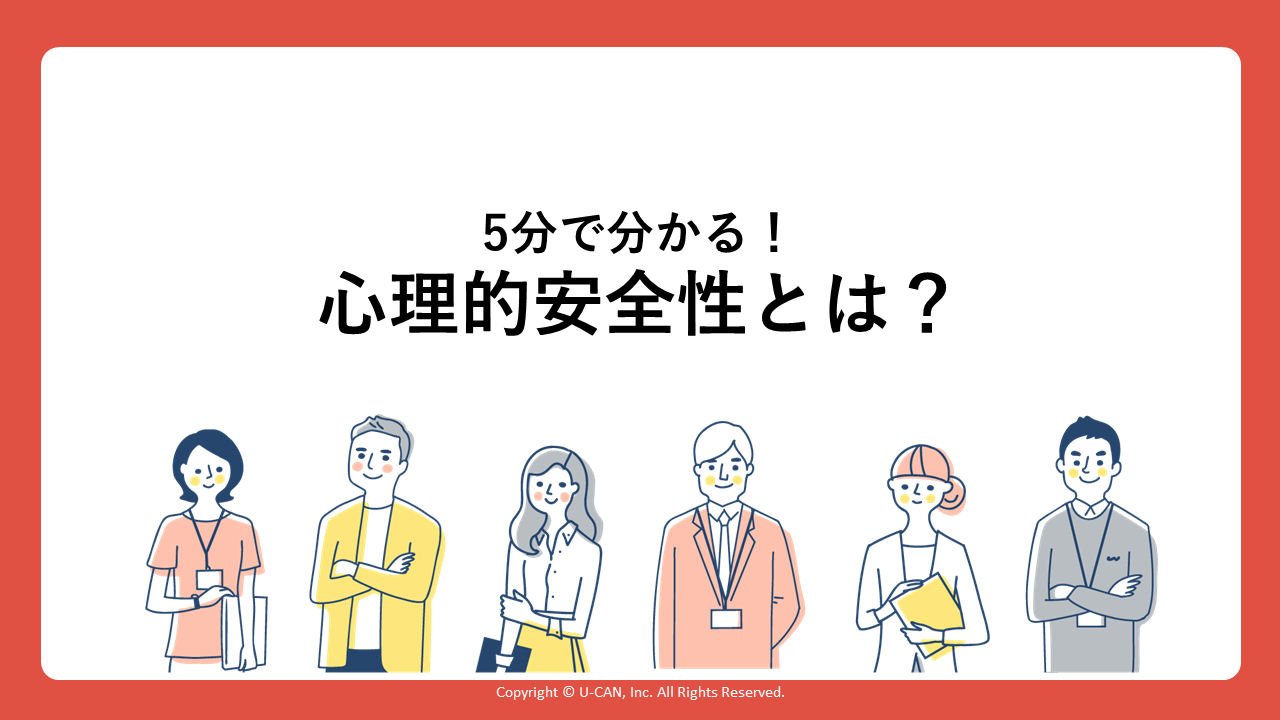モラハラとはなにか?
モラハラとは「モラルハラスメント」の略称です。モラルとは道徳や倫理を意味し、ハラスメントは嫌がらせを意味します。 モラハラは、殴る、蹴るなどの直接的な暴力行為を伴いませんが、人の尊厳を傷つけて精神的に追い詰めるような行為です。モラハラの例は職場における意図的な無視行為や暴言、理由なく不機嫌な態度をとる行為などです。モラハラが生じていると業務が適切に進められず、企業における生産性低下や離職の原因となります。
モラルハラスメントの正確な定義と特徴
モラルハラスメント(モラハラ)は、フランスの精神科医マリー=フランス・イルゴイエンヌによって提唱された概念で「言葉や態度による継続的な精神的暴力」と定義されます。学術的には、身体的暴力を伴わず、被害者の尊厳や自尊心を損なう言動が繰り返されることにより、精神的なダメージを与える行為とされます。一般的には無視、皮肉、否定的な言動、過小評価、孤立化などが代表的な手段です。その特徴として、行為が言葉や態度にとどまるため外傷が残らず、加害者が「冗談」「指導」などと偽装することも多く、被害の立証が非常に困難な点があります。また行為が長期的かつ断片的に行われることが多く、被害者自身がモラハラであると気づきにくい点も問題です。目に見えにくく周囲の理解も得られにくいため、深刻な心理的影響を受けるケースが少なくありません。
職場におけるモラハラとパワハラの違い
パワハラ(パワーハラスメント)とは、上司や先輩などの優位な地位にある人物が、立場を利用して部下や後輩に対して暴言・暴力・威圧行為・無理な要求などを行うことです。日本においてパワハラは以前から社会問題となっており、肉体的・精神的・社会的苦痛により自殺に追い込まれたケースもあります。
一方、モラハラ(モラルハラスメント)は社会通念に照らし、一般的な倫理観(モラル)に反する言動や行動を取り、強い精神的苦痛を与える行為を指します。モラハラは会社の上下関係だけでなく、企業と顧客、家族間でも起こる点が特徴です。顧客が企業に対して過剰な要求をしたり、不当なクレームを入れたりするカスハラ(カスタマーハラスメント)もモラハラの一種です。パワハラの場合、悪化すると社員のプライバシーを侵害することもあり、人としての尊厳を傷つけることにもなりえます。そのため、パワハラに対する社会的な目は厳しくなっており、企業として必要な対策を講じていくことが重要です。また、モラハラはハラスメント行為する側にハラスメントの自覚がなく、善意のつもりで行っている点が問題です。企業としてハラスメント行為に対応するには、パワハラ・モラハラについて正しい知識を社員に学んでもらう必要があるでしょう。
関連記事:ハラスメントとは?意味・定義・種類・職場での対策を解説
モラハラが起こりやすい環境と状況
モラルハラスメントは、権力関係が不均衡な職場で起こりやすい傾向があります。たとえば上司が部下に対し人格を否定する発言を繰り返すケースでは、立場の弱い部下は反論しづらく、被害が継続しやすくなります。またコミュニケーションが不足している環境では誤解や不信感が生じやすく、それがモラハラにつながることもあるため注意が必要です。さらに組織全体が過度なストレスにさらされている場合、感情的な言動がエスカレートし、攻撃的な態度や言葉で相手を傷つける行為が常態化しやすくなります。これらの要因が重なることで、モラハラが発生・拡大しやすい状況が生まれます。
モラハラを行う加害者の心理的特徴
モラルハラスメントを行う加害者には、いくつかの共通した心理的特徴が見られます。まず他人を支配したいという強い欲求があり、自分の思い通りに人を動かすことで安心感を得ようとします。次に自己肯定感が低く、自分の価値を実感できないという点も重大な特徴です。主観的な価値や自尊心が低いため、他人を貶めることで優位に立とうとする傾向があります。またストレス耐性が弱く、感情をうまくコントロールできないことから、いら立ちや不安を他人にぶつける形で解消しようとします。これらの心理は無意識に働くことも多く、加害者自身がモラハラを行っている自覚を持たない場合もある点を知っておくとよいでしょう。
職場におけるモラハラの具体例
職場で起こりうるモラハラの具体例について、5つのパターンを紹介します。
人格を攻撃する
他者への人格攻撃は、モラハラで多い事例です。人格攻撃とは、相手の能力や人間性、交友関係などを否定したり、侮辱したりする行為のことです。人格攻撃の例には次のようなものがあります。
・勉強が苦手な子供に対し「こんなこともできないなんてダメね」「〇〇ちゃんはできるのにこの子は劣っている」などの言葉を浴びせる
・社員の交友関係について「あんな奴と友達だなんて、きっとバカなんだろう」「人を見る目がなくて可哀そう」などの批判を行う
・仕事での失敗を過剰に責め立て「仕事ができないなら辞めてしまえ」「役立たず」などの否定的な言葉を放つ
無視する
話しかけられても無視したり、連絡が来ても返信しなかったりすることもモラハラに該当します。
無視することで業務の進行に支障を来たすこともあり、組織の生産性にも関わる問題です。
・特定の社員だけ挨拶や声をかけられても無視する
・部下や同僚からメールなどで連絡を受けているにも関わらず、意図的に返信しない、または適当な理由をつけて無視する
嫌がらせをする
その日の気分や個人的な感情で、社員や部下に対して嫌がらせを行うこともモラハラです。
また、社員の仕事を邪魔して意図的に進行を妨害する行為も、嫌がらせに当たります。
・機嫌が悪いからと部下を罵る、机やゴミ箱などを強く叩く
・仕事中の同僚に対して執拗に声かけ、邪魔をして集中を乱す
・上司に嘘の報告をして、同僚の評判を落とそうとする
プライバシーを侵害する
仕事に関係のない社員のプライベートに干渉し、私生活について知ろうとしたり、関係性を持とうとしたりする行為もモラハラに当たることがあります。特に性的な内容を含む言動・行為はセクハラに該当し、場合によっては犯罪になる可能性もある点に注意が必要です。
・同僚に仕事と関係ない私的な内容を聞き出そうとする
・部下または同僚の人間関係や家族関係を聞き出そうとする
・社員の住所と電話番号を調べ、電話で連絡したり会おうとしたりする
仲間外れにする
特定の社員のみをグループから仲間外れにする行為も、モラハラに該当する可能性が高いです。
・グループチャットで特定の社員だけを仲間外れにした
・宴会や懇親会で特定の社員だけに予定を伝えなかった
・同僚の足を引っ張るために業務上必要な連絡をあえてしなかった
職場でモラハラが発生・放置することのリスク
職場でモラハラが発生したり、それを放置したりしている場合、企業にはさまざまなリスクが生じます。モラハラは退職者の増加や職場環境配慮義務違反、企業のイメージダウンなどにつながり、業績低下の原因となりうるものです。それぞれについて解説します。
退職者の増加につながる
モラハラを放置していると退職者の増加につながります。モラハラによって精神的な苦痛を継続的に受けている従業員は、心身の健康を損ない離職を考えるようになるでしょう。また、モラハラは直接的な被害者だけでなく、周囲の従業員にも悪影響を与えます。職場の雰囲気の悪さを理由に転職する従業員が増えれば、企業は人手不足に陥るかもしれません。優秀な人材ほど次の就職先も早く見つかるため、退職する可能性が高いといえます。
組織全体の生産性低下と業績悪化
モラルハラスメントが職場で発生すると、まずチームワークが崩れます。被害者が孤立し、周囲も加害者を恐れて自由に意見を言えなくなるため、協力や情報共有が困難になるためです。また職場全体の雰囲気が悪化し、不安や不信感が広がることで、従業員のモチベーションも低下します。これにより集中力や創造性が損なわれ、業務効率が著しく下がります。結果としてミスや遅延が増え、顧客対応の質も低下し、最終的には組織全体の生産性が落ち、業績悪化につながる可能性が高いです。モラハラは個人の問題にとどまらず、組織全体に深刻な悪影響を及ぼすリスクをはらんでいます。
被害者の心身への深刻な影響
モラルハラスメントの被害者は、継続的な精神的圧力により深刻な心身の影響を受けます。うつ病や不安障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症することがあり、日常生活や社会生活に大きな支障をきたします。さらに不眠や食欲不振、胃痛、下痢などの身体症状も現れ慢性化することがあり、身体的な影響も計り知れません。こうした影響は長期に及ぶことが多く、加害者からの否定的な言動が積み重なることで、被害者の自己肯定感が著しく低下し、自分に価値がないと感じてしまいます。結果として、回復に長い時間を要する深刻な状態に陥ることも少なくありません。
職場環境配慮義務違反になる
企業がモラハラに対して適切な対処をせず放置していると、職場環境配慮義務違反となる恐れがあります。職場環境配慮義務とは、事業者が従業員に対して快適な職場環境を提供する義務です。企業が職場環境配慮義務を果たさず、従業員が病気や怪我、精神疾患になると、訴訟によって法的な責任を問われ、損害賠償請求を受ける可能性があります。
企業のイメージダウンにつながる
モラハラが発生した事実が公に知られると、企業のイメージダウンにつながります。 モラハラが訴訟問題に発展すれば新聞やニュースで報じられ、多くの人に知られることになるでしょう。モラハラが横行し、放置している企業だと見なされると、職場の問題改善に取り組まない印象を持たれるかもしれません。イメージダウンによって売り上げが落ち業績が低下したり、採用活動でも人材が集まりにくくなったりと、モラハラは企業の活動に悪影響を及ぼします。
職場でのモラハラの対処法・改善策
企業のモラハラ解消のためには、人事担当者の適切な対処が重要です。人事担当者が知っておきたいモラハラの対処法・改善策をいくつか紹介します。
講座や研修で正しい知識を身につける
職場におけるモラハラ解消のためには、まずは人事担当者が正しい知識を身につける必要があります。また、現場の従業員がそれぞれモラハラについての知識を得れば、モラハラが起こりにくく、発生した場合でも適切に対処できれば被害を抑えやすいでしょう。モラハラを含む職場の人間関係については、外部の専門機関に講座や研修を依頼するのがおすすめです。ハラスメントに関する正しい知識、最新の内容が学べ、実用的なノウハウが身につきます。
例えば ハラスメント防止コミュニケーション講座 では、パワハラの判断基準やパワハラとならない指導方法、職場の雰囲気作りの方法などが学べます。
関連記事:ハラスメント研修を行う目的とその内容とは?
事実確認を行い証拠を集める
社内でモラハラが生じている可能性があるなら、断片的な情報から状況を判断してしまわず、しっかりとした事実確認が重要です。モラハラの判断には証拠が必要なので、被害者や周囲の従業員から、メールや電話のやりとりなどの証拠資料を提出してもらいましょう。証拠資料や現場へのヒアリングなどを合わせて状況を把握し、判断する必要があります。事実確認した結果モラハラと判断されるなら、加害者に対する直接の指導や、再発防止のための対策が必要です。
被害者と加害者と距離を置くよう工夫する
事実確認によってモラハラが起きていると判断された場合は、被害者と加害者と距離を置くよう工夫しましょう。被害者が業務を続けパフォーマンスを高めるためには、加害者から離れる必要があります。例えば配置転換によって被害者と加害者の職場を分ければ、被害者が安心して働き続けられます。配置転換はパワハラの当事者だけでなく、周囲の従業員にも影響があるため、協力してもらえるよう理解を得ることが重要です。
相談窓口を設置する
モラハラを早期発見し適切に対策するには、社内での相談窓口の設置がおすすめです。 誰もが相談しやすい職場環境を整えれば、被害を最小限に抑えやすくなります。相談窓口の設置は社内で実施する他、外部の専門機関への依頼も可能です。モラハラの相談はセンシティブな内容なので、社内の人には知られたくないと感じる従業員も少なくありません。専門機関による相談窓口なら、より被害者が利用しやすくなるでしょう。
モラハラが起きない職場をつくるための予防策
モラハラが起きない職場をつくるには、会社として予防策を講じる必要があります。
効果的な4つの施策を紹介します。
ハラスメントの定義と対応指針の周知徹底
ハラスメントを防止するには、社員に対して定義と対応指針を周知徹底することが重要です。どのような行為がハラスメントに当たるのか、自分のどんな行動がハラスメントになるか理解してもらうことで啓発活動になります。加えて、会社としてハラスメントに厳しく対応する姿勢を示すため、対応指針も明確化して理解してもらうべきです。社内報や就業規則にもハラスメントへの対応指針を明記し、組織全体で取り組んでいくことを伝えましょう。
またハラスメント行為が実際にあった場合も想定し、どのような報告・連絡経路を辿ればよいか、重大性に分けてハラスメントに対する罰則規定も設けると効果的です。
ハラスメント相談窓口の設置
ハラスメント行為が発生した場合や発生が疑われる場合に、社員が相談しやすいように窓口を設置しておくのも重要な防止策です。社内での情報共有と連携した対応を重視するなら社内窓口、専門家による対応を求めるなら社外窓口がよいでしょう。社員にとって、ハラスメント相談窓口があるかないかで心理的な安心感は大きく変わります。相談窓口がなければ、ハラスメント行為をしている上司に相談するしかなくなり、組織の上層部に正しく情報が伝わらない可能性があります。そのため、他の部署とは利害の関係性がなく、第三者の視点で相談を受け付ける窓口の存在は重要です。担当する社員にはハラスメント研修を徹底して行い、正しい対応の検討やマニュアルの作成などをしてもらいましょう。
加害者と被害者の距離を物理的に離す
ハラスメント行為が実際に起こってしまった場合は、加害者と被害者のどちらかを別の部門に移すなど、物理的に距離を取ってもらう配慮も必要です。そのまま同じ部署に置いておくと、加害者が報復に走る危険性もあるため、早期に手を打つことが大切です。ただしハラスメント行為を理由に加害者を孤立させると、逆にハラスメントの被害者として問題になる可能性もある点に注意してください。
健全なコミュニケーション文化の構築
モラハラを防ぐには、健全なコミュニケーション文化の構築が不可欠です。まず誰もが意見を言いやすい雰囲気をつくるために、心理的安全性を重視したオープンな対話を促進する仕組みが必要です。その一環として、上司と部下が定期的に1on1ミーティングを行い、業務や悩みを率直に話せる場を設けることで早期に問題を把握できます。また相手の行動や成果を具体的に伝えるフィードバック文化を根付かせることで、批判ではなく成長を促す関係が築けます。これらの取り組みを継続することで、互いを尊重し合う職場風土が形成され、モラハラの芽を事前に摘むことが可能です。
経営層からの明確なメッセージ発信
モラハラを防止するには、経営層からの明確なメッセージ発信が不可欠です。まずトップ自らがハラスメント撲滅を明言し、組織として不容認の姿勢を示すことが、全社員への強いシグナルとなります。この方針を経営理念や行動規範に組み込み、日々の業務に根付かせることで組織全体の意識改革が進みます。また社内報や朝礼、研修などの機会を通じて、定期的にそのメッセージを繰り返し発信することで、形骸化を防ぎ、継続的な取り組みであることを示せるでしょう。経営層の積極的な関与が予防策としての実効性を高め、安心して働ける職場づくりにつながります。
ハラスメント研修を実施する
ハラスメントが起きない職場をつくるには、社員にハラスメントへの理解を深めてもらうことも不可欠です。ハラスメントと一言で表しても、セクハラ・パワハラ・モラハラ・マタハラなどさまざま種類があります。それぞれのハラスメントがどういうものか、どんなときに起きやすいのか、どんな言葉や講堂がハラスメントになるか知ることは重要です。研修を通してハラスメントへの理解が深まれば、それまでは当たり前に行われてきた行為も、ハラスメントとして再認識することもあるでしょう。ハラスメント行為への理解を深めることで、社員一人ひとりが注意をもって発言・行動するようになり、働きやすい職場がつくられます。
まとめ
モラハラは企業にとって多くの問題を引き起こします。被害者の業務効率が低下し、退職につながるだけでなく、企業全体の生産性も下げる原因となります。職場におけるハラスメントのなかでも、モラハラは特に発生しやすい問題です。 モラハラの解消には対策の実施とともに、モラハラに対する従業員の意識向上が重要です。
ユーキャンではモラハラを含むハラスメント防止に特化した講座を提供しています。法人取引実績5,000社以上と豊富な実績を誇っており、丁寧なヒアリングで課題を抽出し、法人ごとにフィットする提案を行います。企業のモラハラ対策として利用を検討してみてください。