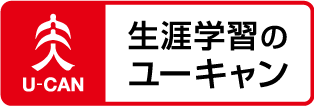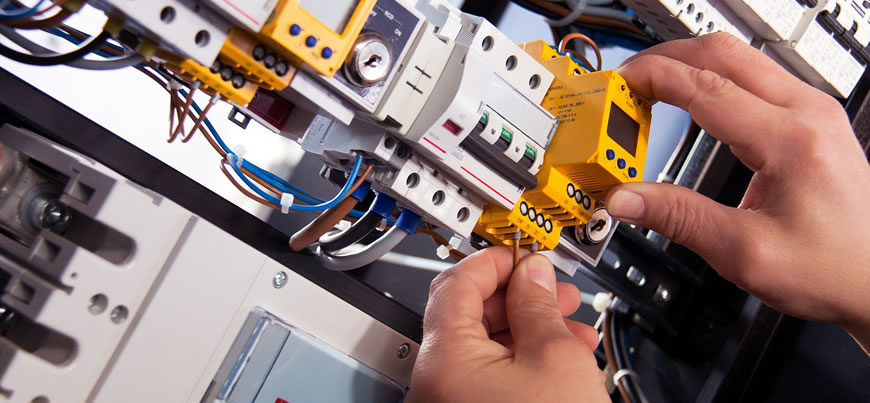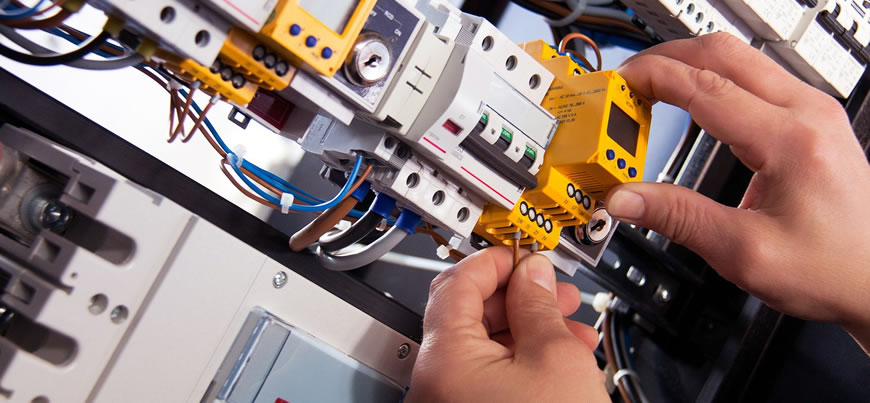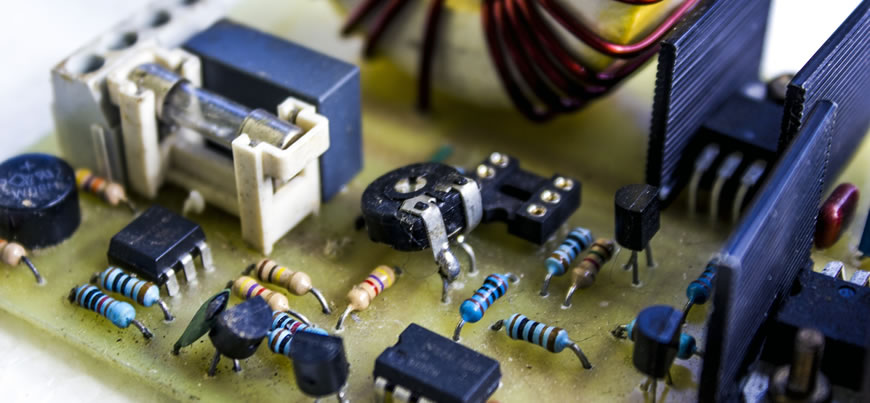- 第二種電気工事士講座 もっと詳しく
第一種・第二種電気工事士の難易度・合格率を解説

- 更新日:2025/10/10
電気工事士とは国家資格の1つで、電気を安全に快適に使うための工事や管理を行う専門技術者です。この記事では、電気工事士の資格取得を検討している人に向けて、第一種・第二種電気工事士試験の難易度を解説します。試験の合格率・概要・効率的な勉強法なども紹介するので、参考にしてください。
このページを簡潔にまとめると・・・
- 電気工事士は、国家資格の中では難易度が比較的低い。電気主任技術者の方がはるかに難易度が高い。
- 第一種電気工事士試験の合格率は、学科試験は40%前後、技能試験は、近年上昇傾向にあり、60%前後。
- 第二種電気工事士試験の合格率は、学科試験は60%前後、技能試験は70%前後と高いです。
- 学科試験の方が難易度が高く、暗記問題が中心となるため、しっかりと勉強しておく必要がある。
- ユーキャンの第二種電気工事士講座はこちら
電気工事士試験の難易度
電気工事士試験は、国家資格の中では難易度が比較的低いです。同じく電気に関する国家資格である電気主任技術者の試験は、取得に3年以上かかることもあると言われる難易度の高い資格試験です。電気工事士の資格試験には第一種と第二種の2種類があり、それぞれ学科試験と技能試験が設けられています。
第一種電気工事士の方が難易度が高い
電気工事士試験は、第二種よりも第一種の方が難易度は高くなっています。第二種は、電気工事関係の人だけでなく高校生や専門学生、キャリアアップを目指す人など幅広い層が受験します。第一種の受験者は、電気工事従事者が中心です。第一種の資格取得者の方が、行える仕事の範囲が広いため、試験範囲も広くなり、難易度が高めとなっています。
学科試験の方が技能試験より難易度が高い
技能試験は、事前に候補問題が公表されるため、前もって練習することが可能です。学科試験が免除されることもあり、その場合、技能に集中した勉強ができます。候補問題が公表されますが、事前に練習していない場合は、当然、難易度は高くなります。学科試験は、暗記問題が中心となるため、試験範囲をしっかりと勉強しておく必要があります。
第一種電気工事士の仕事と将来性
第一種電気工事士は、ビル・工場などの大規模な現場での工事に対応できます。大型施設の配線・大型機材の制御回線の管理など、幅広い業務が行えます。電気工事のスペシャリストであり、仕事がなくなる可能性が低く、多くの企業で重宝されるため、転職にも有利です。
第二種電気工事士の仕事と将来性
第二種電気工事士は、住宅・マンション・小規模のオフィスなどの電気工事に対応できます。
ビルのメンテナンスや設備管理にも欠かせない資格であり、リフォームや建物の改築など、活躍の場は多いです。日常生活に関わる職種であるため、需要がなくなることはありません。
第一種電気工事士試験の合格率
第一種電気工事士試験の合格率や出題科目について解説します。
合格率の推移
第一種電気工事士試験の合格率は、学科試験は40%前後、技能試験は、近年上昇傾向にあり、60%前後です。
第一種電気工事士試験の受験者数・合格率
| 合格率(学科) | 受験者数(学科) | 合格率(技能) | 受験者数(技能) | |
|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 50.3% | 39,013人 | 61.6% | 23,677人 |
| 平成29年度 | 47.0% | 38,427人 | 63.5% | 24,188人 |
| 平成30年度 | 40.4% | 36,048人 | 62.7% | 19,815人 |
| 令和元年度 | 54.1% | 37,610人 | 64.7% | 23,816人 |
| 令和2年度 | 52.0% | 30,520人 | 64.1% | 21,162人 |
| 令和3年度 | 53.5% | 40,244人 | 67.0% | 25,751人 |
| 令和4年度 | 58.2% | 37,247人 | 62.7% | 26,578人 |
| 令和5年度 | 61.6% | 33,035人 | 60.5% | 26,143人 |
| 令和6年度 | 56.7% | 35,320人 | 59.9% | 28,372人 |
試験概要
第一種電気工事士試験は年2回実施され、試験の実施時期は、例年、次の通りです。
・上期試験(学科試験:CBT方式4月上旬~5月上旬、筆記方式なし/技能試験:7月上旬)
・下期試験(学科試験:CBT方式9月上旬~中旬、筆記方式10月上旬/技能試験:11月下旬)
受験手数料はインターネットによる申込の場合10,900円、書面(受験申込書)での申込の場合11,300円となります。
第二種電気工事士試験の合格率
第二種電気工事士試験の合格率や出題科目について解説します。
合格率の推移
第二種電気工事士試験の合格率は平成9年度あたりから上昇しており、近年では学科試験は60%前後、技能試験は70%前後と高いです。
第二種電気工事士試験の受験者数・合格率
| 合格率(学科) | 受験者数(学科) | 合格率(技能) | 受験者数(技能) | |
|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 58.6% | 114,528人 | 73.3% | 84,805人 |
| 平成29年度 | 59.0% | 112,379人 | 68.8% | 81,356人 |
| 平成30年度 | 55.4% | 123,279人 | 67.4% | 95,398人 |
| 令和元年度 | 65.9% | 122,266人 | 65.2% | 100,379人 |
| 令和2年度 | 62.1% | 104,883人 | 72.4% | 72,997人 |
| 令和3年度 | 59.1% | 156,553人 | 72.8% | 116,276人 |
| 令和4年度 | 55.9% | 145,088人 | 72.5% | 97,659人 |
| 令和5年度 | 59.4% | 134,025人 | 71.0% | 95,337人 |
| 令和6年度 | 58.1% | 132,462人 | 70.3% | 94,238人 |
試験概要
第二種電気工事士試験は年2回実施され、試験の実施時期は、例年、次の通りです。
・上期試験(学科試験:CBT方式4月下旬~5月中旬、筆記方式5月下旬/技能試験:7月下旬)
・下期試験(学科試験:CBT方式9月下旬~10月中旬、筆記方式10月下旬/技能試験:12月下旬)
受験手数料はインターネットによる申込の場合9,300円、書面(受験申込書)での申込の場合9,600円となります。
電気工事士試験のための勉強方法
電気工事士試験のための勉強方法について解説します。
- 参考書・過去問題集を使って繰り返し勉強する
- 工具や材料をそろえて技能試験対策をする
学科試験対策としては、第一種・第二種共に、参考書や過去問題集を使って繰り返し勉強すること、また技能試験に関しては、練習を積み重ねることが重要です。実際に試験で使う工具や材料をそろえて、公表されている候補問題を完成させる作業を繰り返しましょう。
まとめ
電気工事士試験は、第一種と第二種があり、比較的難易度の低い国家資格といえます。学科試験は暗記が中心となり、技能試験は事前に候補問題が公表されるため、試験のための勉強がしやすい資格試験です。
ユーキャンの第二種電気工事士講座は、過去の出題実績に基づいて作られたテキストで、学科試験の重要ポイントを効率的に勉強できます。また、技能試験対策として練習用の材料だけでなく、解説のDVDもセットで利用できます。電気工事士の取得を目指すなら、ぜひ受講を検討してみてください。

- この記事の監修者は生涯学習のユーキャン
-
1954年設立。資格・実用・趣味という3つのカテゴリで多岐に渡る約150講座を展開する通信教育のパイオニア。気軽に始められる学びの手段として、多くの受講生から高い評価を受け、毎年多数の合格者を輩出しています。
近年はウェブ学習支援ツールを拡充し、紙の教材だけでは実現できない受講生サポートが可能に。通信教育の新しい未来を切り拓いていきます。
よくある質問
- 電気工事士の年収は?
-
電気工事士の年収は400万~500万円です。ただし、現場の規模・経験・資格などで大きく変わり、中には年収600万円以上の求人もあります。
- 第一種電気工事士と第二種電気工事士の違いは?
-
第一種電気工事士と第二種電気工事士では、工事できる作業範囲や試験難易度が異なります。第一種電気工事士のほうが扱える電圧の幅が広く、工場やビルなどの大規模な現場にも対応可能です。
第二種電気工事士講座

ユーキャンの第二種電気工事士講座は、過去10年間で4,400名以上の合格者を輩出。
基本のキからていねいに解説したわかりやすいテキストに、動画講義や過去問などの副教材も充実。技能試験の練習材料もセットで、作った施工物も添削指導します。知識だけでなく技術力までしっかりと身につくので、十分に対策すれば、はじめてでも一発合格を狙えます!
第二種電気工事士とは、住宅や店舗など600V以下で受電する設備の新築・増改築時に、配線図どおりに屋内配線、コンセントの設置、アース施工などを行う専門技術者のことです。これらの作業で不備があると、感電や火災など、事故の原因となる危険があるため、有資格者でないと作業ができません。そのため、ニーズが高く、好待遇で働ける、安定した収入を期待できるといったメリットが考えられます。履歴書に堂々と書ける国家資格で、就職・転職も有利!
ユーキャンの「第二種電気工事士」講座では、学科試験から技能試験までしっかり対策! イラストや写真が豊富なテキストで学科試験の重要ポイントを習得できます。また、技能試験対策のための練習用材料と映像でポイントをつかむDVD教材をセットでお届けします。さらに、五十音順の「用語集」、テキストに出てきた順番で収録した「公式集」、数学が苦手な方のための「基礎数学」、以上の3つを一冊にまとめた副教材は復習や直前対策にも便利です。