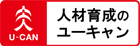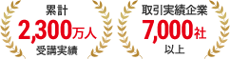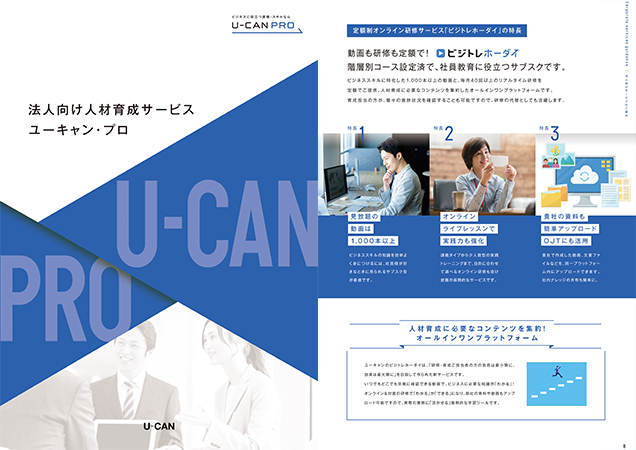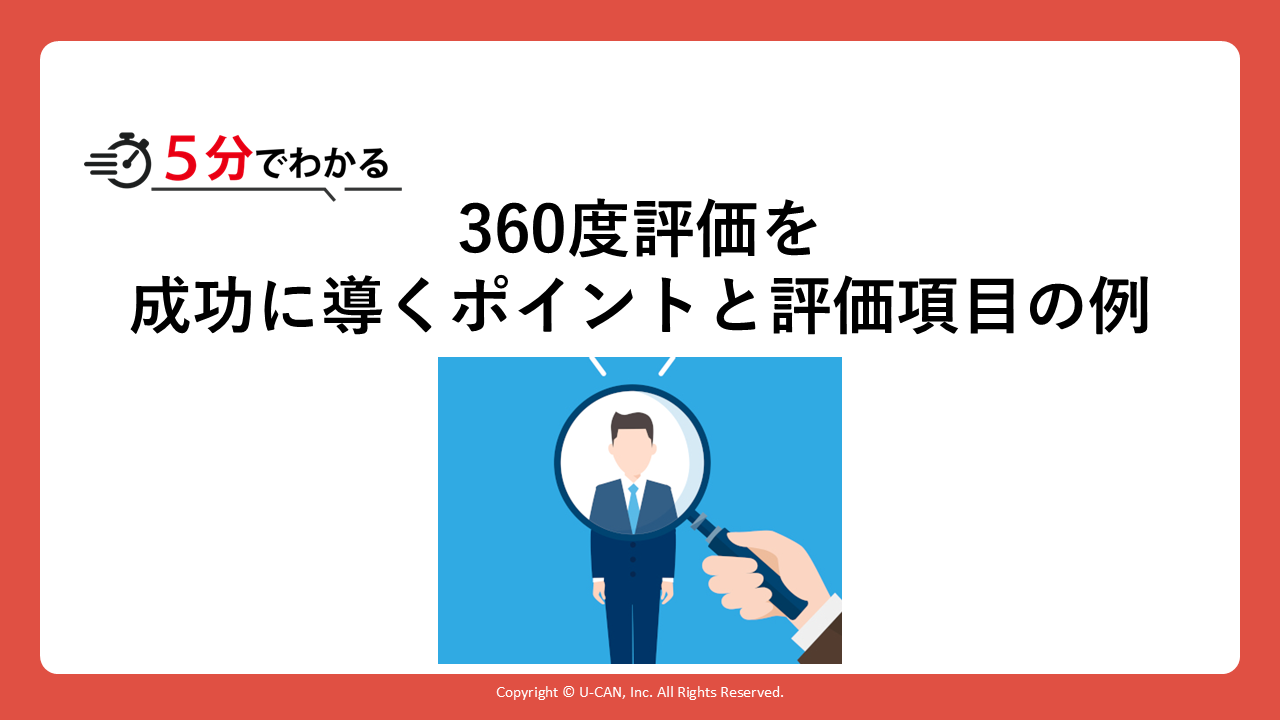フィードバック(feedback)とは何か
フィードバックとは、 反応や結果をもとに再度調整を加えることをいいます。 ビジネスにおけるフィードバックでは、対象者の思考や言動、行動などを評価し、よりよい改善で軌道修正を図ります。 フィードバックは上司から部下に実施するのが一般的ですが、必要に応じて同僚間などで行う場合もあるでしょう。フィードバックは、システム用語である「フィードバック制御」からきています。エアコン機能のように、出力の目標と結果の値の差を埋めるためにはたらきかけるシステムを表現しています。直訳すると「帰還」を表す言葉です。
フィードバックの適切なタイミング
フィードバックの適切なタイミングは、主に以下のとおりです。
・対象者の結果が現れ始めたとき
・対象者に余裕があるとき
・フィードバックをする時間が確保できるとき
フィードバックは、時間の経過とともに効果が薄れます。あまりにも遅いフィードバックはいまさら感が高まり、対象者から不信感や反感を抱かれる可能性があります。そのため 対象者の結果が現れ始めた比較的早い段階で、フィードバックを実施しましょう。また対象者が精神的に追い詰められている状態でフィードバックを実施しても、効果が期待できません。対象者の受け入れ態勢が整ってから、実施するのが望ましいでしょう。ていねいな評価をするために、十分な時間が確保できるときを狙ってフィードバックを実施するのがおすすめです。
フィードバックのビジネスでの使い方
ビジネスにおけるフィードバックの傾向は、主に以下の2つに分かれます。
・ポジティブフィードバック
・ネガティブフィードバック
ポジティブフィードバックとは、対象者の自信を引き出し、積極的に仕事に取り組める姿勢を高めるためのものです。対象者の仕事への姿勢や態度などへの感謝の気持ちを伝えながら、業務における利点を具体的に振り返ります。対してネガティブなフィードバックは、好ましくない行動や態度などを評価します。あえて好ましくない点を振り返り、対象者の今後の成長につなげます。ネガティブフィードバックは評価者の伝え方や態度次第で、伝わり方に変動が見られるでしょう。対象者のなかには否定されたと感じる人もいるため、ポジティブフィードバックとネガティブフィードバックの2つの評価を交えて説明するのがおすすめです。
フィードバックの目的
フィードバックには、主に以下の目的があります。
・人材育成を図るため
・対象者のモチベーションを向上させるため
・個人やチームの目標を達成するため
それぞれの目的について、詳しく解説します。
人材育成を図るため
フィードバックは、対象者の成長のために欠かせない取り組みです。フィードバックの実施は、部下が対象者について知ることができます。業務における対象者の課題を把握することで今後の業務に反映させられるでしょう。また対象者が仕事における自身の問題点や改善点に気がつければ、より効率のよい成長が期待できます。企業によっては数値的な成果よりも対象者の成長を重視するところもあるほどで、これは人材育成で得られるものが大きいことを示しています。
対象者のモチベーションを向上させるため
対象者のモチベーションを上げるのも、フィードバックの目的の1つです。フィードバックでは、問題点を見直して解決策を見出します。対象者だけでは難しいと感じる問題は、評価者が一緒に対策方法を練ることで思考を転換するきっかけとなるでしょう。「できるかもしれない」というポジティブな思考は業務への前向きな姿勢につながるだけでなく、対象者の自己効力感を高めるでしょう。定期的なフィードバックにより対象者の自己効力感が高まれば、業務へのモチベーションの向上が期待できます。
個人やチームの目標を達成するため
こまめなフィードバックは、結果的に対象者の目標達成につながります。方向性を見失った場合はその都度軌道修正を図ることで、遠回りせずに目標に近づくことができるでしょう。最適な取り組み方法が分かれば、効率的な目標の達成が期待できます。またフィードバックは、個人のみならずチームの目標達成にも効果的です。 定期的なフィードバックの実施は、チーム全体の業務の見直しや方向性の改善などができます。 1人で達成するのは難しい目標も、チームが一丸となることで効率的な達成につながるでしょう。対象者やチームの目標達成には、定期的なフィードバックが欠かせません。
人材教育にフィードバックを取り入れるメリット
人材育成にフィードバックを取り入れるメリットは、主に以下のとおりです。
・対象者の仕事への対応力が高まる
・対象者の仕事の質が上がる
・対象者のモチベーションが向上する
評価者が適切なフィードバックを実施することで、困難な状況に陥っても対処方法や解決方法が分かり、適切な対応ができるでしょう。見直すべき点が明確になるため、進む方向が定まり大きな成長にもつながります。仕事の質の向上でポジティブな思考や成功体験を重ねられるため、対象者のモチベーションの向上が期待できるでしょう。
人事評価においてフィードバック面談が重要な理由
人事評価においてフィードバック面談が重要といわれる理由には、対象者と評価者のあいだで築かれる信頼関係があります。フィードバックでは、対象者と評価者同士でコミュニケーションをとるのが特徴です。定期的なフィードバックで会話する時間が増えたり顔を合わせたりする機会が増えると、少しずつ信頼関係が築かれていきます。評価者が対象者へ熱意あるフィードバックを実施すれば、対象者は「自分のことを真剣に考えてくれている」と感じ、期待に答えたい、もっと成長したいという気持ちが高まるでしょう。フィードバック面談は、対象者の成長はもちろん両者の信頼関係を構築するうえで欠かせません。
フィードバックとその他の言葉の違い
フィードバックは反応や結果をもとに再度調整を加えることをいいますが、なかには似た意味をもつ言葉や同じイメージをもたれやすい言葉が存在します。ここでは以下の言葉について、フィードバックとの違いを解説します。
・フィードフォワード
・レビュー
・チェックバック
フィードバックとフィードフォワードの違いとは
フィードバックとフィードフォワードの違いは、評価対象の時期です。フィードバックは過去の時点について評価を実施するのに対し、フィードフォワードは将来や未来の取り組みについて話し合います。対象者が目標を達成するために何をするべきかを考え、解決策を見出します。フィードフォワードは、フィードバックとともに実施される場合も多いのが特徴です。
フィードバックとレビューの違いとは
助言をどこまでするかが、フィードバックとレビューの大きな違いです。フィードバックでは、最終目標達成に向けて解決できていない問題を満たすために評価者から助言があります。一方でレビューは、批評や評論を指します。たとえば、利用者からの率直な感想などです。レビューでは単純な感想がまとめられるため、評価者の率直な意見が伺えるでしょう。
フィードバックとチェックバックの違いとは
フィードバックとチェックバックは、使用される業界が異なります。フィードバックは、一般的にビジネスで使用される言葉です。対してチェックバックは、映像業界をはじめマーケティングやカスタマーサポートなどの分野でも用いられる用語で、確認や修正のためのフィードバックを指します。
フィードバックの要素
対象者へフィードバックを実施する際は、主に以下の要素を取り入れます。
➀フィードアップ
➁フィードバック
➂フィードフォワード
➀フィードアップ
フィードバックとは目標の提示やゴールイメージの明確化することです。フィードアップで目標や目的を明確にし目標達成に向けた進捗状況を確認すると、目指す方向の確認ができるだけでなく軌道修正が可能です。また定期的な目標の確認は、対象者自身が目標を改めて考えるきっかけにもなります。フィードアップの要素は、フィードバックを効率的に実施するために大切なものといえるでしょう。
➁フィードバック
フィードバックでは、以下の点を中心に話し合います。
・目標達成のためにとった行動
・評価されるべき点
・今後改善すべき点
対象者は、目標の達成に向けた自身の行動について振り返ります。上司が助言をする際は、対象者の現在の位置を明確に伝えましょう。過去の行いが現状に結びついているかを、対象者が再確認できます。そして、目標達成に必要な情報を提供するのも評価者の役目です。対象者の行動を冷静に分析し、対象者自身が気づけていない点を深掘りしましょう。もちろん、人格の否定や性格の指摘などは避けるべき行為です。
➂フィードフォワード
フィードバックで対象者の現状を把握したら、フィードフォワードで未来に向けて計画を練りましょう。フィードフォワードの主な手順は、以下のとおりです。
➀次のアクションプランの選出
➁より効果が期待できるプランの選定
➂アクションプランの実施
目標達成に必要な次のプランを計画します。目標から逆算して今何が足りないかを考察し、思いつくままに書き出しましょう。アクションプランが複数出た場合は、より高い効果が得られる計画を次の目標に選定します。無理なく取り組めるものを選ぶことで、モチベーションの維持につながります。選んだ計画は、フィードアップで細やかな目標を立て再度フィードバックを実施しましょう。
効果的なフィードバックの3つのコツ
効果的なフィードバックのコツは、主に以下のとおりです。
・目的や目標に関連づける
・抽象的な表現は避ける
・実現可能なプランを立てる
コツを押さえたフィードバックはより対象者から理解を得られやすく、短期間で大きな成長が見られるでしょう。それぞれのポイントを詳しく解説します。
目的や目標に関連付ける
フィードバックでは、目的や目標を明確に伝えましょう。フィードバックは対象者のモチベーションの向上を図り、個人やチームの目標を達成するのが目的です。目的や目標を明確にしたフィードバックは、目指す方向が分かりやすく対象者の成長につながります。
抽象的な表現は避ける
効果的なフィードバックを実施するなら、具体的な表現を活用しましょう。「よかったね」「うまかったよ」など結果を伝えるだけの抽象的な表現は、何がどのくらいよかったのかが分かりにくいです。そのため評価者は対象者の行動をじっくりと観察し、数値やデータなどの視覚的情報や具体的な表現でフィードバックをしましょう。
実現可能なプランを立てる
対象者が今すぐに取り組めて、目標に向け着実に成長できるプランを採用するのもフィードバックに欠かせないポイントです。対象者の現在のレベルでは達成が難しい目標を設定すると、対象者のモチベーションの低下を招く可能性があります。評価者自身ができる行動を提示するのではなく、対象者側の立場で実行可能な目標を定めましょう。
フィードバックの手法3選
企業におけるフィードバックでは、主に3つの手法が用いられます。ここでは、3つの手法とそれぞれの特徴について詳しく解説します。
| サンドイッチ型 | SBI型 | ペンドルトン型 | |
| 特徴 | 負の評価を前向きな評価で挟む手法 | 現状説明に加えて実際の行動がどんな結果につながったかを伝える手法 | 評価者からの報告だけでなく対象者自身に改善点を考えさせる手法 |
| 期待できる効果 | 対象者のモチベーションの低下を軽減する | 対象者の理解を得やすい | 対象者の主体性がはぐくまれる |
| 主な手順 | ➀褒める ➁指摘する ➂褒める | ➀Situation(状況) ➁Behavior(行動) ➂Impact(影響) | ➀評価者による説明の目的や内容の確認 ➁良かった点の報告 ➂対象者による改善点の考案 ➃両者による今後の計画 |
サンドイッチ型
サンドイッチ型とは、前向きな評価のあいだに負につながりやすい評価を挟んでフィードバックする手法です。 欠点や改善すべき点を指摘する際に、前後に褒める言葉を入れることで、対象者のモチベーションの低下や気分の落ち込みを軽減する効果が期待できます。サンドイッチ型のシンプルな構造は誰もが実践しやすく、ビジネス業界で最も使われるフィードバック方法といわれています。
SBI型
SBI型とは、対象者のおかれた状況を説明し、実際の行動がどのような結果につながったかを伝える手法です。Situation(状況)・Behavior(行動)・Impact(影響)の順に実施するのが特徴です。SBI型は世界的に認知されている手法で、順序に沿ったフィードバックは対象者の理解を得やすいといったメリットがあります。置かれた現状を把握し次に必要な行動を把握できるだけでなく、対象者と評価者のあいだで信頼関係が築きやすい手法の1つです。
ペンドルトン型
ペンドルトン型とは、心理学者のペンドルトンにより開発された、対象者自身に改善点を考えさせる手法です。フィードバックでは、評価者の一方的な評価の報告や指摘が実施される場合があります。一方的な評価の報告は、対象者の意欲的な行動に結びつかない結果を招くおそれがあるでしょう。ペンドルトン型は、評価者の評価結果の報告だけでなく、対象者自身で改善点を考案します。対象者の主体性の構築は、人としての大きな成長につながります。ペンドルトン型を用いる場合は、密なコミュニケーションで対象者の意見を尊重しながら時間をかけて改善策や目標を練りましょう。
フィードバックの具体例
ここではサンドイッチ型・SBI型・ペンドルトン型それぞれの実用的なフィードバックの具体例を紹介します。
サンドイッチ型の手順や具体例
サンドイッチ型は、指摘事項や改善点などのネガティブなフィードバックがある場合におすすめの手法です。サンドイッチ型を取り入れる際は、以下の手順で進めましょう。
➀ポジティブなフィードバック=褒める
➁ネガティブなフィードバック=指摘や改善策の提案
➂ポジティブなフィードバック=褒める
上記の手順をビジネスで活用する際の例文は、以下の表のとおりです。
| 手順 | 例文 |
| ➀ポジティブなフィードバック (=褒める) | プレゼンの資料内容が充実しており、会場にいた方からとても好評でした。 |
| ➁ネガティブなフィードバック (=指摘や改善策の提案) | しかし、質疑応答の対応に時間がかかり、全員が納得する回答ができていなかった点も見られました。あらかじめ指摘されやすい箇所を把握し、回答を準備しておくとよいかもしれません。 |
| ➂ポジティブなフィードバック (=褒める) | プレゼンの説明や資料は問題なくたいへん素晴らしい出来でしたので、今度社内で共有させていただきます。 |
ネガティブなフィードバックでは、どうすればよいか具体的なアドバイスを取り入れることで、対象者のモチベーション低下を防げるでしょう。
SBI型の手順や具体例
SBI型は、ポジティブとネガティブどちらのフィードバックにも効果的です。フィードバックで具体的な行動を振り返る際に役立つ方法でもあります。SBI型を活用する際は、以下の手順で説明を進めます。
➀Situation(状況)=いつ、どこで起きたことか
➁Behavior(行動)=実際にとった行動
➂Impact(結果)=行動の結果感じたこと
上記の手順をポジティブなフィードバックとしてビジネスで活用する際は、以下の表のように説明しましょう。
| 手順 | 例文 |
| Situation(状況) =いつ、どこで起きたことか | 先週の会議での出来事です。 |
| ➁Behavior(行動) =実際にとった行動 | あなたは疑問が生じた際、発言者に積極的に質問をしていました。会議にいるメンバーはあなたの積極的な態度に感化され、次第に全体の発言が増えて意見が飛び交う素敵な議論ができました。 |
| ➂Impact(結果) =行動の結果感じたこと | スタート直後はなかなか発言が見られなかったため、会議の雰囲気が良くなりたいへん助かりました。 |
また、ネガティブなフィードバックでは、以下の表のように説明します。
| 手順 | 例文 |
| Situation(状況) =いつ、どこで起きたことか | 先日の会議の準備を進めている際の出来事です。 |
| ➁Behavior(行動) =実際にとった行動 | あなたに、会議で使用する資料を会議の1週間前までに提出するようお願いしました。しかし、あなたは会議前日に提出をしてきました。 |
| ➂Impact(結果) =行動の結果感じたこと | 確認漏れが起こるリスクを招くだけでなく、印刷などの準備が大幅に遅れました。大切な資料の準備をあなたに任せない方がよいのではと、部署全体にあなたに対してマイナスのイメージが広がりました。 |
順序立てて伝えることで、対象者がいつどんな状況での出来事だったかを振り返りやすくなります。また分かりやすい説明は、対象者の理解を得られるでしょう。
ペンドルトン型の手順や具体例
ペンドルトン型は、SBI型と同じくポジティブとネガティブどちらにも効果的なフィードバック方法です。施策やプロジェクトに対して、より具体的に振り返りたいときにおすすめの方法です。ペンドルトン型を活用する際は、以下の手順でフィードバックを実施します。
➀内容の確認
➁よい点の振り返り
➂改善点の抽出
➃具体的な行動計画
⑤まとめ
上記の手順をビジネスで活用する際は、以下の表のように説明しましょう。
| 手順 | 例文(対象者) | 例文(評価者) |
| ➀内容の確認 | 先日の会議についてです。わたしは、資料作成を担当しました。 | |
| ➁よい点の振り返り | 例年の資料を参考にしつつ最新の情報を盛り込み、資料のアップデートを試みました。いままでにないクオリティで作成できたのではないかと思っています。 | 会議資料、素晴らしい出来でした。図や表を用いた説明は視覚的にも分かりやすく、参加者は有意義な会議の時間を過ごせたのではないかと思います。 |
| ➂改善点の抽出 | しかし、資料を整理するのに多くの時間がかかりました。また、資料の確認を願い出たのが会議の前日となり、多くの方にご迷惑をおかけしてしまいました。 | そうですね。情報量の多い資料の作成にはたくさんの時間がかかります。今回の反省は今後にどう活かそうと考えていますか? |
| ➃具体的な行動計画 | 資料作成の進捗状況をこまめに確認し、上司に報告するよう心がけます。どうしても間に合いそうにない場合はアドバイスをいただき、必要な情報と不要な情報の整理をし、効率よく準備が進められるようにします。 | 素晴らしい改善策です。ぜひ、今後に活かしていただきたいです。 |
| ⑤まとめ | 1ヶ月後に会議があり、資料制作を任されているため、スケジュールをしっかりと管理して準備を進めたいと思います。 |
評価者は必要に応じて補足を加え、対象者が前向きに考えられるようアドバイスをしましょう。
フィードバックに活かせるスキル
フィードバックで活用できるスキルを磨くことは、対象者との信頼関係の構築にもつながるでしょう。ここでは、フィードバックに活かせるスキルについて詳しく解説します。
・ティーチング
・コーチング
ティーチング
ティーチングとは、対象者に必要な知識や技術を直接指導し助言することです。明確な答えを提示しながら指導をするため短時間で成果が得られやすく、教育がスムーズに進められるでしょう。ただし対象者の自分で考える力が育たず、受け身の態度になりやすいです。また、人によってはやる気やモチベーションの維持が難しいケースが考えられるでしょう。必要に応じてティーチングスキルを活用することで、バランスのよい指導が実現します。
コーチング
コーチングとは対象者の話を聞きながら答えを引き出し、目標の達成をサポートする手法を指します。コーチングでは相手の話に耳を傾け、質問を繰り返します。内に秘めた考えや心の中の答えを時間をかけて引き出す、間接的な支援です。本人が納得のいく答えを出すまで、指導者は直接助言することはありません。コーチングのメリットは、考える力や答えを導く力が見につき、主体性の発揮につながる点です。また自分で導き出した答えは、モチベーションを維持しながら目標に向かって取り組みやすいでしょう。誰にもない発想は、ときに新しいアイデアを生み出し、企業の発展につながるかもしれません。ただしこれは、相手が知識やスキルを持っている前提の指導方法です。そして対象者の発想力や想像力を尊重しながら進めるため、ティーチングに比べて成果を出すのに時間がかかるでしょう。
フィードバックで効果が出ない時の対処方法
フィードバックを実施しているにもかかわらず十分な効果が期待できない場合は、以下の対処法を実施してみましょう。
・フィードバックの「伝え方」を見直す
・フィードバックの「頻度」を見直す
・対象者との「関係性」を見直す
ここでは、3つの対処法のポイントを詳しく解説します。
フィードバックの「伝え方」を見直す
フィードバックの伝え方を見直すことで、効果が得られる場合があります。フィードバックは、分かりやすい説明が求められます。遠回しの伝え方では、相手の理解を得られなかったり誤解を招いたりするでしょう。フィードバックは対象者の個性に合わせて実施します。評価者は対象者それぞれの立場や成長に合わせて、伝え方を意識しましょう。
フィードバックの「頻度」を見直す
フィードバックの効果が不十分な場合は、頻度に着目しましょう。たとえば一度のフィードバックでは、対象者の業務の振り返りが十分にできるとはいえません。改善すべき課題が隠れていることもあるでしょう。定期的なフィードバックは、対象者の問題点を見つめて改善する頻度が増えるだけでなく、評価者や企業との信頼関係の構築によってフィードバックの効果が得られやすくなります。対象者の隠れた才能を発掘し、企業の発展につなげるためにも、こまめなコミュニケーションを図りましょう。
対象者との「関係性」を見直す
フィードバックの効果は、評価者と対象者との関係性も影響します。たとえば評価者と対象者のあいだに信頼関係ができていないまま何度もフィードバックを繰り返しても、効果は期待できません。対象者が、評価者の話を素直に聞き入れられない場合もあるでしょう。とくに評価者の高圧的な態度や不誠実な振る舞いは、対象者の反感を招きます。評価者はできるだけ誠実な態度を心がけ、密な連携で信頼関係の構築を図りましょう。
人材育成のことならユーキャンへ
効率的なフィードバックの実施には、評価者の対応力が求められます。 スキルの高い評価者がフィードバックを実施すれば、対象者の問題点をしっかりと把握しながら明確な改善策の提示で効果を得られるでしょう。 ユーキャンの人材育成プログラムでは、各階層に合わせたさまざまなプログラムを用意しています。新入社員や若手の育成にはもちろん、リーダークラスの人材強化におすすめです。効率的な人材育成で、企業全体のモチベーションの向上を目指しましょう。
まとめ
フィードバックとは、 反応や結果をもとに再度調整を加えることです。ビジネスにおいては、対象者の思考や言動・行動などを評価し、改善で軌道修正を図ります。定期的なフィードバックは人材育成だけでなく、対象者のモチベーションの向上や企業全体の業績アップにつながります。 フィードバックを実施する際はティーチングやコーチングを取り入れるなどし、対象者の想いを汲み取りながら適切なタイミングで指導しましょう。 ときには伝え方や関係性を見直して、効率的なフィードバックを心がけるのも大切です。