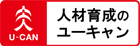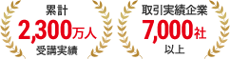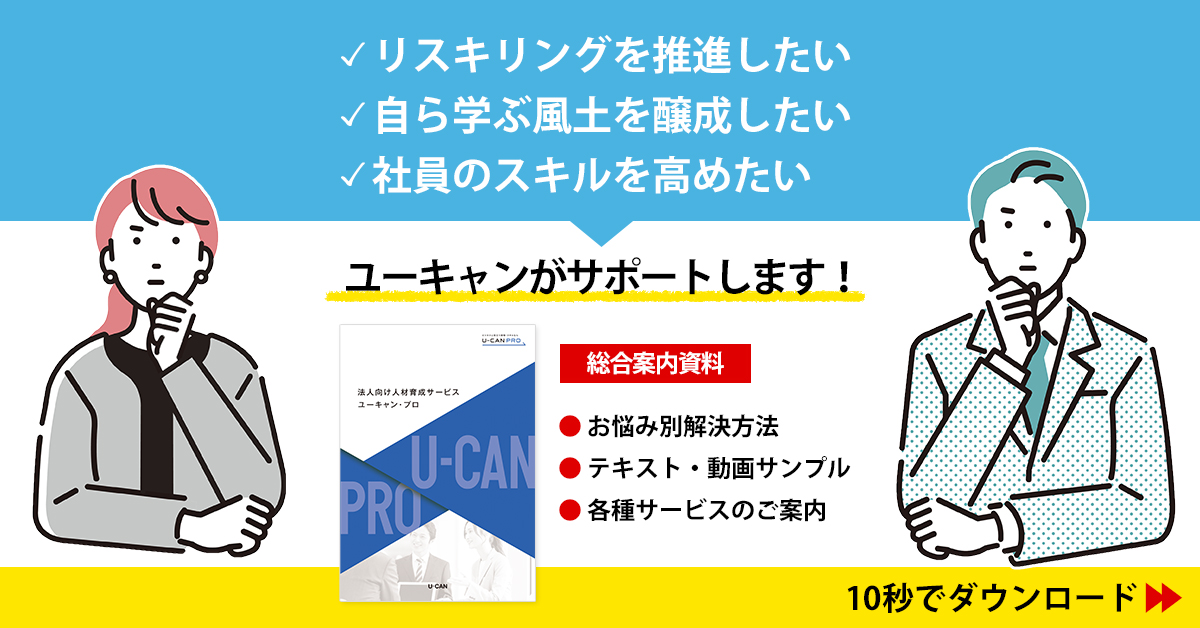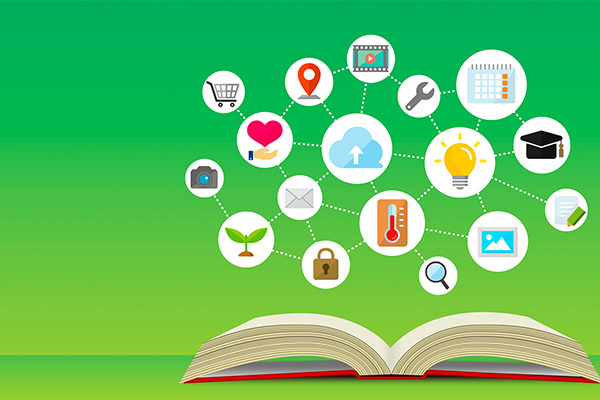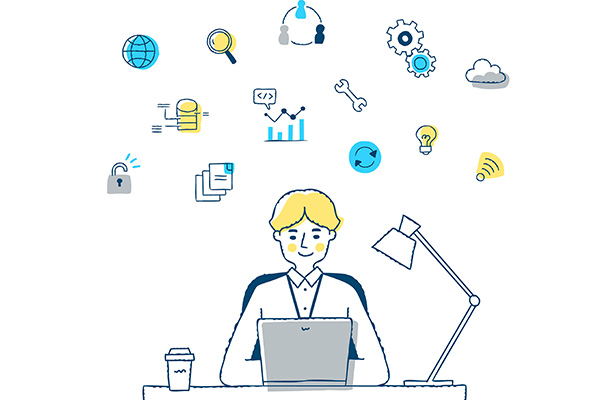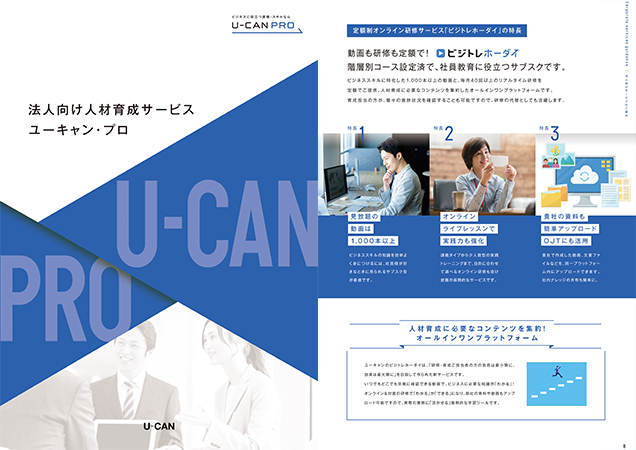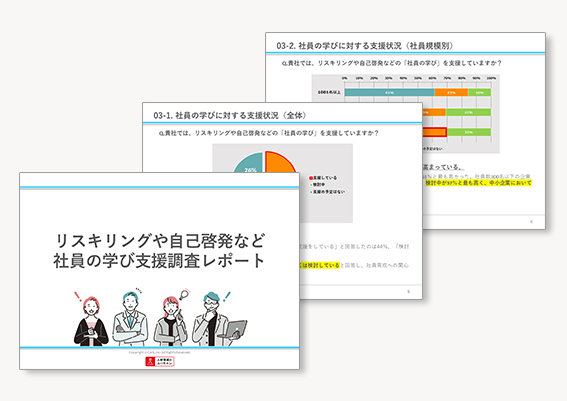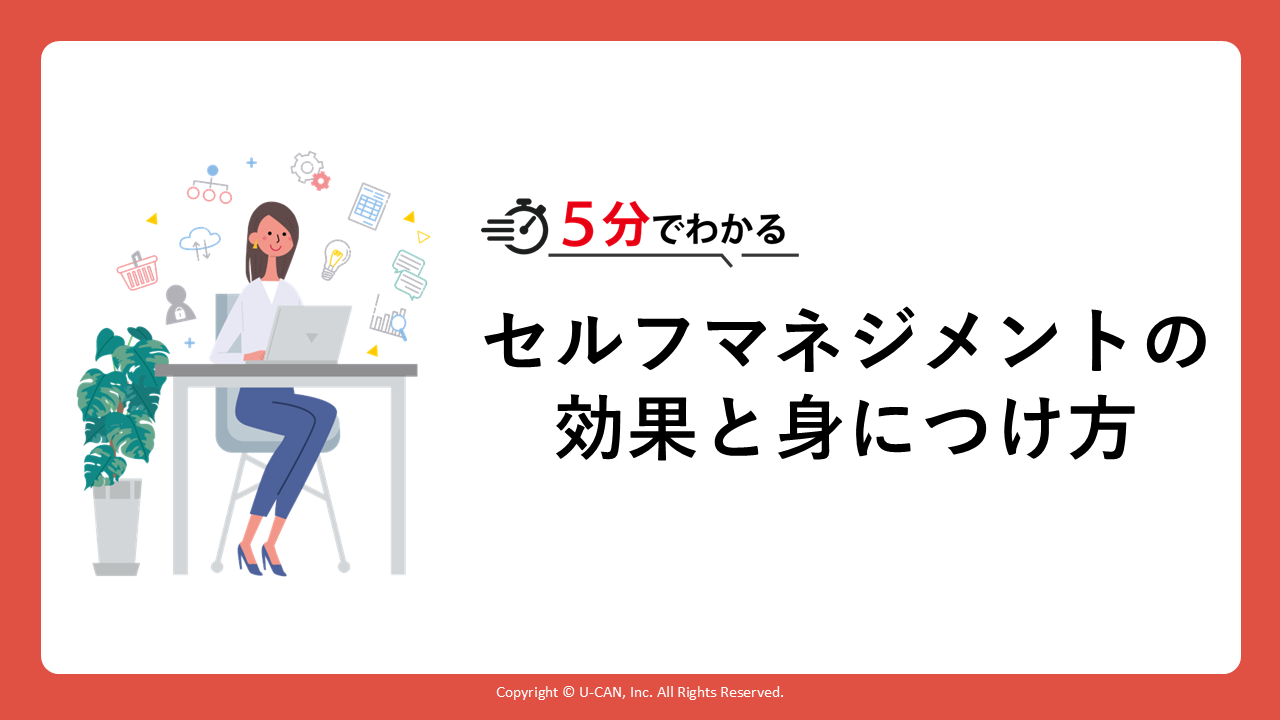リカレント教育とは
リカレント教育とは何であるかについて、その意味や歴史、日本における現状を解説します。
リカレント教育の意味
リカレント教育は、社会人や社会人経験者が、知識や技術を仕事に活かすために再び教育を受けることを指します。循環や繰り返しを意味する英単語の「recurrent」に「教育」が結びついた言葉です。学びと仕事を循環させる考え方で、「社会人の学び直し」ともいわれます。
リカレント教育の歴史
リカレント教育は、スウェーデンの経済学者ゴスタ・レーン氏によって提唱され、1969年に当時の教育相オルフ・パルメ氏が欧州教育大臣会議にて紹介しました。1973年にOECD(経済協力開発機構)が報告書を公表したことにより、学びと仕事を生涯にわたり交互に行うことを理想とする考え方が、世界的に認知されました。
日本のリカレント教育の現状
日本のリカレント教育は、あまり進んでいない現状があります。リカレント教育が進まない背景には、主に企業側と個人側の両方に課題があります。企業は長時間労働や人手不足の中で、従業員の学び直しに十分な時間や資源を割く余裕がなく、教育の仕組みも支援体制も整っていないことが多いです。一方、個人側も経済的・時間的負担、学び直しの必要性や効果への認識不足から、主体的な行動に踏み出せない傾向があります。これらの要因が重なり、社会的には制度や環境が整備されていても、リカレント教育の定着には至っていないのが現状です。
リカレント教育に似ている用語
リカレント教育に似ている用語に、以下があります。
- ・リスキリング
- ・生涯学習
2つの違いについて解説します。
リスキリングとリカレント教育との違い
リスキリングとリカレント教育の大きな違いは、学び方にあります。リスキリングは「Re-skilling」を意味し、従業員が通常の業務を続けたまま、研修等で学び、必要なスキルを身につけることです。一方で、リカレント教育は仕事を離れて学ぶのが一般的です。リスキリングについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
※参考:今話題のリスキリングとはどういう意味?(https://www.u-can.co.jp/houjin/column/cl027.html)
生涯学習とリカレント教育との違い
生涯学習とリカレント教育の大きな違いは、学ぶ目的です。生涯学習は、教養や生きがいに通じる学習で、学校教育を含むスポーツ・文化活動、ボランティア活動、趣味などのあらゆる学びを指します。それに対して、リカレント教育は仕事に活かせる知識や技術を学び、キャリアアップを目指すことが目的です。
リカレント教育が必要とされる背景
リカレント教育が求められる背景には、以下が挙げられます。
- ・人生100年時代の到来
- ・技術の発展や社会の変化
- ・雇用や働き方の変化
「人生100年時代」の到来
近年、日本の長寿化は進み、「人生100年時代」と呼ばれています。定年後も生活のために仕事をする必要性が生まれるほか、人生をより充実したものとするために、長い期間働く人が増えています。新しい知識や技術の学びは、全ての人が元気に活躍し続けられる社会にとって、今後ますます重要となります。
技術の発展や社会の変化
世界的にどの分野においても、AIの導入やDX推進などによる変化や進化が起きています。急速に変化する社会において、個人が新しい知識や技術を身につけることは、企業の新たな事業やサービスの創出につながります。仕事と学びを継続的に繰り返すことで、社会やビジネス構造の変化に対応できるスキルが身につきます。
雇用や働き方の変化
かつて日本の企業で当たり前だった終身雇用は、近年ではスキルを重視するジョブ型へと切り替わってきています。それに伴い、転職や副業・兼業など、雇用市場の活性化も進んでいるといえます。企業や組織、年齢などにとらわれないスキルを身につけ、キャリアアップにつなげる学びが必要とされています。
リカレント教育により企業が得られるメリット
リカレント教育は従業員が新たに知識、スキルを学び直し、組織で活躍するために必要な施策です。具体的に企業にとってどのようなメリットがあるのか、ポイントを紹介します。
競争力が高まる
リカレント教育の導入は、自社の競争優位性を高めることにつながります。従業員が最新の知識や技術を身につけ、スキルアップすることにより、自社の商品やサービスの品質向上、新たなビジネスの創出などといった、いい影響が生まれます。その結果、自社の増益、他社に負けない競争力を強化することが期待されます。
従業員の離職を防げる
企業がリカレント教育を導入することは、意欲ある人材の定着につながります。スキルアップやキャリアアップに対する意欲が高まっている社会において、従業員の教育に力を入れている企業は信頼感を得やすいでしょう。成長できる環境の整備によって、キャリアパスを描きやすくします。
企業イメージが向上する
リカレント教育の導入は、従業員に学びの場や成長の機会を提供していることを社外へアピールできる要素となります。従業員へ投資をしている企業であるという認識が広がることで、企業としての評価が高まり、ステークホルダーからの信頼にもつながります。企業価値を高め、優秀な人材からも注目されるでしょう。
変化への対応力が強化できる
リカレント教育を導入することで、企業は変化への対応力を強化できます。現代のビジネス環境はデジタル技術の進化や市場ニーズの多様化、グローバル化などにより急速な変化が常態化しており、変化への適応は必要不可欠です。その中で従業員が最新の知識やスキルを継続的に学ぶことで、新しい業務や技術に柔軟に対応できる体制が整います。また学び直しを通じて変化に前向きな姿勢が組織内に根付き、挑戦意欲や創造力も向上します。結果として、環境変化に迅速かつ的確に対応し、競争力を維持・強化でき、強い組織づくりの基盤となるでしょう。
イノベーションの創出につながる
リカレント教育は、イノベーションの創出にも大きく寄与します。従業員が最新の技術や知識、異なる分野の視点を学ぶことで、既存の枠にとらわれない発想が促され、新たな商品・サービスの開発や業務改革につながるためです。特にデジタル分野やサステナビリティ、デザイン思考など、変化の激しい領域での学び直しは企業の競争力向上に直結します。また学んだ知識が職場に共有されることで、組織全体の創造性や問題解決力も高まり、革新的な取り組みが生まれやすい風土が醸成されます。
リカレント教育を受ける手段
リカレント教育を受ける手段は、以下です。
- ・大学や大学院
- ・オンライン講座
- ・公的職業訓練制度
大学や大学院で学ぶ
多くの大学・大学院では、社会人向けのコースやリカレント教育のプログラムを実施しており、専門的な分野を体系的に学べるのが特徴です。通信制大学での学位取得や、1科目から履修できる科目等履修制度などの利用ができます。企業は、休職制度の整備や学費支援などをするとよいでしょう。
オンライン講座で学ぶ
リカレント教育には、オンラインで受講可能な大学の講義や企業の研修を利用する方法もあります。文部科学省によって開設された、社会人の学びに関する情報提供サイト「マナパス」では、条件別の講座検索が利用できます。ほかにも、民間の講座配信サービスを利用すれば、オンラインでの学びが可能です。
公的職業訓練(ハロートレーニング)を受講する
公的職業訓練もリカレント教育を受ける方法の1つです。公的な制度として、就業に必要なスキルや知識を身につけられます。求職中の人だけではなく、在職している人も受けられる訓練や講座もあり、基本的に無料です。ただし、ハローワークにて職業相談をし、面接や筆記試験の受験・合格が受講条件となります。
リカレント教育で学ぶべき内容とは
リカレント教育では、時代のニーズや企業の目標・課題に合わせて適した内容を学ぶ必要があります。なかでもリカレント教育で学ぶべきおすすめの内容を4つ紹介します。
IT・デジタルスキル
リカレント教育で重視すべき内容のひとつが、IT・デジタルスキルの習得です。デジタルトランスフォーメーション(DX)が加速する現代において、業種を問わずITリテラシーは必須とされています。具体的にはデータ分析、AI活用、プログラミング、クラウド、サイバーセキュリティなどのスキルがおすすめです。これらを学ぶことで、業務の効率化や新規ビジネスの創出に貢献でき、企業の競争力強化や変化への対応力向上にもつながります。
ビジネススキル
リカレント教育において重要な学習分野のひとつがビジネススキルです。これは業種や職種を問わず汎用性の高い能力であり、論理的思考力、プレゼンテーション力、交渉力、問題解決力、プロジェクトマネジメントなどが含まれます。これらのスキルを磨くことで、業務の質が向上し、チームや組織全体の成果にもつながります。変化の激しいビジネス環境において、柔軟に対応し主体的に行動できる人材の育成に不可欠な学習領域です。
英語力
リカレント教育において英語力の習得は、グローバル化が進む現代においてますます重要になっています。特にビジネス英語や専門分野の英語表現を学ぶことで、海外との取引や情報収集、国際会議での対応力の向上も期待できます。また最新の研究や技術情報は英語で発信されることが多く、英語力があることで学びの幅も広がる点も魅力です。英語は単なる語学スキルではなく、キャリアの選択肢や活躍の場を広げる重要な武器となります。
リーダーシップ・マネジメント力
リカレント教育では、リーダーシップやマネジメント力の習得も重要な学習内容です。組織を率いる立場に求められる能力として、目標設定、部下育成、チームビルディング、意思決定力、問題解決力などが必要です。特に多様な価値観を持つ人材をまとめるためには、柔軟で対話重視のマネジメントが求められます。こうした力を体系的に学ぶことで、管理職としての役割を効果的に果たせるだけでなく、組織全体の生産性やエンゲージメント向上にもつながります。
リカレント教育の導入における課題
リカレント教育は従業員の成長を促す重要な施策ですが、同時にいくつかの課題もあります。起こりうる課題を4つ紹介します。
制度の整備が必要となる
リカレント教育を希望する従業員のために、企業は休職制度や教育訓練休暇制度、修了後の復職制度などを整備する必要があります。整えられた学習環境があることで、従業員の満足度は向上し、安心して学べます。身につけた知識やスキルが、待遇や給料に反映されるなどの人事評価制度もあるといいでしょう。
運用コストがかかる
企業でリカレント教育を推進するためには、社内体制の整備や制度の見直し・導入などの人的コストがかかります。学費の補助や、学習ツールや教材を用意する場合のコストといった予算も必要です。リカレント教育は、効果に対して中長期的な視点を必要とします。かかるコストは投資と捉えるとよいでしょう。
学びの動機付けが必要
リカレント教育の導入における課題のひとつに、学びの動機付けの難しさがあります。従業員にとって、日常業務と並行して新たに学習するには明確な目的意識が必要です。しかし「なぜ学ぶのか」「学んだ内容がどう活かせるのか」が不明確なままだと、学習意欲が湧きにくく、継続も困難になります。特に会社からの一方的な受講指示では「やらされ感」が強まり、主体的な取り組みが期待できません。そのため企業は学習内容とキャリア形成や業務上の成果とのつながりを丁寧に説明し、個人の目標や関心に応じた選択肢を用意するなど、動機付けを支援する仕組みづくりが求められます。
学びに時間の制約がある
リカレント教育の導入において大きな課題となるのが、学習時間の確保が難しいことです。多くの従業員は本業の業務に追われ、業務時間外に学習の時間を割く余裕がないケースも少なくありません。特に長時間労働や人手不足の職場、子どもや要介護者のいる家庭では、学ぶ意欲があっても実際に取り組むのは時間的に困難です。このような状況では、企業側が業務調整や勤務時間内での学習支援、eラーニングなど柔軟な学習環境の提供を行い、従業員が無理なく学びを継続できる仕組みを整えることが重要です。
リカレント教育のために企業が取り組むべきこと
リカレント教育のために、企業は以下のような取り組みが必要です。
- ・学ぶための環境を整える
- ・勤務形態を見直す
- ・受講料を補助する
学ぶための環境を整える
リカレント教育を検討する企業は、外部の企業が提供するツールやオンラインサービスの活用により、従業員が学びやすい環境をスムーズに整えられます。教材やツールをすべて社内で用意することは簡単ではありません。自社に必要な教育や、従業員が求めるスキル向上に役立つものを選びましょう。
勤務形態を見直す
本来のリカレント教育は、学びと仕事を交互に行う考え方ですが、日本では学びと仕事の両立もリカレント教育としています。仕事をしながら学ぶ従業員に対し、学習時間を確保することや学びやすい環境をつくることが企業には求められます。時短勤務やフレックス勤務などの導入も、勤務体系の見直しに含まれます。
受講料を補助する
個人でリカレント教育を受けようとすると、金銭的な負担がかかるものも少なくありません。従業員の学びに対し、企業が受講料の全額もしくは一部を補助する体制をつくれば、個人の金銭的負担を減らすことにつながります。受講料の補助により、学びに対して意欲的な従業員が増えることも期待できます。
目的を明確にする
リカレント教育の成果を高めるためには、対象者や目的を明確にすることが重要です。自社の業務やキャリアパスに沿った内容のように、従業員と企業の双方のニーズに合う学びであれば、成果につながりやすいでしょう。効果測定もしやすく、持続的な従業員教育が可能となります。
リカレント教育への支援制度
リカレント教育には、厚生労働省による以下のような支援制度があります。
- ・教育訓練給付金
- ・高等職業訓練促進給付金
- ・人材開発支援助成金
- ・キャリアコンサルティング
教育訓練給付金
教育訓練給付金は、厚生労働省が指定する教育訓練を修了すると、受講費用の20%〜70%が支給される制度です。訓練はレベルによって、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類に分類され、種類で支給される給付金の割合が変わります。給付金の申請はハローワークへ申し込みます。
高等職業訓練促進給付金
高等職業訓練促進給付金は、ひとり親を対象とした制度で、資格取得のために修業している期間の生活費の支援を受けられます。対象となる資格はさまざまで、看護師や介護福祉士、保育士などの国家資格のほか、デジタル系の民間資格も含まれます。修業期間中は月10万円、修了後は5万円が支給されます。
人材開発支援助成金
人材開発支援助成金は、企業のための支援制度です。正規雇用の従業員を対象に、専門的な知識や技術の習得を目的とする計画的な訓練を実施した企業に対し、訓練の経費や訓練中の賃金の一部として、助成金が支給されます。特定訓練コースや一般訓練コースなど、8つのコースがあります。
キャリアコンサルティング
キャリアコンサルティングは、在職している人を対象にしたもので、専門のコンサルタントにキャリアに関する相談や質問ができます。費用はかからず、対面もしくはオンラインで1時間程度の面談を行います。
リカレント教育の取り組み事例
リカレント教育への取り組みについて、以下の3つの事例を紹介します。
- ・ソフトウェア開発会社
- ・飲料製造・販売会社
- ・総合電機メーカー
ソフトウェア開発会社
あるソフトウェア開発会社では、2012年からリカレント教育のための復職制度をスタートしました。退職後、最長6年間は復職を可能とする制度です。従業員は復職できる安心感から、大学への入学や留学、転職など、スキルアップを目指して意欲的に学ぶことへチャレンジできます。
飲料製造・販売会社
大手飲料製造・販売会社では、自己啓発を支援するプログラムを推進しています。応募型研修、英語力強化、eラーニング、通信教育通学費補助制度の4つのプログラムに、さまざまなコースが用意されています。従業員の教育を投資と考え、意欲的に学べる環境づくりをしています。
総合電機メーカー
大手総合電機メーカーでは、キャリアアップやキャリア継続のための休職制度を設けています。配偶者の海外赴任帯同による離職は最長5年、専門知識や技術を身につける修学は最長2年の休職を認めています。修学の場合は、入学の初期費用の補助制度も整えており、優秀な人材の育成に力を入れています。
まとめ
リカレント教育は人材不足の続く企業にとって、既存人材を有効活用するための重要な施策となります。費用と時間は必要ですが、従業員の誰もが輝ける職場づくりにつながり、組織全体の活性化も期待できます。