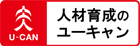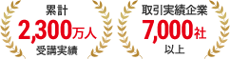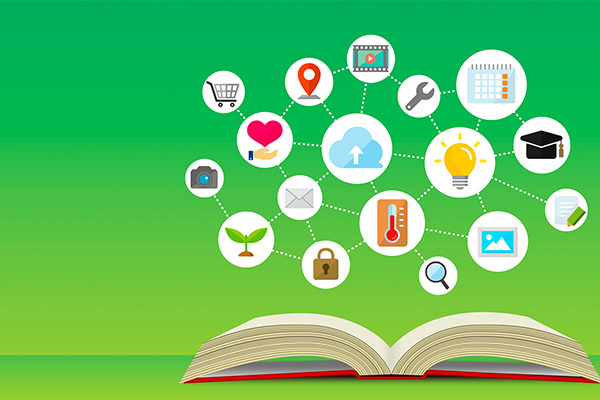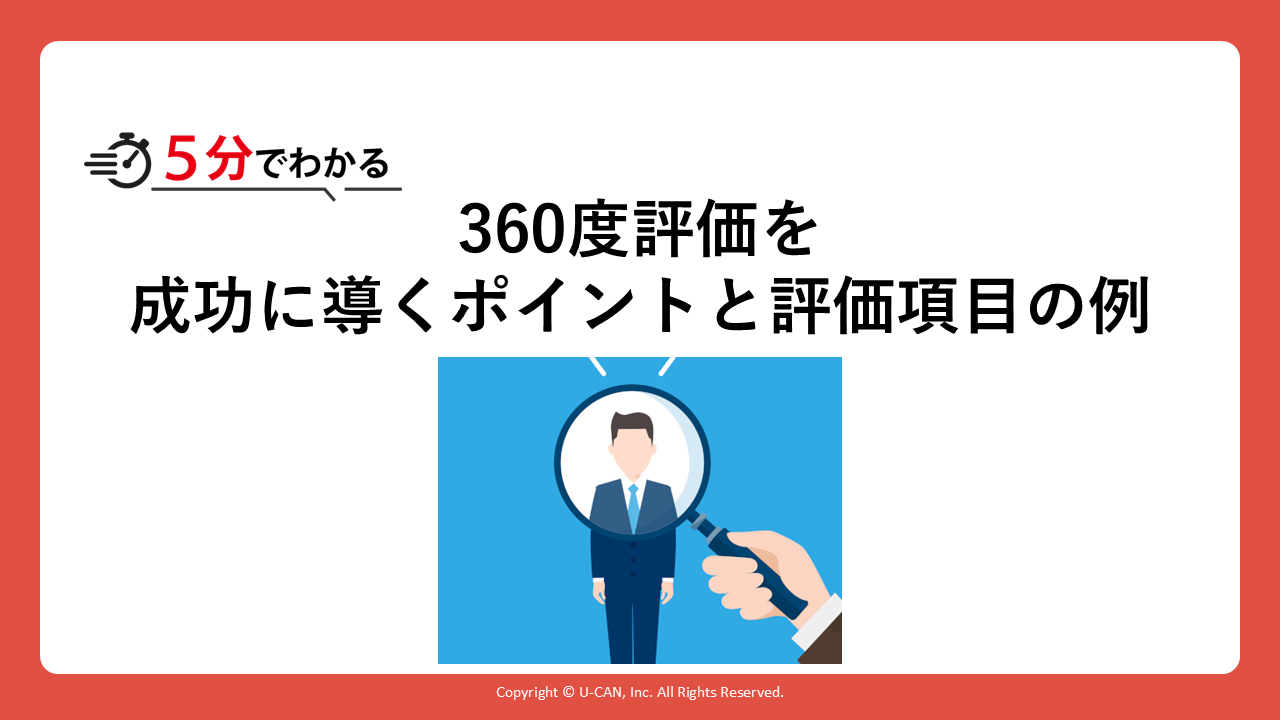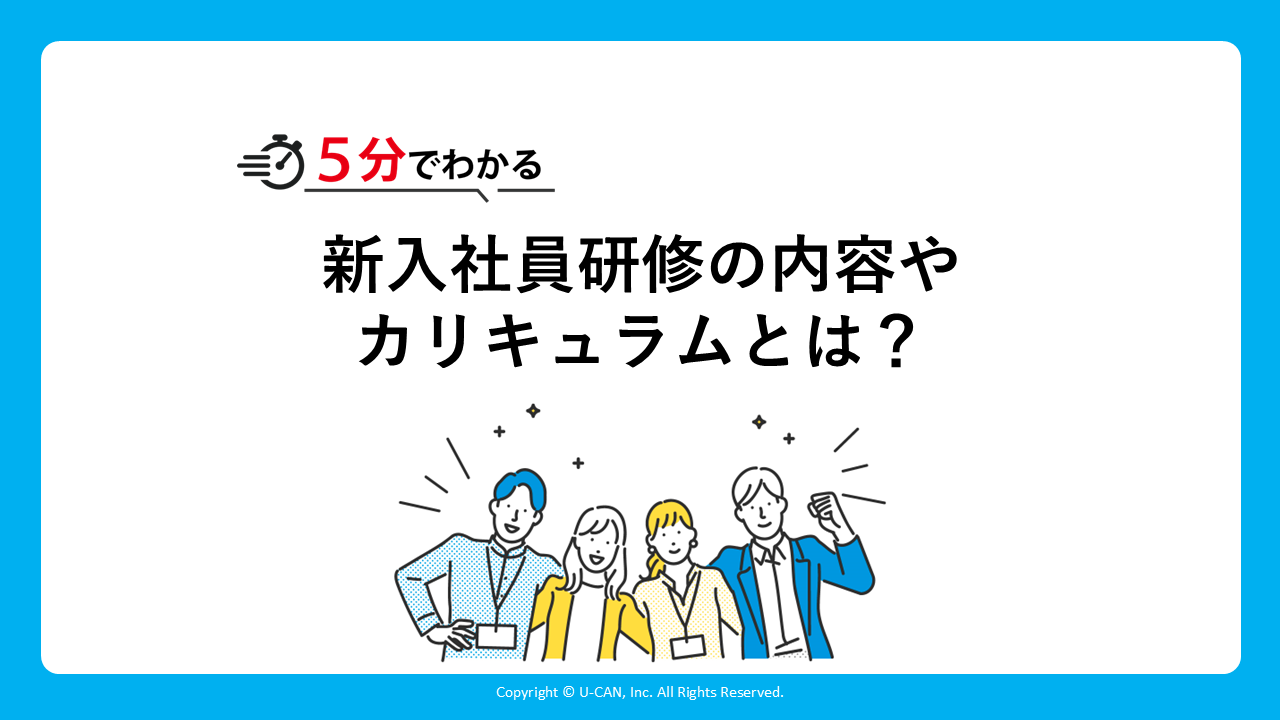社員研修に関する助成金とは?
社員研修に関する助成金とは、企業の人材育成計画に基づき、事業所の置かれた地域を管轄する都道府県や労働局に申請書を提出することで、研修にかかる費用の一部を支給される制度です。助成金にはいくつか種類があり、その種類ごとに決まった研修対象者と内容があるため、受給するにはそれぞれの要件を満たしている必要があります。
助成金の手続き方法とは?
助成金の手続きは企業側が主体となって行い、必要な資料の作成と提出をしなければなりません。簡単に手順を解説すると次の通りです。
1.検討中のプログラム・コースの対象となるか要件を確認
2.プログラム・コースの期間や対象者を確認
3.実施計画書の作成・必要書類の提出
4.研修実施
5.助成金の申請書を提出
助成金制度は受給要件が明確に規定されているため、事前に要項や手順をしっかり読み込んだうえで準備を進めてください。制度の詳しい内容やどのプログラム・コースを利用できるか判断が難しい場合は、社会保険労務士(社労士)に相談するのがおすすめです。
研修に使える助成金
社員研修で利用できる助成金制度には、どのようなものがあるのかを紹介します。
・人材開発支援助成金
・キャリアアップ助成金
・両立支援等助成金
・スキルアップ助成金
参考
人材開発支援助成金:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
キャリアアップ助成金:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
両立支援等助成金:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
スキルアップ助成金:https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/saiyo-sodan/skill-n.html
人材開発支援助成金
人材開発支援助成金は、厚生労働省が行っている助成金制度です。社員に対して職務に関連する専門知識と技能を習得させるため、職業訓練等を計画に沿って実施した場合に訓練経費や期間中の賃金の一部を助成する仕組みです。コースには次の6つがあります。
| コース | 概要 |
| 人材育成支援コース | 労働者に対して、職務に必要な専門知識と技能を習得させる訓練や厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、非正規雇用労働者を対象とした正社員化を目指す訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成 |
| 教育訓練休暇等付与コース | 有給教育訓練等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成 |
| 人への投資促進コース | デジタル人材・高度人材を育成する訓練や労働者が自発的に行う訓練、サブスクリプション型の訓練等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成 |
| 事業展開等リスキリング支援コース | 新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識および技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成 |
| 建設労働者認定訓練コース | 認定職業訓練または指導員訓練のうち、建設関連の訓練を実施した場合の訓練経費の一部や、建設労働者に有給で認定訓練を受講させた場合の訓練期間中の賃金の一部を助成 |
| 建設労働者技能実習コース | 雇用する建設労働者に技能向上のための実習を有給で受講させた場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成 |
それぞれのコースにおける、経費の助成や助成対象となる訓練については次の通りです。
| 対象となる訓練 | 経費助成率 | 賃金助成額 | OJT実施助成額 |
| 人材育成訓練 | 45~70%(30~100%) | 760円(360円) | - |
| 認定実習併用職業訓練 | 45%(30%) | 20万円(11万円) | |
| 有期実習型訓練 | 60~70% | 10万円(9万円) | |
| 高度デジタル人材訓練 | 75%(60%) | 960円(480円) | - |
| 成長分野等人材訓練 | 75% | 960円(国内大学院を利用した場合) | - |
| 情報技術分野認定実習併用職業訓練 | 60%(45%) | 760円(380円) | 20万円(11万円) |
| 長期教育訓練休暇等制度 | 20万円 | 6,000円/日 | - |
| 自発的職業能力開発訓練 | 30% | - | - |
| 定額制訓練 | 45%(30%) | - | - |
※括弧内のものは中小企業以外
また助成金を利用する場合には、事業主の命令で労働者に訓練を受けさせるパターンと、労働者が自発的に行う訓練を支援するパターンの2種類があります。それぞれの支給要件は次の通りです。
【ケース1】
申請事業主が業務命令で対象労働者に訓練を受講させる場合
▼支給要件
・訓練開始日の1か月前までに計画届を労働局に提出すること
・申請事業主が訓練期間中も対象労働者に適正に賃金を支払うこと
・申請事業主が支給申請日までに訓練経費を全額負担すること
・対象労働者の職務に直接関連する訓練であること
・訓練時間数が10時間以上の訓練であること
・OFF-JTを行うこと、またはOFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を行うこと
【ケース2】
申請事業主が自発的に訓練を受講する労働者を支援する場合
▼支給要件
・労働協約または就業規則に規定した制度に基づき、労働者が自発的に訓練を受講すること
・事業主以外の事業主が主催した訓練であること
・労働者が自発的に受講した訓練経費を負担すること、または教育訓練休暇制度等を新たに導入・適用すること
どの条件を満たしているかで利用できるコースが異なるため、詳しくは人材開発支援助成金のホームページで確認しましょう。
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、人材開発支援助成金と同じく厚生労働省による助成金制度です。その概要は以下の通りです。
「有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」)の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成」
そして、支援プログラムは2種類、コースは6つあります。
【正社員化支援】
・正社員化コース有期雇用労働者等を正社員化
・障害者正社員化コース:障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換
【処遇改善支援】
・賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し3%以上増額
・賃金規定等共通化コース:有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たなに規定・適用
・賞与・退職金制度導入コース:有期雇用労働者等を対象に賞与または退職金制度を導入し支給または積立を実施
・社会保険適用時処遇改善コース(令和8年3月31日まで):有期雇用労働者等を新たに社会保険に適用させるとともに、収入を増加させる(手当支給・賃上げ・労働時間延長)、または週所定労働時間を延長し、社会保険に適用させる
さらに、それぞれのプログラムで事業主が申請を行う手順は次のように規定されています。
| プログラム | 申請手順 | 労働局・ハローワーク |
| 正社員化支援 | 1.キャリアアップ計画の作成・提出 2.就業規則等の改定(正社員への転換規定がない場合) 3.就業規則等に基づく正社員化 4.正社員化後6か月の賃金の支払い(正社員化前6か月と比較して3%以上の賃金の増額が必要) 5.支給申請(取組後6か月の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内) |
1.キャリアアップ計画の作成援助・認定 2.就業規則等の改定方法の相談等 3.支給審査・支給決定 |
| 処遇改善支援 | 1.キャリアアップ計画の作成・提出 2.取組の実施(就業規則の改定等) 3.取組後6か月の賃金の支払い 4.支給申請(取組後6か月の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内) |
両立支援等助成金
両立支援等助成金は次の目的で行なわれている助成金制度です。
| 目的 |
| 働き続けながら子育てや介護等を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事業主に対して、両立支援等助成金を支給することにより、仕事と育児・介護等の両立支援に関する事業主の取組を促進し、労働者の雇用の安定を図る。 |
両立支援等助成金には6つのコースがあり、それぞれのコースの概要は次の通りです。
| コース | 内容 | 支給額(休業取得/制度利用者1人あたり) |
| 出生時両立支援コース | 男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備・業務体制整備を行い、この出生後8週以内に育休開始 | ①第1種(男性の育児休業取得) ・1人目20万円 ・2~3人目10万円 ②第2種(男性育休取得率の上昇等)※第1種受給年度と比較し男性育休取得率が30%以上上昇した場合等 ・1年以内達成:60万円 ・2年以内達成:40万円 ・3年以内達成:20万円 |
| 育児休業等支援コース | 育児休業の円滑な取得・復帰支援の取組を行い、「育休復帰支援プラン」に基づき3か月以上の育休取得・復帰 | ①育休取得時30万円(プランに基づき3か月以上の休業取得) ②職場復帰時30万円(育休からの復帰後、継続雇用) ※いずれも無期雇用者・有期雇用労働者各1人限り |
| 育休中等業務代替支援コース | 育児休業や育児短時間勤務期間中の業務体制整備のため、業務を代替する周囲の労働者への手当支給や、代替要員の新規雇用(派遣受け入れを含む)を実施 | ①育児休業中の手当支給最大125万円まで ②育短勤務中の手当支給最大110万円まで ③育児休業中の新規雇用最大67.5万円まで ※①~③合計で1年10人まで、初回から5年間 |
| 柔軟な働き方選択制度等支援コース | 育児期の柔軟な働き方に関する制度等を導入したうえで、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」により制度利用者を支援 | ・制度2つ導入し、対象者が制度利用で20万円 ・制度3つ以上導入し、対象者が制度利用で25万円 ※1年度5人まで |
| 介護離職防止支援コース | 「介護支援プラン」に基づき円滑な介護休業の取得・復帰や介護のための柔軟な就労形態の制度利用を支援 | ・介護休業 ①休業取得時30万円 ②職場復帰時30万円 ・介護両立支援制度30万円 ※休業・両立支援制度それぞれで1年度5人まで |
| 不妊治療両立支援コース | 不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組み、労働者が制度を利用 | 環境整備、休暇の取得等で30万円(対象労働者が5日以上制度を利用) ※1回限り |
※いずれのコースにも加算措置・加算額あり
スキルアップ助成金
スキルアップ助成金は、公益財団法人東京しごと財団が行っている助成金制度です。職務のスキルアップを目的とした自社規格の研修を助成対象にしています。申請できるのは以下の条件に当てはまる企業です。
| 業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
| 小売業・飲食業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| みなし大企業でないこと | ||
上記を満たしている企業で、かつ次の申請要件を満たしている必要があります。
・都内に本社または主たる事業所(支店・営業所等)があること
・都税の未納付がないこと
・過去5年間に重大な法令違反等がなく、暴力団に該当しないこと
助成の対象となる受講者と助成額・助成限度額は次の通りです。
| 助成対象受講者 | 以下の要件をすべて満たす者 ・申請企業等の従業員 ※代表および個人事業主本人を除く ※役員は雇用保険に加入している場合のみ ・常時勤務する事業所の所在地が都内である者 ・研修毎に総研修時間数の8割以上を受講した者 |
| 助成額・助成限度額 | ・助成額:助成対象受講者数×研修時間数×760円 ・助成限度額:1申請企業等あたり150万円まで |
社員研修と合わせて活用できる助成金
上記の助成金だけでなく、併用しても使える助成金があります。その代表例が経済産業省が支援している「IT導入補助金」です。中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的とし、ITツールを利用した業務効率化とDXを支援する補助金です。システムやソフトウェア、セキュリティ、他企業との連携などデジタル化を支援するさまざまなコースが用意されています。
研修に関する助成金に関する注意点
社員研修で助成金を利用する場合、手続き上の注意点がいくつかあります。3つの注意点を確認し、利用する際の参考にしましょう。
手続きの手順を確認する
助成金を利用する際は、必ず申請手続きの手順を確認しましょう。公的機関が提供している助成金は複数ありますが、いずれも手続きの手順には違いがあります。例えば人材開発支援助成金であれば、事前に実施計画を提出したうえで認可をもらわなければなりません。また仮に提出した書類に誤りや漏れがあっても、原則として差し替えもできません。助成金をどこが制度化しているかによって、提出場所が違う点にも注意すべきです。厚生労働省のホームページや各都道府県の労働局ですが、自治体が行っている助成制度なら自治体に問い合わせて確認する必要があります。当然ながら、申請書や提出すべき書類もそれぞれ異なるため、提出先や手続きを確認して、それぞれの主体に合わせて申請を行いましょう。
制度毎の受講対象者を把握する
利用する助成金制度によって、受講対象者が違う点にも注意すべきです。人材開発支援助成金の場合、人材育成支援コースや教育訓練休暇等付与コース、事業展開等リスキリング支援コースなど6つのコースがあります。それぞれのコースで対象者が異なるため、助成金の対象が誰になるのか、どの範囲までが制度として認められるかの判断は重要です。助成金の対象が誰になるのか、どの範囲までが制度として認められるかの判断は重要です。その他の助成金にも同様のことがいえるため、手続きを進める前に受講対象者の把握は必ず行いましょう。受講対象者と認められない人や事業が対象だった場合、事前に計画していた助成金が使えなくなり、研修費用を全額自社で負担することになるリスクがあります。手続きの申請手順と合わせて、受給要件を満たしているかどうかをしっかりと確認しましょう。
社内または社外の社労士に相談する
助成金制度に関しては、法律も関係してくることから初心者には理解しきれない部分もあります。「助成金制度が利用できるか知りたい」「制度についてもっと詳しく理解したい」場合は、社会保険労務士(社労士)に相談しましょう。社労士は社会保険の専門家であり、助成金制度についても詳しいプロです。社内で社労士を雇用していない場合は、助成金制度の申請実績が豊富な外部の社労士に相談するのがおすすめです。助成金制度を利用するには、さまざまなデータを資料として収集する必要があり、手続きの準備だけでも半年程度かかることがあります。利用したい制度または利用できる制度があるか相談するなら、時間に余裕を持って進めることが大切です。
助成金に関するよくあるQ&A
社員研修の助成金に関するよくあるQ&Aを紹介します。
Q.社員研修はすべて助成金の対象になりますか?
社員研修がすべて助成金の対象となるわけではありません。各助成金には受給要件と対象者が決まっており、要件を満たしていない場合は助成金を受けられません。社員研修が対象になるかどうかについては、制度の専門家である社労士や制度の要綱を確認しましょう。
Q.利用する助成金に合わせて研修プログラムの調整はできますか?
外部の研修機関であっても、利用したい助成金に応じて研修プログラムの調整を相談することは可能です。内容そのものの変更は難しいですが、助成金の対象となる研修内容とするために実施方法やカリキュラムの順序を入れ替える等の対応は検討可能です。
Q.助成金が支給されないケースはどのような場合ですか?
助成金を申請したとしても、対象となる人材やカリキュラム、提出書類等に不備があれば支給されない場合が考えられます。この点については該当する申請機関に確認のうえ、プログラムや申請書類に問題がないことを確認することをおすすめします。
Q.助成金の利用について相談することはできますか?
助成金の利用については、原則として社労士や申請機関に相談してください。助成金の利用が可能な社員研修は提供可能ですが、企業の人員や利用したい制度によって対応は変わります。ただし、より効果的な社員研修を実施するための相談に関しては、ヒアリングを行ったうえで最適な提案をさせていだきます。
Q.助成金対象者が退職または解雇された場合はどうなりますか?
助成金制度によっては支給が難しいケースや、支給されないケースが考えられます。例えば、人材開発支援助成金の正社員化支援の場合、正社員化する直前に解雇したり、正社員化後すぐに退職したりすると支給されない可能性が高いです。この点は助成金制度によっても受給要件が異なるため、利用する制度がどのような要件になっているかの確認をおすすめします。
まとめ
人材育成のための社員研修は社員の成長とキャリアアップ、組織の業務効率化と生産性向上につながる重要な施策です。しかし企業にとっては多くのコストが発生することから悩みの種でもあります。そこで企業の財政負担を軽減するためにも、各種助成金制度を利用することは大切です。どのような助成金制度があるか知りたい担当者は、社労士に相談してみることをおすすめします。そして効果的な社員研修と助成金制度に適したプログラムを求めるのであれば、ぜひユーキャンにご相談ください。