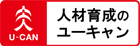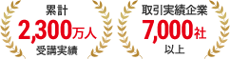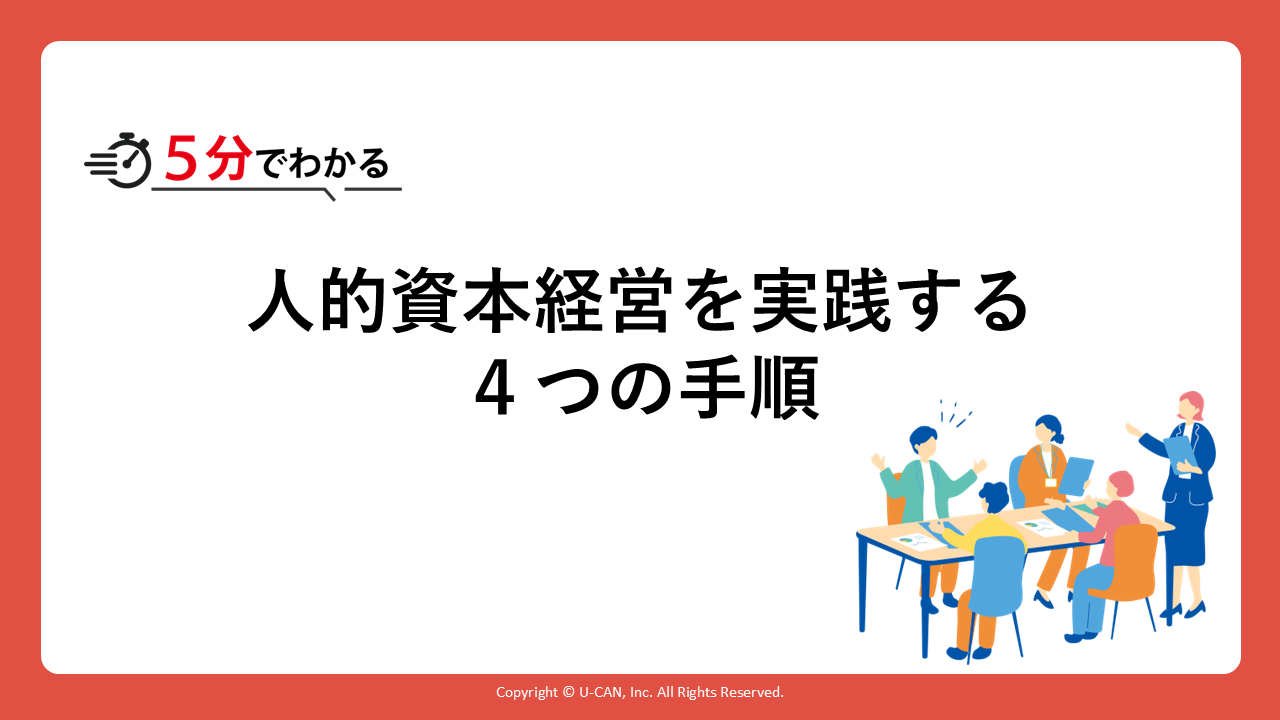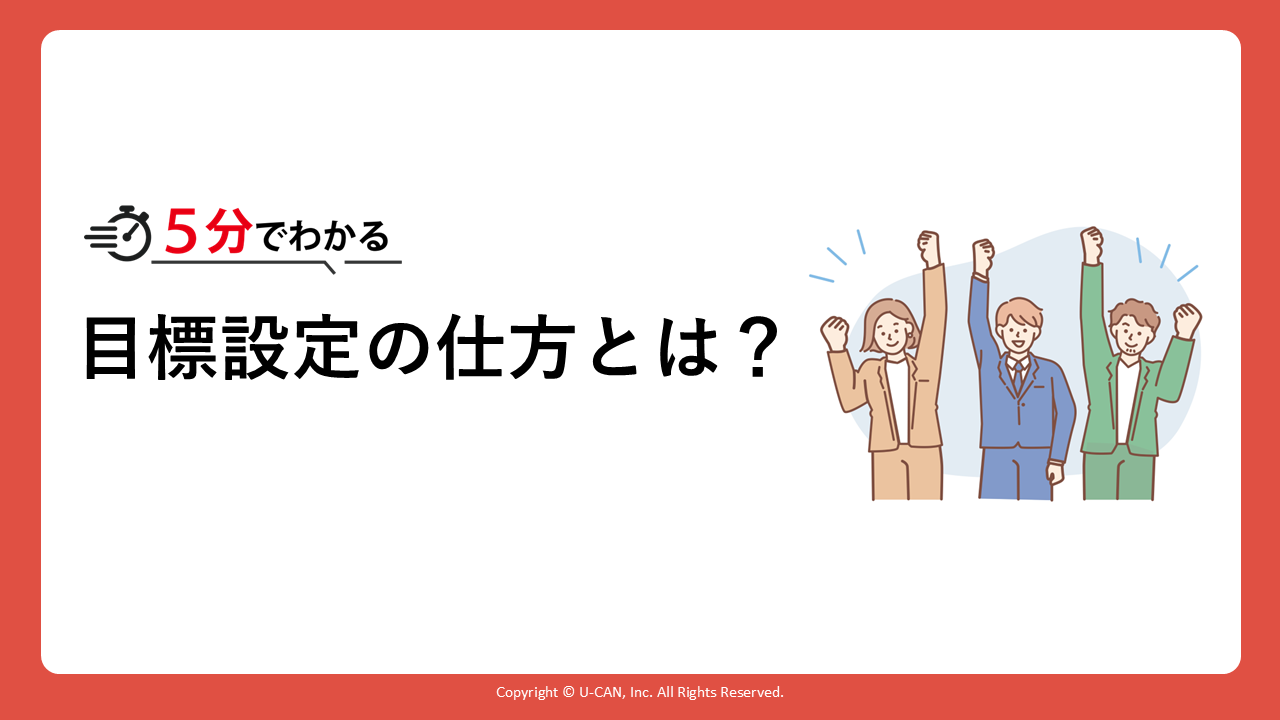財務の業務内容とは?
企業の財務担当者は、企業のお金を運用するための方針策定や資金調達、リソースの配分などさまざまな役割があります。主な業務内容は次の通りです。
・財務戦略の立案
・予算編成・管理
・資金調達
・企業価値の向上
・余剰資金の運用
・監査法人の対応
それぞれの業務内容について詳しく紹介します。
財務戦略の立案
財務戦略の立案とは、企業が持続的に成長し、安定した経営を維持するために資金調達・運用・管理の方針を決定する業務です。 中長期的な視点で最適な資金計画を立てることが目的です。具体的には資金調達戦略(銀行融資、社債発行、増資など)、資本構成の最適化(自己資本と優良のバランス調整)、投資戦略(設備投資やM&Aの計画)などが含まれます。また、キャッシュフローの管理やリスク管理も財務担当者にとって重要な要素です。財務戦略は企業の成長や経営の安定に大きく影響するため、経営と連携しながら慎重に立案していくことが求められます。効果的な財務戦略の立案は企業の成長につながり、企業の競争力を高めることができます。
予算編成・管理
予算編成・管理とは、企業が一定期間(通常は年度単位)の収入や支出を計画し、実際の業績と比較しながら適切に運営するための業務です。 事業計画や過去の実績、経済の動向を分析しながら、その年の売上目標やコストを決定します。具体的には、まず予算編成の段階で、各部門の経費や投資計画を取りまとめ、経営戦略と整合性のある予算を立てます。また予測と実績を比較し、乖離が生じた場合には原因を分析し、修正対応を行うことも重要な業務です。適切な予算編成・管理を行うことで、組織内のコストの最適化、リスクの低減、資金の効率活用につながり、企業の持続的な成長と経営の安定を支える業務となります。
資金調達
資金調達とは、企業が事業運営や投資を行うために必要な資金を確保する業務です。そして財務担当者は資金の必要性を分析し、最適な調達方法を選択して実行します。資金調達の方法には「自己資本」と「他人資本」の2つがあります。自己資本は株式発行などで投資家から資金を調達する方法であり、債務が発生しないため運営の安定性が高い方法です。一方の他人資本は、銀行融資や社債発行などの借入による資金調達であり、一度に大量の資金を確保できますが、利息の支払いや義務が発生するデメリットがあります。財務部門は事業の状況や市場の変化を踏まえながら、コストやリスクを考慮して適切な資金調達方法を選択し、企業の成長や健全性を維持する重要な役割を担っています。
企業価値の向上
財務担当者の重要な業務の一つに、企業価値の向上もあります。 企業価値を高めるためには、収益性を向上させるだけでなく、経営戦略を最適化し資本効率を高めることが求められます。企業価値の向上に関連した財務担当者の具体的な業務としては、投資戦略の立案と実行が挙げられます。成長が見込まれる事業への資金配分を最適化し、ROI(投資利益率)を最大化することが重要な役割です。またM&A(企業の合併・買収)や新規事業への投資を計画し、持続的な成長を支援する役割も担っております。さらに、株主や投資家との関係強化も担当者の役割の一つです。IR(投資家向け広報)活動を正しく伝えることで、投資家からの信頼性を高め、株価の安定と向上を図ります。こうした取り組みにより企業の収益力や信用力を高め、長期的な企業価値の向上に貢献するのが財務担当者の仕事です。
余剰資金の運用
企業の財務担当者は、残余資金の適切な運用、企業の収益を最大化、経営の安定性を高める役割を担っています。余剰資金とは非常用に必要分を差し引いた後に残る資金のことで、基本的には当面の間使う予定のない資金です。具体的な運用手法としては、短期・長期の金融商品への投資が挙げられます。短期的な運用方法なら安全性の高い定期預金、MMF(マネー・マーケット・ファンド)などに投資し、資金の流動性を確保しながら低リスクで運用する方法があります。一方の長期的な運用方法は株式や社債、不動産投資などを活用し、より長期かつ高い利率での運用を目指すこともあります。他にも企業の戦略によっては、自社株買いや設備投資といった形で余剰資金を活用するのも有効な方法です。
監査法人の対応
企業の財務担当者は、監査法人への対応、報告書の透明性や正確性を確保し、企業の社会的信用を向上させる役割も担っています。 査法人は組織内のお金の流れやガバナンスが適正かどうかをチェックする機関であり、新興企業や一定規模以上の企業は、定期的な外部監査を受けなければなりません。監財務担当者の具体的な業務としては、決算書や財務データの提供、内部統制の確認、会計処理の説明などとなります。監査法人は企業の会計処理が適切かどうかを厳しくチェックするため、財務担当者は監査人の細かな質問にも適切に対応し、必要に応じて資料も提供しなければなりません。また監査法人からの指摘事項については、適切な修正や改善策を実施することも求められます。こうした業務を適切に実行することで、企業の健全性を高め、投資家や取引先からの信頼を高めることにつながります。
経理・会計との違いとは?
財務の仕事と経理・会計との業務内容の違いについて紹介します。
経理との違い
財務と経理はどちらも企業のお金を管理する重要な業務ですが、それぞれの役割や目的には明確な違いがあります。経理は企業が過去に使用したお金の出納状況を正確に記録し、管理する業務を担っています。主な業務は、売上や支出の記帳、請求書類発行・管理、給与計算、決算書類作成などです。日別では売上や仕入データの帳簿への記録、月次では1か月間の収支の集計、年次では月次の結果を集計し、決算書や確定申告書の作成も行います。そのため経理は企業の財務状況・経営状況をデータとして把握し、適正に報告するという重要な役割があります。経理の仕事は数字を素早く正確に計算・記録する能力のほか、論理的な思考で諸表を作成する能力、社内でのコミュニケーション能力などさまざまな能力が求められます。財務の仕事内容は、企業の資金調達や予算の編成・管理、企業の資金繰りの最適化、余剰資金の運用、IR、監査対応といったものです。そのため社内のキャッシュフローの管理だけでなく、対外的な折衝や投資・運用など幅広い知識を身につける必要があります。 財務の最大の目的は、企業の成長に必要な資金を確保し、効率的に運用することで経営を安定させることにあります。 こうした点が経理と財務との大きな違いとなるでしょう。
会計との違い
財務と会計も企業の資金に関わる業務ですが、それぞれの役割や目的には大きな違いがあります。まず会計は企業の経済活動を記録・管理し、経営状況を経営者に報告したり、税を正しく納付するための会計を行う役割を担っています。つまり会計は、企業の経済活動を会計基準に基づいて記録し、必要に応じて経営層に報告する業務です。具体的な業務には、日々の取引の記録、決算書(貸借対照表・損益計算書など)の作成、税務申告、諸表の作成と分析などが含まれます。会計の目的は、企業の財産状況を正確に把握し、外部の利害関係者(株主、投資家、取引先など)に対して適切に報告することです。特に管理会計は、経営判断のための内部資料作成に重点を置いています。一方の財務は、企業の資金調達・運用に関する計画や管理を行い、経営の安定と成長を支える業務です。主な業務には、資金調達(銀行融資、社債発行、株式発行など)、資金繰りと管理、投資戦略の策定、リスク管理、キャッシュフローの最適化などが含まれます。財務の目的は、企業の持続的な成長を支えるために必要な資金を適切に確保し、効率的に運用することです。長期的な経営戦略に沿った資金計画が求められる点が、会計業務との大きな違いといえるでしょう。
財務業務の必要性とは?
企業の財務業務がなぜ必要となるのか、3つのポイントから解説します。
・経営の安定性に関わっている
・経理・会計との役割の違い
・財務担当者がいない中小企業が多い
経営の安定性に関わっている
財務の業務は、企業の経営を安定させるために必要不可欠です。企業運営には日々の資金繰りや長期的な資金計画が必要であり、財務担当者は適切な資金管理を行い、事業を安定して継続できるようにする役割を担っています。例えば売上の変動や景気の同行を考慮しながら、無駄なコストを削減し、必要な資金を確保することで企業の戦略基盤を強化することも財務担当者の業務です。また必要に応じて資金調達を行い、安定した経営の下支えと資源の配分を行う役割も担っています。企業の利益が落ち込んでいるときには資金ショートや経営に係るリスクを検討し、最適なコスト削減案の低減と実行も求められるでしょう。そのため財務担当者は企業の安定経営において、資金面で重要な役割を果たしています。
経理・会計との役割の違い
企業の財務担当者は、経理・会計とは異なる視点で企業の資金を管理する役割を果たします。経理・会計は、主に過去の取引や支出から決算書の作成を担当し、諸表を正確に作成することを目的とします。一方の財務は資金の運用、戦略の立案など、企業の成長と安定性を維持するのが役割です。財務担当者が適切な資金計画を立て、資金繰りや投資判断を行うことで、企業の経営基盤強化につながります。そのため財務・経理・会計はそれぞれ異なる役割を担っていますが、いずれも企業の健全性を維持するために必要な存在です。
財務担当者がいない中小企業が多い
多くの中小企業では、財務部門を設置せず、経理や会計部門が資金管理を兼務しています。その理由は、財務に関する知識を持つ人材は人件費が高く、中小企業が雇用するにはコスト面で大きな負担になるためです。しかしその結果として、必要な資金調達が難しくなれば、倒産のリスクを高める原因となります。知識と経験のある財務担当者を雇用することで、資金調達の選択肢を増やし、投資や事業運転資金の計画を正しく考えられるようになり、企業の成長を強く支えることができます。そのため 経営の安定性を向上させる意味でも、現代のビジネスにおいて財務部門は必要不可欠な存在です。
財務研修の目的
財務研修では、財務担当者として働くための基礎知識や財務諸表の読み方、データに基づく分析方法などを理解することが目的です。次の3つが研修の目的となります
・財務に求められる基礎知識を習得する
・財務諸表の読み方を理解する
・数値に基づく財務分析方法を習得する
財務に求められる基礎知識を習得する
財務研修を実施する目的の一つは、担当者に財務の基礎知識を習得してもらい、正確な意思決定に役立ててもらうことです。財務担当者が業務をこなすには、財務諸表や貸借対照表、キャッシュフロー、売上高総利益率、営業利益率などさまざまな用語と意味を理解する必要があります。特に、管理職や経営層を対象に資金調達や経営戦略を伝える際には、財務の基本知識に基づいた説明を行い、利益やコスト、投資判断を適切に行う能力が求められます。そのため財務担当者が資金面から企業を支えるには、財務に求められる基礎知識の習得が重要です。
財務諸表の読み方を理解する
財務研修を実施することで、財務諸表(貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書)を正しく理解できるようになり、経営判断に生かすことも重要な目的です。財務諸表は企業の経営状況を客観的に示す指標であり、利益の増減や資金繰りの健全性、経営状況を把握するために役立ちます。財務諸表の読み方を理解できれば、どこのコスト削減を進めればよいかが判断できるようになり、投資判断でも意思決定がスムーズになります。財務研修を通して、財務担当者が諸表を読むスキルを身につけることで、企業経営の安定に力を発揮してくれるでしょう。
数値に基づく財務分析方法を習得する
企業が財務研修を行う目的の一つとして、財務諸表の数値をベースに企業の状況を分析するスキルを習得することです。具体的にはROE(自己資本利益率)などの指標を活用して、企業の健全性や成長性を評価できる能力が求められます。分析方法で代表的なものは収益性分析や安全性分析、生産性分析、成長性分析、効率性分析などです。目的に応じた適切な分析方法を使うことで、資金繰りの改善や無駄なコストの削減、投資の最適化、生産性の向上など、経営に直結する重要な判断がしやすくなります。
財務研修が必要な職種・従業員
財務研修が必要な職種、対象の従業員について解説します。
会計・経理担当者
会計・経理担当者は企業の財務データを日常的に扱うため、深い財務知識を持つことで業務の効率と生産性向上につながります。財務研修を通して、財務に関する基本知識を学べば、数値が何を意味するのか、データから何が考えられるのかを自然と理解できるようになるでしょう。また研修により財務分析や資金繰りの改善提案を行うスキルを習得することで、経営陣の意思決定をサポートできるようにもなります。会計・経理担当者が財務の知識・スキルを身につけることで、より戦略的な視点を持ち、企業の成長に貢献する人材となることが期待できます。
管理職
管理職は事業部門の運営や意思決定に関与するため、財務の知識を持つことで、コスト面や収支を意識した判断が可能になります。 例えば予算管理やコスト削減、投資判断などの場面では、財務の基本知識があることで的確な決定を下しやすくなるでしょう。また財務研修を受けることで、事業の収益性や将来的なリスクを数値で把握し、経営戦略とリンクさせた部門運営もできます。財務の知識を生かした働き方により、組織全体の重要な意思決定や収益性の向上にも貢献できるようになります。
経営者
経営者は企業の持続的な成長を支えるために、財務知識が必要な立場です。財務研修を受講することで、資金繰りや利益管理、投資判断などの経営戦略を数値に基づいて判断できるようになります。また銀行や投資家との交渉において、知識を持つことで根拠に基づいた信頼性が高まり、資金調達がスムーズに進むことも期待できます。企業の経営を担う立場にある経営者だからこそ、財務知識研修の受講は不可欠です。
財務研修の注意点
財務研修を実施する際は、次の注意点を意識すべきです。
・受講者に合わせたプログラムを選択する
・実践や演習も含まれたプログラムにする
財務研修は知識だけでは現場で力を発揮しにくいため、実践を想定したプログラムで実力をつけてもらうことが非常に重要です。
受講者に合わせたプログラムを選択する
財務研修を効果的に実施するためには、受講者の得意分野やスキルレベルに応じたプログラムを選択することが重要です。 財務担当者には資金調達やその戦略、諸表の読み方、コスト管理、データの分析など、財務にはさまざまな知識が必要です。そして、財務研修を受ける人の立場によっても必要な知識は異なります。一律の内容では、財務初心者には難しすぎたり経験者には物足りなかったりするため、適切なカリキュラム設定が必要です。受講者に適した研修を提供することで、実務に即した内容となり、学びをすぐに活かせるメリットもあります。また受講者が自分の業務をイメージしながら学ぶことで、知識への理解度が向上し、研修の効果も最大化されます。受講者の目的に合った内容と方法で必要な対象に必要な財務知識を学んでもらうことにより、組織全体の意識向上へとつながり、パフォーマンスも向上するでしょう。
実践や演習も含まれたプログラムにする
財務研修を効果的に実施するためには、座学だけでなく実践的な演習を取り入れることも重要です。実践を想定したシミュレーションを行うことで、実務ですぐに活用できるスキルを養うことができます。例えば財務諸表の分析を実際に行うことで、数値の見方や課題発見能力の向上につながります。また企業の経営状況を踏まえて意思決定を行う場合にも、実践的な課題をこなしていくことで判断力が鍛えられ、迅速かつ的確な意思決定が可能です。このように研修内容に実践的な要素を組み込むことで、受講者が実務ですぐに活かせるスキルを身につけられ、効率的な企業の資金管理能力の強化が見込めます。
財務研修のカリキュラム一例
財務研修を実施する場合の一連の流れについて解説します。
企業課題の洗い出し
財務研修を行うためには、まず自社にどのような課題があるか洗い出す作業が必要です。財務に関係する会計・経理・財務部門はもちろん、人事担当者、人材育成担当者、営業部門、管理職など幅広い層から財務に関する課題や意見をヒアリングしましょう。課題の洗い出しにより多くの問題点が見えてくることが予想されるため、同時に優先順位をつける作業も必要です。
研修機関の選定
社内に財務の専門家がいる場合を除き、専門的な教育を求めるなら研修機関に依頼するのがおすすめです。財務研修は実施することが目的ではなく、実際に企業の資金運用やIR、財務諸表の分析を行う知識とスキルを身につけるためのものです。複数の研修機関や会社を比較し、その中から自社の課題解決に役立つノウハウやプログラムの多いところを選択しましょう。また研修機関を選ぶ際は提供しているプログラムのほか、金額、講師、評判、実績など多角的な視点で優れている会社を選ぶことが大切です。
目的・対象者の決定
次に財務研修で何を目的にするのか、そのために誰を対象にするのかも決定します。財務研修を全社員対象にしても、所属部署によっては知識・スキルを使う機会がなく、忘れてしまう社員も現れます。そのため 研修を通じて財務のどのような課題を解決したいのかを明確にし、解決のために主力となって働く人材を対象とすることが重要です。例えば経営戦略の立案やステークホルダーとの関係性を重視するなら経営層、IRや財務諸表からの分析能力を向上するなら財務・会計・経理担当者がよいでしょう。また対象者の知識量やスキル、実務の内容に応じて考慮することで、より効果的な研修を実現できます。
カリキュラムの設計
目的と対象者が決定したら、実施するカリキュラムを設計します。カリキュラムを設計する際は、回数や期間、場所、1回あたりの時間なども細かく設定しましょう。研修の期間については、対象者によっても意識すべきです。例えば新入社員向けに行うなら、他の新入社員研修と一緒に行うことも想定して期間を長くしてもよいでしょう。一方すでに働いている社員や管理職以上を対象にする場合、業務の都合上時間を確保するのが難しいことも想定し、1日で終了できるものにするのがおすすめです。
研修の実施
研修を実施する際は、集合研修かオンライン研修か、eラーニングかも重要になります。知識のインプットを中心に行うならeラーニングがおすすめですが、実践的なスキルを磨くなら集合研修やオンライン研修が向いています。特に財務研修では実践を意識した学びが重要になるため、講師や他の受講者との双方向の情報交換ができる方法で行うのがよいでしょう。
研修の振り返り
研修を実施したら、研修内容の振り返りやアフターフォローも重要です。振り返りを行うことで知識やスキルの定着率が高まり、実務ですぐに活用できる武器となります。振り返りは上司との1on1や受講者同士での交流会など、学びの内容を深められる環境を設定して行うと効果的です。
まとめ
財務とは企業のお金を扱う重要な業務であり、会社を安定的に運営し、拡大していくには欠かせない仕事です。同じようにお金を扱う会計や経理とは違い、投資や資金調達、IRなどを通して資金を運用し、会社が使えるお金を増やすのも財務の役割です。企業規模の大小を問わず、事業の安定性と成長性を高めたいなら財務部門の設置は必要になります。社内に財務のノウハウやスキルを持つ人材を育成するなら、個別性に合わせた財務研修が提供できるユーキャンにご相談ください。