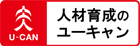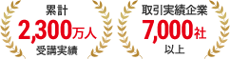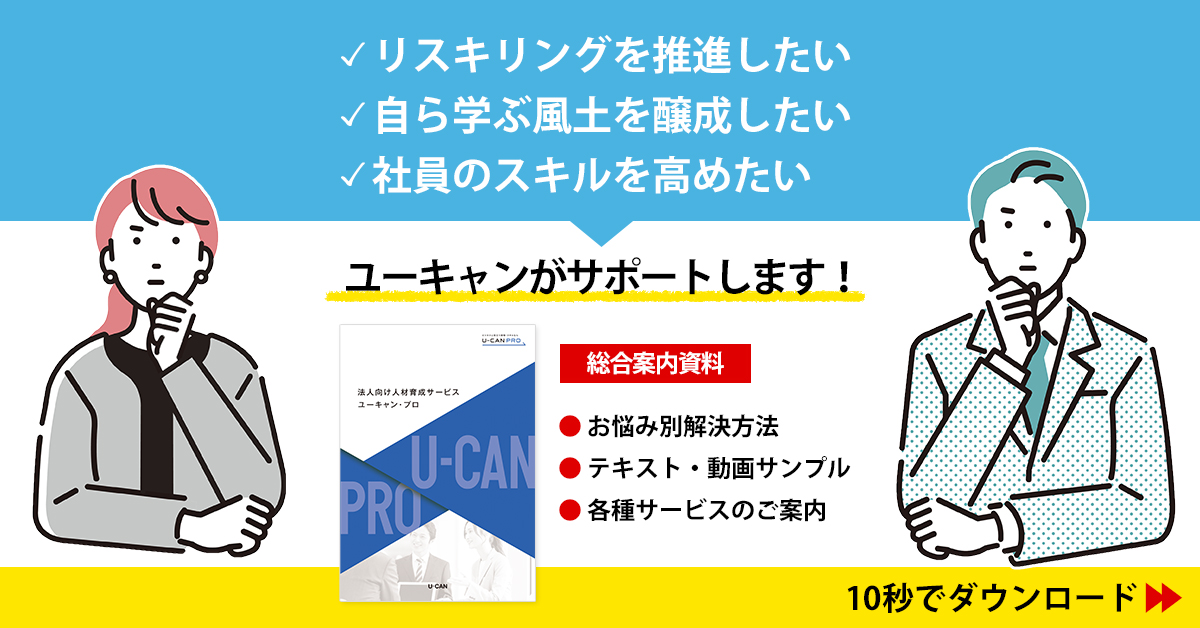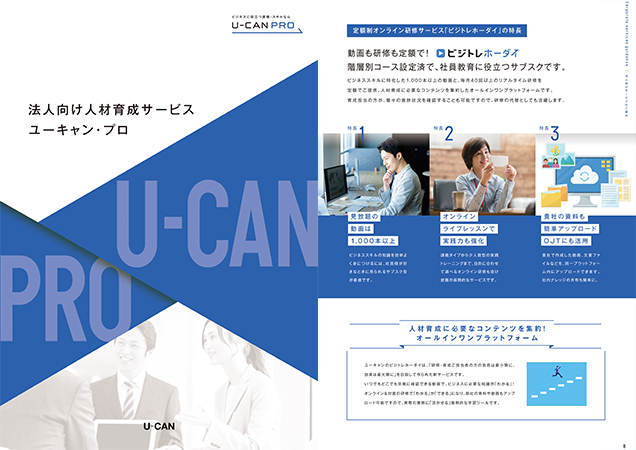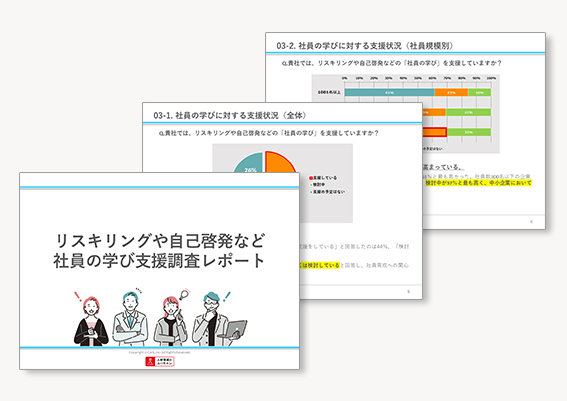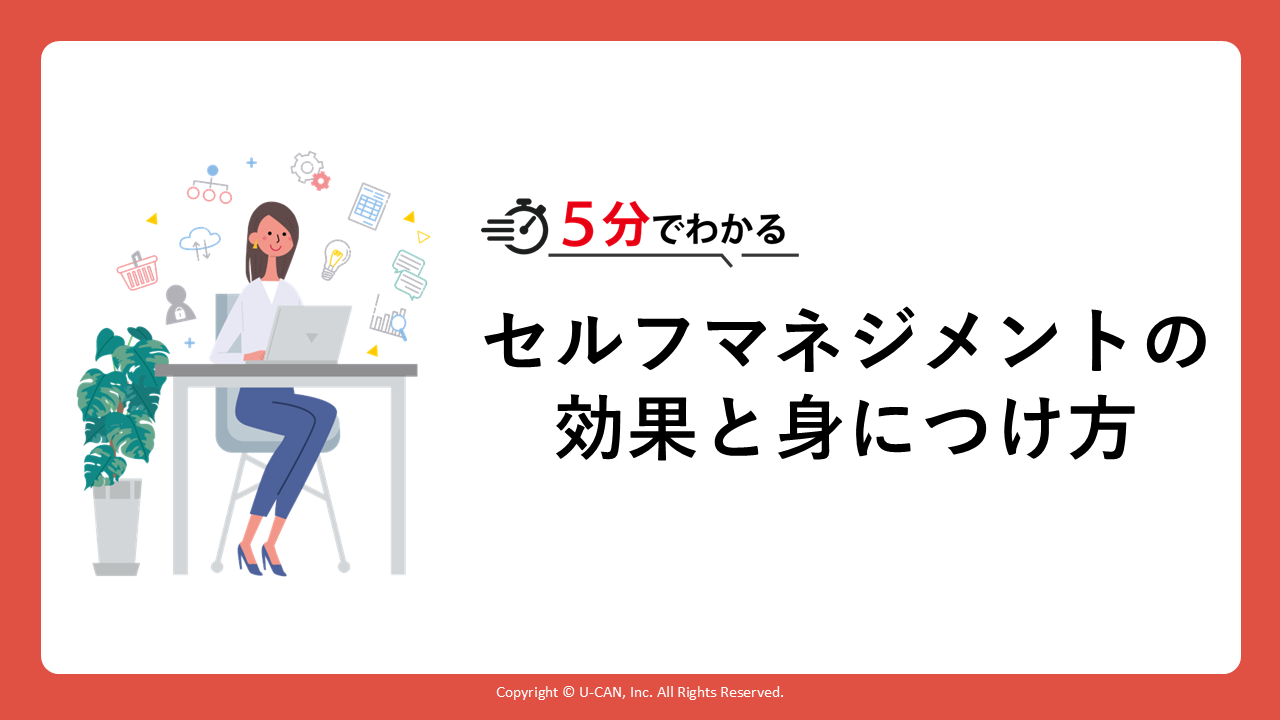ガバナンスの概要
ガバナンスとは、日本語では統治・支配・管理などと訳されます。ビジネスシーンにおいては、企業のガバナンスとしてコーポレートガバナンスがあります。
コーポレートガバナンスは、健全な企業経営に基づき、企業が組織ぐるみで不祥事を起こすのを防いだり、長期的な企業価値の向上によって、企業のステークホルダーの利益を最大化するのが目的です。
そのために、管理体制の構築や企業の内部統治を進めます。具体的な内容としては、取締役と執行役を分離する、社外取締役の設置、役割と指示系統を明確にするための仕組みを作る、内部統制やリスクマネジメントに特化した専門部署の設置などです。
ガバナンスと類似する用語との違い
ガバナンスとは組織を統治する仕組みであり、企業の不正や不祥事を防止する体制を意味します。ビジネスシーンではガバナンスに類似した言葉が複数存在するため、それぞれの違いを解説します。
コンプライアンス
コンプライアンスは、ガバナンスと混同されやすい言葉のひとつです。コンプライアンスは日本語で、追従、応諾、即応などを意味し、ビジネスシーンでは企業活動における法令遵守のほか、倫理観や公序良俗などの社会的な規範の遵守なども含まれます。
コンプライアンスは意識や姿勢といったニュアンスであり、それらを継続的に維持したり改善を目指す仕組みを作ったりするのがガバナンスです。
リスクマネジメント
リスクマネジメントもガバナンスと混同されやすい言葉です。リスクマネジメントは管理手法であり、経営上のリスクを事前に把握し、予防や対策ができる体制を整えるための一連のプロセスを指します。
一方で、ガバナンスは経営において不正や問題が発生しないように、監視したり統制したりするための仕組みを指すため、内実としては手法ではなく機能です。
内部監査
内部監査も、ガバナンスと似ている言葉のひとつです。内部監査とは、会社の不正防止や業務効率化を目的に経営活動への支援を行う部門のことです。
内部監査は独立性を保ちやすい立場上、ガバナンスやリスクマネジメントのプロセスの有効性を客観的に評価しやすく、ガバナンスの維持や強化において重要な役割を担います。
内部統制
内部統制とは、企業が業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、法令遵守などを確保するための仕組みです。経営者が組織全体のリスクを管理し、不正やミスを防止・早期発見するために設計・運用されます。一方ガバナンス(企業統治)は、企業の経営が株主や利害関係者の期待に応えるよう経営の監督や意思決定の枠組みを整える仕組みであり、取締役会や監査役などが代表的です。両者は密接に関連していますが、内部統制は「仕組みの運用」、ガバナンスは「組織全体の監督体制」に重点を置いている点で異なります。
ガバナンスを理解するうえで知っておくべき用語
ガバナンスの意味を理解するうえで、知っておくべき用語もいくつかあります。ガバナンスに関連する用語として、5つを具体的に解説します。
①コーポレートガバナンス・コード
上場企業には、コーポレートガバナンス・コードが求められます。コーポレートガバナンス・コードは、東京証券取引所と金融庁が中心に取りまとめたもので、2015年に公表されました。コーポレートガバナンス・コードの定義は下記の通りです。
コーポレートガバナンスとは、会社が、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえたうえで、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みを意味する。
なお、2021年6月に改訂された際に、企業とステークホルダーの適切な関係性や、組織として望ましい状態についても記載されました。改定の内容が以下のようになります。
- ・株主の権利、平等性の確保
- ・株主以外のステークホルダーとの適切な協働
- ・適切な情報開示と透明性の確保
- ・取締役会等の責務
- ・株主との対話
取締役会などが正常に機能を発揮した上で、情報を適切に開示して不祥事や不正を隠蔽するのを防ぐ、株主を筆頭に各種ステークホルダーへ誠実に向き合うといった内容となっています。
参考:コーポレートガバナンス・コード ~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~
②ガバナンス効果
ガバナンス効果とは、企業における適切な統治体制や監督機能がもたらす成果や利点を指します。具体的には不正行為の防止や経営の透明性向上、経営判断の健全化、ステークホルダーからの信頼獲得などです。ガバナンスが機能することで企業は顧客からの信頼性を高め、長期的な価値向上や持続的な成長を実現しやすくなります。また外部からの投資を呼び込みやすくなるなど、資本市場での評価向上にもつながります。ガバナンス効果は、企業の健全経営とリスクマネジメントの基盤となる重要な要素です。
③ガバナンス強化
ガバナンス強化とは、企業の経営において意思決定の透明性・公平性を高め、経営監督機能を向上させるための取り組みを指します。具体的には社外取締役の活用、取締役会の機能見直し、内部統制やリスク管理体制の整備、情報開示の充実などです。ガバナンスを強化することで、不正や不祥事の防止、経営の健全性向上、企業価値の持続的向上が期待されます。また投資家や社会からの信頼を高める効果もあり、企業の中長期的な成長戦略において重要な要素とされています。
④ガバナンスプロセス
ガバナンスプロセスとは、企業が適切な統治を行うために設ける一連の仕組みや手続きを指します。具体的には経営陣の意思決定プロセス、取締役会の監督機能、内部監査やコンプライアンス体制、情報開示の方法などです。これらを通じて企業は意思決定や財務の透明性、事業への説明責任を確保し、ステークホルダーの信頼を得ながら健全な経営を実現します。
⑤ガバナンスモデル
ガバナンスモデルとは、企業や組織がどのような枠組みで経営を監督・統治するかを示す基本的な構造や仕組みのことです。取締役会や監査役会の構成、社外取締役の役割、権限分担、意思決定の流れなどが含まれます。代表的なモデルには「監査等委員会設置会社」「指名委員会等設置会社」などがあり、企業は自社の特性や経営課題に応じたモデルを選択し、ガバナンスの有効性を高めています。
ガバナンスが注目される背景
カバナンスが注目されるようになった背景には、2000年頃に複数の大企業における不祥事が相次いで起きたことがあります。不祥事の内容は情報改ざんや粉飾決済、労働基準法違反など多岐に渡りました。
不祥事によって企業の業績低迷や信頼の喪失が起こると、株価の下落に繋がり、株主が損失を被るため、対策としてガバナンスに注目が集まりました。 その他にも、日本企業の株価指数が諸外国と比べて低くなっており、経済的な優位性を失っているのを改善する目的もあります。投資家や株主は、企業の持続的成長や中長期的な企業価値向上を評価する上で、ESG(環境・社会・ガバナンス)を重視する傾向になり、企業には、公正で透明性の高い企業経営が求められています。
ガバナンスを強化するメリット
ガバナンスを強化することで、さまざまなメリットが期待できます。
- ・株主からの信頼が高まる
- ・企業価値が上昇する
- ・財務強化に繋がる
- ・企業の不正防止に繋がる
- ・企業の持続的な成長力や競争力の向上
下記でそれぞれの詳細について解説するので、参考にしてみてください。
株主からの信頼が高まる
ガバナンスを強化するメリットとして、株主からの信頼が高まることが挙げられます。コーポレートガバナンスに取り組んでいる企業は、監視体制が行き渡っていて自浄作用が働いています。経営状態が健全で、不祥事や不正などが起こりにくい環境を築けているという理由から、株主からの信頼が高くなりやすいです。
株主からの信頼が高まれば、さらに投資してもらえる可能性が上がるのに加え、株価の上昇にも繋がります。
企業価値が上昇する
ガバナンスを強化するメリットとして、企業価値の上昇も挙げられます。法律や規則、倫理を守る企業として認知されるため、社会的信用が向上して対外的な企業評価が上がり、中長期的な企業価値の向上にも繋がります。
優良企業として成長する可能性が高いと評価されれば、資金や人材が集まりやすくなって経営が安定し、株主やステークホルダーの利益を守りやすくなります。
財務強化に繋がる
財務強化に繋がる点も、ガバナンスを強化するメリットのひとつです。 金融機関は、融資や出資によってリターンが得られるか審査を行いますが、コーポレートガバナンスに則った情報開示を行っている企業は信頼性が高いとして印象が良くなります。 審査が有利になれば、金融機関からの融資や出資によって財務状況が安定し、より健全な経営状態へと繋げられる可能性が高いです。
企業の不正防止に繋がる
企業の不正防止に繋がるというメリットもあります。コーポレートガバナンスの強化によって、企業内での監視体制が行き届いている状態になれば、組織内部の腐敗や企業の私物化、不正会計や横領などの不祥事を防止しやすくなります。
不祥事を防止できれば、株主や顧客、従業員など各関係者への損失を抑えることにも繋がり、健全な経営が実現可能です。
企業の持続的な成長力や競争力の向上
企業の持続的な成長力や競争力を向上させられるのも、ガバナンスを強化する大きなメリットです。企業経営が円滑に進めば、中長期的に成長力を向上させることができ、新規事業への投資や優秀な人材の獲得もしやすくなります。
健全な経営は安定的な雇用を可能にします。安定的な雇用は従業員にとって強力な後ろ盾となってモチベーションや生産性の向上に繋がり、さらなる企業の成長や競争力の向上に繋がります。
ガバナンスを強化するデメリット
ガバナンスの強化はデメリットが発生する場合もあります。具体的なデメリットは下記の4つです。
- ・企業活動が鈍くなる
- ・オーナー企業では機能しにくい
- ・企業の成長の邪魔になる
- ・ビジネスチャンスを逃す可能性がある
企業活動が鈍くなる
ガバナンスを強化するデメリットとして挙げられるのが、企業活動が鈍くなる点です。現場や経営陣の視点では業務や事業が順調に進んでいたとしても、監視側に問題や改善点があると判断されてしまうと、業務や事業を一旦ストップさせられてしまいます。
そのため、効率的かつ円滑に業務や事業を行いにくくなり、企業活動そのものが鈍くなって迅速な対応や経営が難しくなる恐れがあります。
オーナー企業では機能しにくい
ガバナンスはその特性上、株主が社長を務めるオーナー企業では機能しにくいです。また、 株主が経営者の一族であるファミリー企業などの場合も、閉鎖的な体制や環境になりやすく、取締役や社外のステークホルダーなど、外部からの監視や改善が望みにくいです。
企業の成長の邪魔になる
ガバナンスを強化するデメリットとして、企業の成長の障壁になる可能性があります。コーポレートガバナンスではステークホルダーの利益が重要事項とされており、目先の利益を求められた結果、企業の成長のために必要な長期的な経営戦略を実行するのが難しくなります。
ビジネスチャンスを逃す可能性がある
ビジネスチャンスを逃す可能性があるのも、ガバナンスを強化するデメリットのひとつです。なぜなら、取締役によって企業戦略の方向性などを明確にした中長期経営戦略の提示が求められますが、作成には時間がかかる場合が多く、その間に、ビジネスチャンスを逃してしまう可能性があるからです。
ガバナンスを軽視すると起こるリスク
ガバナンスを軽視すると起こるリスクは下記の通りです。
- ・不正や不祥事による信用の低下
- ・グローバル化への対応が遅れる
それぞれの詳細について解説します。
不正や不祥事による信用の低下
ガバナンスを軽視することで起こる可能性があるリスクとして、不正や不祥事による企業への信用の低下が挙げられます。 ガバナンスが機能していないと企業内での監視体制が適切に機能せず、内部組織が腐敗しても自浄作用が働かないため、不正や不祥事が発生する可能性が高まります。 また、企業の管理体制が充分に届いていないと、不正や不祥事に早急かつ適切に対処しにくいため、さらなる信用の低下に繋がりかねません。
グローバル化への対応が遅れる
グローバル化への対応が遅れるのも、ガバナンスを軽視すると起こるリスクのひとつです。経営の健全性や透明性が確保できず、金融機関からの融資や投資家からの投資が受けにくくなることや、業務効率や生産性に問題を抱えることで、市場競争力のマイナスになります。
ガバナンスを強化する具体的な施策
ガバナンスを強化する施策にはさまざまな方法があります。
- ・内部統制の構築や強化をする
- ・第三者視点の監視体制を整える
- ・コンプライアンスを守る
- ・コーポレートガバナンスを意識させる
ここからは、4つの施策を具体的に解説していきます。
内部統制の構築や強化をする
ガバナンスを強化する具体的な施策として挙げられるのが、内部統制の構築や強化です。内部統制とは、企業が達成するべき目的や目標に合わせてルールや仕組みを整備し、適切に運用できる状態にすることです。
取締役会などの組織構造を見直す、リスクの洗い出しや対応策を用意するなどにより、組織が適切な統治を行いやすくなります。
第三者視点の監視体制を整える
第三者視点の監視体制を整えるのも、ガバナンスを強化する具体的な施策のひとつです。社外取締役や社外監査役などの第三者による監査は、自社だけでは察知しにくい問題点や不適切なルールなどを発見しやすくなります。
内部からは指摘しにくい雰囲気があったり、隠蔽のために圧力をかけられるといった不安要素も少ないため、企業経営の透明性や信頼性の向上に繋がります。
コンプライアンスを守る
ガバナンスを強化する具体的な施策として、コンプライアンスを守ることが挙げられます。従業員が不正をしやすい環境になるのを防ぐためです。
具体的な対策には、企業の行動規範の策定、社内リスクの洗い出しと管理、社員教育や研修、コンプライアンス委員会の設置といった監視体制の整備などがあります。
コーポレートガバナンスを意識させる
コーポレートガバナンスを意識させるのも、ガバナンスを強化する具体的な施策です。 コーポレートガバナンスは経営層に限らず、末端の従業員まで含めた企業全体に浸透させ、全員が遵守する意識を持つのが大切です。
そのために、行動規範に代表されるような、従業員の業務遂行や意思決定の判断基準となる仕組みやルールの整備をしましょう。
ガバナンスを整備する際のポイント
ガバナンスを整備する際は、さまざまなポイントを意識すべきです。ガバナンスはステークホルダーからの信頼や組織としての透明性、企業価値などに重要な施策です。具体的にどのようなポイントを押さえるべきか、5つを紹介します。
取締役会の機能強化
ガバナンスを整備するうえで重要なのが、取締役会の機能強化です。取締役会は企業の意思決定と監督を担う中核機関であり、その機能を高めることで経営の透明性と健全性が向上します。具体的には社外取締役の選任によって客観的な視点を取り入れ、多様な意見を経営に反映させることが可能です。また業績評価やリスク管理、経営陣の報酬制度などについての監督体制を明確にすることも求められます。取締役会の構成や運営方法を定期的に見直し、実効性のある体制を整えることが、持続的な企業価値の向上につながります。
内部統制の構築
ガバナンスを整備する際に重要なポイントのひとつが、内部統制の構築です。内部統制とは、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、法令遵守を確保するための仕組みです。リスクの発見と対応、不正やミスの予防、業務プロセスの標準化などを通じて、組織の健全な運営につながります。具体的には職務分掌の明確化、承認手続きの整備、監査制度の導入などが含まれます。また内部統制は一度構築して終わりではなく、定期的に評価・改善を行うことで、施策の実効性を維持し、変化に対応できる体制を整えることも欠かせません。
情報開示の充実
ガバナンスを整備する際に欠かせないのが、情報開示の充実です。情報開示とは、企業が財務情報や経営方針、リスク、ガバナンス体制などをステークホルダーに対して正確かつ適時に提供することです。これにより株主や投資家などは企業の状況を正しく把握し、適切な判断ができます。情報開示の信頼性と透明性を高めることは、企業への信頼獲得や評判の向上につながります。また近年はサステナビリティ情報や非財務情報の開示も重要視されており、統合報告書の活用や国際基準への対応も必要になるでしょう。
監査体制の強化
ガバナンスを整備するうえで重要なポイントのひとつが、監査体制の強化です。監査体制は、経営の適正性や法令遵守をチェックし、不正や誤りを早期に発見・是正する役割を担います。具体的には内部監査部門の設置や外部監査人との連携強化、監査役や監査等委員会の機能向上が求められます。さらにリスクの高い業務への重点的な監査や、監査結果を経営にフィードバックする仕組みも重要です。監査体制を強化することで、企業の透明性と信頼性が高まり、経営の健全性を支える基盤となるでしょう。
経営陣の説明責任の明確化
ガバナンスを整備する際には、経営陣の説明責任(アカウンタビリティ)の明確化が重要です。経営陣は意思決定の背景やその成果について、株主や取締役会、従業員などのステークホルダーに対して適切に説明する責任があります。この責任が果たされることで、経営の透明性が高まり、組織全体の信頼性の向上につながります。具体的には定期的な業績報告や経営方針の共有、質疑応答の場の設置などが有効です。説明責任を明確にすることで、経営判断の妥当性が検証され、ガバナンスの実効性が確保されます。
コーポレートガバナンス強化の事例
実際にコーポレートガバナンス強化を実施した企業の事例について、大手住宅総合メーカー、工業会社、大手化学メーカーの3つを紹介します。それぞれの企業が実施した内容や成果を紹介するので、参考にしてください。
大手住宅総合メーカーの事例
大手住宅総合メーカーでは4つの基本方針を定め、その内容に基づいたガバナンス強化のための基盤作りを行っています。具体的な方針や内容は下記のとおりです。
| 方針 | 具体例 |
| 経営体制及び管理・監督のあり方の再検討 | 社外取締役比率を 3 分の 1 以上に変更 取締役会へのリスク報告基準の再整備 |
| 業務執行の機動性及びリスク対応体制の強化 | 業務執行体制を事業本部制に移行 事業本部リスク管理委員会を各事業本部に設置 |
| リスク情報の収集と共有の強化 | 内部通報の外部窓口新設 有事発生時の対応体制の再整備 |
| 持続性・実行性を支える環境の強化 | 役職員へのリスク・コンプライアンス教育の継続実施 リスク・コンプライアンス関連の社内ルールの検索性の改善 |
大阪の物流市システム会社の事例
社長やCEOの選任、後継者計画において先進的な取組みを行っているとして、コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー2021を受賞した事例です。
各種プロセスの透明性や客観性を保つために、社外を中心に指名委員会に相当する諮問委員会を構成しました。社長の選任は諮問委員会において検討するといった、客観性を重視したプロセスを経ることや、外部から指摘があった場合は迅速に対応・開示を行い、ステークホルダーと真摯に向き合っている点などが受賞の理由でした。
大手化学メーカーの事例
コーポレートガバナンス強化のためにさまざまな施策を行っている、大手化学メーカーの事例です。具体的には、独立社外役員のみの会合を開催して多様な視点での議論を図っています。取締役会は執行役員へ大幅な権限委譲をしつつ、モニタリング機能を強化することで、経営陣による適切なリスクテイクと迅速な意思決定を促します。
また、 コーポレートガバナンス強化のための施策の仔細をまとめて外部へ公開するなど、透明性と公平性の高い経営を心掛けています。
まとめ
近年、企業のコンプライアンス意識が問われるさまざまな問題がニュースで取り沙汰されており、ガバナンスの重要性が再認識されています。ガバナンスを強化することは、企業で起こる大小さまざまなリスクを軽減し、未然に防ぐ効果的な施策となります。