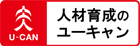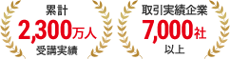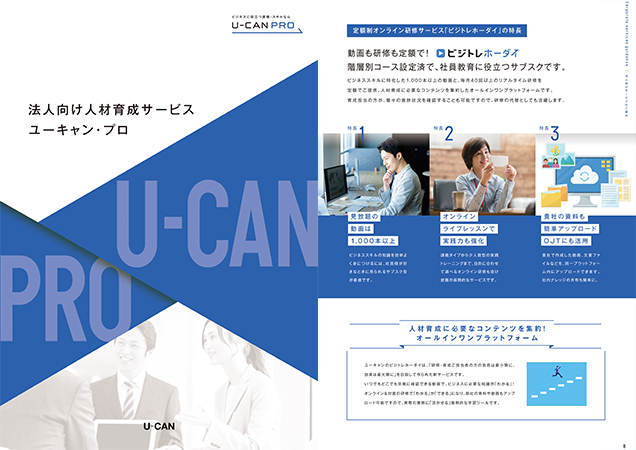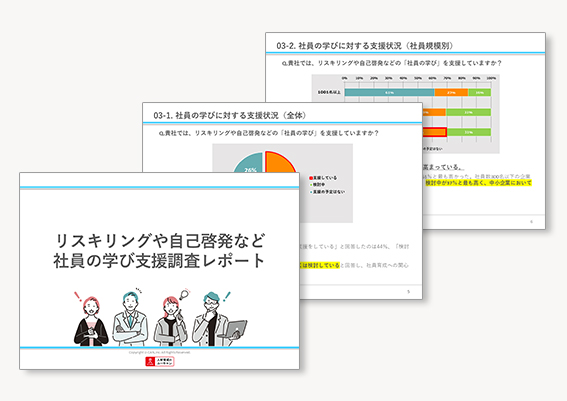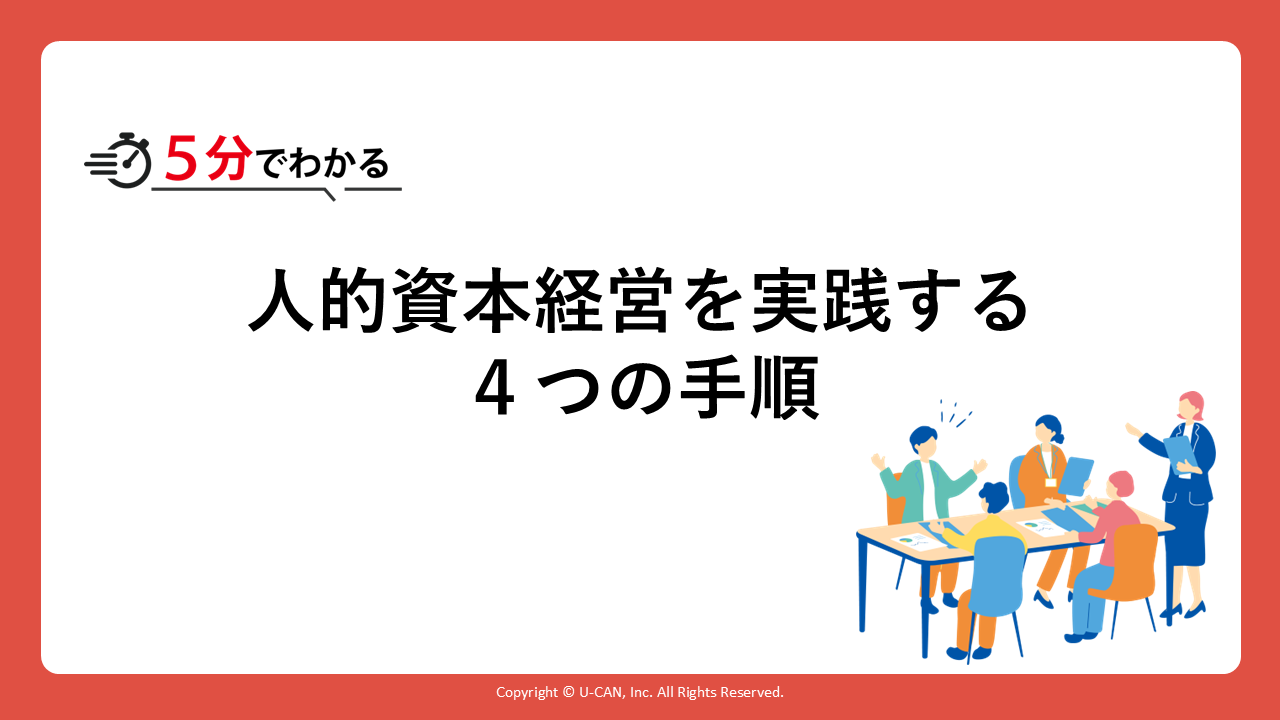高度プロフェッショナル制度とはどのような制度?
高度プロフェッショナル制度とは、特定の対象者に対して労働時間や休憩などを適用しない制度です。主に、高度な専門的知識やスキルを所持する社員や、年収1,075万円以上の稼ぎがある社員が対象です。この制度は欧米のホワイトカラー・エグゼプションの概念を参考に、日本の労働環境に合わせて独自につくられています。高度プロフェッショナル制度が適用された場合、対象者は労働時間に関する規制を受けず、労働時間管理の概念がなくなるのが特徴です。高度プロフェッショナル制度は、本人の同意はもちろん労使委員会の決議で適用が決定します。法定の休憩時間の適用はありませんが、対象者の心身の健康を考慮し、年間104⽇以上の休日の確保や健康管理措置が義務付けられています。
参考:働き方改革 ~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~
https://www.mhlw.go.jp/content/000335765.pdf
参考:高度プロフェッショナル制度について
https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/content/contents/000415522.pdf
高度プロフェッショナル制度が注目された背景には、「働き方改革」
https://www.dodadsj.com/content/20240221_koudo-professional/
裁量労働制との違い
労働時間関係規定の適用について、高度プロフェッショナル制度、裁量労働制、一般労働者を比較すると以下のとおりです。
出典:厚生労働省「労働時間制度間の比較等」
高度プロフェッショナル制度は、対象者に対して労働時間が適用されません。また、労働基準法で定められる休憩や休日割増賃金なども対象外です。対して裁量労働制は、労働時間を通常の労働時間として算出はしませんが、みなし時間として計算します。労働時間の決定は対象者に裁量を委ねるのが特徴です。一般労働者と同じく、休憩や休日外割増賃金などが適用されます。高度プロフェッショナル制度と裁量労働制に共通するのは、対象となる社員に対して労働時間の大きな裁量を与える点です。また、年次有給休暇が適用される点も共通事項といえます。労働基準法が適用されるかが、両者の大きな違いと考えるとよいでしょう。
高度プロフェッショナル制度の対象労働者
高度プロフェッショナル制度は、誰もが対象となるわけではありません。社員のうち以下の条件を満たした人にのみ、高度プロフェッショナル制度が適用されます。
・明確な職務が定められている
・1,075万円以上の年収がある
・対象者から書面での同意を得ている
業務内容が不明確な社員は、高度プロフェッショナル制度が適用されない場合があります。また業績や勤務成績などで変動する金額を除いて、年収が1,075万円以上あることも必須要件です。高度プロフェッショナル制度は、労働者の合意を得て初めて適用されます。ほかの条件を満たしていても対象者の同意が書面で得られない場合は、高度プロフェッショナル制度は適用されません。そして、対象業務以外の業務への常態的勤務がないかもチェックします。
高度プロフェッショナル制度の対象業務
高度プロフェッショナル制度の主な対象職務は、以下のとおりです。
・金融商品の開発業務
・資産運用に関する業務
・証券に関する業務
・コンサルタントに関する業務
・技術や商品または研究開発業務
また、対象業務のなかでも対象となり得る業務となり得ない業務があります。各業務における対象は以下のとおりです。
| 対象となり得る業務 | 対象となり得ない業務 | |
| 金融商品の開発業務 | ・資産運用会社での商品開発業務 | ・金融商品の販売や提供 ・商品名の変更や既存商品における開発 ・データ⼊⼒や整理 など |
| 資産運用に関する業務 | ・ファンドマネージャー業務 ・ディーラー業務 ・トレーダー業務 | ・⾦融機関の窓⼝業務 ・個⼈顧客への預⾦や保険などの販売業務 など |
| 証券に関する業務 | ・特定の業界の中⻑期的な企業価値予測の調査分析や投資判断に必要なレポートの作成業務 | ・時間設定をして行う相談業務 ・分析に必要なデータ⼊⼒や整理 など |
| コンサルタントに関する業務 | ・顧客の海外事業展開の戦略企画の考案業務 | ・調査⼜は分析のみの仕事 ・助⾔のみの業務 ・商品の営業や販売 など |
| 技術や商品または研究開発業務 | ・製薬企業での新薬の上市に向けた承認申請に必要な候補物質の探索や合成、絞り込みの業務 ・特許の取得につながり得る研究開発業務 など | ・技術的改善を伴わない業務 ・新たな価値を⽣み出すものではない業務 ・完成品の検査や品質管理業務 など |
金融商品の開発業務では、資産運用会社で富裕層向け商品の開発にあたる業務は対象となり得る業務ですが、商品の販売や提供をする業務は対象となり得ない業務にカウントされます。また対象業務となり得る業務であっても、企業から具体的な指示を受けて従事する業務も対象外です。
参考:⾼度プロフェッショナル制度 わかりやすい解説
https://www.mhlw.go.jp/content/001140965.pdf
高度プロフェッショナル制度の3つのメリット
高度プロフェッショナル制度は、社員のワークライフバランスの実現や生産性の向上が期待できます。ここでは、高度プロフェッショナル制度のメリットを3つご紹介します。
・不公平のない評価制度が築ける
・生産性の向上につながる
・柔軟な働き方でワークライフバランスが実現しやすい
不公平のない評価制度が築ける
高度プロフェッショナル制度の導入は、公平な評価で社員の納得度を高められるでしょう。多くの日本企業では、残業時間を含んだ実労働時間で計算する賃金制度が採用されています。そのため一般的な労働基準では、労働時間を超えると残業代として給与が支払われます。この場合、仕事のスピードが速く短時間で成果を出している人は、残業をしないため給与の加算はありません。対して、仕事のスピードが遅い人は残業した分だけ給与が高くなるのが特徴です。上記の条件では両者の間に不公平感が生まれ「実績に見合った給与がもらえない」などの不満につながるでしょう。高度プロフェッショナル制度は、労働時間ではなく社員の業務の成果が評価対象です。公平な評価は、社員の納得度が高まり会社への不信感の軽減が期待できるでしょう。
生産性の向上につながる
高度プロフェッショナル制度の導入は、会社の生産性の向上にもつながります。高度プロフェッショナル制度は、業務に対する成果が評価基準です。成果を出せば評価が得られるため、従来の労働に比べて生産性が高まるのがメリットの1つといえるでしょう。また社員それぞれが、効率的に働こうと考えるきっかけにもつながります。短時間で効率的に働くことで、会社全体のモチベーションアップや生産性の向上が期待できるでしょう。
柔軟な働き方でワークライフバランスが実現しやすい
高度プロフェッショナル制度は、ワークライフバランスが実現しやすいのもメリットです。対象者に働く時間の裁量を委ねるため、社員は会社の労働時間に縛られず自由な時間配分で働けます。たとえば、出勤や退勤の時間や休日を個人の都合でカスタマイズできます。そのため子育てや親の介護などで忙しく仕事との両立が難しい環境でも、従来の労働に比べて両立しやすいのが特徴です。高度プロフェッショナル制度は、柔軟な働き方でワークライフバランスが実現しやすくなります。そして、環境の整った企業は社員の定着率の向上も期待できるでしょう。
高度プロフェッショナル制度の3つのデメリット
高度プロフェッショナル制度には魅力的なメリットがありますが、人によってはデメリットに感じるポイントもあるでしょう。ここでは、高度プロフェッショナル制度のデメリットを3つご紹介します。
・制度導入時のハードルが高い
・評価基準や目標の設定が難しい
・長時間労働や休日出勤などのリスクが高まる
制度導入時のハードルが高い
高度プロフェッショナル制度は、導入時にデメリットを感じる可能性があります。制度の導入には、労使委員会の設置や労働基準監督署長への届け出などが必要です。不慣れな準備や手続きは、多くの時間や手間がかかるでしょう。そのため、導入前にハードルが高いと感じがちです。ただし導入後は会社の生産性の向上などが期待でき、メリットも豊富に得られます。社員の不公平感をなくすためにも、制度を導入する際は仕組みについてしっかりと話し合いましょう。
評価基準の設定が難しい
高度プロフェッショナル制度で苦戦するのは、評価基準や目標の設定です。高度プロフェッショナル制度は、社員の業務に対する成果を評価基準とします。そのため従来の勤務時間に対する評価制度に比べると、評価基準の可視化が難しいと感じるでしょう。また研究開発職など成果を出すのに時間がかかる業務もあり、評価基準の設定が自体が課題となります。高度プロフェッショナル制度を導入しても、評価基準が曖昧だと社員の納得が得られなかったり、会社への信頼度の低減につながったりする可能性が考えられます。
長時間労働や休日出勤などのリスクが高まる
高度プロフェッショナル制度の導入により、社員の勤務時間が大幅に増えるリスクが高まります。高度プロフェッショナル制度には、労働時間や休憩、休日などが適用されません。労働基準法に準じた1日の労働時間の規制がないため、社員によっては成果が出るまで働き続ける人もいるでしょう。また、長時間労働だけでなく休日出勤が増えるリスクも高まります。長時間労働や休日出勤の増加により十分な休息が取れないと、心身の健康の阻害を招くおそれがあります。そして高度プロフェッショナル制度は時間外労働や休日出勤に対する割増賃金は発生しないため、合わせて注意が必要です。
高度プロフェッショナル制度を導入する際の流れ
高度プロフェッショナル制度を導入する際は、以下の手順で進めましょう。ここでは導入時の流れに沿って、それぞれの手順のポイントを解説します。
➀労使委員会の設置
➁労使委員会での決議や労働基準監督署長への届け出
➂書面による明示と対象者からの同意
➃対象者の対象業務への就任
労使委員会の設置
高度プロフェッショナル制度を導入する際は、はじめに労使委員会を設置します。労使委員会とは、労働条件である労働時間や賃金などの決まりを審議する委員会です。労使委員会は、以下の手順で設置します。
➀必要事項を労働者と企業側で話し合う
➁代表委員を選出する
③運営ルールを決定する
高度プロフェッショナル制度の設置⽇などを、話し合って決めましょう。代表委員を選出する際は、メンバーの半数を労働者が占めなくてはいけません。運営ルールが決定したら、同時に運営規程を作成しましょう。
労使委員会での決議や労働基準監督署長への届け出
労使委員会で決議するのは、主に以下の10項目です。
・対象業務
・対象労働者の範囲
・対象労働者の健康管理時間の把握および把握方法
・対象労働者の休日の確保(年間104⽇以上かつ4週間を通じ4⽇以上の休⽇)
・対象労働者の選択的措置
・健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置
・対象労働者の同意の撤回に関する手続き
・対象良同社の苦情処理の実施および具体的な内容
・同意しなかった対象者への不利益な取り扱いの禁止
・厚生労働省令で定められたそのほかの項目
決議には、5分の4以上の多数が必要です。そして、高度プロフェッショナル制度の導入には決議の提出が欠かせません。決議後は、労働基準監督署長に届け出ましょう。
参考:⾼度プロフェッショナル制度 わかりやすい解説
https://www.mhlw.go.jp/content/001140965.pdf
書面による明示と対象労働者からの同意
対象労働者に決議内容を説明し、書面で明示し同意を得ます。以下の項目は、対象者に事前に書面で明示する必要があります。
・同意後、労働基準法第4章の規定が適⽤外となること
・同意の対象期間
・同意の対象期間中に⽀払われる賃⾦額の見込み
高度プロフェッショナル制度の対象者には、労働時間や休憩、休日の割増賃金などが適用されないことをしっかりと伝えましょう。同意の判断には、⼗分な時間を与えます。対象者が納得したうえで、書面に署名をもらいます。同意を得られなかった労働者への不利益な対処は、禁止事項のため注意しましょう。
参考:⾼度プロフェッショナル制度 わかりやすい解説
https://www.mhlw.go.jp/content/001140965.pdf
対象者の対象業務への就任
同意を得られた対象者には、高度プロフェッショナル制度の対象業務に就任してもらいます。同時に、企業側は以下の対応が求められます。
・対象労働者の健康管理時間の把握
・対象労働者の休日の確保(年間104日以上かつ4週間を通じ4日以上の休日)
・対象労働者の選択的措置及び健康・福祉確保措置の実施
上記は、決議から6ヵ月以内ごとに労働基準監督署長へ報告をしなくてはいけません。そのほか、対象者の苦情処理措置の実施なども必要です。高度プロフェッショナル制度の対象者は、同意対象の期間中に同意の撤回ができます。そして決議の有効期間の満了とともに、高度プロフェッショナル制度の適用期間も終了します。制度継続を希望する対象者には、労使委員会の決議後、再度同意の署名をもらいましょう。
参考:⾼度プロフェッショナル制度 わかりやすい解説
https://www.mhlw.go.jp/content/001140965.pdf
高度プロフェッショナル制度を導入する際の注意点
高度プロフェッショナル制度の導入でトラブルを招かないためにも、いくつか注意点を把握しておくことが必要です。ここでは、高度プロフェッショナル制度を導入する際の注意点を紹介します。
・人事評価制度を見直す
・社員の健康管理措置を実施する
人事評価制度を見直す
すでに人事評価制度を実施している場合は、既存の制度の見直しをしましょう。高度プロフェッショナル制度は従来の労働評価とは異なり、社員の業務に対する成果を評価します。そのため人事評価制度は、仕事の成果や業績を公正に評価できるものでなくてはいけません。対象者の業務内容はもちろん、ひとりひとりの労働態度などをしっかりと把握し適切に評価できる環境を整えることがポイントです。
社員の健康管理措置を実施する
企業は対象者の健康管理措置として、以下の4つの項目を管理する必要があります。
・健康管理時間の把握
・休日の確保
・選択的措置
・健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置
上記は、社員の心身の健康を守るために重要とされる項目です。ここでは、4つの項目について詳しく解説します。
健康管理時間の把握
健康管理時間とは「対象者が事業場内にいた時間と事業場外で労働した時間の合計」を示します。 企業は、対象者の健康管理時間を客観的な方法で把握しておかなくてはいけません。たとえばICカードの出退勤時刻の記録やタイムカードの打刻記録など、可視化された情報が対象です。高度プロフェッショナル制度を導入する企業は、対象者の⽇々の健康管理時間を記録し、1ヶ⽉の合計を把握しなくてはいけません。
休日の確保
高度プロフェッショナル制度では、対象者の休日確保に対して「年間104日以上、かつ4週間を通じ4日以上」と、具体的な日数が定められています。休日の取得の手続きについては、決議の段階で具体的な内容を明らかにしなくてはいけません。対象者が休日をしっかりと確保するには、対象者本人が休日の年間取得予定や取得状況を企業側に定期的に伝達するのが望ましいでしょう。対象者の疲労の蓄積防止のためにも、連続勤務を避けて適切な間隔で休日を取得し、これらを対象者と企業側が把握しておくことが大切です。
選択的措置
高度プロフェッショナル制度を導入する際は、決議の段階で以下のいずれかの措置を定める必要があります。 ・勤務間インターバルの確保と深夜業の回数制限 ・健康管理時間の上限 ・1年に1回以上の連続2週間の休日を与えること ・臨時の健康診断 勤務間インターバルの確保では、始業から24時間が経過するまでに11時間以上の休息期間を設けなくてはいけません。健康管理時間の上限措置は、1週間で40時間を超えた場合1ヶ月100時間以内または3ヶ月240時間以内とします。健康管理時間が1週間で40時間を超え、1ヶ月で80時間を超えた対象者には、臨時の健康診断を実施する措置もあります。対象者が自ら申出をした場合も対象です。臨時の健康診断の実施が決議された場合は、心電図検査など脳や心臓との関連が認められる項目を受診し、必要に応じて事後措置を実施します。選択的措置は、対象者の意見に耳を傾け決定するのが望ましいでしょう。
健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置
高度プロフェッショナル制度は、健康管理時間の状況に応じて健康や福祉の確保措置も必要です。健康・福祉確保措置は、以下から決議で定め実施をします。
・「選択的措置」のいずれかの措置
・医師の⾯接指導
・代償休日または特別休暇の付与
・心とからだの健康問題に関する相談窓口の設置
・適切な部署への異動
・産業医などの助言指導または保健指導
「選択的措置」のいずれかの措置を決議する際は、選択的措置の決議で定めたもの以外が対象です。
参考:高度プロフェッショナル制度について
https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/content/contents/000415522.pdf
⾼度プロフェッショナル制度 わかりやすい解説
https://www.mhlw.go.jp/content/001140965.pdf
人材育成のことならユーキャンへ
ユーキャンでは、人材育成に効果的なさまざまなプログラムを用意しています。決められたスケジュールに沿って実行するだけで、準備に時間がかからないのがメリットです。育成結果は次年度計画や人事評価に活用可能なため、会社の発展に欠かせない資材となるでしょう。とくに「階層別育成おまかせプログラム」は、若手やリーダーなどの階層に合わせて明確な基準で人材育成ができます。企業が成長し続けるためには、ひとりひとりの社員の成長が重要です。ユーキャンで、効果的な人材育成プログラムを始めましょう。
まとめ
高度プロフェッショナル制度とは、特定の対象者に対して労働時間や休憩などの適用を除外する制度です。対象者は仕事の始業や就業の規定がないため、労働に関する大きな裁量権が得られるのが特徴です。高度プロフェッショナル制度の導入は不公平のない評価制度が築けるだけでなく、社員の理想とするワークライフバランスの実現が期待できます。制度を導入する企業は、社員の心身の健康を保つために、定められた休日の確保や健康管理時間の把握を徹底する必要があります。公平性のある高度プロフェッショナル制度を導入し、会社の生産性の向上につなげましょう。